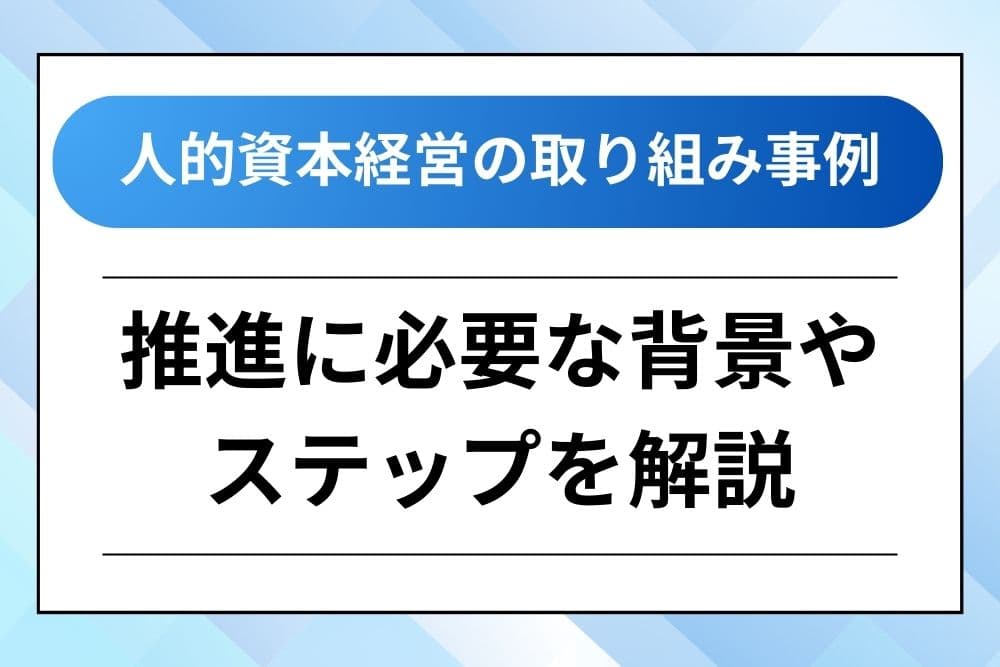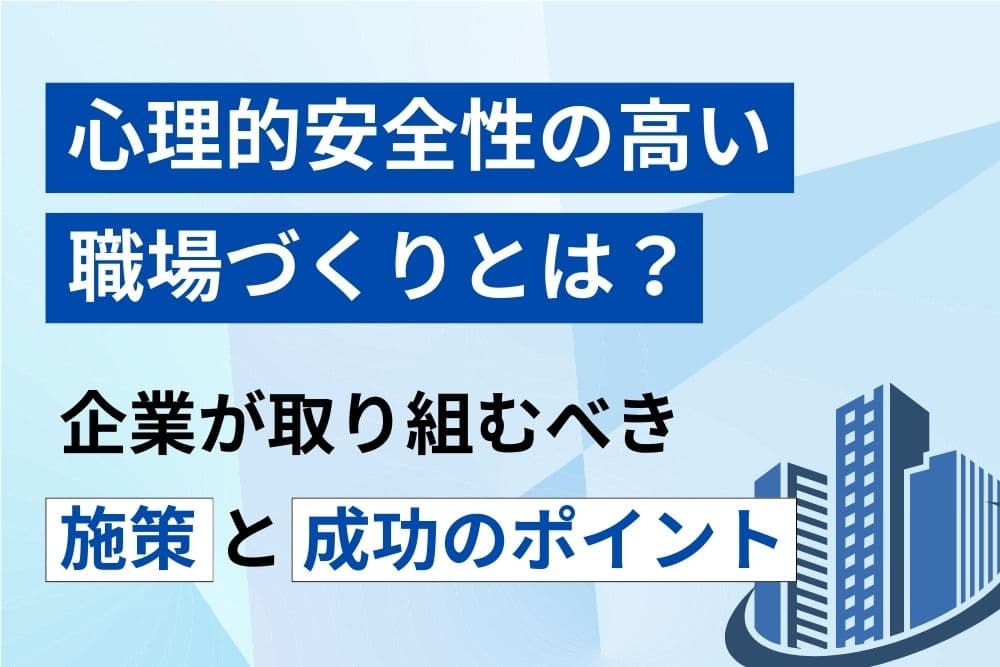お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
退職金の制度を徹底解説!企業が導入すべき理由とは?
 詳細を見る
詳細を見る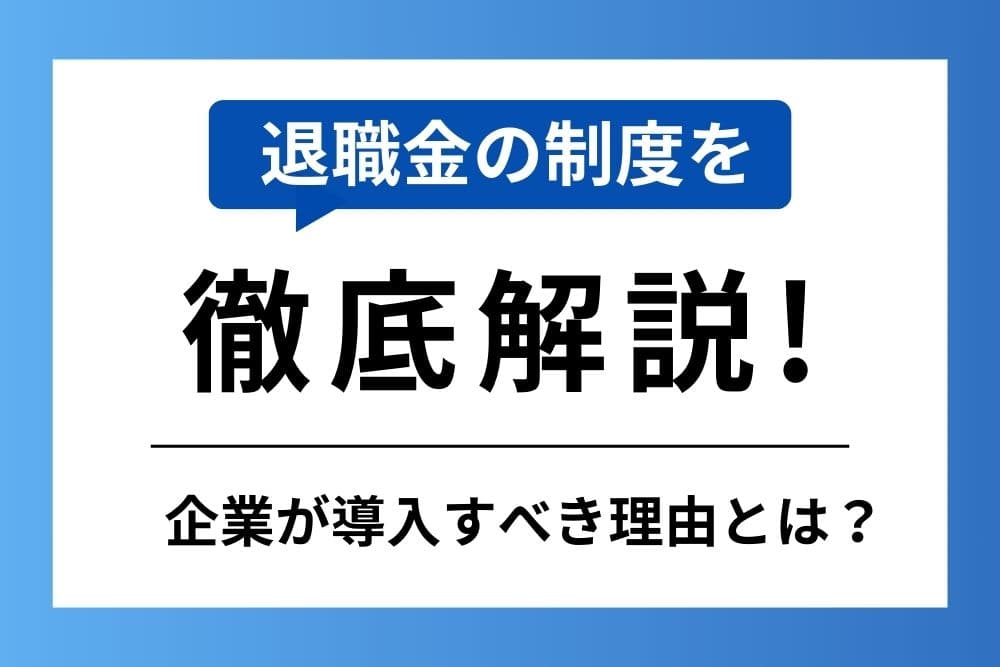
企業が準備する退職金制度の概要
退職金制度の導入割合について
企業規模別の退職金金額の平均
退職金制度を導入するメリット
退職金制度を導入するデメリット
退職金制度は、従業員の長年の貢献に報いる重要な福利厚生です。しかし「うちの会社でも導入すべきか?」と悩む経営者・人事担当者の方も多いでしょう。
実は大企業の多くが整備する一方で、中小企業では未導入の場合も少なくありません。
本記事では、退職金制度の種類や平均支給額、導入状況からメリット・デメリット、具体的な導入方法まで徹底解説します。
退職金制度を理解し、自社の安定経営と人材定着に役立てましょう。ぜひ最後までご覧ください。
自社の将来と従業員の安心のために、退職金制度の導入を前向きに検討してみましょう。
目次
企業が準備する退職金制度の概要

まず、企業が準備できる退職金制度にはどのような種類があるのか、その全体像を把握しましょう。退職金制度は大きく分けて、
- 「自社準備型」
- 「企業年金型」
- 「退職金共済型」
の3種類に分類できます。
それぞれ特徴や仕組みが異なり、会社の規模や方針によって適した制度も変わります。以下の一覧表に主な制度をまとめました。自社に合う退職金制度選びの参考にしてください。
制度の種類
具体的な制度の例
概要・特徴
自社準備型
内部留保による準備
退職金積立保険の活用
社内で資金を積み立て、退職時に会社から直接一時金を支給する方式。比較的シンプルで自由度が高い反面、将来の支給財源を自社で確保する必要あり。
企業年金型
企業型確定拠出年金(企業型DC)
確定給付企業年金(DB)
iDeCo+(イデコプラス)
外部の年金制度を活用し、従業員の退職後に年金または一時金を給付する方式。税制優遇があり、資産運用は制度により企業または従業員が行う。大企業を中心に普及。
退職金共済型
中小企業退職金共済(中退共)
小規模企業共済
特定退職金共済制度
国や団体が運営する共済制度に加入し、掛金を積み立てて退職金に備える方式。中小企業でも導入しやすく、共済から直接従業員へ退職金が支給されます。国の助成が受けられる制度もあり。
自社準備型の退職金制度
自社準備型は、会社が自ら退職金原資を準備する方式です。
典型的なのは社内留保金による積立や、退職金積立保険(養老保険など)への加入です。従業員が退職する際、予め定めた社内規定に従い退職金(退職一時金)を会社から直接支給します。
この方式は制度運用が比較的簡単で、他機関を介さない分コストも低めですが、その反面、毎年の業績に関わらず将来の退職金支給に備えて資金を確保しておく必要があります。
また、適切に準備をしないと大量退職時に資金不足に陥るリスクもあるため注意が必要です。
企業年金型の退職金制度(iDeCoなど)
企業年金型は、企業が外部の年金制度を導入して従業員の退職金相当額を準備する方式です。退職時に一時金としてだけでなく、年金形式で受け取れるプランも含まれます。
企業年金型には大きく分けて確定拠出型と確定給付型があり、それぞれ特徴が異なります。
大企業を中心に導入が進んでいる方式で、税制優遇が受けられ、社員にとっても老後の所得確保に役立つのが利点です。以下、主な企業年金型制度を解説します。
iDeCo+(イデコプラス)
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)は、中小企業向けの新しい企業年金制度です。従業員が個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)に加入している場合に、会社が掛金を上乗せ拠出できる仕組みになっています。
社員一人ひとりのiDeCo口座へ企業が毎月一定額を拠出することで、社員の老後資金形成を会社が支援します。掛金は全額が損金算入(経費扱い)となり、従業員側も所得税控除の対象です。
他の企業年金を導入していない従業員300人以下の会社が利用でき、低コストで導入しやすい企業年金として注目されています。
参照元:iDeCo+(イデコプラス) |iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型DC(確定拠出年金)は、企業が掛金を拠出し、従業員各自が自分の年金資産を運用していく制度です。毎月の拠出額(企業が負担する掛金や従業員拠出分)が確定しており、将来の給付額は運用成績によって変動します。
従業員は60歳以降に積み立てた資産を一時金か年金で受け取ります。企業型DCは日本版401kともいわれ、拠出額は全額非課税扱いになるため企業にとっても税負担の軽減になります。
ただし、社員自身に運用リスクと責任が伴うため、金融知識の啓発や運営管理機関の選定など企業側のサポートも必要です。
確定給付企業年金(DB)
確定給付企業年金(DB)は、将来の給付額があらかじめ約束された企業年金制度です。企業が掛金を拠出し、その資金を基金や信託銀行が運用します。
従業員が退職する際には、勤続年数や最終給与などに応じて一定の額が一時金または年金として支給されます。
給付額が保証されている反面、運用が予定より悪化した場合は企業が不足分を負担する必要があります。安定運用の責任が企業側にあるため、中長期的な財務計画が重要です。
DBは歴史的に大企業や公務員で広く採用されてきた方式で、退職金の安定給付に優れていますが、導入・維持には専門的な管理が求められます。
退職金共済型の退職金制度
退職金共済型は、国の機関や業界団体等が運営する共済制度に企業が加入し、掛金を積み立てることで退職金を準備する方式です。
中小企業でも導入しやすいよう設計されており、企業は毎月の掛金を外部団体に納付し、従業員の退職時にはその団体から直接退職金が支給されます。
掛金は企業の損金(経費)となり、従業員にとっても退職所得扱いとなるため税制上有利です。国の助成制度が用意されている共済もあり、特に退職金制度を持たない中小企業には魅力的な選択肢です。主な退職金共済制度を以下に紹介します。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済(中退共)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する国の共済制度です。従業員数が一定規模以下の中小企業が加入でき、毎月5,000円から30,000円までの範囲で従業員ごとに掛金を設定して積み立てます。
従業員が退職すると、中退共から直接退職金が支払われます。加入手続きも比較的簡単で、初めて加入する企業には掛金の一部を国が助成(掛金月額の1/2〈上限5,000円〉を1年間補助)する制度があります。
中退共は国が運営している安心感から、中小企業の退職金準備に広く活用されています。
参照元:中退共
小規模企業共済制度
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度ですが、こちらは主に小規模企業の経営者や役員自身の退職金準備を目的としています。
個人事業主や小規模な会社の経営者が毎月積み立てを行い、廃業や退職時に共済金を受け取る仕組みです。
掛金月額は1,000円から70,000円まで自由に設定でき、全額が所得控除の対象となるため経営者の節税をしながら退職金準備ができます。従業員向けではなく経営者自身の老後資金準備策ですが、小規模企業にとって重要な制度と言えるでしょう。
特定退職金共済制度
特定退職金共済制度は、商工会議所や業界団体などが運営する退職金共済制度です(所轄税務署長の承認を受けて実施)。
仕組み自体は中退共に似ており、企業が掛金を積み立て、退職時にその団体から退職金が支払われます。特定退職金共済は企業規模に関係なく加入できる点が特徴で、従業員数や資本金による制限がありません。
掛金は一度決めると減額が難しいものの、幅広い企業が利用できる共済として存在しています。自社の業界団体に特退共がある場合は、福利厚生の一環として検討するとよいでしょう。
退職金制度には様々なタイプがあります。自社の規模や財務状況、従業員のニーズに合わせて、最適な制度を選択しましょう。ぜひ当社へお気軽にご相談いただき、将来に備えた制度設計を始めてみてください。
退職金制度の導入割合について

退職金制度がどの程度の企業で導入されているかを、大企業・中小企業・公務員それぞれで見てみましょう。一般的に、大企業ほど退職金制度の整備率は高く、ほとんどの大手企業では何らかの退職給付制度があります。
一方、中小企業では制度未整備の企業も少なくなく、規模によって導入状況に差が見られます。また、公務員については原則として退職金制度が導入されており、その水準は大企業に匹敵しています。
大企業の退職金制度はほとんどの企業が導入している
大企業においては、退職金制度(退職一時金制度や企業年金制度)を導入している企業が非常に高い割合にのぼります。資本金や従業員数が大きい企業ほど制度整備が進んでおり、従業員数300人以上の企業では概ね9割以上が何らかの退職金制度を設けています。
特に従業員1,000人を超えるような企業ではほぼ100%に近い導入率となっており、退職一時金と企業年金(確定給付年金や確定拠出年金)を併用する企業も多いです。「制度がないと優秀な人材を確保できない」という認識が強く、人材戦略上も退職金制度は大企業では標準的な福利厚生となっています。
中小企業の退職金制度は整備があまり進んでいない
中小企業では、退職金制度の導入率が大企業に比べて低い傾向があります。
従業員数が少ない企業ほど未導入の割合が高く、特に小規模事業(従業員数10~49人程度)では「退職金制度なし」の会社も珍しくありません。ただし、全く整備が進んでいないわけではなく、例えば従業員50~99人規模の企業では約75~85%程度が何らかの制度を持っているとの調査もあります。
参照元:3 退職給付(一時金・年金)制度
つまり中小企業全体で見ると退職金制度ありの企業は約70%前後です。
最近では中退共など国の共済制度を活用して制度を持つ中小企業も増えていますが、依然として「退職金制度まで手が回っていない」という小企業も多い状況です。公務員の退職金は大企業並みの水準になっている
公務員(国家公務員・地方公務員)は法律に基づく退職手当制度が整備されており、民間の大企業に匹敵する水準の退職金が支給されます。
公務員の場合、勤続年数や職務に応じて退職手当の額が決まっており、定年退職時には大企業平均並みのまとまった退職金を受け取るのが一般的です。
たとえば国家公務員の定年退職者の平均退職手当は約2,100万円前後、地方公務員も職種によりますが概ね2,000万円強の水準となっています。
公務員の場合は国家公務員退職手当法や各自治体の条例により計算方法が定められており、勤続年数が長いほど手厚く、役職や級別によっても加算があります。このように、公務員の退職金は大企業に遜色ない充実した内容であり、安定した職業生活を支える一要素となっています。
企業規模別の退職金金額の平均
次に、企業規模ごとの退職金支給額の平均を見てみましょう。退職金の額は企業規模によって大きな差があり、大企業ほど高額、中小企業では相対的に低い傾向があります。
また、公務員についても平均額を把握しておくことで、自社の水準と比較する参考になります。
ここでは、主に定年退職まで勤務した場合の退職金額を企業規模別に紹介します。
大企業の退職金平均は2,100万円程度
大企業(一般的に資本金5億円以上・従業員1,000人以上の企業)の場合、定年まで勤続した従業員に支払われる退職金の平均は約2,100万円前後とされています。
学歴別に見ると、高校卒で約2,000万円、大学卒で約2,300万円程度が平均的なモデル退職金額です。
この金額には退職一時金に加え企業年金としての給付を含む場合もありますが、いずれにせよ大企業では2,000万円超の退職金が支給されるケースが多いことが分かります。
歴史的には1990年代後半が退職金のピークで、その頃に比べるとやや減少傾向にあるものの、大企業では依然として手厚い退職金制度が維持されています。
引用元:<図表8-1>モデル退職金
中小企業の退職金平均は1,000万円付近
中小企業(一般的に従業員数300人未満・資本金3億円以下の企業)の場合、定年まで勤続した従業員のモデル退職金は約1,000万円前後となっています。
例えば東京都産業労働局の調査によれば、大卒で約1,092万円、高卒で約994万円がモデル退職金の水準でした。
大企業の水準と比較するとおよそ半分程度であり、中小企業では退職金額が抑えられる傾向が明らかです。ただし、これらはあくまで「平均」であり、各企業の状況によって支給額は大きく異なります。
中小企業でも業績好調な企業や従業員に長く勤めてもらいたい方針の企業では、平均以上の退職金を用意している例もあります。反対に、業種や財務状況によっては平均を下回るケースもあります。
自社の退職金水準がどの程度か、業界団体の資料なども参考に把握しておくとよいでしょう。
引用元:<図表8-1>モデル退職金
公務員の退職金平均は職種によって異なる
公務員の退職金平均額は、一律ではなく職種や級職によって異なります。国家公務員の場合、定年退職者の平均退職手当は約2,100~2,200万円とされています(行政職〔一般職〕の場合)。
地方公務員も自治体や職種(教員、警察官、一般行政職など)によって差がありますが、概ね1,800万~2,400万円程度の範囲に収まることが多いです。
例えばある年の調査では、全地方公務員の平均支給額は約2,200万円、都道府県職員では平均約2,100万円、市町村職員ではそれよりやや低い水準との結果が出ています。
公務員の退職金制度は法律で細かく定められており、基本給や勤続年数に応じた計算式によって算出されます。したがって、民間企業のように会社業績で増減することはありません。
職種による差はありますが、公務員全体として退職金平均はおおむね大企業と同等と言えるでしょう。
※大企業・中小企業の具体的な数字は、厚生労働省「賃金事情等総合調査」や東京都「中小企業の退職金事情」等の公表値をもとにしたモデルケースの値です。
退職金制度を導入するメリット
それでは、企業が退職金制度を導入することで得られるメリットにはどんなものがあるでしょうか。経営者にとって退職金制度はコストにもなりますが、それを上回る利点がいくつも存在します。ここでは主なメリットを3点解説します。
求人の際に企業の安定性をPRできる
退職金制度が整っていることは、求職者に対して企業の安定性・将来性を示す有力なアピール材料になります。
福利厚生が充実している企業は「社員を大切にする会社」という印象を与え、優秀な人材の応募を呼び込みやすくなります。特に新卒採用や中途の即戦力採用において、求人票に「退職金制度あり」と明記できることは他社との差別化につながります。
終身雇用制が揺らいでいるとはいえ、安定志向の強い人材は今も多く、退職金制度の有無で応募を検討するケースも少なくありません。
「将来にわたって安心して働ける場を提供できる」という企業の姿勢をPRできる点で、退職金制度は重要なメリットとなります。
働く際のエンゲージメントを高められる
退職金制度は従業員のエンゲージメント(愛社精神や仕事へのコミットメント)を高める効果も期待できます。社員にとって退職金は将来受け取れる大きな報酬です。
制度があれば「この会社で長く頑張れば、まとまった退職金がもらえる」というインセンティブになり、勤続年数の延長や離職率の低下につながります。
特に退職金の額を勤続年数に応じて増加する設計にしておけば、社員は長期的視点でキャリアを積もうという意識を持ちやすくなるでしょう。
また、「会社が自分たちの老後まで面倒を見てくれる」という安心感は企業への信頼感を醸成し、日々の仕事への意欲向上にも寄与します。結果として生産性向上や定着率アップにつながり、企業にとってプラスに働くのです。
社会保険料などのコスト削減が可能
意外に思われるかもしれませんが、退職金制度の導入は社会保険料や税金面でのコスト削減につながる場合があります。
例えば、給与として従業員に支給する分を一部退職金積立に振り替える「選択制退職金制度」を導入すれば、その分は給与ではなく福利厚生費扱いとなり、厚生年金や健康保険の算定対象額から除外できます。
これにより会社負担の社会保険料を抑制することができます。また、企業型年金(確定拠出年金や確定給付年金)に拠出する掛金は全額損金算入でき、法人税の軽減につながります。
さらに従業員側も、退職金として受け取る金額には退職所得控除という大きな税優遇が適用されるため、同じ額を給与で受け取るより手取りが増えます。
このように、退職金制度は会社と従業員双方にとって税制上有利に働く面があり、トータルのコスト管理に寄与するメリットがあります。
退職金制度を整えることで、人材獲得力の強化や従業員の定着・意欲向上、さらにコスト面での効率化まで期待できます。貴社の魅力向上と長期的発展のために、ぜひ退職金制度の導入メリットを活かしましょう。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。1人当たり500円の料金で、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。
退職金制度を導入するデメリット
一方で、退職金制度には留意すべきデメリットや課題も存在します。導入を検討する際には、こうした点も踏まえて慎重に計画を立てることが重要です。主なデメリットを挙げると以下のようになります。
- 企業の財務負担が増える
- 制度運用の手間や専門知識が必要
まず、企業の財務負担が増えることが挙げられます。退職金の支給原資を用意するために毎期一定の積立や掛金拠出が必要となり、資金繰りやコスト構造に影響を及ぼします。特に業績が不安定な場合でも退職金債務は累積していくため、計画的な資金管理が求められます。
次に、制度運用の手間や専門知識が必要という点です。企業年金や共済に加入する場合は各種手続きや運用管理が発生し、社内の人事・総務担当者の負担が増えます。また、退職金制度を変更・廃止する際には労使間の合意形成や法的手続きが必要で、柔軟な調整が難しい側面もあります。
さらに、若年層の中には「退職金より現在の給与を重視する」という考えの人もおり、短期的な報酬への満足度向上には直結しにくいという指摘もあります。このように、退職金制度にはコスト面・運用面のデメリットが存在しますが、適切な制度設計と管理を行えば十分に克服可能な範囲と言えるでしょう。
退職金制度と従業員のエンゲージメントの関係
退職金制度と従業員エンゲージメント(愛社精神や仕事への主体的な関与)には密接な関係があります。
退職金制度があることで従業員の会社に対する信頼感・安心感が高まり、結果としてエンゲージメントが向上する傾向が見られます。
特に終身雇用的な働き方を望む従業員にとって、退職金制度は「会社が自分の将来を保障してくれている」という心理的な支えになります。
逆に、制度がない場合「この会社に長く勤めてもメリットが少ない」と感じてしまい、キャリアアップ転職や離職の動機づけになりかねません。
エンゲージメントの高い社員ほど生産性が高く、組織に貢献してくれることが各種調査で明らかになっていますが、その土台には待遇面での安心感が必要です。
退職金制度の整備は、従業員との長期的な信頼関係を築き、「この会社で頑張ろう」という意欲を引き出す重要な施策となります。ただし、一方で退職金だけに頼らず、日頃の待遇改善や評価、公正な人事制度と組み合わせることで、より一層エンゲージメントを高めることができるでしょう。
退職金の支給額
ここでは、具体的な退職金の支給額に関する知識をまとめます。退職金がどのように計算されるか、その相場感、企業規模による違い、さらに退職金制度に関連する助成金について解説します。自社の制度設計や従業員への説明に役立ててください。
退職金の計算方法
退職金の計算方法は企業や制度によって異なりますが、一般的には勤続年数と在職中の給与水準、退職事由(自己都合退職か定年退職・会社都合退職か)などを組み合わせて算定されます。
多くの企業で採用されているのが「勤続年数別の基準額表」による方法です。
例えば「勤続○年で基本給の×ヶ月分」といった基準を設け、さらに退職理由(定年退職なら100%、自己都合退職なら80%など)に応じて支給率を調整します。また、ポイント制を採用する企業もあります。
ポイント制では、勤続年数や役職ごとにポイントを蓄積し、退職時にポイントに一定の金額を掛けて支給額を算出します。
企業年金の場合、確定給付型であればあらかじめ定めた数式(例:最終給与×給付率×勤続年数)で計算され、確定拠出型であれば拠出金とその運用収益の合計額がそのまま退職金となります。
さらに公務員などでは法律で細かい算定式が決まっており、勤務期間と平均給与に基づいて厳密に計算されます。
このように、退職金の計算方法は様々ですが、基本は「長く勤めるほど多く支給される」よう設計されています。また企業ごとに就業規則(退職金規程)で計算方法を明文化しておく必要があります。
退職金の相場
退職金の相場を把握するには、厚生労働省などが発表する統計データが参考になります。
直近のデータを見ると、大学卒・定年退職者の平均退職金はおおむね1,900万円前後、高校卒・定年退職者では1,600万円台となっています(企業規模全体の平均値) 。
ただしこれは企業規模や業種をすべて含めた平均であり、実際には大企業と中小企業で大きな差があります。
大企業では同じ条件(大卒・定年退職)で2,300万円前後、中小企業では1,100万円前後と倍近い開きがあることは前述の通りです。また業種によっても差が見られ、金融業やインフラ系の企業は退職金水準が高めで、外食・小売など労働集約的産業では低めといった傾向があります。
さらに学歴や職種による違いも無視できません。一般的に管理・技術系の大卒社員の方が、高卒現業社員より退職金は高く設定されるケースが多いです。
このように一概に相場といっても幅がありますが、自社と同規模・同業種の水準を知ることが大切です。企業年金連合会や労働組合連合会などが公表している業種別退職金データも参考になります。自社の退職金が世間相場と比べて高すぎないか低すぎないかをチェックし、必要に応じて制度の見直しを検討しましょう。
企業規模における退職金
企業規模による退職金の差については既に述べましたが、制度面でも傾向があります。
大企業では退職一時金と企業年金を併用している場合が多く、退職時にまとまった一時金を支給しつつ、その後企業年金として分割受取できる仕組みを整えていることがあります。
これにより従業員は退職後も年金収入を得られるため、老後の安定に寄与します。一方、中小企業では企業年金まで用意できないケースも多く、退職一時金のみのシンプルな制度にとどまることが一般的です。
その場合、支給額も大企業ほど高額にはできないため、従業員の老後資金としては十分でない可能性があります。こうした企業規模間の格差を埋めるために、中小企業向けには中退共やiDeCo+といった制度が用意されています。
中小企業でもこれらを活用すれば、ある程度大企業に近い水準の退職金準備が可能になります。逆に大企業であっても、確定拠出年金の導入により従業員ごとの運用次第で給付額が変わるなど、新しい動きも出ています。
企業規模ごとの傾向はあるものの、各社が自社に見合った形で制度設計を工夫しているのが現状と言えるでしょう。
退職金制度における助成金
退職金制度の導入や運用に際して、国から支給される助成金を活用できる場合があります。中小企業が代表的な制度として利用できるのが、前述した中小企業退職金共済(中退共)の掛金助成です。
新規に中退共へ加入する事業主に対して、加入後一定期間(1年間)、月額掛金の一部を国が補助してくれる制度で、具体的には従業員一人あたり月額掛金の半額(上限5,000円)を助成します。これにより導入初期の企業負担を軽減し、中小企業での退職金制度普及を後押ししています。
また、厚生労働省のキャリアアップ助成金には「賞与・退職金制度導入コース」というメニューがあり、非正規社員に退職金制度を導入するなど一定の条件を満たすと助成金が支給される場合があります。
その他、地方自治体や商工団体が独自に中小企業の福利厚生充実を支援する助成制度を設けていることもあります。こうした助成金は時期や要件によって変わるため、制度導入の際には最新情報を調べてみましょう。
助成金を上手に活用すれば、退職金制度導入時の負担を和らげ、スムーズに制度を立ち上げることができます。国や自治体も中小企業の退職金制度整備を促進する方向ですので、ぜひ活用を検討してください。
退職金制度を導入する方法
実際に自社で新たに退職金制度を導入したり、既存の制度を見直したりする際の進め方について解説します。中小企業で初めて制度を作るケースと、既にある制度を変更するケースに分けてポイントを整理します。
新しく退職金制度を導入する方法
新規に退職金制度を導入する場合、以下のようなステップで進めるとスムーズです。
導入目的と予算の明確化
まず、なぜ退職金制度を導入するのか目的をはっきりさせます(人材定着のため、求人競争力強化のため等)。同時に、将来にわたって拠出可能な予算枠を試算し、企業の財務的に無理のない制度規模を把握します。
制度タイプの選定
自社に適した制度を検討します。社内準備型でいくのか、中退共など共済に加入するのか、企業型年金(DC/DB)を導入するのか、あるいは複数組み合わせるのか、従業員規模や予算に応じて最適な方式を選びます。
この際、専門の社会保険労務士や退職金コンサルタントに相談すると、各制度のメリット・デメリットを踏まえた提案が得られるでしょう。
就業規則(退職金規程)の作成
具体的な支給基準や計算方法を定めた退職金規程を作成します。誰が対象で、何年以上勤務で支給し、金額はどう算定するか、支給方法や時期、不支給事由(懲戒解雇時は支給しない等)まで明文化します。
退職金規程は就業規則の一部として作成し、従業員代表の意見聴取を経て労働基準監督署へ届け出ます。
制度運用の準備
社内準備型なら社内積立の方法(積立口座の用意や保険加入)、共済や企業年金型なら関係機関への加入申請を行います。
中退共であれば所定の書類提出、企業型DCであれば運営管理機関との契約や従業員への投資教育計画策定など、制度開始に必要な手続きを進めます。
従業員への周知
制度を導入したら、従業員に対してその内容を十分に説明します。誰にどのような退職金が将来支給されるのかを理解してもらい、会社の制度として周知徹底します。新入社員にも入社時に説明し、就業規則にも明記して開示します。
積立・拠出の開始
規程と計画に沿って積立金の計上や掛金拠出をスタートします。毎年の決算時には退職給付引当金を適切に計上し、将来債務を把握していきます。制度開始後も定期的に運用状況を確認し、問題点があれば早めに対処します。
以上が基本的な流れです。初めは難しく感じるかもしれませんが、専門家のサポートを受けながら進めれば円滑です。重要なのは会社の実情に合った無理のない制度を作ることです。
退職金制度を導入してエンゲージメントを高めよう
退職金制度は企業にとって長期的な視点での人材投資と言えます。本記事では制度の種類から導入状況、金額相場、メリット・デメリット、導入・見直し方法まで幅広く解説してきました。
大企業では当たり前の退職金制度も、中小企業では未整備だと感じられた方もいるかもしれません。しかし、事業規模に関わらず従業員の将来を支える仕組みを持つことは、企業の信頼性向上と人材確保に直結します。
退職金制度の導入には確かにコストや手間も伴いますが、それを上回る効果が期待できます。
ぜひ今回の解説を参考に、自社の状況に合った退職金制度を検討してみてください。小さな会社でも利用できる制度や助成策もありますので、まずはできる範囲から始めてみることが重要です。
退職金制度の整備によって、従業員が安心して働ける職場環境を整え、企業の魅力と競争力を高めていきましょう。
従業員の安心と会社の発展のために、今こそ退職金制度の導入・充実に踏み出しましょう。将来を見据えた福利厚生の充実が、優れた人材の定着と企業の安定成長につながります。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。1人当たり500円の料金で、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。