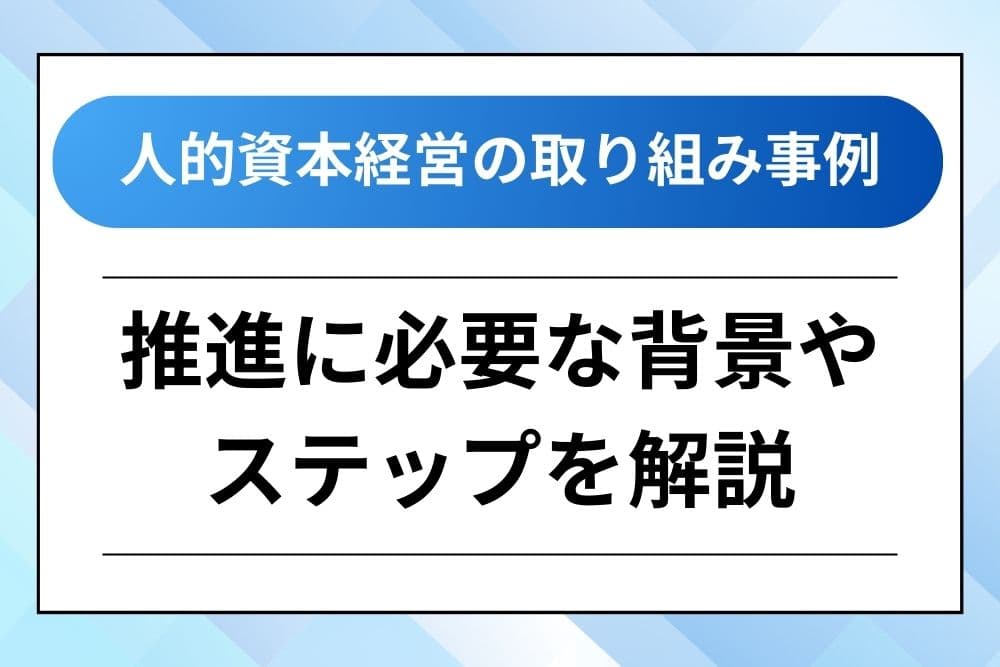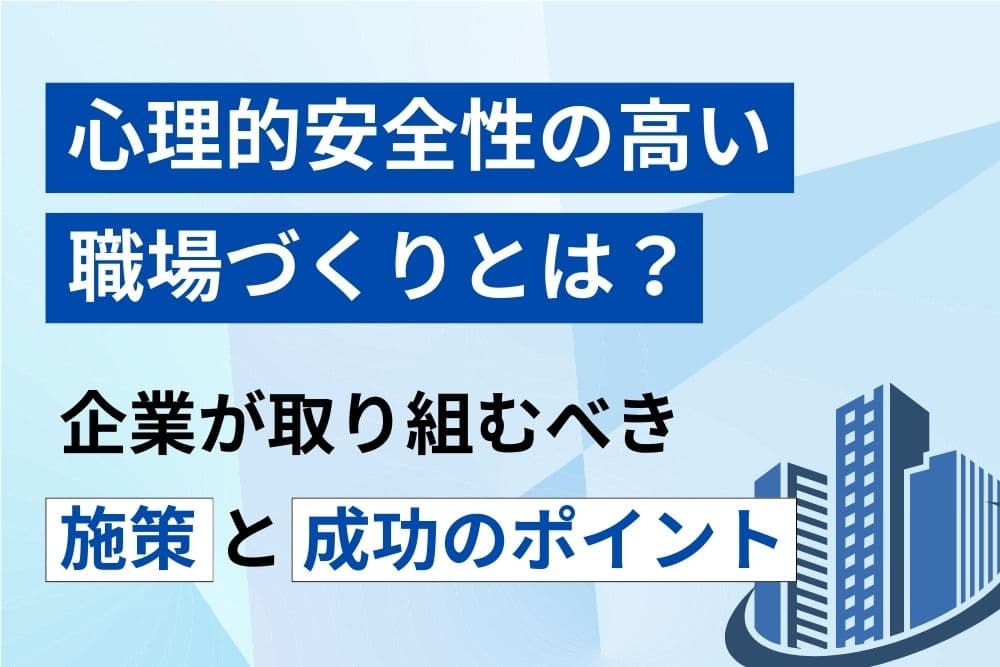お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
企業が知っておくべき退職金制度のメリット・デメリットと導入の要点
 詳細を見る
詳細を見る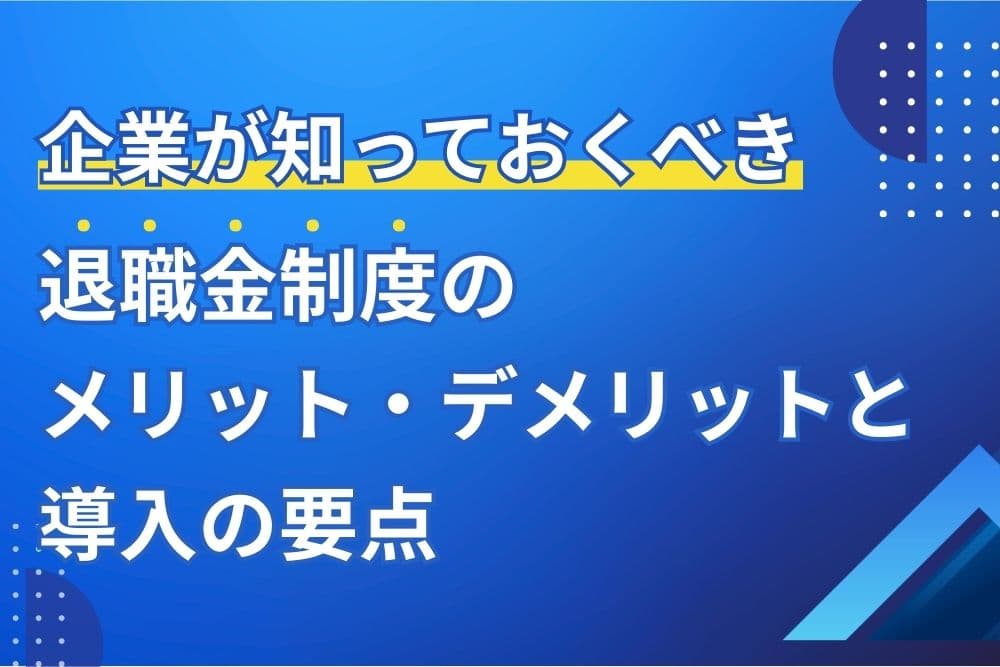
退職金制度とは何か
なぜ、企業は今、退職金制度導入を検討すべきなのか?
退職金制度のメリット
退職金制度のデメリット
退職金制度の種類と特徴
企業にとって「退職金制度」は、従業員の長期的な貢献に報いる重要な福利厚生です。
一方で、制度の維持にはコストや設計上の課題も伴うため、導入を迷う経営者・人事担当者も多いでしょう。
本記事では、退職金制度の基本からメリット・デメリット、導入時のポイントまで専門家の視点で詳しく解説します。自社に適した制度選びや運用の参考にしてください。目次
退職金制度とは何か

「退職金制度」は企業から従業員に対し、退職時に支給される一時金や年金給付の制度です。長年勤めた従業員への功労報償や老後資金の支援として、多くの企業で採用されています。
まずは仕組みや普及状況、日本での歴史的背景について押さえておきましょう。
退職金制度の基本的な仕組み
退職金制度は、従業員が一定の年数勤続して退職する際に、企業があらかじめ定めた算定ルールに基づいて金銭を支給する制度です。
支給額は、
- 勤続年数
- 最終給与額
- 退職理由(自己都合・会社都合・定年など)
によって決まるのが一般的です。
例えば、勤続年数に応じたポイントや係数を用いて計算し、定年退職者には大きな金額を支払う、といった設計になっています。支給形態には一括で支払う「退職一時金」と、年金形式で分割受取する「企業年金」があります。
企業は就業規則や退職金規程でこれらのルールを定め、従業員に周知します。
なお、退職金制度の有無や内容は法律で一律に定められているものではなく、企業が任意に設計できる制度です。つまり極端に言えば「退職金ゼロ」の制度も可能ですが、従業員の安心感や企業イメージを考慮し、多くの企業が何らかの形で用意しています。
支給時には税制上の優遇(退職所得控除)が適用され、従業員にとっては手取り額が増えるメリットがあります。一方、企業側は支給に備えて内部留保を積み立てたり、外部の年金基金に拠出するなど、資金準備と管理が求められます。
関連記事:退職金の制度を徹底解説!企業が導入すべき理由とは?
退職金制度の導入率

では、実際にどの程度の企業が退職金制度を導入しているのでしょうか。
厚生労働省の調査(令和5年就労条件総合調査)によれば、日本企業全体の約75%が何らかの退職給付制度を実施しています。規模別に見ると、大企業ほど導入率が高く、従業員1000人以上の企業では9割超(約90%)が導入しています。
中堅規模(300人以上)でも約88%、中小企業(30~99人規模)でも約70%が制度を設けており、退職金制度は日本の企業に広く定着していると言えます。
さらに制度形態を見ると、退職一時金制度のみ導入している企業が約70%と最多で、企業年金制度のみは約10%、一時金と年金を併用している企業が約20%となっています。
多くの企業がまずはシンプルな一時金制度を採用し、余裕のある企業が年金制度を併せて導入している状況です。また、中小企業向けの共済制度(後述する中小企業退職金共済)を活用しつつ、自社独自の上乗せ退職金を組み合わせるなど、工夫した設計を行う企業も増えています。
日本における歴史的背景と導入の流れ
日本の退職金制度のルーツは江戸時代の「のれん分け」にまで遡ると言われます。当時、奉公人が長年勤め上げて独立する際に、主人が暖簾(のれん)や資金を譲渡した習慣が、退職金の起源とされています。
近代的な退職金制度は明治以降に徐々に整備され、第二次世界大戦後の経済成長期に企業福利厚生の一環として本格的に広まりました。
高度経済成長期には終身雇用と年功序列賃金が一般的となり、その集大成として定年退職時にまとまった退職金を支給する制度がほぼ標準となりました。企業は「退職金規程」を整備し、勤続年数に応じた金額テーブルを設けるようになりました。
また1970年代以降、大企業を中心に退職金の一部を年金形式で支給する企業年金(厚生年金基金や確定給付企業年金など)が普及しはじめます。
しかし、1990年代のバブル崩壊後は、退職金制度を取り巻く環境も変化しました。企業年金では運用悪化による積立不足が問題化し、多くの企業が制度見直しを迫られました。2000年代には確定拠出年金(日本版401k)制度が導入され、従来の企業年金(確定給付型)から移行する企業も増えています。
また、従来あった税制適格退職年金制度(中小企業向け企業年金)は2012年に廃止され、現在は確定給付企業年金か中小企業退職金共済などへの転換が進みました。
このように、日本の退職金制度は時代の雇用慣行や経済状況に応じて進化してきました。伝統的な一時金制度を守り続ける企業がある一方、時代に合わせて年金型や確定拠出型にシフトする企業も増えています。自社の状況に合わせて最適な制度を選ぶことが大切です。
社内の福利厚生、金融リテラシーの向上によるエンゲージメント経営ならマネーリペア
また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。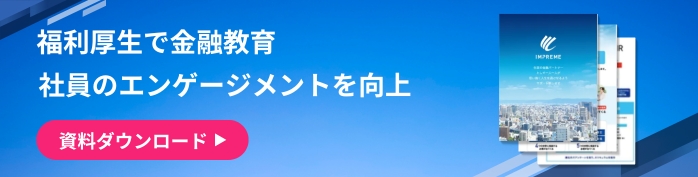
退職金と年金の違い・関係性
退職金制度について考える際に、公的年金や企業年金との違いを整理しておきましょう。まず公的年金(国の年金制度)は、国民全員が加入する老後の所得保障制度であり、企業が支給する退職金とは別物です。
公的年金には国民年金や厚生年金があり、これは法律で加入・拠出が義務付けられています。一方、企業の退職金はあくまで企業任意の制度であり、法定の義務はありません(導入すればその規程に従い支給義務が生じます)。
企業の退職金には、一時金として支給するもの(退職一時金)と、企業年金として分割支給するものがあります。企業年金とは企業が独自に設ける年金制度で、代表的なものに確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)があります。
退職金一時金との関係性としては、企業年金も広義には退職金制度の一種であり、「退職給付」の形式が一括払いか年金払いかの違いと言えます。実際、多くの企業では退職時に「一時金か年金か選択権を与える」ケースもあります。
例えば「一時金で○○万円、もしくは終身年金に移行して年○○万円支給」といった選択肢を提供し、従業員が自分のライフプランに合わせて受取方法を決められるようにしている企業もあります。
まとめると、公的年金は国の制度であり退職金とは別枠で支給されます。
その上で企業は任意に退職金制度(自社積立の一時金や企業年金)を用意し、公的年金を補完する形で従業員の老後資金を支援するのが一般的です。
退職金と年金はいずれも老後の所得になりますが、退職金は勤めた企業からの恩典、年金(公的・企業年金)は保険料拠出に基づく権利という違いがあります。
なぜ、企業は今、退職金制度導入を検討すべきなのか?

近年、働き方や人材市場の変化に伴い、改めて退職金制度の価値が見直されています。ここでは、2020年代の企業経営において退職金制度を導入・整備する意義について考えてみましょう。
人材確保の競争が激化する中、退職金制度が果たす役割やメリットを解説します。
企業ブランディングと人材確保
優秀な人材を採用しようとするとき、その企業の「待遇面の充実度」は重要な判断材料になります。退職金制度があることは、求職者に対して「従業員を大切にする会社」というメッセージを伝えることにつながります。
実際、求人票でも「退職金制度あり」と記載されているだけで、企業イメージがワンランク上がる傾向があります。特に中途採用市場では、同程度の給与提示であれば退職金制度の有無が入社の決め手になるケースも少なくありません。
また、企業ブランディングの観点でも、しっかりとした退職金制度を持つことは社会的信用のアピールになります。
創業間もないベンチャー企業などでは退職金制度が未整備なこともありますが、あえて導入することで「福利厚生に力を入れている会社」として注目を集め、人材確保につなげる戦略も考えられます。長期的に働ける環境を提供できる企業は、人材市場でも魅力的に映るでしょう。
従業員への長期的なインセンティブ
退職金制度は、在籍期間が長くなるほど受取額が大きくなるため、従業員に長期勤務を促すインセンティブとなります。例えば「勤続○年以上で大幅増額」などの制度であれば、「もう少し頑張って勤めよう」という動機付けになるでしょう。
これは企業にとって人材の定着率向上というメリットにつながります。
従業員側から見ても、勤続年数に応じた報酬が約束されていることで将来の見通しが立てやすくなり、安心して働き続けることができます。特に住宅ローンや教育費など人生の大きな支出計画を考える際、「定年時にこれだけの退職金が見込める」というのは大きな心の支えです。
結果として従業員は腰を据えて業務に取り組み、スキル蓄積や社内ノウハウの継承も進みます。
このように、退職金制度は長期的なロイヤリティを高める装置として機能します。一時的なボーナスとは異なり、長いスパンで効いてくるインセンティブであるため、社員のキャリア形成や会社への忠誠心に良い影響を与えます。
エンゲージメント向上による業績への影響

退職金制度の存在は従業員のエンゲージメント(仕事に対する愛着心や熱意)向上にもつながります。企業が従業員の将来を考えてくれているという安心感は、会社への信頼やモチベーションとして跳ね返ってきます。
エンゲージメントの高い社員は生産性が高く、離職率も低い傾向があります。結果的に企業の業績や競争力向上に寄与するでしょう。
また、退職金制度は従業員の家族にも安心感を与えます。家族から見ても「この会社で働き続ければ将来まとまった退職金が得られる」というのは、働き手が会社に留まることを後押しする材料になります。
社員が仕事に集中できる環境(将来の不安が小さい状態)を整えることは、業績面でのプラス効果につながります。
さらに、従業員満足度が向上することで社内の雰囲気やチームワークも良くなり、職場全体のパフォーマンス向上につながる好循環も期待できます。
制度一つで劇的に業績が上がるわけではありませんが、エンゲージメントという土台を支える重要な要素として退職金制度は機能すると言えるでしょう。
節税や社会保険料の削減効果がある
退職金制度の導入は、税務・財務面でも一定のメリットがあります。まず、退職金の支給は税制優遇の対象です。従業員が受け取る退職金には「退職所得控除」が適用され、勤続年数に応じて大きな控除額が設定されています。
結果として、同じ額を給与として受け取るよりも税負担が軽減されるため、従業員にとって有利です。
企業側にとっても、退職金(特に企業年金や確定拠出年金として拠出する部分)は損金算入(経費計上)が認められます。例えば確定給付企業年金に掛金を拠出すれば、その分法人税の課税所得を圧縮できます。
同様に中小企業退職金共済の掛金や企業型確定拠出年金の拠出額も全額損金算入できます。
さらに、社会保険料の面でもメリットがあります。一般に毎月の給与や賞与として支払えば企業は厚生年金保険料・健康保険料の負担が生じますが、退職金として支給する分には社会保険料がかからないため、その分コスト圧縮になります。
極端な例を言えば、給与を少し抑えて退職金に回す設計にすれば、企業・従業員双方で社会保険料の節減が可能です(※制度変更時には従業員理解が必要ですが)。
確定拠出年金(DC)では、拠出額が給与ではなく福利厚生費扱いとなるため、同額を給与支給した場合と比較して社会保険料負担が抑えられる効果があります。
このように、退職金制度は財務戦略やコスト管理のツールとしてもうまく活用できます。ただし注意点として、退職金の損金算入は支給時または拠出時であり、社内で引当金を積んでいるだけでは税効果が得られない場合もあります。
適切な制度(企業年金や共済など)を利用することで、初めて節税効果が発揮されます。
退職勧奨時のトラブルを防止する
経営環境の変化や人員構成の適正化のために、企業が早期退職制度を募集したり、特定の従業員に退職を勧奨(希望退職の打診)する場面もあります。その際、明確な退職金制度があることはトラブル防止に役立ちます。
退職金制度がない企業ですと、個別の退職交渉で「いくら支払うか」をゼロから話し合う必要があり、条件次第では不公平感や紛争の火種となりかねません。
一方、制度が整っていれば「規程に沿った退職金+αの割増金」といった形で提示しやすく、基準が明確な分、従業員も納得しやすくなります。割増退職金の算定も、通常の退職金を基に○割増しなど合理的な根拠で提示できるため、公平性を説明しやすくなります。
また、仮に解雇や希望退職で揉めた場合でも、最低限の退職金は支払うことで訴訟リスクの低減や円満解決の余地が生まれます。退職金は労働者にとって長年の対価であるという社会通念があるため、これを用意しているか否かでトラブル時の印象も大きく異なります。
このように、退職金制度は「いざ」というときのセーフティネットにもなります。会社都合退職の際の上乗せ金も含め、制度として体系立てておくことで、想定外の人事リスクに備えることができます。
退職金制度の導入や運用でお悩みの企業様は、専属ファイナンシャルプランナー導入サービス「マネーリペア」の福利厚生・退職金サポートにご相談ください。ファイナンシャルプランナーなど専門家が、退職金制度の位置付けや従業員へのメリットの伝え方まで包括的にアドバイスいたします。福利厚生の充実による人材確保策として、マネーリペアが貴社をサポートします。
また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
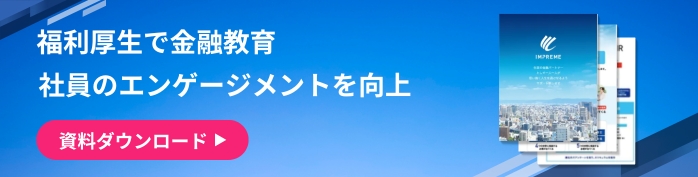
退職金制度のメリット

ここまで触れたように、退職金制度は人材面・会社経営面で様々なプラス効果をもたらします。改めて、企業が退職金制度を設ける主なメリットを整理します。
優秀な人材の流出防止と定着率向上
退職金制度があることで、社員は長く勤めるインセンティブを得られます。特に優秀な人材ほど社外から誘いを受ける機会も多いものですが、在籍年数に応じて大きな退職金が見込める場合、「このまま今の会社でキャリアを積もう」という判断につながりやすくなります。
結果として人材の流出防止に効果があります。
また、勤続年数が長くなるほど社内に知見が蓄積され、チームの安定感も増します。退職金制度はその定着率向上を裏側で支える存在です。企業にとって、採用・育成した人材が長く戦力として活躍してくれることは大きな利益です。
退職や転職が減れば、採用コストや引継ぎに伴う生産性低下も抑えられるでしょう。
さらに、社員同士の信頼関係構築にも寄与します。長く勤める社員が増えることで職場の人間関係が安定し、組織としての結束力が高まります。優秀な社員が定着する会社は、その人材を軸にさらなる優秀層が集まるという好循環も生み出しやすくなります。
従業員モチベーションの継続的維持
人は将来に希望が持てるとき、高いモチベーションを保ちやすいものです。退職金制度によって「この会社で頑張り続ければ将来○○万円の退職金がもらえる」という具体的な見通しが立つことは、日々の仕事への励みになります。
特に中堅・ベテラン社員にとって、退職金はキャリアの総決算とも言えるものです。その獲得を目標の一つとして据えることで、勤労意欲が長期にわたり持続しやすくなります。
モチベーション維持の観点では、定年まで働き切ることへの安心感も大きいでしょう。最近では定年延長や再雇用制度も普及していますが、それでも「定年退職して退職金をもらう」という節目は働く人のモチベーションサイクルに組み込まれています。
仮に50代以降で業務内容が変わったり第一線を退く場面があっても、「最後に退職金があるから頑張ろう」と踏ん張れる心理的支えになります。
さらに、退職金制度は企業への愛着心を育む効果もあります。「この会社に貢献した分だけきちんと報いてくれる」という信頼感は、日々の仕事の質にも現れます。
目先の成果だけでなく長期的視野で業務改善や後輩育成に取り組む社員が増えれば、組織全体の生産性向上につながります。退職金制度は、社員のモチベーションを継続的に高めるエンジンとして機能するのです。
他社との差別化と採用活動でのアピール
福利厚生が充実していることは、企業にとって大きな差別化要因です。特に退職金制度は見えにくい部分ではありますが、「ない会社」と「ある会社」の印象差は歴然としています。同業他社に先駆けて手厚い退職金制度を整備すれば、採用市場でのアピールポイントとなり得ます。
例えばベンチャー企業が優秀なエンジニアを採用しようとする際、通常は大企業に比べ不利と言われますが、退職金制度など長期インセンティブを用意することで「安心して参加できるベンチャー」というポジショニングを打ち出せます。
また地方企業が都市部企業と人材を奪い合う場合でも、「地元で腰を据えて働けて、退職金もきちんともらえる職場です」というアピールは有効でしょう。
さらに、大学新卒の採用活動においても、学生や親御さんから見て退職金制度がある会社は魅力的に映ります。総合的な待遇面で他社をリードできれば、優秀な学生を囲い込むことができます。
定年まで勤め上げるケースが減っているとはいえ、「最終的な待遇がしっかりしている」ことはやはり企業選びの重要な尺度です。
総じて、退職金制度は対外的な企業価値のアピールにつながります。商品やサービスで差別化するのはもちろん大事ですが、人材獲得競争においては福利厚生面での差別化も無視できません。その中で退職金制度は伝統的かつ強力な武器となります。
退職金制度のデメリット

一方で、退職金制度には導入・維持に際して注意すべきデメリットも存在します。時代や経営状況によっては、デメリットがメリットを上回るケースもあり得ます。ここでは主な課題を整理し、導入判断や見直し検討の材料としましょう。
人材流動化時代では優秀な人材が退職金比重が大きい企業に転職したいと考えない可能性
近年は転職が一般化し、特に若手~中堅の優秀な人材ほどキャリアアップのために複数社を経験する傾向があります。そのような人材にとって、退職金制度のメリットは相対的に小さくなりがちです。
勤続20年・30年でようやく得られる将来の報酬よりも、目先の年収アップや魅力的な仕事を優先するケースが多いからです。
その結果、退職金を厚く用意している企業であっても、「自分は長く勤めるつもりがないから関係ない」と捉えられてしまえば、人材獲得競争で不利になる可能性があります。
特にスタートアップ思考や成果主義志向の強い優秀層にとっては、退職金に資源を割くくらいなら今の給与や成長機会に還元してほしいと感じることもあるでしょう。
退職金比率が高い伝統的大企業よりも、退職金なしでもストックオプションや高年俸を提示するベンチャーに人材が流れるといった現象も起こりえます。
また、退職金制度があるがゆえに社員が「長く居る」ことを期待される企業文化になってしまうと、向上心の高い人材には窮屈に映ることも考えられます。
人材の流動性が前提となる時代においては、優秀な人材ほど退職金以外の部分(仕事内容・環境・処遇の柔軟性)を重視する傾向があるため、制度の重みづけを誤るとミスマッチを招く恐れがあります。
企業負担の増加とキャッシュフローリスク
退職金制度を維持する最大の課題は、企業の財務負担です。特に従業員数が多い企業や定年退職者が集中する時期には、一度に巨額の資金が流出します。適切に準備していないと、支給のたびにキャッシュフローを圧迫し、最悪の場合資金繰り悪化を招くリスクがあります。
例えば、長年業績が好調で社員も定着していた会社が、創業以来初めて大量の定年退職者を出すタイミングになり、退職金の支払いが重荷になるケースがあります。退職者一人当たり数千万円規模の支給が必要となれば、10人退職するだけで数億円の支出です。
黒字倒産という言葉があるように、利益計上上は問題なくても退職金支払い資金を用意できずに困窮する可能性も否定できません。
また、退職金債務は将来的な支払い義務として企業のバランスシートに影響します。会計上は退職給付引当金(または退職給付に係る負債)として計上され、企業の財務指標を悪化させる一因にもなります。
特に確定給付型の企業年金を導入している場合、専門家の計算により将来債務額が積算されますが、業績悪化や金利変動で負債が膨らむこともあり得ます。
キャッシュフローリスクの観点では、早期退職制度の実施などイレギュラーな大量支給にも注意が必要です。本来定年まで分散するはずの退職金支払いが特定年度に集中すると、資金調達が必要になることもあります。
このように、退職金制度は企業に長期の金銭的コミットメントを要求するため、経営環境によっては負担が重くのしかかります。制度導入にあたっては、長期シミュレーションを行い、持続可能な設計にすることが不可欠です。
制度設計の複雑化と運用コスト
一見シンプルに思える退職金制度ですが、実際に構築しようとすると決めるべき事項が多岐にわたり、制度設計が複雑です。例えば以下のようなポイントを検討しなければなりません。
- 支給水準の決定
勤続何年でいくら支給するか、役職や等級で差をつけるか、自己都合退職は何割減額するか、など具体的な金額テーブル作り。
- 資金準備方法
社内預金で積立てるか、生命保険や年金基金に外部積立するか、退職金共済に加入するか。
- 併用制度
一時金と年金を併用するか、確定給付と確定拠出を組み合わせるか、など制度の複合運用。
- 他の人事制度との整合
賃金カーブや定年延長とのバランス、早期退職優遇制度との関係など。
これらを自社に最適化するには、相当の専門知識と手間が必要です。大企業であれば人事や財務の専門部門がシミュレーションを重ねて決定しますが、中小企業では社労士やコンサルタントに相談しながら進めるケースも多いでしょう。
当然、そのためのコンサル費用やシステム構築コストも発生します。また、一度制度を設計して終わりではなく、継続的な運用管理が求められます。
従業員ごとの勤続年数管理や支給額試算、退職金引当金の会計処理、企業年金であれば運用状況のモニタリング、確定拠出年金であれば加入者教育と運営管理機関とのやり取りなど、事務作業や管理コストがかかります。
制度内容が複雑になるほど社員への説明も難しくなり、「自分の退職金は結局いくらもらえるのか分からない」といった不満・不安が生じる恐れもあります。そのため、あまりに入り組んだ制度は逆効果になる可能性もあるのです。
以上より、退職金制度導入には見えないコストとして設計・運用の手間が存在します。社内リソースが限られている場合、シンプルで運用しやすい制度からスタートするなどの工夫が必要でしょう。
就業規則や法改正への対応リスク
退職金制度は一度決めたら永遠に固定というわけにはいきません。経営方針の転換や外部環境の変化に応じて、就業規則や制度内容の見直しを行う必要が出てくることがあります。その際の変更対応には労使間の調整や法的なリスクが伴います。
まず、退職金に関する規定は就業規則や労働契約の一部となるため、不利益変更をする場合は慎重な手続きが求められます。例えば「退職金計算のベースを基本給から定額制に変更し、将来的な支給額を引き下げる」ような改定を行うと、従業員にとってデメリットとなります。
その場合、労働契約法の規定上、労働者の同意や合理的な理由の説明が必要とされ、下手をすると訴訟リスクを招きかねません。
また、法改正による影響も無視できません。今後、退職金に関わる税制が変更されたり、企業年金に関する法律(厚生年金基金の廃止など過去にも例あり)が変わったりすれば、それに合わせて制度運用を変更しなければなりません。
例えば確定拠出年金の拠出限度額が改定された場合、企業型DCを導入している企業は規約変更が必要になります。
このように、退職金制度は一度作って終わりではなく、常にアップデートを迫られる可能性があります。その対応を誤ると法的トラブルや従業員の士気低下につながりかねないため、常にアンテナを張り、専門家の助言を得ながら適切に制度管理することが重要です。
退職金制度の種類と特徴

一口に退職金制度と言っても、運用方法や仕組みによっていくつかの種類に分かれます。それぞれメリット・デメリットが異なり、企業規模や経営方針に応じて選択する必要があります。ここでは代表的な4種類の退職金制度について、その仕組みと特徴を解説します。
1.退職一時金制度の仕組みとメリット・デメリット
退職一時金制度とは、従業員が退職する際に一度きりでまとまった金額を支給する退職金制度です。もっともシンプルで伝統的な方式であり、日本企業の多くが採用しています。
具体的には、就業規則や退職金規程で勤続年数や退職理由に応じた支給額テーブル(例えば基準額×勤続年数係数×支給率など)を定めておき、退職時にその計算結果を一括支払いします。
- メリット
制度設計が比較的簡単で柔軟性があります。社内積立(内部留保)で準備する場合、運用の自由度が高く、企業の裁量で増減や特別加算も行いやすいです。
また社員側にとっては退職時に大きな資金を得られるため、住宅ローン返済や起業資金など一時的な資金需要に応えられます。税制上も退職所得控除が適用され、手取り額の優遇があります。
- デメリット
企業にとっては支払い負担が一時期に集中する点です。計画的に積立していないと、大量退職時に財務を圧迫します。内部留保で積立ても、その間は税務上損金にできず資金効率が悪い面があります。
また、制度としては「長く勤めないともらえない」ため、短期間で辞める人には恩恵がなく、逆に不公平感を招く可能性もあります。社員から見ると、退職まで受け取れないため実感が薄く、若手にはインセンティブになりにくいという側面もあります。
2.確定給付企業年金制度の仕組みとメリット・デメリット
確定給付企業年金(Defined Benefit: DB)は、退職後に支給する年金や一時金の額(給付額)があらかじめ確定している企業年金制度です。企業はその給付を賄うための掛金を外部機関(信託銀行や保険会社など)に拠出し、資金運用を行います。
将来の給付設計に基づき、必要な掛金額を算出して積立てる仕組みです。
- メリット
従業員が受け取る金額が約束されているため、老後資金の柱として安心感があります。例えば「勤続30年で定年退職したら月額○万円の年金を10年間支給」など明確に保証されます。
企業側は掛金拠出時に損金算入でき、計画的に費用処理できるメリットがあります(退職一時金と違い、積立時点で税務上経費処理可能)。また、専門の基金や保険を活用することで計画的に資産運用でき、社内で引当金を抱える必要が減る利点もあります。
- デメリット
最大のデメリットは運用リスクが企業にあることです。予定利率や賃金上昇率の想定通りに資産運用ができず不足が生じた場合、企業が不足分を補填しなければなりません。バブル崩壊後にこの補填負担が重荷となった企業が続出しました。
また、制度管理が複雑で専門知識が必要なため、中小企業ではハードルが高い面があります(そのため中小向けの基金「はぐくみ企業年金」など共同でDBを運営する仕組みもあります)。さらに、一度約束した給付を減額することは困難で、企業に将来債務として固定的な負担が生じます。
3.企業型確定拠出年金制度の仕組みとメリット・デメリット
企業型確定拠出年金(Defined Contribution: DC)は、企業が拠出する掛金額が確定しており、最終的な給付額は運用の結果によって変動する制度です。企業は毎月または毎年、一定額を各従業員の個人年金口座に拠出し、従業員自身が運用方法を選択します。
米国の401(k)に相当する制度で、日本でも2001年に導入されました。
- メリット
企業側にとってはコストが明確かつ限定されます。拠出額さえ支払えば、その後の運用結果による追加負担はありません。掛金は損金算入でき、給与扱いではないため社会保険料負担も増えません。
従業員側は自分の口座として資産が蓄積され、転職時には個人型DC(iDeCo)に移管するなどポータビリティ(持ち運び)が高いです。投資教育を受けながら資産形成でき、運用が上手くいけば給付額が大きく増える可能性もあります。将来の受け取りも一時金か年金か選べ、税制優遇も退職金同様に受けられます。
- デメリット
運用リスクは従業員本人にあるため、加入者の金融リテラシーによって老後資金に差が出ます。運用がうまくいかなかった場合、想定より少ない額しかもらえず不満に感じる恐れがあります。
そのため企業は法律上、加入者への投資教育や情報提供を行う義務がありますが、これにもコストや手間がかかります。また、社員によっては「自分で運用なんて無理」「元本保証がないなら嫌だ」という声もあり、理解を得るまで時間がかかることもあります。
さらに、制度運営には信託銀行や証券会社など運営管理機関との契約が必要で、選定商品や手数料の検討など導入時の事務負担もあります。
4.中小企業退職金共済の仕組みとメリット・デメリット

中小企業退職金共済(中退共)は、国が運営する中小企業向けの退職金制度です。中小企業の事業主がこの共済制度に加入し、従業員ごとに毎月一定額の掛金を納付することで、従業員の退職時に共済から退職金が直接支給されます。
中退共は独立行政法人勤労者退職金共済機構が管轄し、法律(中小企業退職金共済法)に基づいて運営されています。
- メリット
中小企業でも簡便に退職金制度を導入できるのが最大のメリットです。共済への加入手続きを行い掛金を払うだけで、社内に引当金を積む必要も複雑な計算も不要です。掛金月額は従業員ごとに5,000円から30,000円までの16区分から選べ、途中で増額も可能な柔軟性があります。
掛金は全額損金算入でき、さらに新規加入時には国から掛金の一部助成(加入後一定期間、掛金の半額を国が補助)も受けられるため、中小企業に手厚い優遇措置となっています。
従業員にとっても国が管理する制度なので受給権が確実に保全され、安心感があります。仮に会社が倒産しても、中退共から退職金は支払われます。
- デメリット
掛金に対する給付金額は中退共の共通ルールで決まるため、企業独自の退職金制度に比べカスタマイズ性が低いです。例えば業績連動で特別加算したり、役職別に大幅に差をつける、といった設計はできません(あくまで掛金と勤続年数に応じた共済金額のみ)。
また、基本的に全従業員を共済に加入させる必要があり、一部の社員だけ対象外にすることはできません(短時間労働者の特例はあります)。給付は原則一時金で支払われ、年金形式にはできない(希望すれば一部年金化は可能ですが限定的)ため、企業年金のような継続受給オプションは弱いです。
さらに、加入対象は中小企業に限定され、一定規模以上に成長した場合は新規加入が認められなくなる点にも注意が必要です。
主要な退職金制度4種の特徴を見てきました。それぞれ「誰が運用リスクを負うか」「企業負担がどう発生するか」が異なります。自社の規模や財政状況、人材戦略に合った制度を選ぶことが重要です。
中小企業であれば中退共+社内上乗せ、大企業であればDBとDCの併用など、複数の制度を組み合わせることも可能です。
関連記事:中小企業の退職金制度を解説!中退共などは活用すべきなのか?
退職金制度の導入方法
自社に退職金制度を導入しようと決めた場合、具体的にどのようなステップを踏めば良いのでしょうか。新規に制度を導入するケースと、既存制度を見直すケースに分けてポイントを解説します。計画的かつ丁寧な準備を行うことで、スムーズな制度導入が可能になります。
まず新規導入の一般的な流れは以下のとおりです。
自社の方針決定
経営陣で退職金制度導入の目的(人材定着、企業イメージ向上など)と予算感を確認し、どの程度の制度を目指すか方針を固めます。ここで上で説明した制度種類から概ねの方向性(例:中退共に加入+一定額上乗せ)を検討します。
制度設計の詳細検討
人事担当者や専門家とともに、支給水準、計算方法、対象範囲など細部を詰めます。複数案を作成し、将来の費用シミュレーションも行って、最適案を選定します。
就業規則・退職金規程の作成
決定した制度内容を文章化し、社内規程として整備します。就業規則の一部または付属規程として「退職金規程」を作成し、支給条件や計算式を明記します。
労使協議・届出
新たに退職金制度を設ける場合は従業員にとって有利な変更ですので、労使トラブルは少ないはずですが、念のため労働組合や従業員代表に意見を聞き、合意形成します。就業規則として定めた場合、所轄の労働基準監督署へ届出を行います。
社内周知
全従業員に対し、新設する退職金制度の内容を説明します。制度開始日や適用範囲、将来の受取額試算の例などを示し、従業員に制度を理解・納得してもらいます。
運用開始
規程施行日以降の勤続について退職金が発生するようになります。外部機関を利用する場合は、事前に契約締結やシステム設定を済ませ、掛金拠出などの運用をスタートします。
このように、導入には制度設計と社内手続き、従業員説明という3つの軸で準備が必要です。中小企業で専門知識が足りない場合、社会保険労務士や中退共の相談窓口など外部の力を借りることも有効でしょう。
既存の退職金制度を変更する方法
既に退職金制度がある企業が、その制度を変更・見直しするケースも多々あります。例えば「従来の退職金を減額して確定拠出年金に移行する」「中退共から自社制度に切り替える」「定年延長に合わせて計算方法を調整する」といったケースです。
既存制度の変更は、新規導入以上に慎重な対応が求められます。
変更方法のポイントは次のとおりです。
労働条件の不利益変更に注意
退職金制度の改定で従業員にとって不利になる部分がある場合(例えば将来の受取額が減る、支給要件が厳しくなる等)は、労働契約法上の不利益変更となります。
その際は変更の必要性や合理性を丁寧に説明し、労働組合や従業員の納得を得る努力が不可欠です。一方的に強行すると紛争に発展しかねません。場合によっては経過措置として「現従業員には旧制度分を保障し、新入社員から新制度適用」などソフトランディング策を検討します。
制度移行のテクニック
例えば確定給付から確定拠出への移行では、一旦従業員の退職金債権を確定させて、その分のポイントを確定拠出年金口座に移換する「カッシュバランスプラン」的な手法を用いることがあります。
専門的な計算が必要ですが、公平に移行するための工夫です。また、中退共から自社制度に変える場合は、中退共を解約して得た積立金を元手に社内準備金に充当するなど、資金面の段取りも重要です。
従業員への十分な説明
制度変更時には、対象となる全従業員に向けて説明会や書面での案内を行います。変更の理由(例:「企業年金の安定運用が難しくなったため確定拠出に切り替えます」)、新旧制度の比較、従業員への影響などを分かりやすく示し、不安や疑問を解消します。
特にマイナス面がある場合は、代替措置(例:「基本給に退職金相当分を上乗せ支給します」など)も含め誠意を持って説明し、理解を求めます。
必要な手続き
就業規則の変更や企業年金規約の変更が伴う場合、所定の手続き(労基署届出や厚生労働省への認可申請など)を行います。確定給付企業年金から確定拠出年金への移行などは関係当局の認可が必要となり、実施までに時間を要する点にも注意が必要です。
このように、既存制度の変更はステークホルダーとの調整と制度間の橋渡しがカギとなります。社員に不利益を強いる場合には、その影響を最小限に抑える創意工夫と、将来に向けた代替メリットの提示が求められます。
退職金制度導入・見直しのポイント

退職金制度を新たに導入する場合でも、既存制度を見直す場合でも、検討段階で押さえておきたいポイントがあります。自社の戦略や従業員ニーズにマッチした制度にするため、以下の観点をチェックしておきましょう。
自社の人事戦略・人件費構造との整合性
退職金制度は、人事制度全体の中で整合性を保つ必要があります。まず自社の人事戦略を振り返り、退職金制度に何を期待するのかを明確にしましょう。例えば「定年まで勤める社員を増やしたい」のか「中堅層の離職を防ぎたい」のかによって、制度設計の力点も変わります。
若手育成に注力したい会社なら、勤続5年10年時点で一時金を支給する制度を盛り込むのも一案です。
また、人件費全体のバランスも考慮が必要です。退職金に厚く振りすぎると、現役期間の給与が相対的に低くなり、人材競争で不利になるかもしれません。逆に給与ばかり高くて退職金ゼロでは定着に不安が残ります。
給与・賞与・福利厚生・退職金といったトータルの人件費配分を検討し、自社にとって最適なバランスを探ることが重要です。
さらに、自社の財務状況を踏まえ、長期的に支払える水準に設定することも肝心です。制度導入前に将来の退職者数予測と支給総額シミュレーションを行い、無理のない原資計画を立てましょう。
業績連動部分を組み込むなどして、業況に応じ柔軟に負担調整できる仕組みにしておくのも有効です。
要は、退職金制度を単独で考えるのではなく、自社の人事・経営戦略の一部として位置付けることです。他の報酬制度との整合性が取れてこそ、効果的に機能する退職金制度となります。
就業規則や契約書への明確化とトラブル防止
退職金制度を導入したら、それを明文化しておくことが極めて重要です。多くの企業では就業規則に「退職手当規程」ないし退職金に関する項目を設けています。ここに支給対象者、算定方法、支給時期、減額事由などを明確に定め、従業員に周知します。
制度が明文化されていないと、将来「もらえると思っていたのに貰えなかった」「金額計算がおかしいのではないか」などのトラブルが起こり得ます。
例えば自己都合退職の場合に退職金を支給しない方針であれば、その旨をはっきり規程に書いておかなければ後で紛争になる可能性があります。逆に規程で「勤続○年以上は支給」と書いてあるのに出し渋ることも許されません。
また、管理職や契約社員など雇用形態によって扱いを変える場合も、契約書や雇用条件通知書にて個別に退職金の有無を明示しておくことが必要です。そうしないと、後から「自分も正社員同様にもらえるはずだ」と主張されるリスクがあります。
退職金制度は長期にわたる約束ですから、法的拘束力のあるルールとして整備し、誰にとっても分かりやすく透明性を担保することが肝心です。その際、専門家のレビューを受けておくと安心でしょう。
就業規則の不備は労務トラブルの温床となりますので、明確なルール作りと周知徹底でトラブル発生を未然に防ぐことができます。
従業員への十分な説明・コミュニケーション体制
どんなに良い退職金制度を作っても、従業員に理解されていなければ宝の持ち腐れです。制度導入時や変更時にはもちろん、その後も継続的に従業員への説明・コミュニケーションを図ることが大切です。
導入時には説明会を開き、制度の目的や内容、従業員にもたらすメリットを丁寧に伝えましょう。特に若手社員には退職金の価値が実感しにくいので、「例えば○年勤めると○○万円受け取れます」と具体例を示すなどして関心を持ってもらいます。
質疑応答の場を設け、不明点を解消することも重要です。
また、就業規則の配布だけでは読み込まれない可能性もあるため、わかりやすいガイド資料や社内FAQを用意すると良いでしょう。「退職金はいくら貰えるの?」「途中で辞めたらどうなる?」といった疑問に答える資料があれば、社員も安心できます。
運用開始後も、定期的に制度をリマインドしたり、新入社員研修で説明したりといった継続的なコミュニケーションを行いましょう。社員がキャリアの節目(結婚、住宅購入など)で将来の退職金額を知りたいと思ったときに、気軽に相談できる窓口を設けておくのも親切です。
人事部内に問い合わせ対応フローを整備しておけば、「退職金について聞きたいけど誰に聞けば…」という状況を避けられます。
従業員に制度を十分理解してもらうことで、会社からの保障を実感し、より安心して働いてもらえます。双方向のコミュニケーションを大事にし、疑問や不安には真摯に答える姿勢が、制度定着と従業員満足度向上につながります。
退職金制度を活用する上での注意点
制度を導入して終わりではなく、実際にそれを有効活用していく段階での留意点もいくつかあります。不公平感のない運用、法改正への柔軟な対応、そして経営層と人事部門の協力体制など、制度を継続的に活かすためのポイントを見ていきましょう。
不公平感を生まない評価制度との連動
退職金制度は勤続年数など客観的な指標で計算されることが多く、基本的には公平な仕組みです。しかし、社員が感じる公平感という意味では注意が必要です。
例えば、「成果を出している人もそうでない人も、同じ年数いれば同じ退職金」という設計の場合、高業績者が不満を覚える可能性があります。自分は人一倍貢献したのに、さほど成果を上げていない同僚と退職金が同額では報われない、といった心理です。
この対策として、退職金制度と人事評価制度をある程度連動させることが考えられます。一例として、役職や最終職位で退職金額に差をつける方法があります。
役職は通常評価・昇進と連動していますから、最終的に管理職まで昇格した人には基本給が高く退職金も多くなるなど、間接的に評価が退職金に反映されます。また、ポイント制退職金制度であれば、毎年の人事評価に応じて付与ポイントを加算する仕組みを組み込むことも可能です。
これにより高評価の社員は多くのポイント=退職金を積み上げられるようになり、納得感が増すでしょう。
他方、極端に評価連動を強めすぎると、今度は退職金本来の趣旨(長年の勤労への功労報償)が薄れ、不安定さが増してしまいます。あくまで一定の範囲で調整することがポイントです。
例えば「勤続年数の要素8割+評価要素2割」程度にとどめ、基本は勤続重視だが多少は功績も考慮する、といったバランスが現実的です。
要は、会社の中で「この退職金制度は公正だ」と思われることが大切です。そのために、他の評価・報酬制度との整合を図り、社員が納得できる仕掛けを盛り込むことが求められます。
税制改正や法規制への対応策
退職金制度を取り巻く外部環境は、将来的に変化しうるものとして注視しておく必要があります。特に税制や関連法規の改正は定期的にチェックし、それに合わせて制度を微調整することが重要です。
例えば税制面では、退職所得控除額や課税方法が見直される可能性があります。現行制度では退職金の2分の1課税など手厚い優遇がありますが、将来この優遇が縮小されるようなことがあれば、従業員の手取り額に影響し、制度の魅力にも関わります。
その際には企業として何らかの補填策や別の福利厚生強化を検討する必要が出てくるかもしれません。
また、企業年金関連法の改正も時々起こります。過去には確定給付企業年金の規制緩和や、確定拠出年金の加入可能年齢拡大などが行われてきました。
例えば今後、企業型DCの拠出限度額が引き上げられれば、それを活用して退職金相当額を増額拠出するチャンスになりますし、逆に法改正で想定外の追加コストが発生することもあり得ます。
さらに、労働法制の変化(定年延長義務化など)があれば、退職金支給タイミングや計算式の変更を迫られます。例えば定年が65歳に延長されれば、60歳時点での退職金支給を廃止し65歳支給に統一する、あるいは60歳時点で一部支給・65歳で残額支給にする等の見直しが要るでしょう。
このように、制度運用担当者や経営陣は最新の制度変更情報にアンテナを張り、シナリオを用意しておくことが大切です。必要に応じて社労士や年金コンサルタントに相談し、タイムリーに就業規則や規約の改定を行える体制を整えておきましょう。
経営層と人事部門の連携・モニタリング体制
退職金制度は長期にわたる企業のコミットメントであり、経営戦略と直結する側面もあります。そのため、経営層と人事・労務部門の密接な連携が不可欠です。導入時だけでなく、運用フェーズにおいても定期的なモニタリングを行い、状況を共有することが望まれます。
まず、毎期の決算や中期経営計画の中で、退職給付に関する指標を確認しましょう。退職給付引当金の残高、今後◯年間の退職者予測と支給予定額などをアップデートし、財務インパクトをチェックします。
これらは経営会議の議題に上げ、トップマネジメントが把握しておくべき情報です。とりわけ業績悪化局面では早めに状況を共有し、必要なら制度変更や早期退職募集といった大きな判断も経営層で議論できるようにしておきます。
人事部門は、従業員の声やエンゲージメント指標について経営層にフィードバックしましょう。退職金制度に対する社員の満足度や、新卒・中途採用時の応募者からの反応など、現場の情報は経営判断に役立ちます。
「うちの退職金制度は転職市場で評価されています」「逆に若手には響いていないようです」といった報告をすることで、制度のあり方を定期的に見直すきっかけになります。
また、制度に問題が起きた時の対処フローも決めておきます。例えば計算ミスや支給漏れなどが発覚した際の調査・是正・社内説明の手順、予算を超える支給が必要になった際の財務部門との調整などです。
経理・財務部門とも連携し、退職金支払いの資金計画や年次予算をきめ細かく管理することも大切です。
このように、退職金制度は会社全体で見守り育てていくものです。経営陣のコミットメント、人事・労務の専門知識、財務の裏付けが三位一体となって初めて、制度が安定的に運用されます。
定期的なモニタリングとチーム連携で、時代の変化や会社の成長に合わせたベストな制度を維持していきましょう。
退職金制度まとめ
退職金制度は、企業と従業員の双方にとって長期的な安心とメリットをもたらす重要な仕組みです。企業側には人材の定着や採用力向上、税務上のメリットがあり、従業員側には老後資金の確保や精神的な安定感につながります。
しかしその反面、制度維持のコストや時代に合わない制度設計によるデメリットも存在します。
本記事では退職金制度の基本から種類ごとの特徴、導入・運用のポイント、そして実際によくある疑問への回答まで幅広く解説しました。
退職金制度を有効な人材マネジメントツールとするため、経営トップから現場まで一丸となって育てていく意識が求められます。時代の変化に合わせて柔軟に制度をアップデートしながら、従業員にとって魅力的で企業にとって負担過大とならないバランスを追求しましょう。
退職金制度は社員への最大の感謝の形でもあります。「あなたの貢献に報いたい」という企業の思いが形になったものです。そうした思いを込めた制度を運用し続けることで、社員のエンゲージメントが高まり、結果的に企業の成長発展にもつながるでしょう。
長期的視野に立った人事戦略の一環として、退職金制度の導入・活用を前向きに検討してみてください。
退職金制度の導入や運用、従業員への説明に不安がある企業様は、ぜひマネーリペアのサービスをご利用ください。マネーリペアは従業員の金融リテラシー向上を支援する福利厚生サービスで、退職金や年金、資産形成に関するセミナーや個別相談を提供しています。
専門家のアドバイスにより、社員の将来不安を解消し離職率低下につながった事例も多数ございます。従業員の安心と会社の活性化のために、マネーリペアがお力になります。資料請求や無料相談もお気軽にお申し込みください。
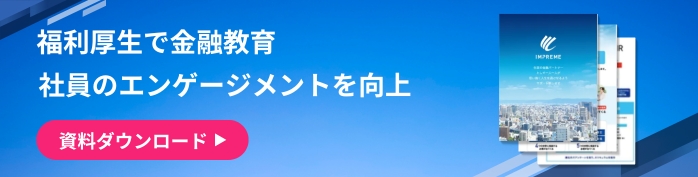

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。