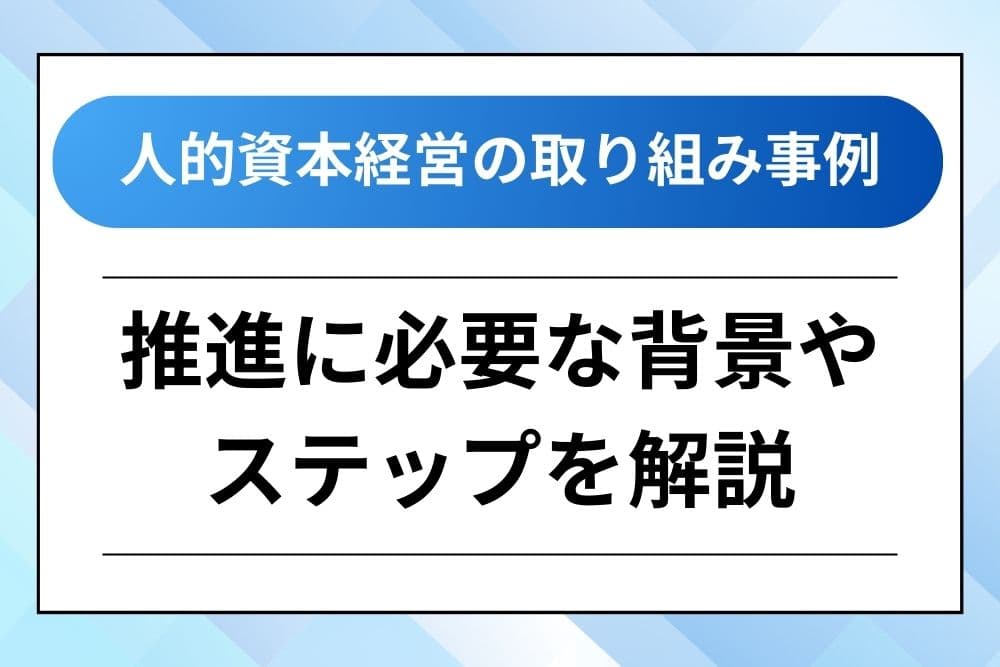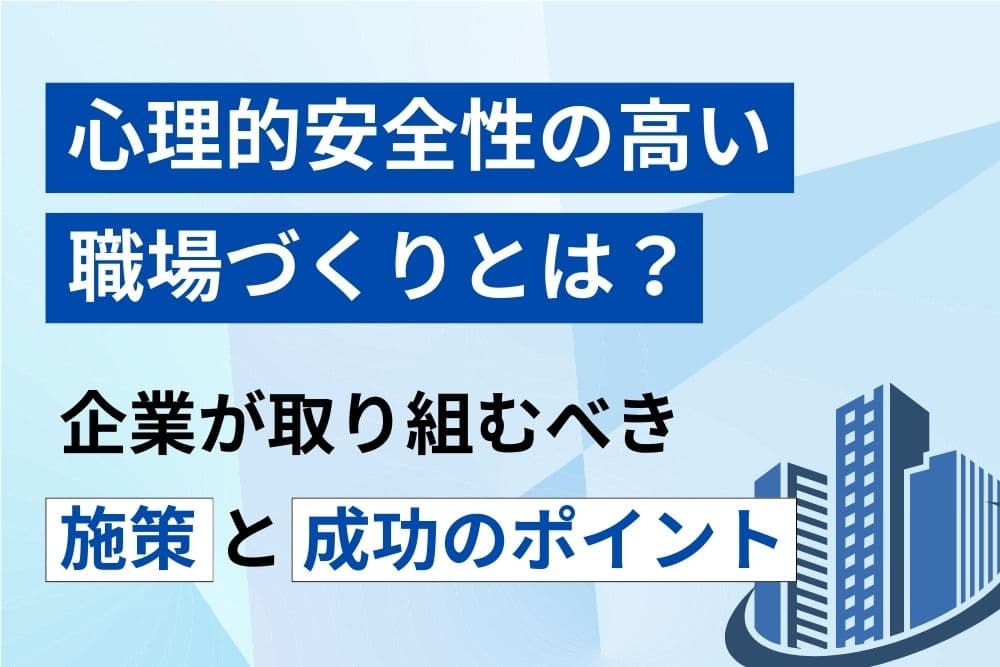お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
マネーリテラシーとは?金融のプロが教える身につけるべき最低限知識
 詳細を見る
詳細を見る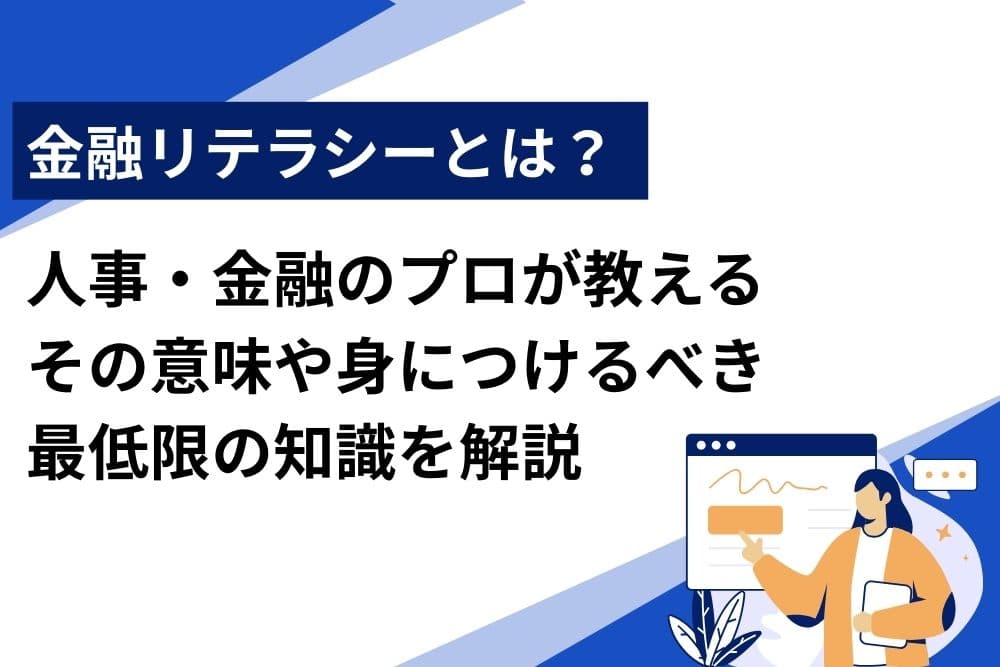
金融リテラシー(マネーリテラシー)とは何か
「金融リテラシー(マネーリテラシー)」はなぜ必要なのか
政府が提唱する最低限身に付けておきたい「金融リテラシー」
マネーリテラシーを構成する要素
金融リテラシー(マネーリテラシー)が高い人の特徴
お金の知識は、現代社会を生きる上での必須スキルです。しかし、実際にどれくらいの人がマネーリテラシーを身につけているでしょうか?
マネーリテラシー(金融リテラシー)とは、お金に関する基本的な知識や判断力を持ち、それを実生活で活用できる能力のことです。日常生活でのお金の管理から、将来の資産形成まで、私たちの人生のあらゆる場面で活きる重要なスキルです。
本記事では、マネーリテラシーの基礎知識から、なぜそれが必要なのか、どのようにして高めることができるのかまで、人事・金融の専門家の視点から詳しく解説します。
目次
金融リテラシー(マネーリテラシー)とは何か

マネーリテラシーとは、日常生活においてお金に関する知識を持ち、適切な判断ができる能力のことです。単なる知識だけでなく、その知識を実際の生活の中で活用し、自分自身や家族の経済的な安定と幸福を実現するための実践的な能力を指します。
具体的には、収入と支出のバランスを取る家計管理能力、将来に向けた貯蓄や投資の知識、税金や社会保障制度への理解、そして様々な金融商品のリスクとリターンを把握して適切な選択ができる判断力などが含まれます。
マネーリテラシーは、単なる「お金持ちになるためのテクニック」ではなく、ライフステージに応じた適切な経済的意思決定ができる総合的な能力です。いわば「お金との上手な付き合い方」を知っていることといえるでしょう。
日本におけるマネーリテラシーの現状
残念ながら、日本人のマネーリテラシーは国際的に見ても低い水準にあります。金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」によれば、日本人の金融リテラシースコアは国際平均を下回っており、特に若年層と高齢層で課題が見られます。
日本人の金融リテラシーが低い背景には、いくつかの要因があります。
まず、学校教育においてお金に関する教育が十分に行われてこなかったことが挙げられます。日本特有の「お金の話はタブー」という文化的背景も影響しています。家庭内でお金について話し合う機会が少なく、実践的な知識が世代間で伝わりにくいのです。
さらに、日本では長らく「銀行に預けておけば安心」という考え方が一般的でした。しかし、超低金利時代が続く中、単純な預金だけでは資産形成が難しくなっています。
にもかかわらず、投資や資産運用に関する知識や経験が乏しいため、新たな金融環境に適応できていない人が多いのが現状です。
このような状況は、個人の経済的自立を妨げるだけでなく、日本経済全体の活力低下にもつながる懸念があります。だからこそ、今マネーリテラシーの向上が強く求められているのです。
従業員の金融リテラシー向上にお悩みではありませんか?マネーリペアは、企業向けの包括的な金融教育プログラムを提供しています。専門家による実践的なセミナーから、個別相談、従業員のニーズに合わせたソリューションをご用意しております。詳しくはこちらのページからお問い合わせください。
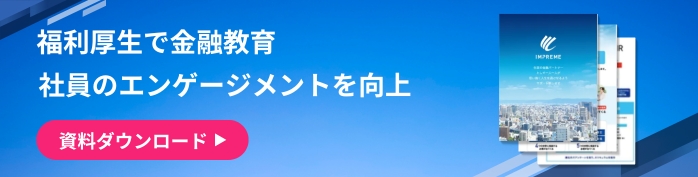
「金融リテラシー(マネーリテラシー)」はなぜ必要なのか

マネーリテラシーは現代社会を生きる上での必須スキルです。その必要性は個人のライフプランから社会全体の健全性まで幅広く影響します。
老後資金やライフプランへの影響
人生100年時代といわれる今日、私たちは従来よりも長い老後生活に備える必要があります。公的年金だけでは十分な老後生活を送ることが難しくなりつつある中、自助努力による資産形成の重要性が高まっています。
マネーリテラシーが高い人は、早い段階から計画的に資産形成を始め、老後に必要な資金を準備することができます。
例えば、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を活用した長期投資や、ライフステージに応じた適切な保険選びなど、様々な金融商品を自分のニーズに合わせて選択できるのです。
また、ライフプランにおいては、結婚、住宅購入、子どもの教育など、人生の大きなイベントに合わせた資金計画が必要です。マネーリテラシーがあれば、これらのライフイベントに対して計画的に準備し、不測の事態にも柔軟に対応できます。
反対に、マネーリテラシーが不足していると、将来に対する漠然とした不安を抱えたまま、効果的な対策を取れないまま時間だけが過ぎていくことになりかねません。老後破産や子どもの教育費不足など、取り返しのつかない事態に陥るリスクも高まります。
個人の行動経済学的視点から見る課題
人間は必ずしも合理的な経済行動をとるわけではありません。行動経済学の知見によれば、私たちは様々な心理的バイアスによって非合理的な経済判断をしがちです。
例えば、「現在バイアス」によって目先の満足を優先し、将来のための貯蓄や投資を後回しにする傾向があります。また、「損失回避バイアス」によって、利益を得るチャンスよりも損失を避けることに過剰に注力し、必要以上にリスクを避ける行動をとることもあります。
マネーリテラシーを高めることで、こうした心理的バイアスを認識し、より合理的な経済判断ができるようになります。
例えば、自動的に給与から一定額を積立投資に回すような仕組みを作ることで「現在バイアス」を克服したり、分散投資の重要性を理解することで過度のリスク回避を防いだりすることができるのです。
さらに、マネーリテラシーの向上は、消費者としての賢明な選択にもつながります。不必要なローンや高額な手数料を避け、自分のニーズに合った商品やサービスを選択することで、経済的な無駄を減らすことができます。
社会全体の経済健全化と国民教育
マネーリテラシーの向上は個人の問題にとどまらず、社会全体の経済健全化にも大きく寄与します。
まず、国民全体のマネーリテラシーが向上すれば、家計の健全化につながり、消費と貯蓄のバランスが取れた経済活動が促進されます。過剰な借入や浪費による家計破綻が減少し、社会全体の経済的安定性が高まるでしょう。
また、金融市場においても、知識を持った個人投資家が増えることで、より効率的で透明性の高い市場形成につながります。適切なリスク管理ができる投資家が増えれば、市場の急激な変動も緩和される可能性があります。
国際的な競争力という観点でも、国民のマネーリテラシー向上は重要です。グローバル化が進む現代において、金融知識の格差は国家間の経済格差にもつながりかねません。日本が国際社会で競争力を維持するためにも、国民全体のマネーリテラシー向上は急務といえるでしょう。
このような認識から、政府も「金融経済教育研究会」を設置し、学校教育や社会人教育におけるマネーリテラシー教育の強化に取り組んでいます。しかし、公的な教育だけでは限界があり、企業や家庭、メディアなど社会全体での取り組みが求められています。
政府が提唱する最低限身に付けておきたい「金融リテラシー」

金融経済教育研究会では、成人として最低限身につけるべき金融リテラシーを4つの分野に分けて提唱しています。
これらの基礎知識は、健全な経済生活を送るための基盤となります。
分野1. 家計管理
家計管理は、マネーリテラシーの基本中の基本です。どれだけ収入があっても、適切な管理ができなければ経済的な安定は得られません。
家計管理の第一歩は、収入と支出の把握です。毎月の給与やボーナスなどの収入に対して、固定費(家賃、光熱費、通信費など)と変動費(食費、交際費、娯楽費など)がどれくらいかかっているのかを明確に把握することから始まります。
家計簿アプリや家計管理サービスを活用することで、より簡単に家計の状況を可視化することができます。支出の傾向を分析することで、無駄な出費を見直す機会も生まれるでしょう。
また、「先取り貯蓄」の習慣も重要です。給与が入ったらまず一定額を貯蓄に回し、残りの金額で生活するという方法は、着実に資産を増やすための効果的な方法です。
緊急時のための備えとして、3〜6ヶ月分の生活費を「緊急用資金」として流動性の高い預金で確保しておくことも推奨されています。予期せぬ出費や収入の減少があった場合でも、生活を維持できる安心感につながります。
分野2. 生活設計
人生には様々なライフイベントがあり、それぞれに経済的な準備が必要です。結婚、出産、住宅購入、子どもの教育、そして老後など、ライフステージに応じた計画的な資金準備が求められます。
生活設計の基本は、将来のライフイベントを想定し、そのために必要な資金を試算することです。例えば、子どもの教育費は、幼稚園から大学までで約1,000万円〜2,000万円程度必要と言われています。
住宅購入の場合は、物件価格だけでなく、諸経費や修繕費なども含めて計画する必要があります。
また、老後資金については、公的年金だけでは不足する可能性が高いため、iDeCoやNISAなどの制度を活用した自助努力による資産形成が重要です。
老後に必要な資金は、望むライフスタイルによって大きく異なりますが、一般的には現役時代の年収の70〜80%程度の収入が必要と言われています。
生活設計においては、単なる資金計画だけでなく、ワークライフバランスや健康管理も含めた総合的な人生設計を考えることが大切です。
お金はあくまで手段であり、どのような人生を送りたいかというビジョンを明確にした上で、それを実現するための資金計画を立てることが望ましいでしょう。
分野3. 金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル
金融商品は多種多様で、それぞれ特性やリスクが異なります。自分のニーズやリスク許容度に合った金融商品を選ぶためには、基本的な金融知識が欠かせません。
まず、金融商品の三大要素である「安全性」「流動性」「収益性」について理解することが重要です。一般的に、安全性が高い商品は収益性が低く、収益性が高い商品はリスクも高いという特性があります。自分の目的や期間に合わせて、これらのバランスを考慮した選択が必要です。
代表的な金融商品としては、預貯金、債券、株式、投資信託、保険商品などがあります。預貯金は安全性と流動性が高いものの、現在の低金利環境では収益性は期待できません。一方、株式や投資信託は、長期的には高い収益が期待できますが、短期的には価格変動リスクがあります。
また、経済の基礎知識として、インフレーションや金利の仕組み、為替レートの影響なども理解しておくと、より適切な資産運用の判断ができるでしょう。例えば、インフレ時代には実質的な資産価値の目減りを防ぐために、インフレに強い資産への投資が重要になります。
金融商品を選ぶ際には、手数料や税金の影響も考慮する必要があります。一見収益性が高く見える商品でも、手数料が高ければ実質的なリターンは低くなる可能性があります。税制優遇のある商品(iDeCo、NISA等)を活用することで、税負担を軽減することも可能です。
分野4. 外部の知見の適切な活用
金融に関する知識や情報は膨大で、かつ常に変化しています。すべてを自分一人で把握し、最適な判断を下すことは困難です。そのため、外部の専門家や信頼できる情報源を適切に活用することも、マネーリテラシーの重要な要素です。
金融アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、税理士、社会保険労務士など、各分野の専門家に相談することで、より専門的な観点からのアドバイスを得ることができます。
ただし、専門家を選ぶ際には、資格や実績、報酬体系などをよく確認し、自分の利益を第一に考えてくれる信頼できる相手を選ぶことが重要です。
また、金融機関や公的機関が提供する情報、セミナー、教育プログラムなども有用な知識源です。インターネット上には様々な金融情報がありますが、信頼性の高い情報源を選び、複数の情報を比較検討する習慣を持つことが大切です。
社内で提供される福利厚生プログラムや研修も、外部知見を得る貴重な機会です。特に、企業が導入する従業員向けの金融教育プログラムは、仕事と関連づけながら実践的な知識を得られる点で非常に有効です。
関連記事:企業向け金融教育とは?導入メリットや成功事例、実践方法を徹底解説
【マネーリペアによる従業員向け金融教育】
マネーリペアでは、政府が提唱する4分野をカバーした総合的な金融教育プログラムをご提供しています。家計管理の基礎から、投資の知識、老後設計まで、従業員それぞれのニーズに合わせた教育コンテンツで、実践的なマネーリテラシーを身につけることができます。個別相談も可能ですので、こちらのページからお気軽にご相談ください。

マネーリテラシーを構成する要素

マネーリテラシーは様々な要素から構成されています。
ここでは、その核となる4つの要素について詳しく見ていきましょう。
お金の使い方:収入・支出のバランス
健全な家計の基本は、収入と支出のバランスを取ることです。収入を上回る支出を続ければ、いずれ借金に頼らざるを得なくなり、経済的な破綻の危険性が高まります。
支出を管理するためには、「固定費」と「変動費」に分けて考えることが効果的です。固定費とは、家賃や光熱費、通信費など毎月ほぼ一定額がかかる費用です。一方、変動費は食費や交際費、娯楽費など月によって変動する費用です。
固定費は契約の見直しなどで削減できる余地がありますが、短期間で大きく変えることは難しいものです。一方、変動費は日々の選択によって調整が可能です。まずは変動費から見直すことで、比較的容易に支出を削減することができるでしょう。
健全な家計管理のための目安として、「50-30-20ルール」が知られています。これは、収入の50%を住居費や食費などの必要経費に、30%を趣味や旅行などの自由裁量の支出に、そして20%を貯蓄や投資、借金の返済などの将来のための支出に割り当てるというものです。
もちろん、個人の状況によって最適な割合は異なりますが、一つの参考になるでしょう。
また、「ペイ・ユアセルフ・ファースト(自分自身にまず支払う)」の原則も重要です。給料が入ったら、まず決めた金額を貯蓄や投資に回し、残りのお金で生活するという方法です。これにより、無理なく着実に資産を形成することができます。
貯蓄・投資・資産運用の基礎
経済的な安定と成長のためには、単なる貯蓄だけでなく、投資や資産運用の知識も必要です。特に、長期的な資産形成においては、インフレリスクを考慮し、適切なリターンを得ることが重要になります。
貯蓄は安全性と流動性が高く、緊急時の備えとして重要です。一般的には、3〜6ヶ月分の生活費を緊急用資金として普通預金などですぐに引き出せる形で確保しておくことが推奨されています。
一方、長期的な資産形成には投資が有効です。投資の基本は「複利の力」を活用することです。例えば、年利3%で運用した場合、元本が2倍になるのに約24年かかりますが、年利5%なら約14年で2倍になります。
長期間にわたって少しでも高い運用利回りを確保することが、大きな資産形成につながるのです。
投資においては、「分散投資」の考え方が重要です。株式、債券、不動産など異なる資産クラスに分散することで、リスクを軽減しながらリターンを追求できます。また、同じ資産クラスの中でも、国や地域、業種などを分散することで、特定の要因による大きな損失を避けることができます。
日本では、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などの税制優遇制度を活用することで、より効率的な資産形成が可能です。これらの制度のメリットやルールを理解し、自分のライフプランに合わせて活用することも、マネーリテラシーの重要な要素です。
リスク管理と保険の活用
人生には予期せぬ事態がつきものです。病気や怪我、自然災害、失業など、さまざまなリスクに対して備えることも、マネーリテラシーの重要な一部です。
リスク管理の基本は、まず自分が直面する可能性のあるリスクを認識し、その影響度と発生確率を評価することです。そして、対策として「リスクの回避」「リスクの軽減」「リスクの移転」「リスクの保有」という4つの方法のうち、最適なものを選択します。
保険は「リスクの移転」の代表的な手段です。生命保険、医療保険、損害保険など、様々な種類があり、それぞれ保障する内容が異なります。保険を選ぶ際には、自分や家族のライフステージやニーズに合わせて、必要な保障を過不足なく確保することが重要です。
特に、家族の生活を支えている人は、万が一の場合に家族の生活が維持できるよう、生命保険や収入保障保険を検討する必要があるでしょう。また、医療保険は高額な医療費に備えるためのものですが、公的医療保険と合わせて考え、二重払いにならないよう注意が必要です。
一方で、過剰な保険加入は家計の負担になります。本当に必要な保障は何か、公的保障でカバーされる部分はどこかを理解した上で、適切な保険選びをすることがマネーリテラシーの一つです。
税金・社会保障制度への理解
税金や社会保障制度は複雑で分かりにくいものですが、これらへの基本的な理解もマネーリテラシーの重要な要素です。制度を理解することで、適切な節税策を講じたり、受けられる給付を確実に受け取ったりすることができます。
所得税、住民税、消費税などの基本的な税金の仕組みや、確定申告の方法について知っておくことは、健全な経済生活の基盤となります。特に、副業や投資による収入がある場合は、確定申告の知識が必要になることが多いでしょう。
また、様々な控除や特例制度を活用することで、合法的に税負担を軽減することも可能です。医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税など、自分の状況に応じて活用できる制度を知っておくことは大きなメリットになります。
社会保障制度については、年金、健康保険、介護保険、雇用保険などの基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。特に年金については、将来受け取れる金額の試算方法や、加入期間の確認方法などを知っておくと、老後の生活設計に役立ちます。
iDeCoやNISAなどの税制優遇制度も、効率的な資産形成には欠かせません。これらの制度の特徴やメリット、注意点を理解し、自分のライフプランに合わせて活用することも、マネーリテラシーの一部といえるでしょう。
金融リテラシー(マネーリテラシー)が高い人の特徴

マネーリテラシーが高い人には、いくつかの共通した特徴があります。
適切な家計管理ができる
マネーリテラシーが高い人は、収入と支出のバランスを常に意識し、計画的な家計管理ができます。無駄な支出を抑え、適切な貯蓄率を維持しながら、生活の質も確保するというバランス感覚を持っています。
彼らは単に節約しているだけではなく、「価値があると判断したものにはお金を使い、そうでないものには使わない」という価値観に基づいた支出の選択をしています。
高価でも長く使えるものを選んだり、趣味や学びなど自己成長につながるものにはしっかり投資したりするなど、お金の使い方に一貫性があります。
また、急な出費や収入の減少に備えて、緊急用資金を確保していることも特徴です。3〜6ヶ月分の生活費を流動性の高い資産で持っていることで、予期せぬ事態にも慌てずに対応できる安心感を得ています。
さらに、クレジットカードやローンなどの借入を賢く活用しています。必要に応じて適切に借り入れることはありますが、返済計画を明確にし、高金利の借入れは避ける傾向があります。
多様な金融商品を理解し、活用できる
マネーリテラシーが高い人は、預貯金だけでなく、株式、債券、投資信託、保険商品など多様な金融商品の特性を理解し、目的に応じて適切に活用できます。
彼らは金融商品を選ぶ際、リスクとリターンのバランス、手数料の水準、税金の影響など多角的な視点から比較検討します。例えば、長期的な資産形成にはインデックス投資信託を活用し、短期的な資金には安全性の高い預金を選ぶなど、目的に合わせた最適な選択ができます。
また、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度の仕組みを理解し、積極的に活用している点も特徴です。これらの制度を利用することで、同じ投資額でもより大きな資産形成が可能になります。
さらに、彼らは投資において「分散投資」の重要性を理解しています。国内外の株式や債券、不動産など異なる資産クラスに分散投資することで、リスクを抑えながら安定したリターンを追求しています。
「卵は一つのカゴに盛るな」という格言通り、一つの商品や市場に集中投資するリスクを避ける傾向があります。
リスク管理能力が高い
マネーリテラシーが高い人は、様々なリスクを認識し、それに対する備えができています。
彼らは保険を単なるコストとしてではなく、リスク管理のための重要なツールとして捉えています。生命保険、医療保険、損害保険など、自分や家族のニーズに合わせて必要な保障を過不足なく選択し、定期的に見直しを行っています。
また、投資におけるリスク管理も得意としています。市場の変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で資産運用を続けることができます。株価が下落したときにパニックになって売却するのではなく、むしろ割安になった時に追加投資を検討するなど、冷静な判断ができます。
さらに、複数の収入源を持つことでリスクを分散させる「キャッシュフロー多様化」の意識も持っています。本業の給与収入だけでなく、副業や投資による収入など、複数の収入源を築くことで、一つの収入が途絶えても生活を維持できる体制を整えています。
情報収集と分析力が高い
マネーリテラシーが高い人は、金融や経済に関する情報を積極的に収集し、それを自分の状況に当てはめて分析する能力に長けています。
彼らは新聞やビジネス誌、専門書籍、ウェブサイトなど複数の情報源から情報を集め、その信頼性を吟味します。一つの情報源に偏らず、様々な視点からの情報をバランスよく取り入れることで、より客観的な判断ができるのです。
また、数字やデータを読み解く能力も高い傾向があります。例えば、投資信託を選ぶ際には、過去のパフォーマンスだけでなく、経費率(コスト)や運用手法、ポートフォリオの内容などを詳細に分析した上で判断します。
さらに、最新の制度改正や税制の変更、金融商品の新しい動向にも敏感です。自分に関係する可能性のある情報には常にアンテナを張り、必要に応じて行動に移すことができます。
長期的視点での生活設計をしている
マネーリテラシーが高い人は、目先の欲求に流されず、長期的な視点で生活を設計しています。
彼らは人生の各ステージで必要となる資金を想定し、それに向けた準備を計画的に進めています。例えば、住宅購入、子どもの教育費、老後資金など、大きな出費が予想されるライフイベントに対して、早い段階から準備を始めることで、無理なく目標を達成できるよう工夫しています。
また、「今の満足」と「将来の安心」のバランスを取ることに長けています。現在の生活の質を過度に犠牲にすることなく、かつ将来に不安を残さないよう、適切な配分で生活設計を行っています。
さらに、人生の価値観や優先順位が明確であることも特徴です。何にお金を使うかという選択は、自分にとって何が大切かという価値観の反映でもあります。マネーリテラシーが高い人は、自分の価値観に基づいた生活設計ができています。
継続的な学習姿勢がある
マネーリテラシーが高い人は、金融知識やスキルを継続的に学び、アップデートする姿勢を持っています。
彼らは金融や経済に関する情報を常にチェックし、新しい制度や商品について学び続けています。世の中の経済環境や制度は常に変化しているため、一度得た知識を更新していく必要があることを理解しているのです。
また、自分の知識やスキルの限界を認識し、必要に応じて専門家のアドバイスを求める謙虚さも持ち合わせています。すべてを自分で判断しようとするのではなく、複雑な問題については専門家の知見を活用することも、マネーリテラシーの一部と言えるでしょう。
さらに、失敗や間違いから学ぶ姿勢も重要です。投資で損失を出したり、不適切な商品を選んでしまったりした経験があっても、それを次に活かす教訓として捉え、同じ失敗を繰り返さないよう努めています。
客観的な視点で判断できる
マネーリテラシーが高い人は、感情に流されず、客観的な視点でお金に関する判断ができます。
人間は本来、様々な心理的バイアスを持っており、それがお金の判断にも影響します。例えば、「損失回避バイアス」によって、利益を得るチャンスよりも損失を避けることに過剰に注力したり、「確証バイアス」によって自分の信念に合致する情報だけを重視したりする傾向があります。
マネーリテラシーが高い人は、こうした心理的バイアスの存在を認識し、できる限り客観的な判断ができるよう意識しています。例えば、投資判断においては感情を排除し、事前に決めた投資方針やルールに基づいて行動することで、衝動的な判断を避けています。
また、「サンクコスト(埋没費用)の誤謬」にも陥りにくい特徴があります。過去に投じたコストにとらわれず、現時点での最適な判断ができるのです。
例えば、値下がりした株式を「買った値段まで戻るまで売れない」と考えるのではなく、今後の見通しに基づいて保有継続か売却かを判断します。
お金に関する相談ができる相手がいる
マネーリテラシーが高い人は、お金について相談できる信頼できる相手を持っていることが多いです。
配偶者や家族とお金について率直に話し合える関係性を築いていることは、健全な家計管理の基盤となります。特に共働き世帯では、収入や支出の管理、将来の目標について共有し、協力して取り組むことが重要です。
また、同じような価値観や目標を持つ友人や知人との情報交換も貴重な機会となります。投資の経験や金融商品の選択について意見を交わすことで、自分では気づかなかった視点や情報を得ることができます。
さらに、必要に応じてファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家に相談できる関係を持っていることも強みです。専門的な知識が必要な分野や、重要な意思決定の際には、プロのアドバイスを受けることで、より確かな判断ができるようになります。
マネーリテラシーが高い人は、こうした人間関係を通じて継続的に学び、自分の知識やスキルを向上させています。お金に関する話題をタブー視せず、オープンに対話できる環境を作ることも、マネーリテラシー向上の一助となるでしょう。
金融リテラシー(マネーリテラシー)の高め方

マネーリテラシーは生まれながらに備わっているものではなく、学習と実践によって高めていくことができます。ここでは、具体的なマネーリテラシーの高め方について解説します。
基礎知識の習得と現状の把握
マネーリテラシーを高める第一歩は、基礎知識を身につけ、自分の現状を正確に把握することです。
まずは、家計の状況を明確にしましょう。収入と支出の詳細を把握するために、少なくとも3ヶ月程度の家計簿をつけてみることをおすすめします。家計簿アプリやクレジットカードの明細を活用すれば、比較的簡単に支出の傾向を分析できるでしょう。
また、自分の資産と負債の全体像を「家計バランスシート」として整理してみることも有効です。銀行預金、投資商品、不動産などの資産と、住宅ローンやカードローンなどの負債を一覧にすることで、自分の純資産(資産 - 負債)が明確になります。
基礎知識の習得には、書籍やウェブサイト、セミナーなど様々な方法があります。金融広報中央委員会や金融庁などの公的機関が提供する情報は、中立的で信頼性が高いため、まずはそこから始めるとよいでしょう。
また、職場で提供される金融教育セミナーなども、実践的な知識を得る良い機会です。
自分の将来設計についても考えてみましょう。5年後、10年後、そして老後にどのような生活を送りたいのか、そのためにはどれくらいの資金が必要かを具体的にイメージすることが、計画的な資産形成の第一歩となります。
実践的なスキルの獲得
知識を得たら、次はそれを実践に移すことが重要です。マネーリテラシーは知識だけでなく、実際の行動によって高められるものだからです。
まずは、月々の支出を見直し、固定費の削減や不要な支出の見直しを行いましょう。携帯電話料金やサブスクリプションサービス、保険料などは、見直すことで大きな節約につながる可能性があります。
次に、計画的な貯蓄や投資を始めましょう。給与が入ったら、まず一定額を貯蓄や投資に回す「先取り貯蓄」の習慣をつけることで、無理なく資産形成を進めることができます。
初めての投資は不安かもしれませんが、少額から始めることで実践的なスキルを身につけることができます。例えば、つみたてNISAやiDeCoなどの税制優遇制度を利用し、インデックス投資信託から始めるのが初心者におすすめです。
また、定期的に自分の資産状況や投資方針を見直す習慣も大切です。ライフステージの変化や経済環境の変化に応じて、適切に調整していくことで、長期的な資産形成を実現できるでしょう。
さらに、継続的な学習も忘れずに行いましょう。金融や経済の状況は常に変化しているため、定期的に情報をアップデートすることが必要です。書籍やセミナー、専門家との対話などを通じて、常に新しい知識を取り入れる姿勢を持ちましょう。
企業でマネーリテラシーを高める意義
企業がマネーリテラシー教育に取り組むことは、従業員のためだけでなく、企業自身にとっても大きなメリットがあります。ここでは、企業でマネーリテラシーを高める意義について解説します。
従業員の経済的安定がもたらすメリット
従業員のマネーリテラシー向上は、彼らの経済的安定に直結します。経済的に安定した従業員は、以下のようなメリットを企業にもたらします。
まず、経済的な不安が軽減されることで、仕事への集中力が高まります。家計の問題や借金の悩みなどに気を取られることなく、業務に専念できるようになるのです。
実際の調査によれば、経済的な不安を抱える従業員は、仕事中も頻繁にその問題について考え、生産性が低下する傾向があります。
また、経済的な理由による欠勤や休職が減少する効果も期待できます。特に、急な出費に対応できないような経済状況では、体調不良を押してでも出勤する「プレゼンティーイズム(出勤しているが十分に機能していない状態)」が生じやすく、長期的には健康問題につながる恐れがあります。
さらに、経済的に安定していることで、従業員のメンタルヘルスも改善されます。金銭的な不安はストレスの大きな要因の一つであり、それが軽減されることでメンタル面での不調も減少することが期待できるでしょう。
福利厚生とのシナジー効果
マネーリテラシー教育は、他の福利厚生プログラムとのシナジー効果も生み出します。
例えば、多くの企業が導入している401k(企業型確定拠出年金)や財形貯蓄などの制度は、従業員のマネーリテラシーが低ければ十分に活用されません。
マネーリテラシー教育を通じて、これらの制度の仕組みやメリットを理解してもらうことで、既存の福利厚生の利用率と効果を高めることができるのです。
また、健康経営の取り組みとも相乗効果があります。経済的な安定は精神的な余裕を生み、健康的な生活習慣の維持にもつながります。経済面と健康面の両方をサポートすることで、より包括的な従業員支援が可能になるでしょう。
さらに、ワークライフバランスの推進にも寄与します。経済的な不安がなければ、無理な残業や休日出勤を避け、適切な休息や家族との時間を確保することができます。これにより、長期的な健康維持と仕事のパフォーマンス向上が期待できるのです。
生産性・定着率向上の実例
マネーリテラシー教育の導入によって、実際に生産性や定着率が向上した事例も多く報告されています。
ある大手製造業では、全社的なマネーリテラシー教育プログラムを導入した結果、一年後には従業員の欠勤率が15%減少し、生産性が7%向上したという報告があります。経済的な不安の軽減が、業務への集中力向上と直結した好例といえるでしょう。
また、IT企業の事例では、新入社員向けのマネーリテラシー研修を実施したグループと、実施しなかったグループを比較したところ、研修を受けたグループの3年後の定着率が約20%高かったというデータがあります。
特に若手社員にとって、初めての給与管理や資産形成は大きな不安要素となるため、早い段階での教育が効果的だったと考えられます。
さらに、金融業界の企業では、マネーリテラシー教育の一環として家計相談サービスを導入したところ、従業員のエンゲージメントスコアが向上し、顧客満足度との相関も見られたという興味深い結果も報告されています。
自社のサービスに対する理解が深まり、顧客への説明力も向上したのでしょう。
これらの事例は、マネーリテラシー教育が単なる福利厚生の一つではなく、企業の競争力向上にも直結する戦略的な取り組みであることを示しています。従業員のウェルビーイングと企業の業績向上を同時に実現できる、まさに「Win-Win」の施策といえるでしょう。
マネーリテラシー教育に使える制度やプログラム
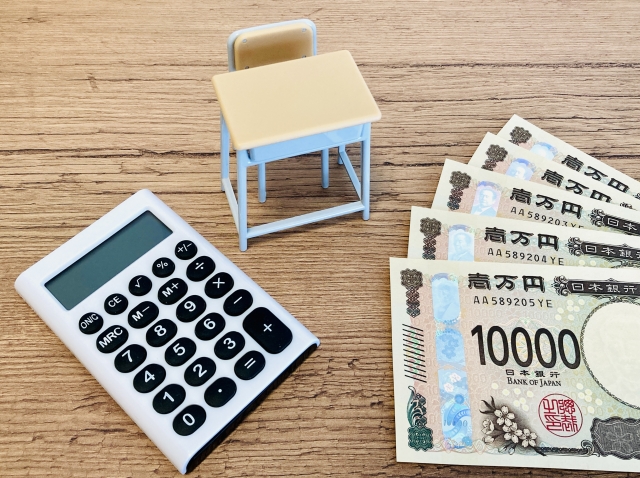
マネーリテラシーを高めるための教育は、様々な場面で実施されています。ここでは、活用できる制度やプログラムについて解説します。
学校教育・社会人教育での取り組み
マネーリテラシー教育は、学校教育から社会人教育まで幅広く行われています。
学校教育では、2020年度から実施された新学習指導要領において、金融教育の内容が強化されました。小学校での「家計と消費」、中学校での「計画的な金銭管理」、高校での「資産形成」など、発達段階に応じた金融教育が行われています。
大学では、一般教養科目としての金融リテラシー講座や、就職活動を控えた学生向けのキャリア教育の一環としてのマネーリテラシー教育が広がっています。社会人になる前の段階で基礎知識を身につけることで、新社会人としての経済的自立をサポートする狙いがあります。
社会人教育としては、金融機関や公的機関が提供する無料セミナーや講座が充実しています。例えば、金融広報中央委員会の「知るぽると」では、全国各地で金融リテラシーに関するセミナーを開催しています。
また、日本証券業協会や各金融機関も、投資教育や家計管理に関するセミナーを定期的に実施しています。
オンライン教育の普及により、時間や場所を選ばずに学べる環境も整ってきました。無料の金融教育ウェブサイトやYouTubeチャンネル、スマートフォンアプリなど、様々な媒体を通じて知識を得ることができます。
企業が導入できる研修プラン・eラーニング
企業がマネーリテラシー教育を導入する方法としては、以下のようなものがあります。
専門家による集合研修は、従業員が一同に会して学ぶ機会を提供します。金融の専門家や社内の人事・福利厚生担当者が講師となり、基礎知識から実践的なスキルまで幅広く学ぶことができます。新入社員研修や昇進時研修など、キャリアの節目に実施するのが効果的です。
eラーニングは、従業員が自分のペースで学べる柔軟性が魅力です。基礎から応用まで段階的に学べるコンテンツや、クイズやシミュレーションを通じて楽しく学べる工夫が施されたプログラムも増えています。業務の隙間時間に取り組めるため、多忙な従業員にも受け入れられやすいでしょう。
ワークショップ形式では、少人数のグループで実践的な課題に取り組むことで、より深い理解と定着を促します。例えば、架空の家計データを基にした予算立てや、人生の様々なイベントを想定したシミュレーションゲームなど、参加型の学習が可能です。
また、個別相談会の実施も効果的です。ファイナンシャルプランナーなどの専門家が、従業員一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを提供することで、具体的な行動につなげやすくなります。プライバシーに配慮した形で実施することが重要です。
これらのプログラムは、従業員のライフステージに合わせてカスタマイズすることで、より効果を高めることができます。
例えば、若手社員には基礎的な家計管理や貯蓄の重要性、中堅社員には住宅購入や子どもの教育費の準備、ベテラン社員には退職準備や年金活用など、それぞれのニーズに応じたテーマ設定が望ましいでしょう。
公的機関・民間団体による無料セミナー
マネーリテラシー向上のための無料リソースも充実しています。
金融庁や金融広報中央委員会などの公的機関では、定期的に無料の金融セミナーを開催しています。基礎的な家計管理から、投資、税金、年金制度まで、幅広いテーマで学ぶことができます。企業内で実施する場合は、これらの機関に講師派遣を依頼することも可能です。
各金融機関も、社会貢献活動の一環として金融教育セミナーを提供しています。例えば、銀行や証券会社の多くは、資産形成や老後資金の準備などをテーマにしたセミナーを定期的に開催しており、これらは無料で参加できることが多いです。
業界団体も積極的に金融教育に取り組んでいます。日本証券業協会や日本FP協会などは、特定のテーマに特化した専門性の高いセミナーを提供しており、より深い知識を得たい方に適しています。
また、消費者団体や地方自治体が主催する生活経済セミナーも、実践的な家計管理や消費者トラブル防止に役立つ情報を提供しています。地域に密着した内容で、参加しやすい環境が整っていることが多いです。
これらのセミナーやプログラムは、企業の福利厚生担当者が情報収集し、従業員に案内することで、マネーリテラシー向上の機会を提供できます。また、外部の無料リソースと企業独自のプログラムを組み合わせることで、より包括的な教育体制を構築することも可能です。
【マネーリペアの包括的プログラム】マネーリペアでは、企業規模や従業員のニーズに合わせた柔軟なプログラム設計が可能です。社員研修、個別相談会を組み合わせた総合的なアプローチで、効果的なマネーリテラシー教育を実現します。
導入企業の96%が満足と回答し、従業員の金融リテラシー向上と経済的ウェルビーイングの実現に貢献しています。詳しくはこちらのページからお問い合わせください。

マネーリテラシー不足がもたらすリスク
マネーリテラシーの重要性を理解するためには、それが不足した場合のリスクについても認識しておく必要があります。ここでは、マネーリテラシー不足がもたらす主なリスクについて解説します。
不安定な家計運営やローン問題
マネーリテラシーが不足していると、基本的な家計管理ができず、収入と支出のバランスが崩れやすくなります。
収入以上の支出を続けると、やがて貯蓄を取り崩したり、借入に頼ったりする状況に陥ります。クレジットカードの支払いが滞ったり、多重債務に陥ったりするリスクが高まるのです。
特に、金利の高いカードローンやキャッシングに頼る状況になると、利息の負担が雪だるま式に膨らみ、返済がますます困難になるという悪循環に陥りかねません。
また、住宅ローンやマイカーローンなど、大きな借入をする際に適切な判断ができないリスクもあります。自分の返済能力を超えた借入をしてしまうと、後に大きな負担となり、最悪の場合、住宅の差し押さえなどの事態に発展する可能性もあります。
さらに、急な出費(病気や怪我、家電の故障など)に対応できる緊急用資金を確保していないと、生活が一気に不安定になる恐れがあります。貯蓄がなければ、急な出費の度に借入に頼らざるを得ず、借金が膨らんでいく原因となります。
マネーリテラシーの向上によって、収支のバランスを取る基礎的な家計管理能力を身につけ、計画的な貯蓄と適切な借入判断ができるようになることが、これらのリスクを回避するために重要です。
詐欺・投資トラブルへの巻き込まれ
マネーリテラシーが不足していると、詐欺や投資トラブルの被害に遭うリスクが高まります。
「必ず儲かる」「元本保証」などといった甘い言葉に惑わされ、実態のない投資話や詐欺的なビジネスに資金を投じてしまう危険性があります。金融商品の仕組みやリスクを十分に理解していないと、詐欺師の巧みな言葉に騙されやすくなるのです。
また、投資の基本原則である「ハイリターンにはハイリスクが伴う」という点を理解していないと、非現実的に高い利回りを約束する商品を信じてしまいがちです。詐欺だけでなく、自分のリスク許容度を超えた商品に投資してしまうことで、大きな損失を被るリスクもあります。
さらに、契約内容や手数料体系を十分理解しないまま金融商品を購入することで、想定外のコストが発生したり、解約時に高額な手数料がかかったりするケースもあります。
中には、解約制限のある商品に気づかずに契約し、必要な時に資金を引き出せないという事態に陥ることもあるでしょう。
近年は、インターネットの普及により、投資に関する情報が溢れる一方で、誤った情報や悪質な勧誘も増加しています。SNSやWeb広告などを通じた投資詐欺も多発しており、正しい知識を持たないまま情報に接すると、判断を誤るリスクが高まります。
マネーリテラシーを高めることで、怪しい投資話を見分ける目を養い、自分の状況に合った適切な金融商品を選択できるようになります。
- リスクとリターンの関係
- 分散投資の重要性
- 長期投資の意義
など、投資の基本原則を理解することが、詐欺やトラブルから身を守る上で不可欠です。
老後破産・生活保護に陥る可能性
マネーリテラシー不足は、長期的には老後の経済的困窮を招くリスクがあります。
人生100年時代と言われる現代において、退職後の生活は20〜30年以上に及ぶ可能性があります。しかし、公的年金だけでは十分な老後生活を送ることが難しくなりつつあり、自助努力による資産形成が不可欠です。
マネーリテラシーが不足していると、この重要性を認識できず、老後に向けた準備が不十分なまま高齢期を迎えてしまいます。
また、退職金を計画性なく使ってしまい、早期に資金が底をつくリスクもあります。特に、投資や金融商品に関する知識がないまま、見知らぬ人からの勧誘で退職金を投資し、大きな損失を被るケースも少なくありません。
さらに、長寿リスクに対する備えが不足していると、想定以上に長生きした場合に資金が枯渇する「長生きリスク」に直面する可能性があります。平均寿命を基準に計画を立てていると、それを超えて生きた場合に経済的に困窮するリスクが高まるのです。
マネーリテラシーの不足は、介護や医療などの高齢期特有のリスクへの備えも不十分になりがちです。公的介護保険でカバーされない部分の費用負担や、高額な医療費に対する備えがないと、資産の急速な減少につながる恐れがあります。
これらの結果、最悪の場合「老後破産」に陥り、生活保護に頼らざるを得ない状況になることもあります。自立した老後生活を送るためには、若いうちからのマネーリテラシー向上と計画的な資産形成が欠かせないのです。
【マネーリペアの予防プログラム】 マネーリペアでは、これらのリスクを予防するための実践的なプログラムを提供しています。
詐欺やトラブルの最新事例の紹介から、老後資金の効果的な準備方法まで、従業員が直面する可能性のあるリスクを未然に防ぐための知識とスキルを身につけることができます。リスク予防は、事後対応よりも効果的です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
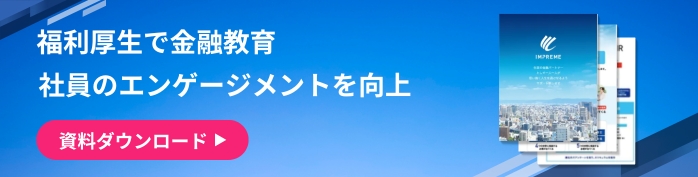
まとめ:マネーリテラシーを身につけることが未来を変える
マネーリテラシーは現代社会を生きる上で欠かせない能力であり、その向上は個人の経済的安定だけでなく、企業の成長や社会全体の健全性にも寄与します。
日本人のマネーリテラシーは国際的に見ても高いとは言えない状況ですが、教育の機会は着実に増えています。学校教育での金融教育の強化や、企業での福利厚生としてのマネーリテラシー教育の普及など、社会全体での取り組みが進んでいます。
企業にとっても、従業員のマネーリテラシー向上は大きなメリットをもたらします。経済的な不安が軽減された従業員は、仕事に集中でき、生産性や創造性の向上につながります。また、離職率の低下や企業イメージの向上など、人材マネジメントの観点からも効果が期待できます。
企業としては、従業員のマネーリテラシー向上をサポートする教育プログラムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。