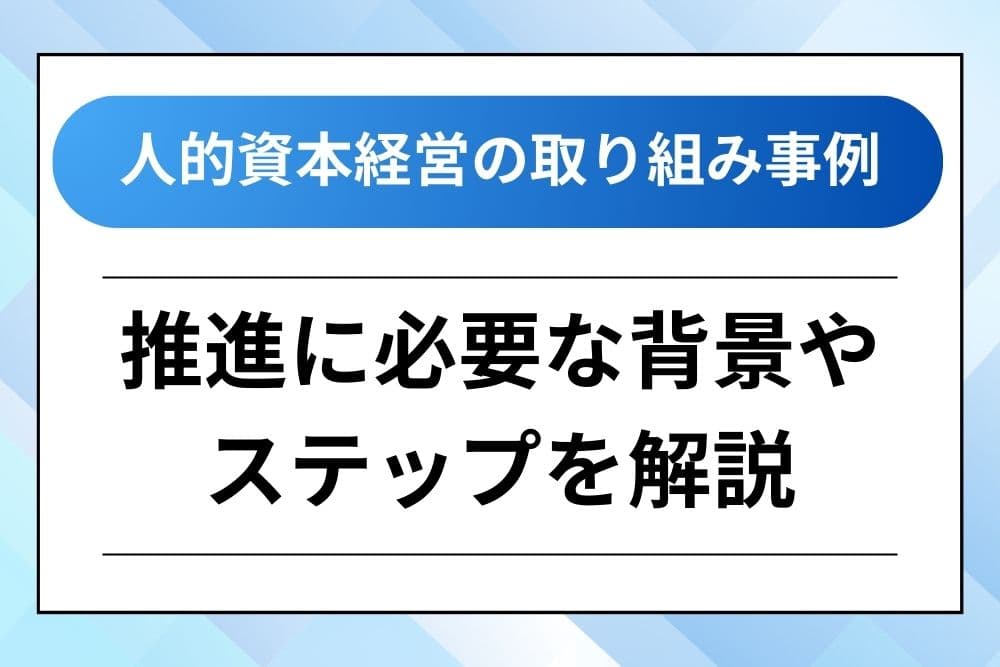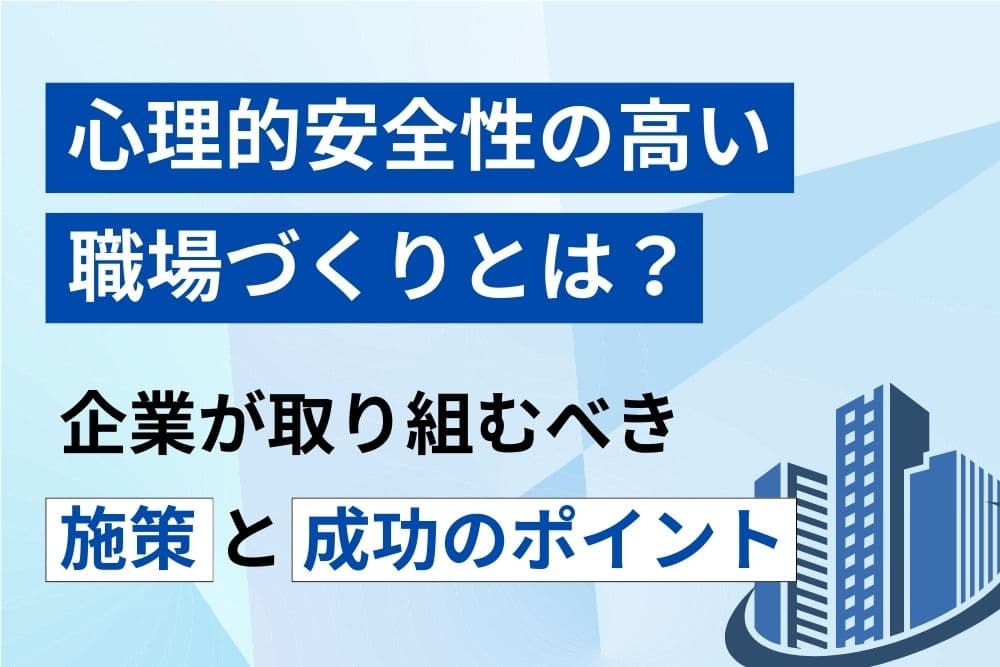お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
企業型確定拠出年金は転職時に損する?企業が意識すべきポイントを解説
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
企業型確定拠出年金とは何か
転職したら確定拠出年金はどうする?転職先のパターン別に解説
人事・金融の専門家から見る転職と年金・退職金設計
転職時に損をするケースはどのように発生するか
損を回避するために知っておくべき確定拠出年金の移換の注意点
「転職を考えているけれど、今の会社で加入している企業型確定拠出年金はどうなるの?」「せっかく積み立ててきた資産が無駄になってしまうのでは?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、企業型確定拠出年金は転職時に適切な手続きを行わないと、せっかく積み立ててきた資産が目減りしてしまうケースがあります。
本記事では企業型確定拠出年金について解説します。
目次
企業型確定拠出年金とは何か
企業型確定拠出年金は、老後の資産形成を支援するための制度として多くの企業に導入されています。従業員一人ひとりが資産運用に主体的に関わることで、将来の経済的安定を図ることができます。
制度の基本的な仕組みと背景
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が毎月一定の金額を拠出し、従業員がその資金を自分自身で運用して老後の資産を形成する制度です。少子高齢化が進み、公的年金だけでは老後の生活を十分に支えられないという懸念から、2001年に確定拠出年金法が施行され、導入が始まりました。
企業型確定拠出年金の最大の特徴は、運用成績によって将来受け取る金額が変動する「確定拠出型」であることです。運用は従業員自身が行い、その結果に応じて将来の年金額が決まります。
掛金は全額事業主が負担するのが基本ですが、企業によっては「マッチング拠出」を導入し、従業員も追加で掛金を拠出できる場合もあります。
また、運用益は非課税、掛金は全額損金算入(企業側)または所得控除(従業員のマッチング拠出分)となるなど、税制上の優遇措置も大きな魅力です。
個人型(iDeCo)との違い
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)は、同じ確定拠出年金制度の中の二つの形態ですが、いくつかの重要な違いがあります。
まず、掛金の負担者が異なります。企業型DCでは基本的に企業が掛金を負担しますが、iDeCoでは加入者本人が掛金を負担します。そのため、企業型DCは従業員にとって「もらえる福利厚生」という性質が強いのに対し、iDeCoは「自分で行う資産形成」という側面が強くなります。
次に、加入できる対象者が異なります。企業型DCは、その制度を導入している企業に勤めている従業員が対象です。一方、iDeCoは国民年金の被保険者であれば、原則として誰でも加入することができます(ただし、加入区分や他の年金制度の加入状況によって拠出限度額が異なります)。
また、手数料の負担者も異なります。企業型DCでは、口座管理手数料などの各種手数料は基本的に企業が負担しますが、iDeCoでは加入者本人が負担します。この点は、コスト面で企業型DCが有利と言えるでしょう。
さらに、運用商品の選択肢にも違いがあります。企業型DCでは、企業が選定した運用商品(最低3つ以上)の中から選ぶ必要がありますが、iDeCoでは自分で選んだ金融機関が提供する運用商品から選ぶことができます。
確定給付年金との違い
確定給付年金(DB)は企業型確定拠出年金(DC)とは異なり、あらかじめ将来受け取る年金額が決まっている制度です。この二つの制度には、以下のような違いがあります。
まず、最大の違いは「給付額の決まり方」です。
確定給付年金では、勤続年数や退職時の給与などに基づいて、将来受け取る年金額があらかじめ決められています。一方、企業型DCでは、掛金とその運用成績によって将来の給付額が決まります。
次に「運用リスクの負担者」が異なります。確定給付年金では、約束した給付を行うための運用リスクは企業が負いますが、企業型DCでは運用リスクは従業員個人が負うことになります。
また、「ポータビリティ(持ち運びのしやすさ)」にも違いがあります。企業型DCは転職時に資産を持ち運ぶことが比較的容易ですが、確定給付年金は一般的に転職時に一時金として受け取るか、もしくは企業年金連合会に移換するかの選択を迫られます。
企業が導入する目的と従業員への恩恵
企業が企業型確定拠出年金を導入する主な目的は、以下のようなものが挙げられます。
福利厚生の充実
従業員の老後の資産形成を支援することで、福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めることができます。
退職金制度の見直し
従来の退職金制度を企業型DCに移行することで、企業の財務負担を平準化し、将来の退職金支払いに関するリスクを軽減できます。
人材確保・定着
充実した年金制度は、人材の採用や定着に効果的です。特に将来を見据えた制度設計は、長期的な雇用関係を築く上で重要な要素となります。
従業員の資産形成意識の向上
従業員自身が運用に関わることで、資産形成に対する意識が高まり、金融リテラシーの向上にもつながります。
一方、従業員にとっての恩恵としては、以下のような点が挙げられます。
税制優遇
企業型DCの掛金や運用益には税制優遇があり、効率的な資産形成が可能です。
自己責任での運用
自分のニーズやリスク許容度に応じた運用ができ、自分の資産は自分で増やすという意識を高められます。
ポータビリティ
転職時にも資産を持ち運べるため、長期的な資産形成が継続できます。
老後の経済的安定
公的年金を補完する私的年金として、老後の経済的安定に寄与します。
このように、企業型確定拠出年金は企業と従業員の双方にメリットがある制度であり、適切に活用することで、Win-Winの関係を構築することが可能です。
転職したら確定拠出年金はどうする?転職先のパターン別に解説

転職する際、企業型確定拠出年金(企業型DC)の扱いはどうなるのでしょうか。転職先の状況に応じて、選択肢が異なります。ここでは、転職先のパターン別に解説します。
転職先に確定拠出年金制度がある場合
転職先の企業が企業型確定拠出年金を導入している場合、基本的には転職前に積み立てた資産を転職先の制度に移すことができます。これを「ポータビリティ」といい、確定拠出年金の大きなメリットの一つです。
大企業に勤めていて確定拠出をしていた場合、転職先でも活用できる
大企業から別の企業型DC導入企業への転職では、通常、スムーズに資産を移換できます。ただし、いくつか注意点があります。
まず、資産移換の手続きは、転職先の企業型DC担当部署に確認しましょう。手続きは転職(資格喪失)の翌月から起算して6ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されてしまい、余計な手数料がかかったり、運用ができなくなったりするデメリットが発生します。
また、移換時には一度資産が現金化され、転職先で選択した商品に再投資されます。そのため、移換のタイミングによっては、市場価格の変動で損失が発生する可能性もあります。
さらに、転職前と転職先では、選択できる運用商品が異なる場合があります。転職先の運用商品についてしっかり理解した上で、自分の運用方針に合った商品を選択しましょう。
なお、2022年10月からは、企業型DCに加入していても、規約の定めにより個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時加入して、企業型DCの資産をiDeCoに移換できるようになりました。
転職先の企業型DCよりもiDeCoの方が運用商品の選択肢が多い場合など、自分のニーズに合わせて選択することができます。
転職先に確定拠出年金制度がない場合
転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換するのが一般的です。この場合、以下の手順で手続きを進めることになります。
まず、iDeCoを取り扱っている金融機関の中から、自分に合ったところを選んでiDeCo口座を開設します。金融機関選びでは、手数料や運用商品のラインナップ、サポート体制などを比較検討することが重要です。
iDeCo口座開設後、「個人別管理資産移換依頼書」などの必要書類を提出し、前の企業型DCからiDeCoへの資産移換手続きを行います。資産移換が完了すると、それまでに積み立てた資金がiDeCo口座に移され、その後は自分で選んだ運用商品で運用を続けることができます。
ここで注意したいのは、企業型DCでは企業が負担していた口座管理手数料が、iDeCoでは自己負担になる点です。また、iDeCoへの掛金拠出も自己負担となるため、継続的に資産形成を行いたい場合は、毎月の家計から掛金を捻出する必要があります。
さらに、iDeCoへの移換も、退職(資格喪失)の翌月から起算して6ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、自動移換のデメリットを被ることになりますので、退職後はできるだけ早めに手続きを進めましょう。
自営業者になる場合
会社を退職して自営業者(国民年金第1号被保険者)になった場合も、前の企業型DCの資産をiDeCoに移換することになります。手続きの流れは基本的に前項と同じです。
自営業者のiDeCo掛金の拠出限度額は月額6.8万円と、他の加入者区分と比べて最も高く設定されています。そのため、自営業に転身した後も、より多額の掛金を拠出して効率的な資産形成を行うことが可能です。
また、自営業者の場合、iDeCoの掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、大きな節税効果が期待できます。特に高い所得税率が適用される高所得の自営業者にとって、iDeCoはメリットの大きい制度と言えるでしょう。
ただし、自営業者は収入が不安定になりがちなため、無理のない範囲で掛金額を設定することが重要です。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、当面の生活資金や事業資金を確保した上で、余裕資金で運用することをお勧めします。
公務員になる場合
企業型確定拠出年金に加入していた方が公務員になった場合も、資産をiDeCoに移換することになります。公務員(国民年金第2号被保険者で共済組合員)のiDeCo掛金の拠出限度額は月額1.2万円です。
公務員は基本的に安定した年金制度に加入しているため、iDeCoの拠出限度額は比較的低く設定されています。しかし、公的年金を補完する形で私的年金を準備することで、より豊かな老後生活を実現できます。
また、公務員になると、共済年金(年金払い退職給付)に加入することになります。これは公務員の退職給付の一部を年金として支給する制度で、企業型DCとは異なり、給付額が勤続年数や退職時の給与などに基づいて決まる確定給付型の制度です。
iDeCoへの移換手続きは、退職(資格喪失)の翌月から起算して6ヶ月以内に行う必要があります。公務員になった後の忙しい時期ですが、この手続きを忘れないようにしましょう。
専業主婦になる場合
企業型確定拠出年金に加入していた方が退職して専業主婦(夫)(国民年金第3号被保険者)になった場合も、資産をiDeCoに移換することになります。専業主婦(夫)のiDeCo掛金の拠出限度額は月額2.3万円です。
専業主婦(夫)は収入がない場合が多いため、iDeCoの掛金を継続的に拠出するためには、家計の中から資金を捻出する必要があります。ただ、iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、配偶者に一定の所得があれば、世帯全体での節税効果が期待できます。
また、専業主婦(夫)から再び就業して国民年金第2号被保険者になった場合、iDeCo加入者としての資格を再び変更する手続きが必要です。このような状況変化に応じた手続きについても、金融機関に相談しながら適切に対応しましょう。
人事・金融の専門家から見る転職と年金・退職金設計
転職による人生のキャリアチェンジは、給与や職場環境だけでなく、退職金や年金制度にも大きな影響を与えます。ここでは、人事・金融の専門家の視点から、転職と年金・退職金設計について解説します。
従業員が適切にリスク管理できるよう投資教育を行う
企業型確定拠出年金を導入する企業にとって、従業員への投資教育は単なる法的義務ではなく、制度を効果的に機能させるための重要な取り組みです。特に転職者を受け入れる場合、前職での投資経験や知識レベルが異なるため、丁寧な教育が必要になります。
また、従業員の年齢や投資経験に応じた教育内容を用意することも重要です。若年層には長期投資の魅力を、中高年層にはリスク管理の重要性を強調するなど、対象に合わせたアプローチが効果的です。
転職者を受け入れる際には、前職での運用状況や資産移換の流れについても丁寧に説明し、スムーズな移行をサポートすることが求められます。
キャリア形成と資産形成を両立させる視点
キャリアと資産形成は密接に関連しており、転職を検討する際には両者のバランスを考慮することが重要です。
まず、転職によってキャリアアップを図る場合、短期的には給与アップが実現しても、退職金や企業年金などの長期的な資産形成の仕組みが不利になるケースがあります。特に勤続年数によって退職金が大きく増加する制度がある企業からの転職は、慎重な検討が必要です。
一方で、企業型確定拠出年金のようなポータブルな制度があれば、転職によるキャリアチェンジと資産形成の継続を両立させやすくなります。転職先選びの際には、給与水準だけでなく、企業年金や退職金制度の内容も重要な判断材料になります。
また、転職を繰り返すことで企業年金のポータビリティが十分に活用できず、資産が分散して効率的な運用ができなくなるリスクもあります。転職の際には、分散した資産を可能な限り一つにまとめる戦略も検討すべきでしょう。
キャリアプランと資産形成計画を統合的に考えることで、人生100年時代の長期的な経済的安定を実現することができます。
雇用契約書・福利厚生制度のチェック項目
転職の際には、給与や職務内容だけでなく、企業年金や退職金などの福利厚生制度も重要なチェックポイントです。雇用契約書や福利厚生制度の確認には、以下の項目に注目しましょう。
- 企業年金制度の有無と種類
確定給付型年金か確定拠出型年金か、またはその併用型かを確認します。それぞれ特徴やリスクが異なります。 - 企業型DCの掛金額
企業が拠出する掛金の金額や、役職・年齢によって差があるかどうかを確認します。 - マッチング拠出の可否
従業員自身も掛金を拠出できるマッチング拠出を認めているかどうかを確認します。 - 運用商品のラインナップ
どのような運用商品が用意されているか、自分の投資方針に合った商品があるかを確認します。 - 退職金制度との関係
企業型DCが退職金制度の一部となっているのか、別制度なのかを確認します。 - ポータビリティの条件
転職時の資産移換についての条件や手続きを確認します。 - 投資教育の内容
企業がどのような投資教育を実施しているかを確認します。充実した教育体制は効果的な運用につながります。
これらのチェック項目を事前に確認することで、転職後の資産形成について見通しを立てることができます。不明点があれば、面接時や内定後に人事担当者に質問することも重要です。
転職時に損をするケースはどのように発生するか
企業型確定拠出年金は、転職時に適切な手続きを行わないと、思わぬ損失を被る可能性があります。ここでは、どのようなケースで損失が発生するのかを詳しく見ていきましょう。
企業型DCの資産移換にまつわるトラブル例
転職時の企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産移換では、以下のようなトラブルが発生することがあります。
手続き期限切れによる自動移換
資格喪失(退職)後6ヶ月以内に移換手続きを行わないと、資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されます。自動移換されると、資産は現金化されて運用できなくなり、また手数料が継続的に発生します。
さらに、自動移換期間は老齢給付金の受給資格期間にカウントされないため、受給開始時期が遅れる可能性があります。
移換時の市場変動リスク
資産移換時には一度資産が現金化されるため、市場の変動によっては、売却時と再投資時の価格差で損失が生じる可能性があります。特に市場が大きく変動している時期の転職では、このリスクに注意が必要です。
運用商品の選択ミス
転職先での運用商品選択を誤ると、長期的な運用パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。特に転職先の運用商品に不慣れな場合、十分な検討なしに選択してしまうリスクがあります。
これらのトラブルを避けるためには、転職決定後すぐに前職と転職先の企業型DC担当者に相談し、スムーズな資産移換の準備を進めることが重要です。
転職先企業での取り扱い制度との差異
転職前と転職先の企業型確定拠出年金制度には、様々な違いがあり、これらの差異が知らず知らずのうちに損失につながることがあります。
- 掛金額の違い
転職先の企業型DCの掛金が前職よりも少ない場合、老後資産の積立ペースが鈍化する可能性があります。特に、前職では役職に応じた手厚い掛金設定だったのに、転職先では一律の低い掛金設定という場合は注意が必要です。
- 運用商品ラインナップの違い
転職先で選択できる運用商品が前職と大きく異なる場合、自分の投資スタイルに合った商品がない可能性があります。特に、低コストのインデックス投資信託などを活用していた場合、転職先にそうした商品がないと運用コストが上昇するリスクがあります。
- マッチング拠出の有無
前職ではマッチング拠出(従業員自身による追加拠出)が可能だったのに、転職先では不可能という場合、税制優遇を活用した資産形成の機会が減少します。
- 投資教育サポートの差
前職では充実した投資教育が行われていたのに、転職先ではほとんど行われていない場合、適切な投資判断が難しくなるリスクがあります。
- 手数料体系の違い
転職先の制度では運用商品の信託報酬や口座管理手数料が高くなる可能性があります。長期的には小さな手数料の差も大きな影響を与えます。
転職を検討する際には、給与や職務内容だけでなく、こうした企業型DC制度の違いも比較検討することが望ましいでしょう。また、転職先の制度が不利な場合は、iDeCoとの併用や個人での資産形成強化など、代替策を検討することも重要です。
損を回避するために知っておくべき確定拠出年金の移換の注意点
企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産移換時に損失を回避するためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。ここでは、制度改正の影響や具体的な移換ルールについて解説します。
確定拠出年金法改正の概要と影響
確定拠出年金法は、社会環境や働き方の変化に対応するため、定期的に改正されています。近年の主な改正とその影響について見ていきましょう。
2022年10月からの法改正では、企業型DCとiDeCoの併用に関するルールが大きく変わりました。これまでは企業型DCに加入している人がiDeCoに加入するには、企業型DCの規約で認められており、かつ企業型DCの事業主掛金が拠出限度額に達していないことが条件でした。
しかし、法改正後は企業型DCの規約で認められていれば、事業主掛金の額にかかわらずiDeCoに加入できるようになりました。
この改正により、転職時の選択肢が広がりました。たとえば、転職先に企業型DCがある場合でも、運用商品や手数料面で魅力的なiDeCoを選んでそちらに資産を移換するという選択が可能になりました。
また、他の重要な改正としては、2017年1月からのiDeCo加入対象者の拡大があります。これにより、専業主婦(夫)や公務員も含め、基本的にすべての20歳以上60歳未満の方がiDeCoに加入できるようになりました。
転職してさまざまな立場になった場合でも、iDeCoを活用した資産形成を継続できる環境が整っています。
さらに、65歳までの加入年齢の引き上げや、受給開始時期の選択肢の拡大なども行われ、より柔軟な制度設計になってきています。これらの改正は、転職や働き方の変化があっても、確定拠出年金を通じた老後資産形成を継続しやすくするものです。
今後も社会情勢に応じた制度改正が予想されるため、常に最新情報をチェックしておくことが重要です。
中小企業退職金共済(中退共)などとの併用について
企業型確定拠出年金と中小企業退職金共済(中退共)などの他の退職給付制度を併用する場合の注意点について解説します。
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員のための退職金制度です。企業型DCとは異なり、運用は個人ではなく機構が行い、掛金と予定利率に基づいて将来の給付額が決まります。中退共と企業型DCは併用が可能ですが、いくつか注意点があります。
- 拠出限度額の管理
企業型DCと中退共を併用する場合、企業型DCの拠出限度額(月額5.5万円)から中退共の掛金相当額を差し引いた額が、実際の企業型DC拠出限度額となります。企業はこの上限を超えないよう、掛金設計に注意する必要があります。
- 制度間の移行
企業が成長して中小企業の要件を満たさなくなった場合、中退共からの脱退が必要になります。その際、積立資産を企業型DCに移換することが可能です。ただし、従業員の同意が必要であり、一部資産が減額される可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
- 役員の加入資格
中退共では役員は加入できませんが、企業型DCでは役員も加入可能です。役員の退職給付を考える場合、企業型DCの活用を検討する価値があります。
- 転職時の取り扱いの違い
中退共は転職時に一時金として受け取るか、転職先が中退共に加入していれば資産を移換することができます。一方、企業型DCは前述のように様々な移換先があります。両制度に加入している場合は、それぞれの特性を理解した上で適切な選択をする必要があります。
- iDeCoとの関係
中退共に加入していても、iDeCoへの加入は可能です。企業型DCとiDeCoの併用と同様、税制優遇を最大限活用するための選択肢となります。
- 税制優遇の違い
中退共の掛金は全額損金算入できる一方、給付時には退職所得課税が適用されます。企業型DCも掛金は全額損金算入できますが、給付時には退職所得控除または公的年金等控除が適用されます。税制面での違いも理解しておくことが重要です。
中退共と企業型DCは、それぞれに特徴があり、企業や従業員のニーズに応じて適切に組み合わせることで、より効果的な退職給付制度を構築できます。併用する場合は、各制度の特性や限度額管理などの注意点をしっかり理解し、従業員に十分な説明を行うことが重要です。
まとめ
企業型確定拠出年金は、老後の資産形成を支援する重要な制度ですが、転職時には適切な対応が求められます。本記事では、企業型確定拠出年金の基本から転職時の注意点まで幅広く解説してきました。
転職や退職を検討している方は、企業型確定拠出年金の資産をどう扱うかをしっかり検討し、必要な手続きを期限内に行いましょう。また、企業側も従業員への適切な情報提供と投資教育を行い、制度の効果的な運用をサポートすることが求められます。
老後の資産形成は早い段階から計画的に取り組むことが重要です。企業型確定拠出年金を有効活用し、将来の経済的安定を実現しましょう。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。

.jpg&w=1080&q=75)