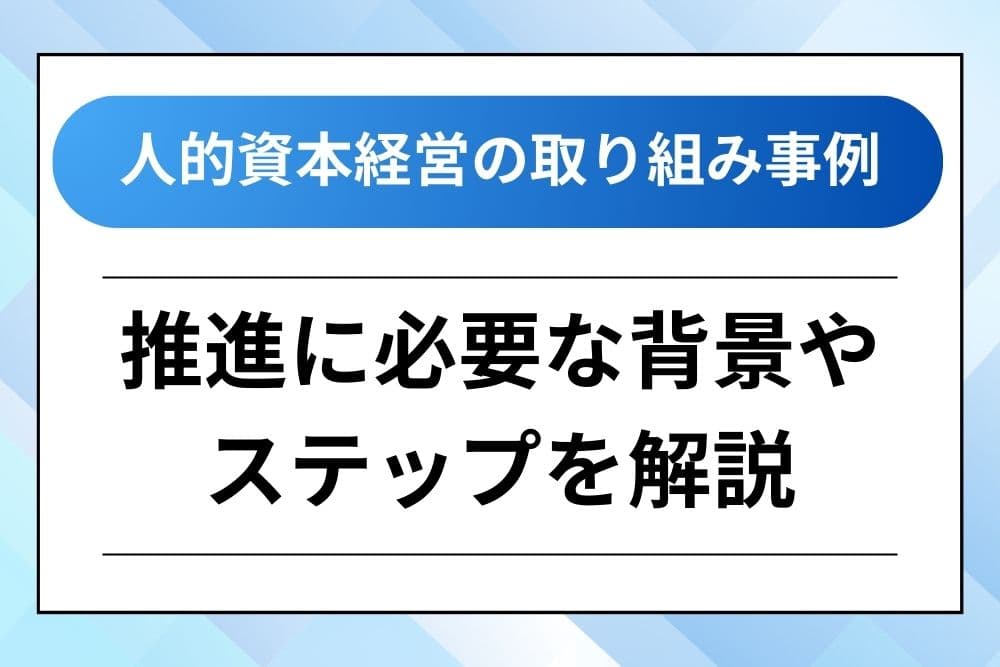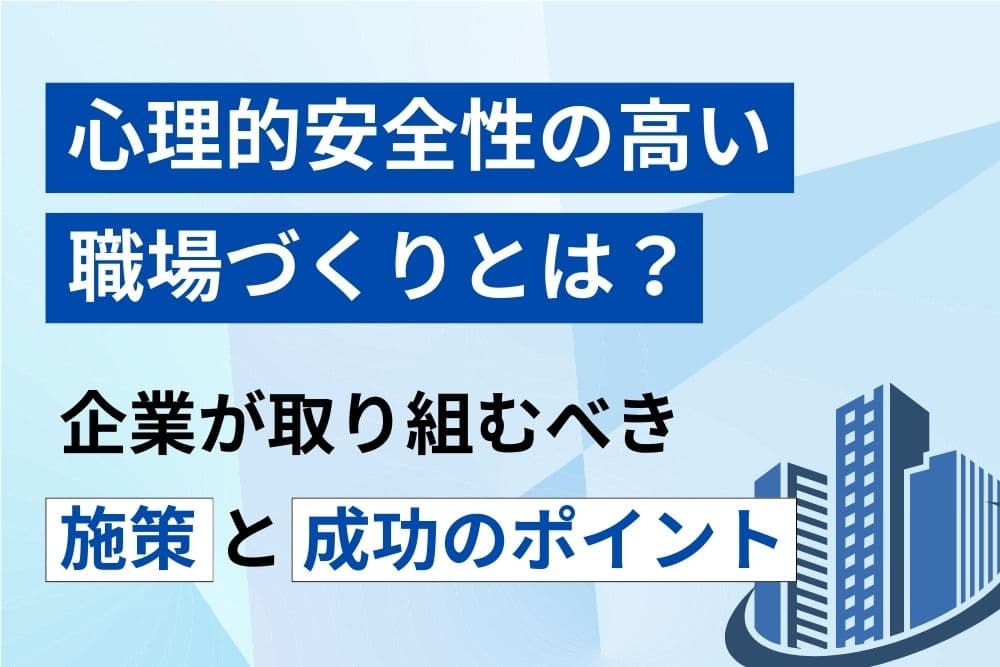お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
エンゲージメント経営とは?導入するメリットや特徴、事例や実践方法を徹底解説
 詳細を見る
詳細を見る%2520(1).jpg&w=1080&q=75)
エンゲージメント経営とは
エンゲージメント経営が企業にもたらすメリット
エンゲージメント経営を支える人事施策のポイント
金融・人事の専門家視点から見るエンゲージメント経営のROI
エンゲージメント経営の流れ
みなさんは、自社の従業員が仕事に熱意を持ち、会社に愛着を感じながらいきいきと働いていると言えるでしょうか? 近年、「エンゲージメント経営」という言葉を耳にする機会が増えています。
従業員と企業の信頼関係や絆を高め、互いに高め合う経営手法のことです。特に人事担当者や経営層の方にとって、社員のモチベーションや定着率の向上は重要な課題です。
エンゲージメント経営は、この課題を解決する新たなアプローチとして注目されています。
本記事では、エンゲージメント経営の基本的な意味や重要性から、導入することで得られるメリット、具体的な事例、そして実践するためのポイントまでを丁寧に解説します。
従業員エンゲージメントと似た言葉である従業員満足度との違いや、日本企業と海外企業の取り組みの差にも触れながら、なぜ今エンゲージメント経営が求められているのかを解説していきます。
目次
エンゲージメント経営とは何か

まず、エンゲージメント経営という言葉の意味を押さえておきましょう。エンゲージメント経営とは、従業員の会社に対するエンゲージメント(愛着心や信頼、貢献意欲)を高めることで、従業員が自発的に能力を発揮し、組織全体の成果向上を図る経営手法です。
関連記事:従業員エンゲージメントとは
簡単に言えば、社員と会社がお互いに強い信頼関係で結ばれ、二人三脚で成長していくような経営を目指すものです。
エンゲージメントが高い状態とは、社員が「この会社のために力を尽くしたい」「自分の仕事が会社や社会に役立っている」と感じながら働けている状態です。内部エンゲージメントという言い方もあります。
その結果、仕事への熱意や主体性が生まれ、新しいアイデアの提案や積極的な問題解決など、プラスアルファの貢献が期待できます。一方でエンゲージメントが低いと、言われたことだけをこなす受け身の働き方になりがちで、生産性の低下や離職の増加につながってしまいます。
このような背景から、従業員(内部)エンゲージメントを高める経営が注目されています。従来は給与アップや福利厚生の充実といった施策で従業員満足度を高め、定着率向上を図るのが一般的でした。
しかし、満足度だけでは社員の主体的な成長や熱意まで引き出すことは難しく、現代ではそれ以上に心のつながりややりがいを重視したエンゲージメント経営へのシフトが進んでいるのです。
エンゲージメント経営がなぜ重要なのか
では、なぜ今エンゲージメント経営がこれほど重要視されているのでしょうか。その背景には、経営環境の変化と人材に関する課題があります。
まず第一に、少子高齢化による人手不足が深刻化するなか、優秀な人材の確保と定着が企業の死活問題となっています。従業員の転職へのハードルが下がり、働く側がより良い職場環境を求めて流動化する時代において、社員に「この会社で働き続けたい」と思ってもらうには、給与や福利厚生だけでなく働きがいや職場への愛着を感じてもらうことが欠かせません。
エンゲージメント経営によって社員の愛社精神や仕事への熱意を高めることは、離職防止と人材流出の抑制に直結します。
第二に、企業の競争力強化の観点があります。イノベーションが求められる現代、社員一人ひとりが主体的に考え行動する組織でなければ、新しいアイデアや改善提案は生まれにくくなります。
エンゲージメントが高い職場では、社員が自ら進んで提案や挑戦を行う文化が醸成され、生産性やサービス品質の向上、ひいては業績アップにつながります。実際、世界的な調査では従業員エンゲージメントの高い企業ほど生産性が約15〜20%高く、利益率も20%以上向上するとのデータもあります。つまり、エンゲージメント経営は企業の成長戦略と直結しているのです。
さらに、日本企業特有の事情として、従業員エンゲージメントの低さが指摘されています。米国の調査機関ギャラップによれば、直近の調査で「自社に熱意あふれる社員」の割合はアメリカが約30%であるのに対し、日本はわずか6%程度と世界最低水準でした。
この数字は、国内企業にとって見過ごせない警鐘です。エンゲージメント経営が重要なのは、日本全体として労働生産性を高め国際競争力を維持するためにも、社員のやる気と定着率を底上げする取り組みが急務であるということでもあります。
まとめると、エンゲージメント経営が重要視される背景には、人材確保(離職率低下と採用難への対応)、競争力強化(生産性向上とイノベーション促進)、そして日本企業におけるエンゲージメント水準の改善という課題があります。
こうした理由から、「エンゲージメント経営を行わない企業は淘汰されていく」とまで言われ、今や経営層にとって避けて通れないテーマとなっているのです。
エンゲージメントの定義と経営への影響
ここで改めて「エンゲージメント」という言葉自体の意味を整理しておきましょう。ビジネスにおける従業員エンゲージメントとは、社員が自社に対して抱く信頼や愛着、そして「この会社のために貢献したい」という意欲や情熱の度合いを指します。
単なる契約上の労働関係を超えて、心理的にどれだけ深く結びついているかを表す指標と言えます。
エンゲージメントが高い社員は、与えられた仕事以上のことにも前向きに取り組み、困難に直面しても粘り強く解決策を模索します。例えば、顧客対応でトラブルが起きた際にも「自分ごと」として迅速に対処し、信頼回復に努めるでしょう。
また、自社のミッションや目標を自分のものとして捉え、達成に向けて主体的に動いてくれます。こうした姿勢は生産性向上や顧客満足度の向上に直結し、結果的に企業業績にもポジティブな影響を与えます。
エンゲージメントという指標は、単に社員の機嫌や満足度を見るものではなく、企業と社員の関係性の質そのものを示す重要なものなのです。そしてその質が高ければ高いほど、経営に良い影響をもたらし、低ければ組織パフォーマンスに悪影響を及ぼします。
経営層にとって、エンゲージメントを定期的に把握し高めていくことは、人材戦略のみならず経営戦略上の必須事項となりつつあります。
エンゲージメントと従業員満足度の違い
しばしば混同されがちな概念に従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)があります。従業員満足度は、その名の通り社員が会社にどれだけ満足しているか、待遇や職場環境に対して不満がないかといった“一方通行の評価”を測るものです。
例えば給与水準や福利厚生、勤務時間や上司との関係などにおいて、社員が「まあ満足している」と感じている状態を指します。
一方、従業員エンゲージメントは前述のように、社員と会社の相互の信頼関係や愛着心に基づく“双方向のつながり”を示す指標です。
満足度が「会社が社員に提供するもの」に対する評価だとすれば、エンゲージメントは「社員が会社にどれだけ尽くしたいと思っているか」という主体的な思いの強さと言えます。
両者は関連する概念ではありますが、必ずしも一致しません。たとえば、給与や待遇に満足している社員(満足度が高い社員)でも、自社への愛着や誇りが薄ければエンゲージメントは低い可能性があります。
逆に、多少不満要素があっても「この会社で成長したい」「仲間と達成感を味わいたい」という気持ちが強ければ、エンゲージメントは高く維持されるでしょう。つまり、満足=エンゲージメントではないのです。
また、安定性の違いも指摘できます。エンゲージメントは信頼関係に基づくため、一朝一夕では築けないものの、一度高い状態になると多少の困難では揺らぎにくいと言われます。
これに対し満足度は、例えば昇給が見送られたりオフィス環境が悪化したりといった要因で簡単に低下してしまう傾向があります。このような違いから、企業としては満足度だけでなくエンゲージメントを高める施策に力を入れる必要があるのです。
日本企業と海外企業の意識・取り組みの違い
従業員エンゲージメントへの取り組みには、日本企業と海外企業で意識や手法に違いが見られます。前述のとおり日本のエンゲージメント水準は国際的に見て非常に低く、これは必ずしも日本人の働きぶりが悪いというより、企業側のマネジメント手法や文化に起因する部分が大きいと指摘されています。
海外では以前からエンゲージメント調査(社員意識調査)を定期的に実施し、その結果を経営改善に活かす企業が多く存在します。経営陣自らが従業員の声に耳を傾け、職場環境や制度を柔軟に変えていくことで、社員のモチベーション維持に努める文化が根付いているのです
。例えば、米国の企業では四半期ごとに従業員エンゲージメントスコアを測定し、管理職の評価指標に組み込むケースもあります。また、社員表彰制度やボトムアップ型の提案制度など、社員の自主性を引き出す取り組みも一般的です。
一方、日本企業では長年、終身雇用や年功序列といった制度のもと、従業員が会社に定着することが前提となっていました。そのため「社員は会社に尽くすもの」「会社は生活を保証するもの」という暗黙の了解のような関係が築かれ、改めてエンゲージメントを測定したり高めたりする発想が乏しかった面があります。
しかし近年、働き方の多様化や若手社員の価値観変化により、企業のビジョンと社員個人の価値観をすり合わせる重要性が認識され始めました。日本企業でもエンゲージメントサーベイ(意識調査)の導入や、フラットなコミュニケーション文化づくりに着手するところが増えています。
加えて、海外では「従業員は貴重な資本である」という考え方が以前から浸透しており、人材開発や社員のウェルビーイング向上に積極的に投資する企業が多い傾向にあります。
日本でも近年は「人的資本経営」というキーワードのもと、社員をコストではなく資本と捉え、そのエンゲージメントや成長に投資する動きが加速しています。ただ、現状では海外先進企業と比べて制度整備やマインドセットにギャップがあり、これを埋めていくことが課題と言えるでしょう。
エンゲージメント経営が企業にもたらすメリット
1.(労働生産性)生産性向上とイノベーション創出
エンゲージメント経営の最大のメリットの一つが、従業員の生産性向上です。社員が仕事に熱意を持ち、主体的に動けば、同じ時間内でも生み出せる成果が増えます。
例えば、指示待ちではなく自分で考えて行動する社員が増えれば、業務の無駄を自発的に省いたり、効率的な手順を提案したりするでしょう。その結果、プロジェクトの納期短縮やサービス品質の向上といった具体的な成果が現れます。
また、イノベーションの創出にもつながります。エンゲージメントが高い組織では、社員が安心して意見を出せる雰囲気が醸成されているため、「こんな改善はどうか」「新しい商品アイデアを試したい」といった提案が活発になります。
実際に、社内公募制度やアイデアコンテストを導入して新規事業の種を発掘している企業もありますが、これらは社員のエンゲージメントが高くなければ形骸化してしまいます。
逆にいえば、エンゲージメント経営によって社員のやる気と創造性を引き出せれば、そこから思わぬ革新的な商品・サービスが生まれる可能性が高まります。
つまり、エンゲージメント経営は日々の業務効率を上げると同時に、将来の成長を支える新たな価値創造の原動力にもなるのです。
2.(離職率への影響)離職率の低減と採用コスト削減
社員のエンゲージメントが高まると、離職率の低減という形で大きなメリットが得られます。会社への愛着や信頼感が強い社員は、多少困難なことがあっても簡単には辞めません。
逆にエンゲージメントが低ければ、些細な不満や他社からの誘いをきっかけに離職してしまうケースが増えます。エンゲージメント経営を推進し社員との絆を深めることは、「この会社でもう少し頑張ってみよう」と思ってもらえる土壌を作ることにほかなりません。
離職率が下がれば、当然ながら採用コストの削減につながります。新たな人材を採用し育成するには時間も費用もかかります。特に専門性の高い職種では、一人辞めると代わりを見つけるまでに数百万円規模のコストがかかるとも言われます。
優秀な人材の流出を防ぎ定着してもらえれば、こうした採用・研修コストの浪費を抑えることができます。また社内に経験やノウハウが蓄積しやすくなるため、中長期的には組織力の強化にもつながるでしょう。
例えばある企業では、エンゲージメント向上施策(上司と部下の定期面談やキャリア支援プログラム等)を実施したところ、翌年の離職者数が前年より大幅に減少し、人件費に対する採用費用の比率も下がったという報告があります。
このようにエンゲージメント経営は、人材の定着率を高めることで経営資源のロスを防ぎ、安定した組織運営に寄与します。
3.(関係性)企業と社員の関係性が良好になる
エンゲージメント経営によって得られるもう一つの利点は、企業と社員の関係性が良好になることです。信頼に基づく良好な関係は、職場の雰囲気やコミュニケーションにも大きく影響します。
社員が「会社は自分たちを大切にしてくれている」と感じ、会社も「社員がよく頑張ってくれている」とお互いに思える状態になれば、職場には一体感や安心感が生まれます。
具体的には、経営層や上司と社員との間で建設的な対話が増えます。エンゲージメントの高い組織では、経営理念や目標に対する共通認識が浸透しているため、日々の会話でも「どうすればもっと良くできるか」「会社のために何ができるか」といった前向きな話題が出やすくなります。
また、社員が心理的安全性を感じていれば、問題点や改善提案も遠慮なく共有できるため、ミスの早期発見・対応や業務改善のスピードアップにつながります。
さらに、社員と会社がお互いを信頼しサポートし合う関係が築かれると、従業員エクスペリエンス(社員が会社で経験する体験価値)が向上します。
社員にとって働くこと自体がやりがいや誇りにつながれば、「この職場で長く働きたい」と感じるようになりますし、会社側も安心して権限委譲や人材育成に踏み込めるようになります。このようにして生まれる好循環は、組織全体の安定と成長を下支えします。
4.(ブランディング)ブランド力強化と顧客満足度への波及効果
従業員エンゲージメントの向上は、社内だけでなく社外にも良い影響をもたらします。その代表的な例が、企業ブランド力の強化と顧客満足度への波及効果です。社員が自社に誇りと愛着を持って働いている姿は、企業のイメージアップに直結します。
エンゲージメントが高い社員は自社の商品やサービスに自信と責任を持っているため、顧客対応にも熱意がこもり、質の高いサービス提供につながります。
例えば、小売業などでは、現場スタッフのモチベーションがお客様の満足度に大きく影響します。エンゲージメントの高い従業員は笑顔で丁寧な接客を心がけ、たとえトラブルが起きても真摯に対応するため、結果的にお客様からの信頼も獲得しやすくなります。
従業員満足度(ES)が上がれば顧客満足度(CS)も上がるという「サービス利益連鎖」の考え方がありますが、エンゲージメント経営はまさにこの好循環を生み出す土台となります。
また、社員が自社の熱心なファンであれば、SNSや友人知人を通じて自然と良い評判が広がることも期待できます。最近では就職・転職希望者がお店やSNSで社員の生の声を参考にする時代です。
社員が自社を誇りに思っていれば、「この会社で働いてみたい」「この会社の製品なら信頼できそう」と周囲に感じさせる力となります。つまり、エンゲージメント経営は採用ブランディングや顧客から選ばれるブランド作りにも寄与する、一石二鳥の効果を持っています。
エンゲージメント経営を支える人事施策のポイント
1.明確なビジョン・ミッションの共有
社員のエンゲージメントを高めるには、まず会社のビジョンやミッションを明確に示し、共有することが重要です。人は自分の仕事がどんな価値につながるのかを理解できたとき、大きなやりがいを感じます。
そこで経営層は、自社が目指す方向性(「私たちの存在意義は何か」「将来どう社会に貢献したいのか」)をしっかり言語化し、社内に浸透させましょう。
単に経営理念を掲示するだけでなく、日々のコミュニケーションや社内イベントなどを通じて繰り返し発信することが大切です。
例えば朝礼でミッションステートメントを唱和したり、経営者自ら自社のビジョンについて語る機会を設けたりする企業もあります。また、ビジョンと各社員の目標を紐づける工夫も有効です。
上司が1on1ミーティングで「あなたの今の仕事は会社のこの目標に貢献している」と伝えるなど、社員一人ひとりが自分の役割の意義を実感できるようにしましょう。
ビジョン・ミッションが腹落ちすれば、「この会社の一員であることが誇らしい」「目標達成に貢献したい」という思いが自然と芽生えてきます。
2.公正な評価制度とキャリア開発支援
社員が安心して力を発揮できる環境を整えるためには、公正な評価制度とキャリア開発の支援が欠かせません。どんなに頑張っても正当に評価されなかったり昇進の機会が不透明だったりすると、社員の士気は下がりエンゲージメントも損なわれてしまいます。
人事部門は、成果や貢献を適切に反映した評価・報酬制度を整備し、運用の透明性を高めましょう。
具体的には、評価基準を明文化して社員に開示したり、上司による評価フィードバック面談を定期的に実施したりするといった取り組みが考えられます。また、社員のキャリア開発を支援することもエンゲージメント向上に有効です。
研修や自己啓発の機会提供、ジョブローテーション制度、メンター制度など、社員が成長できる場を用意しましょう。自分の成長が実感できると「この会社で長く働きたい」「もっと貢献できるよう頑張ろう」という前向きな気持ちが生まれます。公平な評価とキャリア支援の充実は、社員の信頼感を高めエンゲージメントを底上げする基盤となります。
3.組織文化づくりと心理的安全性の確保
エンゲージメント経営を支えるには、社員が安心して意見を言え、挑戦できる組織文化を醸成することも重要です。その鍵となるのが職場の心理的安全性です。心理的安全性とは、簡単に言えば「このチームでは本音を言っても大丈夫」「失敗しても責められない」という安心感のこと。これが確保されていると、社員は自分らしく働け、積極的に意見やアイデアを出せるようになります。
人事としては、各部署の管理職に対して心理的安全性の重要性を教育し、率先してオープンなコミュニケーションを取るよう働きかけましょう。
具体的な施策としては、定期的な1on1ミーティングで部下の悩みや提案に耳を傾ける、会議で発言しやすい雰囲気をつくる、失敗事例を共有して学びに変える文化を推奨する、といったものが考えられます。また、ハラスメントの防止や、公平でインクルーシブな職場づくりも心理的安全性には不可欠です。
組織文化は一朝一夕には変わりませんが、小さな積み重ねがやがて大きな信頼の風土を築きます。社員同士が尊重し合い、上司にも遠慮なく意見できる環境が整えば、社員の会社に対するエンゲージメントは飛躍的に高まるでしょう。
4.社員を守る福利厚生、働きやすい環境構築
社員が心身ともに健康で安心して働けるよう、手厚い福利厚生や働きやすい職場環境を整備することもエンゲージメント向上に寄与します。企業が社員の生活や健康を気遣いサポートする姿勢を示すことで、「大切にされている」という安心感が生まれ、会社への信頼と愛着が深まります。
例えば、健康診断の充実や予防医療への補助、メンタルヘルス相談窓口の設置、育児・介護休業制度の拡充、リフレッシュ休暇の導入など、社員を守るための制度は多岐にわたります。
また、働きやすい環境づくりとして、オフィスの快適性向上(フリースペースやリラクゼーションルームの設置等)や在宅勤務・フレックスタイム制度の導入も有効でしょう。仕事と家庭の両立を支援する取り組みは、社員のワークライフバランス満足度を高め、結果的に仕事への集中度も上がります。
さらに、近年注目されているのが社員の経済面を支える福利厚生です。給与以外の部分で社員の生活の質を向上させる施策として、金融教育サービスの提供があります。
「マネーリペア」福利厚生による金融教育サービスの提供
従業員の多くは日々の生活費や将来の資金計画など、お金に関する悩みや不安を少なからず抱えています。そこで企業が福利厚生の一環として金融教育サービスを提供すれば、社員の金銭面のリテラシー向上と不安の解消につながります。
具体的には、資産形成や税金対策、保険の見直しといったテーマで専門家によるセミナーや相談会を実施したり、役立つ金融知識を発信するコンテンツを社内向けに提供したりする形が考えられます。
このような金融教育を受けることで、社員は手取り収入を増やすための知識や将来に備える資産運用のコツを身につけることができます。
例えば、節税制度(年末調整やふるさと納税等)の活用や、NISA・iDeCoといった投資制度の正しい理解が深まれば、無駄な税金の支払いを減らし貯蓄を効率よく増やすことができます。結果として、社員の経済的な安心感が高まれば、仕事に専念しやすくなりエンゲージメント向上にもつながります。
福利厚生として金融教育を導入する企業は増えており、社員からも「お金の知識が身についた」「将来への不安が和らいだ」と好評です。会社にとっても、社員の金銭ストレスが軽減すれば生産性アップや離職防止といったメリットが期待できます。
まさに社員と会社双方にメリットがある先進的な福利厚生と言えるでしょう。

金融・人事の専門家視点から見るエンゲージメント経営のROI
人的資本投資の捉え方と測定指標
エンゲージメント経営への取り組みを検討する際、経営者やCFO(財務責任者)の視点から気になるのは投資対効果(ROI:Return on Investment)でしょう。社員の研修や福利厚生に予算を投じることは、いわば人的資本への投資です。
そのリターンをどのように測定し評価するかが、専門家の間でも議論されています。
人的資本投資のROIを捉える指標として、いくつかのアプローチがあります。まず直接的なものとして、離職率や従業員エンゲージメントスコアの改善が挙げられます。エンゲージメント経営により離職率が下がれば、新たな採用・育成にかかるコスト削減という定量的なリターンが得られます。
同様に、従業員サーベイでエンゲージメントスコアが向上すれば、それ自体が社員満足度や意欲の高まりを示す成果といえます。
さらに一歩踏み込んで、従業員一人当たり売上高や人件費あたり利益といった生産性・収益性の指標で効果を測る方法もあります。例えば、人材に投資した結果として一人当たりの売上が上昇したり、利益率が向上したりすれば、それは人的資本投資のROIがプラスであることを意味します。
実際に「人的資本ROI」という指標も提唱されており、(営業利益などの成果)÷(人件費や教育訓練費など人材投資額)で算出することで、人材投資がどれだけ企業の利益に貢献しているかを定量化しようという試みもあります。
近年では、エンゲージメントの高さと財務指標との相関を分析した調査も出てきています。それによれば、従業員エンゲージメントの高い企業ほどROE(自己資本利益率)や株価の指標(PBR等)が良好な傾向が見られるとの報告もあります。
もちろんエンゲージメントだけが原因ではないにせよ、社員を大切にしエンゲージメントを高める経営は、長期的に見て企業価値の向上にもつながると専門家は指摘しています。
福利厚生・給与制度の最適化と財務インパクト
人事・財務双方の観点から、福利厚生や給与制度を最適化することも重要です。限られた予算の中で社員のエンゲージメントを最大化するには、効果の高い施策にメリハリをつけて投資する必要があります。
例えば、単にベース給与を一律に引き上げるよりも、社員が価値を感じる福利厚生に充当した方がエンゲージメント向上に効果的な場合があります。ある調査では、「自社の福利厚生に満足している社員」はそうでない社員に比べてエンゲージメントスコアが有意に高いという結果も報告されています。社員のニーズを把握し、費用対効果の高い施策に絞って実施することがポイントです。
具体的には、健康経営や先述の金融教育プログラムなどは比較的少ないコストで大きな効果を生むケースがあります。社員の健康増進施策に投じた費用が、病欠の減少や医療費負担の軽減となって企業コストを下げたり、生産性向上による業績改善という形でリターンを生むこともあります。
同様に、エンゲージメント向上策にかけたコストが離職削減による採用費圧縮や、業績アップにつながれば、投資に対する十分な財務インパクトがあったと評価できます。
一方で、給与水準そのものの適正化も無視できません。業界水準と比べて極端に低い給与であればどんな施策を講じても離職は防げませんし、不公平な給与体系はエンゲージメントの阻害要因となります。
したがって、給与(直接的報酬)と福利厚生・非金銭的報酬のバランスをとりながら、総合的にリワード(報酬制度)を設計することが重要です。その最適化こそが、社員満足と会社の費用対効果を両立させ、結果的にエンゲージメント経営のROIを高める鍵と言えるでしょう。
エンゲージメント経営の流れ
エンゲージメント経営を実践するには、計画的にステップを踏んで取り組むことが大切です。以下に、一般的な進め方の流れを示します。
1.現状診断:組織サーベイとKPI設定
まずは自社のエンゲージメントの現状を正しく把握することから始めます。具体的には、従業員エンゲージメントサーベイ(意識調査)を実施しましょう。匿名で回答できるアンケートを通じて、社員の会社に対する信頼度や満足度、職場環境への意見などを収集します。
あわせて、離職率や平均勤続年数、有給消化率など現在の人事関連データも確認するとよいでしょう。
調査結果を分析し、経営層と人事で共有したうえで、KPI(重要業績指標)を設定します。例えば「エンゲージメントスコアを次回調査で10ポイント向上させる」「年間離職率を5%未満に抑える」など、目標とする数値を明確に定めます。
現状診断とKPI設定によって、課題の輪郭がはっきりし、次のステップへの指針が得られます。
2.課題抽出:問題点や改善点を洗い出す
サーベイ結果や各種データから、自社のエンゲージメント向上を阻んでいる問題点や改善点を洗い出します。
例えば、上司とのコミュニケーションに関する設問のスコアが低ければ「評価面談の頻度や質に課題あり」、部署間連携に不満の声が多ければ「組織のサイロ化が問題」といった具合に、症状と原因を紐づけて整理します。
この段階では、社員から自由記述で募った意見や、退職者のフィードバックなども参考にすると効果的です。
定量データと定性意見の両面から分析し、「何が社員のエンゲージメントを下げているのか」「どの分野を改善すれば効果が大きいか」を見極めます。課題に優先順位をつけ、着手すべきテーマを絞り込むことがポイントです。
3.目標策定:経営陣と人事部門の協働体制
課題が明確になったら、それらを解決するための目標を策定します。この際、経営陣と人事部門がしっかり協働し、一枚岩で取り組む体制を作ることが重要です。経営層はエンゲージメント経営の意義を理解し、自らコミットする姿勢を示しましょう。
目標は前述のKPIを踏まえ、具体的かつ達成可能なものに落とし込みます。例えば「社内コミュニケーション活性化」を目標に掲げる場合、「経営トップによる全社タウンホールミーティングを四半期ごとに実施」「部門長による月次1on1を全社員対象に実施」といった具合に、誰が何をするかを明文化します。経営陣と人事が連携し、このような目標と計画を社内に発信することで、全社的な理解と協力を得る土台ができます。
4.アクションプラン策定:ガイドラインを作成する
設定した目標を達成するため、具体的なアクションプラン(施策の計画)を策定します。人事部門を中心に、関係部署とも連携して、いつまでにどのような施策を実行するかを決めていきます。
例えば、コミュニケーション活性化が課題なら「社内SNSツールを導入し社員同士の感謝を伝え合う仕組みを開始する」「部門を横断したプロジェクトを立ち上げ異なる部署の交流機会を増やす」などの具体策を洗い出します。
これらを実行する上でのガイドラインも整備します。ガイドラインには、施策の目的・内容、担当者、スケジュール、評価方法などを明記し、社内で共有します。これにより、現場の管理職や社員も含め、組織全体で一貫した行動をとれるようになります。
5.評価・改善サイクル:PDCAで持続的に高める
施策を実行した後は、効果検証と改善のサイクルを回します。具体的には、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルに沿って、エンゲージメント向上策を継続的に見直します。
一定期間(例えば半年から1年)経過後に再度エンゲージメントサーベイを実施し、KPIの達成度を確認します。スコアが向上していれば成功事例として展開し、改善しきれていない項目があれば新たな施策を検討します。
また、社員からのフィードバックも逐次集め、現場感覚とのズレがないかチェックします。
このように評価・改善を繰り返しながら、エンゲージメント経営を企業文化として根付かせていきます。一度で完璧に成果を出そうとするのではなく、トライアル&エラーを繰り返しつつ着実に前進する姿勢が大切です。
継続的な取り組みにより、エンゲージメントは徐々に底上げされ、強い組織力が構築されていくでしょう。
エンゲージメント経営を成功させるための実践ポイント
エンゲージメント経営を軌道に乗せるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。以下に成功のための3つの要点をまとめます。
企業方針を明確化
まず、会社としてエンゲージメント向上に取り組むという明確な方針を打ち出すことが欠かせません。経営トップが「人を大切にする経営」をコミットメントし、その姿勢を社内外に示すことで、初めて本格的な取り組みが可能になります。
企業理念や経営計画の中にエンゲージメント向上を位置づけるなど、会社の方針として明文化しましょう。
方針を明確にしたら、それを全社員に周知徹底することも重要です。「なぜエンゲージメントが必要なのか」「どんな組織を目指すのか」を繰り返し説明し、社員一人ひとりの理解と協力を得ます。トップメッセージとして社内報や朝会で訴えるのも有効です。会社の揺るがぬ方針が示されれば、現場も安心して追随でき、組織一丸となって取り組めます。
正確にエンゲージメント調査ができる環境構築
次に、従業員の本音を正確に把握できる仕組みを整えることが必要です。エンゲージメント調査(サーベイ)は、匿名性の確保や集計分析の客観性が肝心です。社員が安心して率直な回答ができるよう、信頼できる第三者ツールを使ったり、アンケート回答が完全に匿名であることを周知したりしましょう。
また、結果の分析手法や評価指標も整備します。社内にデータ分析の専門家がいれば参加してもらい、いなければ外部サービスの力を借りるのも一つです。ポイントは、正しい現状認識ができる環境を作ること。
そのためには、社員の声を歪みなく収集する土壌と、得られたデータを適切に読み解くスキル・ツールが必要です。この準備があってこそ、施策の効果検証も的確に行えます。
双方のコミュニケーションを大切にする
最後に、経営陣と社員の双方のコミュニケーションを重視する姿勢です。エンゲージメント経営は一方通行では成り立ちません。上層部からのメッセージ発信と同時に、社員からのフィードバックを受け止める風通しの良さが必要です。
経営陣は、現場の意見や提案に耳を傾け、可能なものは積極的に採用・実行するよう心がけましょう。たとえば、全社アンケートの結果を社員にフィードバックして「ここは改善する」「これは次年度検討する」と発信すれば、社員は自分たちの声が届いたと感じ信頼感が高まります。
また、日常的にも上司と部下の対話や、現場社員と役員の懇談会など双方向のコミュニケーション機会を増やすことが大切です。お互いに言うべきことを言い合える関係が築ければ、誤解や不満が蓄積しにくくなり、エンゲージメントは自然と向上していくでしょう。
エンゲージメント経営と福利厚生の取り組み
健康経営・ウェルビーイングとの相乗効果
エンゲージメント経営を語る上で、社員の健康やウェルビーイング(心身の幸福状態)への配慮は切り離せません。健康経営とは、社員の健康増進を経営的視点で捉え戦略的に推進する考え方で、日本でも多くの企業が取り組み始めています。社員の心身の健康が守られてこそ、仕事への意欲も湧き、エンゲージメント向上につながるからです。
具体的には、定期健康診断の受診率向上や運動促進プログラム、メンタルヘルスケアの充実などが健康経営の施策として挙げられます。これらは直接的に社員のコンディションを整えるだけでなく、「会社が自分たちの健康を本気で考えてくれている」という安心感をもたらします。結果として社員の会社への信頼感が増し、エンゲージメントを高める相乗効果を生みます。
また、ウェルビーイングの観点では、仕事とプライベート両面の充実を支援することが重要です。フレックスタイム制度や在宅勤務制度の導入、カウンセリングサービス提供など、社員一人ひとりの生活の質を高める取り組みが、長期的なエンゲージメント維持に寄与します。
職場積立NISAや企業年金制度を活かした資産形成支援
社員の将来の経済的安定を支援することも、エンゲージメント向上に有効な福利厚生施策です。その一例が、職場積立NISAや企業年金制度を通じた資産形成支援です。職場積立NISAとは、社員が給与天引きなどで少額投資非課税制度(NISA)を活用しやすくする仕組みで、会社が窓口となって積立投資をサポートするものです。
また企業年金(企業型DCや確定給付年金)は、会社が退職金・年金として拠出や運用の機会を提供する制度です。
これらの制度を整えることで、社員は日常業務をしながら将来の資産形成を効率的に行うことができます。例えば、会社がマッチング拠出(一定額を上乗せ拠出)する企業型DCを導入すれば、社員にとっては“給料以外に将来のための貯蓄を会社が手伝ってくれている”という安心感につながります。
職場積立NISAも、金融知識が豊富でない社員でも手軽に投資を始められるメリットがあります。こうした取り組みを通じて、社員は将来への不安を減らし、現在の仕事により集中できるようになります。
実際に、手厚い企業年金や資産形成支援策を持つ企業は、社員ロイヤリティが高い傾向があると言われます。「この会社で働き続ければ将来も安心だ」と思えることが、エンゲージメントを下支えする大きな要因となるのです。
柔軟な就業環境(テレワーク・フレックス制度)の整備
近年、働き方の柔軟性に対するニーズが高まっています。特にコロナ禍を経て、テレワーク(在宅勤務)やフレックスタイム制度は、多くの企業で導入が進みました。これら柔軟な就業環境の整備も、エンゲージメント向上に大きく寄与します。
テレワークやフレックスによって、社員は自分のライフスタイルに合わせて働く時間・場所を調整できるようになります。通勤ストレスの軽減や育児・介護との両立がしやすくなることで、仕事への満足度と集中力が高まります。
また、「柔軟な働き方を認めてくれている」という事実自体が、社員にとっては会社から信頼されている証と受け止められ、モチベーションアップにつながります。一方で、リモート環境下でもエンゲージメントを保つためには、オンラインでのコミュニケーション活性化策(バーチャル会議での工夫や定期的なオンライン懇親会など)も合わせて取り組むと良いでしょう。
柔軟な働き方のメリットを最大限活かしつつ、社員とのつながりを保てれば、地理的な距離を超えて高いエンゲージメントを維持できるはずです。
中小企業がエンゲージメント経営を実現するには
限られたリソースを有効活用するコツ
中小企業の場合、大企業に比べて人員や予算が限られているため、エンゲージメント経営に取り組みたくても「リソースが足りない」と感じるかもしれません。しかし、ポイントを押さえれば、限られたリソースでも効果的にエンゲージメントを高めることは可能です。
コツの一つは、身近なところから着手することです。例えば、特別な予算がなくても、経営者自らが社員一人ひとりと定期的に対話する時間を設けたり、日々の業務の中で社員の努力に感謝の言葉を伝えたりするだけでも、社員のモチベーションは上がります。小規模な組織であればこそ、トップと現場の距離が近いという利点があります。
その強みを活かし、コミュニケーション量を増やす、迅速な意思決定で現場の声に応える、といった取り組みは大きなコストをかけずに実施できます。
また、メリハリある投資も有効です。限られた予算を闇雲に使うのではなく、効果の高い施策に集中投下します。例えば、「従業員満足度アンケートツールの導入には費用をかけるが、無料でできる社内SNS活用はフルに活かす」など、工夫次第で費用対効果を高められます。
重要なのは、規模が小さいからと諦めずに、できる範囲で少しずつでも改善を積み重ねる姿勢です。
外部専門家やツールとの経営・協業事例
中小企業がエンゲージメント経営を進めるにあたっては、外部の専門家やツールを上手に活用することも大きな助けになります。自社内に専門知識やノウハウがなくても、信頼できる外部リソースを取り入れることで効率的に取り組めます。
例えば、従業員エンゲージメントの調査分析に強いコンサルタントや社労士にスポットで協力を仰ぎ、サーベイ設計や結果の読み取り方についてアドバイスをもらうケースがあります。
また、エンゲージメント向上のためのクラウドサービスやアプリを導入し、従業員同士の称賛(ピアボーナス)を促進するなど、ツールの力を借りる方法もあります。
前述の金融教育サービス「マネーリペア」のように、福利厚生部分を外部サービスに委ねることで社内負担を軽減しつつ社員満足度を上げる取り組みもその一例です。
こうした外部との協業は、自社にない発想や最新の知見を取り入れるチャンスでもあります。中小企業では「人手が足りないからできない」となりがちですが、外部リソースを上手く組み合わせれば、少人数でも充実したエンゲージメント施策を実現できます。
組織の規模に応じた段階的導入アプローチ
エンゲージメント経営の手法は、組織の規模に合わせて調整・導入することが重要です。大企業と同じ施策をいきなり小さな会社で真似してもうまくいかないことがあります。そこで、自社の規模や状況に合った形で、段階的に取り入れていくアプローチが有効です。
例えば、社員数が数十名規模の会社であれば、まずは非公式なヒアリングや少人数ミーティングなど柔軟な方法で社員の声を集め、改善につなげるところから始められます。
社員数が増えてきた段階で、改めて正式なエンゲージメントサーベイを導入する、といった段階的な展開が考えられます。また、初めは特定の部署でパイロット的に施策を試し、効果を検証してから全社展開するのも良いでしょう。
組織規模に応じて「できること」「効果が出やすいこと」は異なります。重要なのは、小さく始めて大きく育てる意識です。無理なく段階を踏むことで、社員の負担感も少なく、自然にエンゲージメント経営を浸透させていくことができます。
中小企業でも、自社にフィットした形で着実に取り組めば、規模のハンデを乗り越えて高いエンゲージメントを実現できるでしょう。
マネーリペアの導入による内部エンゲージメント経営戦略
金融教育サービスの具体例として、「マネーリペア」というプログラムがあります。マネーリペアは、企業の従業員向けに金融・投資・税務のプロフェッショナルが講師となってお金の知識を提供する金融リテラシー向上支援サービスです。
名前の由来は「長年のデフレで凝り固まったお金の知識を修復(Repair)する」という発想で、社員の金銭面の不安を取り除き経済的に豊かになる手助けをすることを目的としています。
マネーリペアでは、金融勉強会(セミナー形式で税金や資産運用について学ぶ場)や個別のファイナンシャルプランナー相談、さらには資産管理ツールの提供など、多角的なサポートを行います。
例えばセミナーでは「源泉徴収票の正しい見方」「NISAやiDeCoの活用法」「経済ニュースの読み解き方」といった実践的なテーマを扱い、個別相談では各従業員の家計や資産運用の悩みに専門家がアドバイスします。
実際にマネーリペアを導入した企業からは、「社員の手取り収入が増えて喜ばれた」「お金の不安が減ったことで仕事に集中できるようになった」といった声が聞かれます。
中には、「マネーリペア導入後1年で離職率が低下した」という事例も報告されています。社員の金融リテラシーが上がることは、社員個人の生活の安定だけでなく、企業にとっても定着率向上や生産性向上というリターンを生むのです。
マネーリペアのサービスは比較的低コストで導入でき、福利厚生として手軽に始められる点も魅力です。
「社員に資産形成のきっかけを与えたい」「金融教育を通じてエンゲージメントを高めたい」「エンゲージメント経営に力を入れていきたい」と考える企業様は、ぜひ一度マネーリペアの導入を検討されてはいかがでしょうか。
資料請求や無料相談も可能ですので、興味のある方はお気軽にお問い合わせしてみてください。

まとめ:エンゲージメント経営の導入がもたらす企業変革
エンゲージメント経営は、一言で言えば「社員と会社の関係性を良くする経営」です。社員の意欲と会社の成果が相乗効果で高まるこの仕組みを取り入れることで、企業はこれまでにない変革を遂げる可能性があります。
生産性向上や離職率低減といった数値で表れる成果はもちろん、社員が会社に誇りを持ち主体的に動くようになるという質的な変化は、組織文化そのものをポジティブに塗り替えます。
本記事で述べたように、エンゲージメント経営の実践にはビジョン共有から人事施策、福利厚生の工夫まで幅広い取り組みが必要ですが、一歩ずつでも着実に進めることが大切です。
社員との信頼関係を築くことに近道はありませんが、その先に得られる企業の持続的成長と働く人々の幸せは、取り組む価値のあるゴールだと言えるでしょう。
これからエンゲージメント経営を導入しようと考えている皆さん、ぜひ本記事の内容を参考に、自社に合った形で第一歩を踏み出してみてください。社員のエンゲージメント向上という種を蒔けば、やがてそれは大きな実を結び、企業全体に活力と競争力という果実をもたらすはずです。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。

.jpg&w=1080&q=75)