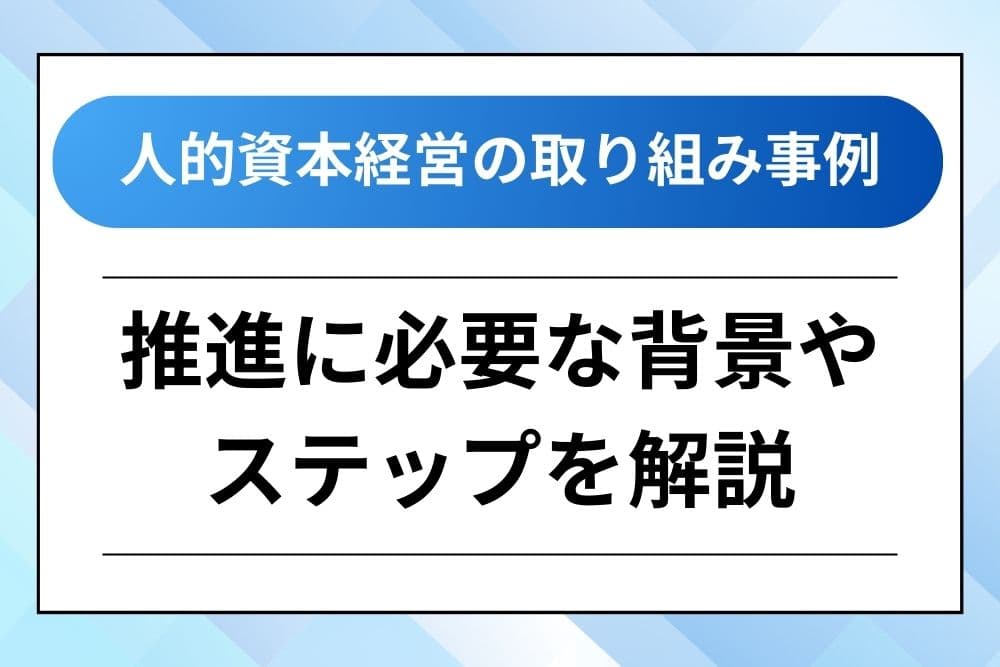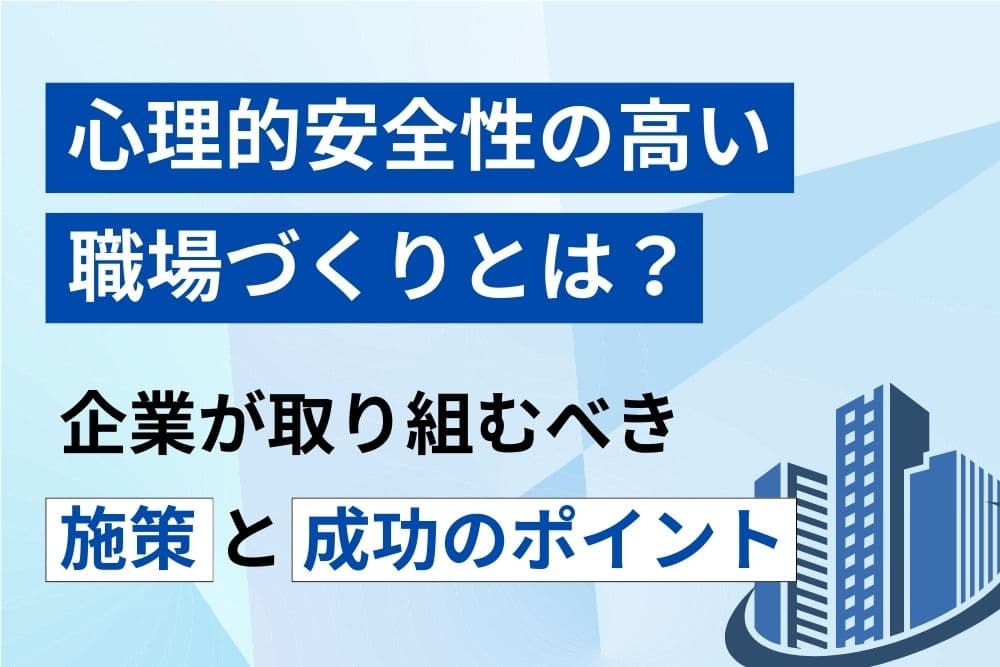お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
最低限身に着けるべき金融の基礎知識は?企業で金融教育を提供すべき理由を解説
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
「金融の基礎知識」とは
人事が押さえるべき金融関連制度と福利厚生
従業員の金融リテラシー向上がもたらす企業メリット
企業が取り組む金融リテラシー教育の方法
金融教育についてよくある質問
従業員の幸せと企業の成長は表裏一体です。近年、社員の経済的安定が企業パフォーマンスに直結することが明らかになってきました。
目次
「金融の基礎知識」とは
金融の基礎知識とは、お金の流れや活用方法を理解し、自身の経済状況を適切に管理するための知識体系のことです。具体的には、預貯金、投資、保険、税金、ローンなどの基本的な仕組みや活用法を指します。
多くの人が「金融」というと難しい専門用語や複雑な計算が必要と思いがちですが、実はそうではありません。日々の家計管理から将来のライフプランニング、そして適切な資産形成まで、私たちの生活全般に関わる実践的な知恵です。
例えば、給与の受け取り方や使い方、住宅ローンの選び方、老後資金の準備など、人生の様々な場面で金融の知識が必要となります。
特に近年は、年金制度の先行き不安から「自助努力による資産形成」の重要性が高まっており、投資の基礎知識やリスク管理の考え方も金融リテラシーの重要な要素となっています。
多くの企業では、従業員が金融リテラシーを高めることで、より安定した生活基盤を築き、仕事に集中できる環境づくりを支援しています。これは単なる福利厚生ではなく、企業の生産性向上にも寄与する戦略的な取り組みといえるでしょう。
【マネーリペアなら金融教育も安心】 マネーリペアでは、従業員向けの金融基礎セミナーを企業規模に合わせて提供しています。初心者にもわかりやすいカリキュラムで、社員の金融リテラシー向上を支援します。まずはお気軽にご相談ください。

金融が企業経営・人事に与えるインパクトについて
金融知識は個人の生活を豊かにするだけでなく、企業経営や人事戦略にも大きなインパクトを与えています。その影響は以下のような形で表れています。
まず、従業員の金融リテラシーが高まることで、経済的な不安が軽減されます。経済的不安を抱える従業員は、仕事への集中力が低下し、パフォーマンスに影響することが研究で明らかになっています。
金融教育を通じて従業員の経済的ウェルビーイングを高めることは、生産性向上や欠勤率低下につながります。
次に、福利厚生としての金融サポートは、優秀な人材の獲得・定着に直結します。
特に若年層は将来への不安を強く感じており、資産形成をサポートする企業に魅力を感じる傾向があります。退職金制度や企業年金、従業員持株会などの制度を整備し、その活用方法をしっかり伝えることで、採用市場での競争力が高まるでしょう。
さらに、財務指標や経営状況への理解が深まることで、従業員の当事者意識が高まります。売上や利益、コストなどの基本的な財務概念を理解することで、日々の業務が企業の経営状況にどう影響するかを意識した行動が促進されるのです。
人事部門にとっては、これらの金融関連制度を戦略的に活用することで、単なる「福利厚生の提供」から一歩進んだ「人的資本への投資」という視点での施策展開が可能になります。従業員の長期的な幸せと企業の持続的成長を両立させる鍵は、実は金融リテラシーにあるのかもしれません。
【マネーリペアで企業価値向上を実現】 マネーリペアは、金融教育を通じた企業価値の向上をサポートします。従業員の経済的不安を解消し、仕事への集中力を高める効果的なプログラムをご提案。詳しくはこちらをご覧ください。

人事が押さえるべき金融関連制度と福利厚生
従業員の経済的安定と将来への安心を支える金融関連制度は、人事担当者にとって必須の知識領域です。効果的な福利厚生を設計するための基礎を解説します。
退職金制度・企業年金制度の基本構造
退職金制度と企業年金制度は、従業員の老後の経済的安定を支える重要な仕組みです。両制度の基本構造を理解することは、人事担当者にとって不可欠な知識といえるでしょう。
退職金制度には、主に「一時金制度」と「年金制度」の2種類があります。一時金制度は退職時に一括して支給する方式で、簡便で分かりやすい反面、受給者の長生きリスク(長生きすることでお金が足りなくなるリスク)への対応が課題です。
一方、年金制度は定期的に分割して支給するため、老後の生活を安定的に支える効果がありますが、制度運営の複雑さが増します。
企業年金制度の代表的なものには、「確定給付企業年金(DB)」と「確定拠出年金(DC)」があります。DBは給付額があらかじめ決まっており、運用リスクは企業側が負います。一方、DCは掛金が決まっていて、運用結果によって給付額が変動する仕組みで、運用リスクは従業員側が負います。
人事担当者としては、自社の退職金・企業年金制度の構造を正確に理解し、従業員に分かりやすく説明できることが重要です。特に若手社員は老後の備えについての意識が低い傾向があるため、制度の価値や活用方法を丁寧に伝えることで、福利厚生としての価値を最大化できるでしょう。
また、退職金・企業年金制度は税制面でも優遇されているケースが多いため、税務上のメリットを含めた総合的な説明ができると、従業員の理解と満足度が高まります。自社の制度について不明点がある場合は、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
【マネーリペアで退職金・企業年金制度を見直し】 マネーリペアでは、企業の退職金・企業年金制度の最適化をサポートします。従業員にとって魅力的で、企業にとっても持続可能な制度設計をご提案。

財形貯蓄・社内融資・従業員持株会の活用
従業員の資産形成を支援するための仕組みとして、財形貯蓄、社内融資、従業員持株会などの制度があります。これらは比較的導入しやすく、従業員からも高い評価を得やすい福利厚生です。
財形貯蓄制度は、給与天引きで自動的に貯蓄できる便利な制度です。特に「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は、一定の条件を満たせば利子等が非課税となる税制優遇もあり、住宅取得や老後資金の準備に役立ちます。
給与からの天引きで「貯める仕組み」を作ることで、従業員の計画的な資産形成を後押しできるでしょう。
社内融資は、従業員が住宅購入や教育資金などの目的で資金を必要とする際に、市中の金融機関よりも有利な条件で融資を受けられる制度です。特に若手社員の住宅取得支援は、長期的な定着率向上にもつながります。
制度設計においては、融資条件や返済方法を明確にし、公平性を担保することが重要です。
従業員持株会は、自社株式を従業員が購入・保有するための仕組みです。多くの企業では、持株会を通じた株式購入に対して奨励金を支給するなどの優遇措置を設けています。従業員が株主となることで経営参画意識が高まり、会社の業績向上への意欲も強まるという効果が期待できます。
これらの制度は、従業員のライフステージに合わせた選択肢を提供することで、より効果的に機能します。例えば、若手社員には財形貯蓄で基本的な貯蓄習慣を身につけてもらい、キャリアが進むにつれて従業員持株会への参加を促すなど、段階的なアプローチも有効でしょう。
確定拠出年金(DC)やiDeCoの仕組みとメリット
確定拠出年金(DC)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金を補完する私的年金制度として、近年特に注目を集めています。これらの制度の基本的な仕組みとメリットを理解することは、人事担当者にとって不可欠です。
確定拠出年金(DC)は、企業が毎月一定額を拠出し、従業員自身がその資金を運用する仕組みです。運用商品は従業員が選択し、その結果に応じて将来の年金額が決まります。最大の特徴は、拠出金が全額損金算入できる税制メリットと、運用益が非課税で成長する点です。
また、転職時にはポータビリティ(持ち運び)が可能で、iDeCoや他社のDCに資産を移管できます。
一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)は、会社員や自営業者など幅広い人が個人で加入できる年金制度です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税、受取時も税制優遇があるという三重の税制メリットがあります。
企業型DCと同様に、自分で運用商品を選んで資産を育てる点が特徴です。
人事担当者としては、DCの導入・運用管理に加え、従業員への投資教育が重要な責務となります。多くの従業員は投資経験が少ないため、制度の基本的な仕組みから運用商品の選び方、長期投資の考え方まで、分かりやすく伝える工夫が必要です。
また、2022年10月からは、企業型DCとiDeCoの併用が原則可能になるなど、制度は徐々に拡充されています。こうした最新の制度改正情報をキャッチアップし、従業員に適切に案内することも人事部門の重要な役割と言えるでしょう。
従業員の金融リテラシー向上がもたらす企業メリット

金融教育は単なる福利厚生ではなく、企業経営に様々なポジティブな効果をもたらします。従業員と企業の双方にとっての価値創造につながる理由を解説します。
資産形成サポートによる定着率とモチベーション向上
従業員の資産形成をサポートすることは、単なる福利厚生の提供を超えた戦略的な人材マネジメント施策となります。その効果は定着率向上やモチベーションアップなど、多岐にわたります。
まず、資産形成支援は「この会社は自分の将来を考えてくれている」という安心感を従業員に与えます。特に終身雇用が崩壊しつつある現代において、自分の経済的将来に対する不安は大きなストレス要因となっています。
企業が確定拠出年金やiDeCo、財形貯蓄などの制度を整備し、その活用方法を丁寧に伝えることで、従業員は将来への備えができ、現在の仕事により集中できるようになります。
実際に、金融教育を充実させている企業では離職率が低下するというデータもあります。特に若手社員は「お金の教育」を受ける機会が少なく、基本的な知識が不足していることが多いため、企業による金融教育は貴重な学びの場となります。
この学びが「この会社でしか得られない価値」として認識されれば、帰属意識の向上につながるでしょう。
さらに、資産形成が順調に進むことで、従業員は将来の経済的不安から解放され、より創造的な仕事にチャレンジできるようになります。
短期的な収入増加だけを追い求めるのではなく、長期的なキャリア形成や自己成長に目を向けられるようになることで、企業にとっても質の高い人材が定着するという好循環が生まれます。
金融リテラシー向上は、従業員の生活満足度を高め、その効果は仕事のパフォーマンスにも波及します。人事担当者は単なる「お金の知識提供」ではなく、「従業員のウェルビーイング向上のための重要施策」として金融教育を位置づけることで、より大きな効果を得られるのではないでしょうか。
経営指標への理解促進と主体的な組織貢献
従業員の金融リテラシーが向上すると、企業の経営指標への理解が深まり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。これは単なる「お金の知識」を超えた、ビジネスパーソンとしての総合力向上を意味します。
基本的な財務知識を持つことで、従業員は自社の売上、利益率、コスト構造などの経営指標を正しく理解できるようになります。例えば、「利益率1%の向上がなぜ重要なのか」「コスト削減がどのように企業価値に貢献するのか」といった点を、自分ごととして捉えられるようになるのです。
この理解は日々の業務における意思決定の質を高めます。例えば、営業担当者が利益率の高い商品に注力したり、管理部門が効率的な予算執行を心がけたりといった、会社全体の最適化につながる行動が自然と増えるでしょう。
まるで自分の家計を管理するように、会社のリソースを大切に扱う意識が育まれるのです。
また、株式市場の基本的な仕組みや企業価値評価の考え方を知ることで、経営陣が発信するメッセージの背景にある意図や、中長期経営計画の意義をより深く理解できるようになります。
これにより、「なぜこの施策が必要なのか」という本質的な理解が進み、変革への抵抗感が減少する効果も期待できます。
特に管理職層の金融リテラシー向上は組織全体に大きな影響を与えます。部門予算の意義や投資判断の基準、コスト管理の重要性などを理解した管理職は、チーム全体にその考え方を波及させ、組織文化として根付かせることができるでしょう。
金融リテラシーの向上は、単なる個人のスキルアップではなく、組織全体の経営参画意識を高め、より強固な企業体質の構築につながる戦略的投資と言えるのではないでしょうか。
企業ブランド力強化と社会的評価
従業員への金融教育の提供は、内部的な効果だけでなく、企業の外部評価にも大きく寄与します。具体的には、企業ブランド力の強化と社会的評価の向上というかたちで現れます。
まず採用市場において、金融教育を含む充実した福利厚生は大きな差別化要因となります。特に近年の若手人材は、給与水準だけでなく「自分の成長を支援してくれる環境があるか」を重視する傾向があります。
金融リテラシー向上プログラムや資産形成支援制度の存在は「この会社は従業員の将来まで考えてくれている」というメッセージとなり、優秀な人材を惹きつける磁石の役割を果たすでしょう。
また、金融教育の提供は企業の社会的責任(CSR)活動としても評価されます。従業員の経済的自立を支援することは、持続可能な社会の実現に貢献する取り組みとして認識されます。
実際に、ESG投資の観点からも、従業員の幸福度向上に取り組む企業は「S(社会)」の評価項目でポジティブに評価される傾向にあります。
さらに、金融教育を通じて社員のウェルビーイングを高めている企業は、「従業員を大切にする企業」として顧客からの信頼も獲得しやすくなります。特にBtoC企業では、従業員満足度の高さが顧客体験の質に直結するため、この効果は無視できません。
金融教育の取り組みを社内報や採用サイト、SNSなどで積極的に発信することで、これらのブランディング効果をさらに高められます。
単に「制度があります」という事実だけでなく、「どのような効果があったか」「従業員の声はどうか」といった具体的なストーリーを伝えることで、より説得力のあるメッセージとなるでしょう。
企業価値向上の観点からも、金融教育は「コスト」ではなく「投資」として捉えるべき重要な施策と言えるのではないでしょうか。
企業が取り組む金融リテラシー教育の方法
従業員の金融リテラシー向上には、体系的なアプローチが効果的です。自社の状況に合わせた最適な教育プログラムの設計・実施方法を紹介します。
社内研修プログラムの設計と実践
効果的な金融リテラシー教育を行うためには、体系的な社内研修プログラムの設計が欠かせません。具体的な設計のポイントと実践方法を見ていきましょう。
まず、ターゲット層を明確にすることが重要です。新入社員、若手社員、中堅社員、管理職など、キャリアステージによって必要な金融知識は異なります。
例えば、新入社員には「給与明細の見方」や「基本的な貯蓄の方法」から始め、管理職には「退職金制度の詳細」や「資産運用の考え方」などを提供するといった段階的なアプローチが効果的でしょう。
次に、カリキュラムの設計では、理論と実践のバランスを意識することが大切です。単なる知識の伝達だけでなく、ワークショップ形式で自分のライフプランを考えたり、シミュレーションツールを使って将来の資産形成を体験したりする実践的な内容を取り入れましょう。
参加者が「自分ごと」として捉えられる工夫が学習効果を高めます。
研修の実施形態も重要です。集合研修とeラーニングを組み合わせたブレンド型学習や、短時間のマイクロラーニングを定期的に提供するなど、従業員が無理なく学べる環境づくりを心がけましょう。
特に、業務多忙な従業員でも参加しやすいよう、ランチタイムセミナーや動画コンテンツの提供など、柔軟な学習機会の創出が効果的です。
また、研修効果を高めるためには、上司からのフォローも重要です。例えば、1on1ミーティングで学んだ内容の振り返りや実践状況の確認を行うことで、知識の定着を促進できます。
こうした組織的なサポート体制があることで、従業員は「会社全体で金融リテラシー向上を重視している」というメッセージを受け取り、学習意欲が高まるでしょう。
社内研修プログラムを通じて、従業員の経済的自立と安定を支援することは、長期的な企業価値向上につながる重要な投資と言えるのではないでしょうか。
【マネーリペアで効果的な社内研修を実現】 マネーリペアでは、企業規模や従業員の特性に合わせた金融教育プログラムをご提供します。講師派遣から教材開発まで、トータルでサポート。まずはお気軽にご相談ください。

外部専門家・金融機関との連携事例
金融教育を効果的に実施するためには、専門知識を持つ外部機関との連携が非常に有効です。実際の企業事例を交えながら、外部専門家・金融機関との連携方法について解説します。
多くの企業では、確定拠出年金(DC)の運営管理機関や保険会社、証券会社などと提携し、定期的なセミナーやワークショップを開催しています。
例えば、A社では四半期ごとに運営管理機関の講師を招き、「DCの運用状況レビュー」と「投資の基礎知識」をテーマにしたセミナーを実施。参加者からは「専門家の話を直接聞けて安心感が増した」という声が多く寄せられています。
B社では、地元の金融機関と連携し、ライフプランニングセミナーを年2回開催しています。住宅購入や教育資金、老後資金など、ライフステージごとの資金計画について専門家がアドバイスを提供することで、従業員の将来への不安軽減に役立てています。
若手社員の参加率が特に高く、早い段階からの資産形成意識醸成に効果を発揮しています。
外部専門家を活用する際のポイントは、単発の講演に終わらせず、継続的な関係構築を図ることです。例えば、セミナー後の個別相談会を設けたり、社内イントラネットで質問を受け付けたりするなど、フォローアップの仕組みを整えることで、学びを実践につなげやすくなります。
また、連携先選定の際には、単に知名度だけでなく、教育コンテンツの質や講師の分かりやすさなどを重視することが大切です。事前に小規模なトライアルセミナーを実施してから本格導入を検討するなど、段階的なアプローチも有効でしょう。
費用面では、確定拠出年金の運営管理機関や取引金融機関であれば、福利厚生の一環として無料または低コストでセミナーを提供してくれるケースも多いため、まずは既存の取引先に相談してみることをおすすめします。
外部の専門性と客観性を活かした金融教育は、従業員からの信頼感も高く、高い教育効果が期待できます。自社のニーズに合った連携先を見つけることが成功の鍵と言えるでしょう。
オンライン学習ツール活用と継続的フォローアップ
デジタル技術の進化により、金融教育においてもオンライン学習ツールの活用が進んでいます。効果的なツール選定と継続的なフォローアップの方法について解説します。
オンライン学習ツールの最大のメリットは、従業員が「いつでも・どこでも・自分のペース」で学べることです。特に多忙な社会人にとって、この柔軟性は非常に重要です。例えば、通勤時間やランチタイムなど、隙間時間を活用して学習できるよう、スマートフォン対応のeラーニングコンテンツを提供している企業が増えています。
効果的なオンライン学習ツールの選定ポイントとしては、まず「分かりやすさ」が挙げられます。難解な金融用語を平易に解説し、図表やイラストを効果的に活用したコンテンツは学習効果が高いでしょう。
また、クイズや診断機能など「インタラクティブ要素」があることで、一方的な知識の詰め込みではなく、主体的な学びが促進されます。
さらに重要なのが、継続的なフォローアップの仕組みです。一度学んだだけでは定着しないため、定期的なリマインドや復習機会の提供が効果を高めます。
従業員の金融リテラシー向上は一朝一夕に実現するものではなく、継続的な取り組みが必要です。長期的な視点での教育プログラム設計と、着実なフォローアップが成功の鍵と言えるでしょう。
金融教育についてよくある質問
企業における金融教育の導入・運用に関して、人事担当者からよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。具体的な事例や知見を交えて解説します。
金融リテラシー教育は企業にとって必須なのでしょうか?
「金融リテラシー教育は本当に必要なのか」という疑問は、多くの人事担当者が抱くものです。結論から言えば、従業員の幸福度と企業の持続的成長の両方を実現するために、今や必須の取り組みと言えるでしょう。
まず、従業員の側面から見ると、経済的な不安やストレスは仕事のパフォーマンスに大きく影響します。研究によれば、経済的ストレスを抱える従業員は集中力が低下し、創造性も発揮しにくくなるとされています。
特に現代は年金制度の先行き不安や、終身雇用の崩壊など、将来の経済的安定を脅かす要素が増えており、従業員の不安も高まっています。
企業側の視点では、金融リテラシー教育を通じて従業員の経済的ウェルビーイングを向上させることで、生産性向上や優秀人材の定着率アップなど、具体的なビジネス成果につながります。
実際に、金融教育プログラムを導入した企業では、従業員満足度の向上や離職率の低下といった効果が報告されています。
また、確定拠出年金(DC)を導入している企業においては、投資教育は法的な義務でもあります。単に「制度があります」というだけでなく、効果的な活用方法を伝えることで、制度の真の価値が従業員に届くのです。
金融リテラシー教育の「必須度」は業種や従業員層によっても異なります。例えば、若手社員が多い企業では基礎的な家計管理や貯蓄の習慣づけから始め、中堅社員が多い企業では住宅購入や教育資金など、ライフイベントに関連した内容を重視するなど、自社の状況に合わせたアプローチが効果的です。
重要なのは「やるかやらないか」ではなく「どのように効果的に実施するか」という視点です。従業員の金融リテラシー向上は、単なるコストではなく、人的資本への投資として捉えることで、企業価値向上につながる戦略的施策となるでしょう。
小規模企業でも導入しやすい福利厚生の事例はありますか?
「大企業のような豊富な予算がなくても、従業員の金融リテラシー向上や資産形成を支援できる方法はないか」という質問をよくいただきます。小規模企業でも十分に実施可能な、効果的で導入しやすい施策をご紹介します。
まず、コストをかけずに始められる取り組みとして、「勉強会」の開催があります。例えば、ある企業様(従業員30名)では、月に1回のランチタイムに「マネー勉強会」を実施。
ファイナンシャルプランナー資格保持者や、外部の専門家を招き、家計管理や投資の基礎などをテーマに気軽に学べる場を提供しています。参加は任意ですが、毎回8割以上の社員が参加する人気企画となっています。
次に、比較的導入ハードルが低い制度として「財形貯蓄」があります。給与からの天引きで自動的に貯蓄できる仕組みで、従業員の計画的な資産形成をサポートできます。特別な初期投資は不要で、給与計算システムの設定変更程度で始められるケースが多いでしょう。
また、福利厚生サービスを提供する外部企業と契約する方法も効果的です。金融セミナーや個別相談サービスを従業員に提供しています。自社単独では難しい専門的なサポートも、こうしたサービスを活用することで実現可能です。
重要なのは「できることから始める」という姿勢です。完璧な制度を一度に導入する必要はなく、小さな取り組みを積み重ね、従業員の反応を見ながら徐々に拡充していくアプローチが、小規模企業には特に適しているでしょう。
従業員の金融リテラシー向上は、企業規模に関わらず重要なテーマです。予算や人員の制約はあっても、工夫次第で効果的な支援が可能であることを、多くの小規模企業の事例が証明しています。
【マネーリペアなら小規模企業でも安心】 マネーリペアでは、小規模企業向けの低コストで効果的な金融教育プランをご用意。初期投資を抑えながら従業員満足度を高める方法をご提案します。詳しくはこちらをクリック。

社員への投資教育はコンプライアンス上問題ないのでしょうか?
「投資に関する教育を行うと、特定の金融商品を推奨しているととられないか」「損失が出た場合に会社が責任を問われないか」など、コンプライアンス面での懸念を抱く企業は少なくありません。この点について整理してみましょう。
まず、確定拠出年金(DC)を導入している企業においては、加入者への投資教育は法的義務とされています。DCの運用責任は加入者自身にあるため、適切な判断ができるよう必要な知識を提供することは、むしろ企業の責務と言えるでしょう。
重要なのは「教育」と「アドバイス」の線引きです。投資の基本的な考え方や、リスクとリターンの関係、分散投資の重要性といった普遍的な知識を伝えることは問題ありません。一方で、「この商品がおすすめ」「今がチャンス」といった具体的な投資判断に踏み込む内容は避けるべきです。
また、教育内容の中立性を担保することも大切です。特定の金融機関や商品に偏らない内容とし、情報源や講師選定においても公平性を確保しましょう。外部講師を招く場合は、事前に内容を確認し、営業色の強い内容にならないよう注意することも必要です。
実務上のポイントとしては、参加者に対して「この教育は情報提供が目的であり、個別の投資判断を推奨するものではない」という免責事項を明示することが一般的です。これにより、参加者の誤解を防ぎ、企業側のリスクも軽減できます。
人事が金融商品の選定や運用にどこまで関与すべきか悩んでいますが、どうすればよいですか?
「確定拠出年金の運用商品ラインナップをどう選べばよいか」「従業員の資産形成にどこまで踏み込むべきか」など、人事部門の関与度合いに悩む声は多く聞かれます。適切なバランスを見極めるポイントを解説します。
基本的な考え方として、人事部門の役割は「従業員が自分で適切な判断ができる環境を整えること」にあります。具体的な商品選定や運用方法の指南ではなく、必要な知識の提供や制度の整備が中心となるでしょう。
例えば、確定拠出年金(DC)の運用商品ラインナップについては、リスク・リターン特性の異なる商品をバランスよく揃え、従業員が自分のリスク許容度に合わせて選択できるようにすることが重要です。
I社では、商品数を15種類程度に絞り込み、低リスク商品から高リスク商品まで段階的に選べるよう設計。さらに、モデルポートフォリオを3種類提示することで、選択のハードルを下げる工夫をしています。
また、運用状況のモニタリングも人事部門の重要な役割です。例えば、「元本確保型商品への過度な集中」「長期間の放置」などの状況が見られる場合は、追加の教育機会を設けるなどの対応が考えられます。ただし、個別の従業員に特定の行動を促すような関与は避けるべきでしょう。
適切な関与度合いを見極める鍵は「パターナリズム(過度な保護)に陥らないこと」と「必要な支援は惜しまないこと」のバランスにあります。従業員の自立を促しながらも、必要なサポートを提供する姿勢が理想的でしょう。
まとめ:人事部門が担う金融知識の要点
本記事では、企業における金融教育の重要性と具体的な取り組み方について解説してきました。
金融の基礎知識は、単なる「お金の知識」ではなく、従業員のウェルビーイングと企業の持続的成長を両立させるための重要な基盤です。特に公的年金の先行き不安や雇用の流動化が進む現代において、自助努力による資産形成の重要性はますます高まっています。
従業員の金融リテラシー向上を支援することは、人事部門が担う重要な社会的役割の一つです。この取り組みが、従業員と企業の双方にとって価値ある成果をもたらすことを願っています。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。

.jpg&w=1080&q=75)