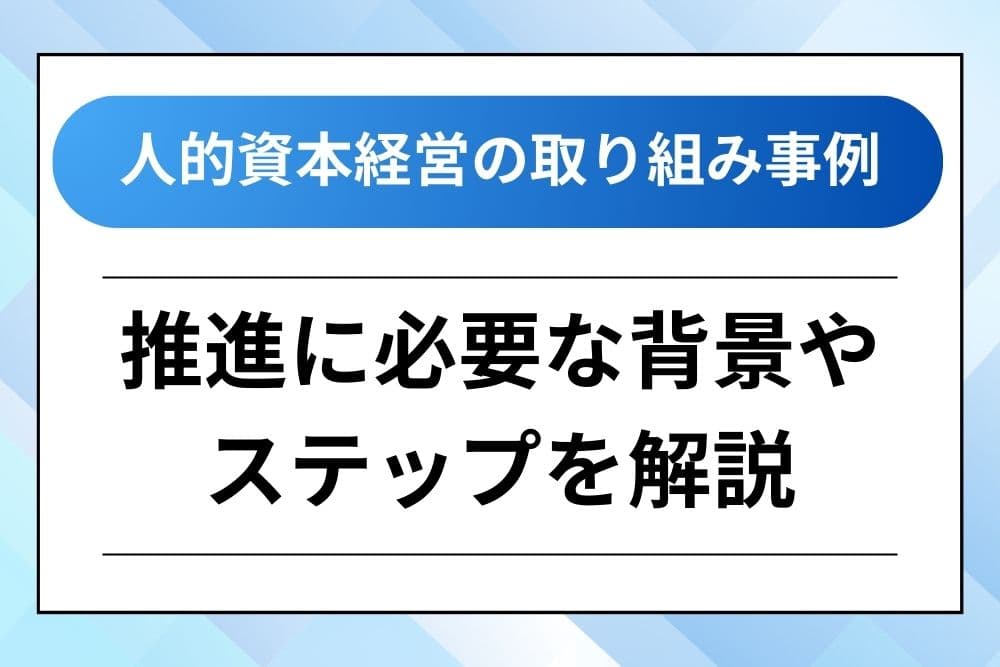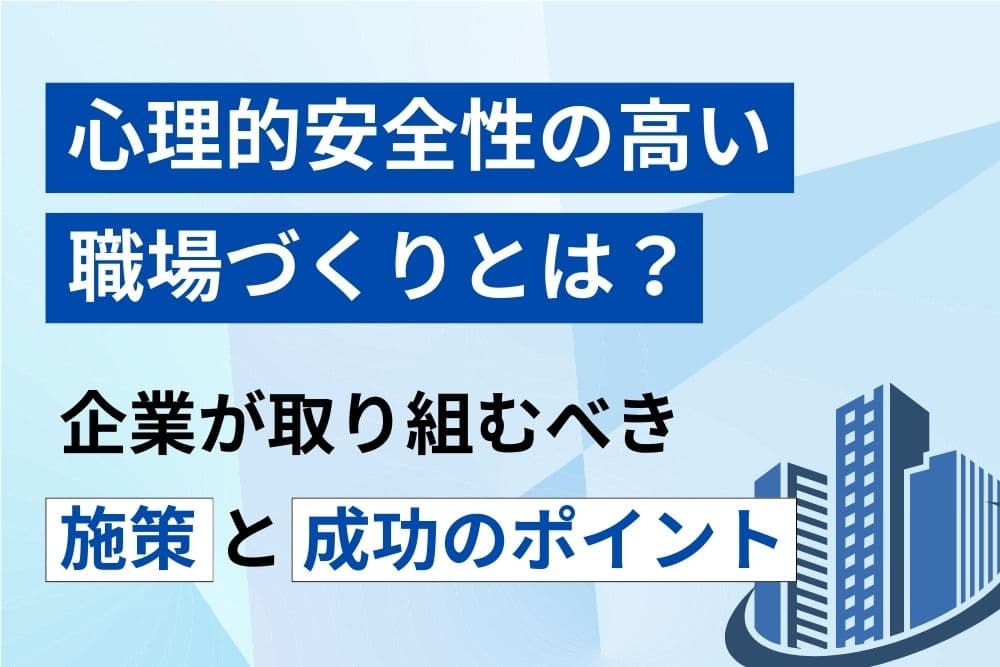お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
従業員エンゲージメントとは?従業員満足度(ES)の違いや高める方法を解説
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
従業員エンゲージメントとは
従業員満足度とエンゲージメントが注目される背景
従業員満足度とエンゲージメントの違い
エンゲージメントの測定と指標の考え方
従業員満足度が向上するメリット
この記事では、従業員エンゲージメントとは何か、その重要性と従業員満足度(ES)との違い、さらに社員のエンゲージメントを高める具体的な方法について解説します。
人事担当者として「従業員満足度 エンゲージメント」で悩んでいる方が、本記事を通じて課題解決のヒントを得られることを目指します。
エンゲージメント向上が企業にもたらすメリットや、金融専門家の視点から提案する福利厚生施策も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
従業員エンゲージメントとは
エンゲージメントとは?
「エンゲージメント(Engagement)」とは、
- 約束
- 契約
- 結びつき
といった意味を持つ言葉です。
ビジネスや人事の領域では、組織や仕事に対する愛着心や情熱、コミットメントの度合いを指す言葉として使われます。
例えば顧客エンゲージメントであれば企業と顧客の強いつながりを意味しますが、従業員エンゲージメントでは企業と従業員の強いつながりを表すものになります。
つまり、エンゲージメントとは対象への深い結びつきや熱意を示す概念です。
従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメントとは、従業員が所属する企業に対して抱く愛着心や信頼感、そして「この会社のために貢献したい」という意欲の度合いを表す指標です。エンゲージメントが高い社員は、自社の理念や目標に共感し、仕事に前向きに取り組みます。
例えば、自発的に業務改善の提案をしたり、周囲にも良い影響を与えたりと、企業の成長に主体的に関与する行動が見られます。従業員エンゲージメントはアンケート調査などで数値化され、人事施策の効果測定にも利用されます。
近年、この従業員エンゲージメントが企業の業績や競争力に直結する重要な要素として注目されています。
従業員満足度(ES)との違い
従業員満足度(Employee Satisfaction:ES)は、その名のとおり従業員が職場の労働条件や仕事内容、待遇、人間関係などにどの程度満足しているかを示すものです。一方で従業員エンゲージメントは、従業員が企業にどれだけ貢献しようとする意欲や愛着心を持っているかを示す指標です。
つまり、満足度は主に職場環境に対する受動的な評価であり、エンゲージメントは組織への主体的な関与度合いを測るものと言えます。
例えば、オフィス環境や給与に「満足」している社員が必ずしも会社の目標に熱意を持つとは限りません。一方、エンゲージメントが高い社員は多少不満があっても企業に貢献しようと踏ん張る傾向があります。
このように両者は密接に関連しますが指す内容は異なります。なお、両者には相関関係があり混同されることもありますが、厳密には異なる指標である点に注意が必要です。
ワーク・エンゲージメントとは?
ワーク・エンゲージメントとは、従業員エンゲージメントと混同されやすい用語ですが、その内容は少し異なります。ワーク・エンゲージメントは「仕事」に対するポジティブな心理状態を指し、具体的には仕事に活力を持って没頭し、やりがいを感じている状態を意味します。
オランダのユトレヒト大学の研究者らによって提唱された概念で、活力・熱意・没頭という3つの要素で測定されることが一般的です。一方で先述の従業員エンゲージメントは「組織」に対する愛着心や貢献意欲を示すもので、学術的には別の概念です。
簡単に言えば、ワーク・エンゲージメントは仕事そのものへの熱意、従業員エンゲージメントは会社への思い入れと捉えると分かりやすいでしょう。ただしどちらも従業員のモチベーションやパフォーマンスに関わる重要な要素であり、人事施策では両面からアプローチすることが望まれます。
従業員満足度とエンゲージメントが注目される背景

企業成長と採用競争、人口減少による人材確保難の関係性
近年、企業が従業員満足度やエンゲージメント向上に注力する背景として、まず挙げられるのが人材の確保難です。
日本では少子高齢化による生産年齢人口の減少が深刻で、2020年から2070年にかけて働き手となる生産年齢人口は約7,500万人から約4,500万人へと40%近く減少する見通しです。多くの企業で人手不足が常態化しつつあります。
実際、2023年に日本商工会議所が行った調査では中小企業の約70%が「人手が不足している」と回答し、そのうち60%以上が事業に支障が出ていると報告されています。
このように優秀な人材を採用し維持することが難しくなる中、企業が持続的に成長するには現在働いている社員の定着率を上げ、生産性を最大化することが不可欠です。
そこで、社員の満足度を高め働きがいを感じてもらうことで離職を防ぎ、ひいては企業の成長エンジンを維持しようという狙いから、エンゲージメント経営への関心が高まっているのです。
また採用競争が激化する中、エンゲージメントの高い企業は「社員を大切にする魅力的な職場」として評価され、求職者から選ばれやすくなるという側面もあります。
個人の価値観の多様化
働き手である個人の価値観が多様化していることです。従来であれば「給与が高い」「安定している」といった条件が整えば社員は満足し長く勤める傾向にありました。
しかし現代では、仕事に対して求めるものが人によって異なります。ある人はワークライフバランスを重視し、リモートワークやフレックス制といった柔軟な働き方を望むでしょう。またある人は自己成長やキャリアアップの機会を重視し、研修制度や公正な評価制度を求めます。
さらには企業の社会的使命やビジョンに共感できるかを重視するケースもあります。このように従業員一人ひとりの重視するポイントが多岐にわたるため、企業側は単に給与や従来型の福利厚生を充実させるだけでは全員の満足・エンゲージメントを高めることが難しくなっています。
結果として、企業は社員の声をきめ細かく拾い上げ、多様なニーズに応える施策を講じる必要性に迫られているのです。その中で、従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイを活用して社員の本音を把握し、それを経営に活かそうとする動きが活発化しています。
グローバル化による国際競争の激化
グローバル化による国際競争の激化が挙げられます。市場がグローバルに拡大・統合する中で、日本企業も国内だけでなく海外企業との競争に晒されています。その競争に勝ち抜くためには、新製品・サービスの開発や生産性向上など、社員一人ひとりの創意工夫と高いパフォーマンスが欠かせません。
言い換えれば、人材の質とやる気こそが国際競争力の源泉となっています。海外の先進企業では以前から従業員エンゲージメントを高める人材戦略が重視されており、働きがいのある職場ランキングなどで上位に入る企業は総じて高業績を上げています。
一方で日本は従業員エンゲージメントの水準が低い傾向にあり、米Gallup社の調査によれば「熱意あふれる(エンゲージメントの高い)社員」の割合は世界平均23%に対し日本はわずか5%と最下位でした。
このような状況では国際競争で不利になる可能性が高く、各企業がエンゲージメント向上による生産性アップに本腰を入れ始めています。また、昨今ではESG投資の観点から人的資本(Human Capital)情報の開示が求められるようになり、エンゲージメントスコアを含む従業員関連指標が企業評価に直結しつつあります。
グローバルな投資家やステークホルダーに向けても「従業員を大切にしエンゲージメントが高い会社」であることを示す必要性が出てきたことが、注目度をさらに高めているのです。
従業員満足度とエンゲージメントの違い
従業員満足度が示す組織内の状態とは
従業員満足度(ES)は、社員が自分の職場環境や待遇、仕事の内容、人間関係などにどれだけ満足しているかを表す尺度です。満足度が高い状態というのは、社員が職場に対して不平不満が少なく、居心地の良さや安心感を持って働けていることを意味します。
例えば給与水準が適切である、福利厚生が充実している、上司との関係が良好である、仕事にやりがいを感じている、といった条件が満たされていると従業員満足度は高まります。
従業員満足度は従来から人事評価や労務管理で重視されてきた指標であり、アンケート(従業員意識調査)によって「職場環境に満足しているか」「会社に愛着を持っているか」などの質問項目で定量的に測定されます。
満足度が示すのは組織内の「現在の状態」に対する評価であり、社員の本音を知るバロメーターといえます。満足度が高ければ離職リスクが低減しやすく、逆に満足度が低い職場では不満が鬱積して生産性低下や離職増加に繋がる恐れがあるため、まずは社員が快適に働ける環境を整えること(衛生要因の確保)が重要です。
エンゲージメントがもたらす行動・モチベーション
一方で従業員エンゲージメントが高い場合、組織にはどのようなポジティブな行動やモチベーションがもたらされるのでしょうか。
エンゲージメントの高い社員は、単に職場に満足しているだけでなく「自分も会社の目標達成に貢献したい」「もっと良い会社にしていきたい」という主体的な意欲を持っています。そのため、具体的な行動としては以下のような傾向が見られます。
自主性・創造性の発揮
与えられた業務だけでなく、自ら課題を見つけ改善提案を行ったり、新しいアイデアを積極的に提案したりします。言われたこと以上の成果を上げようと努力する「 discretionary effort(裁量労働)」が発揮されます。
高いモチベーションの維持
仕事に困難があっても前向きに乗り越えようとし、目標達成に向け粘り強く取り組みます。多少忙しくても「会社やお客様の役に立つなら頑張ろう」という気持ちで仕事に臨むため、生産性が高くなります。
周囲への好影響
エンゲージメントが高い社員は周囲の同僚にもポジティブな影響を与えます。自社への誇りや仕事への情熱があるため、チーム内で協力し合ったり後輩を積極的に指導したりと、職場全体の士気向上につながります。またエンゲージメントの高い社員は離職しにくく、定着率向上にも寄与します。
このように、エンゲージメントは社員の内面的なモチベーションを引き出し、具体的な行動変容(プロアクティブな行動や高業績)につながる点で、単なる満足度とは異なる次元の効果をもたらします。
例えば米Gallupの調査では、エンゲージメントの高い社員は低い社員に比べ欠勤率が41%低く、離職率も59%低いことが報告されています。さらに顧客評価が10%向上し、売上も20%向上するといったデータもあり、エンゲージメントの高さが社員本人だけでなく顧客や業績にも良い影響を及ぼすことが示されています。
両者をバランス良く高める必要性
従業員満足度と従業員エンゲージメントは、このように別々の側面を測る指標ですが、どちらか一方だけを追求すれば良いというものではありません。重要なのは両者をバランス良く高めていくことです。
エンゲージメントを高めるには前提として満足度(働きやすさ)を高めることが不可欠です。
社員が劣悪な労働環境に不満を抱えたままでは、いくら理念や目標を訴えても心からコミットしてもらうのは難しいでしょう。
例えば、長時間労働で疲弊していたり給与が著しく低かったりすると、まず不満解消が優先でエンゲージメントどころではありません。
一方で、満足度が高い(居心地は良い)がエンゲージメントが低い状態にも注意が必要です。待遇や環境には満足しているため不満はないものの、社員が受け身で主体性を発揮しない場合、組織として大きな成果には結びつきません。
そのため、企業としてはまず従業員満足度を土台として確保しつつ、その上でエンゲージメントを引き出す施策を講じることが大切です。
具体的には、社員の基本的欲求(安全な職場、適切な報酬など)を満たした上で、さらに企業のビジョン共有や評価・報酬制度の工夫、成長機会の提供によって「この会社で頑張りたい」という意欲を高めるアプローチが求められます。
両者は車の両輪のような関係であり、どちらが欠けても真に機能しないため、バランス良く指標管理と施策実施を行うことが重要です。
エンゲージメントの測定と指標の考え方
定性評価と定量評価を組み合わせる手法
従業員エンゲージメントを正しく把握するには、定量評価と定性評価の両面からアプローチすることが効果的です。定量評価とは数値で測る評価、つまりサーベイ(アンケート)によるスコア算出などが該当します。
一方、定性評価とは数値には表れにくい生の声や感情を把握する手法で、面談やグループインタビュー、自由記述のフィードバックなどが含まれます。それぞれ特徴があり、一長一短があります。
まず定量評価では、質問票に対する社員の回答を集計しエンゲージメントスコアや満足度スコアを算出できます。これにより部署間の比較や前年との推移など客観的な分析が可能です。
数値であるため経営層にも報告しやすく、施策の効果測定にも使えます。しかし数字だけでは「なぜそのスコアになったか」という背景までは読み取れません。
そこで重要になるのが定性評価です。例えばサーベイの自由記述欄に書かれた意見を分析したり、従業員有志に集まってもらいフォーカスグループで議論してもらったりすることで、スコアの背後にある要因を探ります。「上司との面談頻度が少ない」「評価制度に不公平感がある」など具体的な課題が浮き彫りになるのは定性評価の強みです。
経営幹部とのオープンな対話の場(タウンホールミーティング等)を設けるのも、社員の本音を引き出す定性アプローチと言えるでしょう。
定量と定性を組み合わせることで数字の根拠や改善策の方向性を明確にできるのです。
このようなハイブリッドな測定アプローチによって、施策立案者は「何を優先的に改善すべきか」を正しく判断でき、より的確なエンゲージメント向上策につなげることができます。
サーベイツール・パルスサーベイの活用事例
近年はエンゲージメント計測のための専門サーベイツールが数多く登場しており、その活用も広がっています。従来は年1回程度の大規模な従業員意識調査を行う企業が一般的でしたが、現在では「パルスサーベイ」と呼ばれる小規模で高頻度のアンケートを取り入れる企業が増えています。
パルスサーベイとは、月次あるいは週次など高い頻度で数問程度の簡易アンケートを実施し、社員のコンディションやエンゲージメントの変化を機敏に捉える手法です。
例えば「最近仕事にやりがいを感じていますか?」といった問いに定期的に答えてもらい、社員のモチベーション低下の兆候を早期に発見するといった使い方がされています。
活用事例として、ある企業では毎月1回のパルスサーベイを全社員にメール配信し、5段階評価で回答してもらう運用をしています。そしてその結果はリアルタイムでダッシュボードに集計され、人事担当者や経営陣が確認できるようになっています。
これにより、「今月は部署Xのエンゲージメントスコアが下がったが何かあったか?」といったチェックを素早く行い、必要に応じて該当部署の管理職と対策を協議する、といったPDCAサイクルを実現しています。
また、年1回の大規模調査では捉えきれない季節要因や組織変更直後の心理状態などもパルスサーベイなら把握できます。最近ではスマホアプリで手軽に回答できるツールもあり、回答率向上にも工夫が凝らされています。
結果を経営指標に活用するメリット
サーベイなどで計測した従業員エンゲージメントの結果を経営指標(KPI/KGI)として活用するメリットも注目されています。従来、人事関連の数値は経営会議で重視されにくい傾向がありましたが、近年は「人的資本経営」の重要性が認識され、エンゲージメントスコアを経営目標の一つに掲げる企業も出てきています。
従業員満足度が向上するメリット

業績の向上
従業員満足度やエンゲージメントの向上は、最終的に企業業績の向上につながることが多くの調査で示されています。満足度が高い社員・エンゲージメントが高い社員は、生産性や創造性が高くミスも減る傾向があります。その積み重ねが部署全体・企業全体の業績に反映されるのです。
具体例として、前述のGallup社のデータではエンゲージメント上位20%のチームは下位20%に比べて収益性が21%高いとの結果が報告されています。また売上も20%向上し、顧客評価(顧客満足度スコアなど)も10%高いという関連性が明らかになっています。
従業員が仕事に熱意を持ち、顧客の課題解決や製品品質向上に全力を注げば、当然ながら商品・サービスのクオリティが上がり顧客から選ばれやすくなります。逆に社員が不満を抱え意欲を欠いた状態では、サービス対応が形式的になったり新しい挑戦が生まれなかったりして業績停滞につながるでしょう。
従業員満足度ランキング上位の企業は長期的な株主リターンも高めだという研究報告もあり、投資家から見ても「社員を大切にしている会社」は将来性があると評価される傾向があります。
まとめると、社員満足度やエンゲージメントに配慮することはコストではなく将来への投資であり、業績拡大というリターンをもたらす可能性が高いのです。
人材の確保
従業員満足度・エンゲージメントの向上は優秀な人材の確保と定着にも直結します。まず社内的には、社員の満足度が高ければ離職率が下がり、培ったノウハウを持つ人材が長く活躍してくれるため人材流出による損失を防げます。
新卒・中途を問わず、今は一つの企業に固執せずより良い条件や働きがいを求めて転職する時代です。そのような中で「今の会社が好きだ」「この職場で働き続けたい」と社員に思ってもらえることは、何より強力な人材維持策となります。
また社外的にも、社員満足度やエンゲージメントが高い会社は「働きがいのある会社」「社員を大切にする会社」として評判が広がり、人材募集をかけた際に応募者が集まりやすくなります。
昨今はSNSや口コミサイトで社員の生の声が世間に伝わる時代です。例えば、ある企業が従業員エンゲージメント向上に熱心に取り組み成果を上げていると、そのこと自体がニュースや採用ページを通じて発信され、共感した人材が「ぜひ自分もここで働きたい」と志望してくれるケースが増えます。実際に「従業員エンゲージメントスコア◯◯を達成」などとアピールする企業も登場しています。
さらに現社員からの紹介採用(リファラル採用)も活発化します。社員が自社に満足し愛着を持っていれば、自信を持って友人知人に「うちの会社はいいところだよ」と紹介してくれるでしょう。これにより信頼性の高い採用候補者を得ることができます。
反対にエンゲージメントが低い会社では「自分の知り合いをこんな会社に紹介したくない…」となりがちで、結果として採用力の差が出てきます。
このようにエンゲージメント向上は採用・定着コストの削減にもつながります。慢性的な人手不足に悩む日本企業にとって、社員が辞めずに働き続け、かつ仲間を呼び込んでくれる好循環は非常に貴重です。
そのためにも、社員に選ばれる魅力ある職場作り=エンゲージメント向上が重要な経営課題となっています。
顧客満足度の向上
「従業員満足なくして顧客満足なし」というサービス業の格言がありますが、エンゲージメントや満足度を高めることは顧客満足度(CS)の向上にも大きく寄与します。社員が会社を好きで誇りに思っている場合、自然とその想いは顧客対応の質に現れます。
例えば、エンゲージメントが高い社員は顧客の立場に立った親身な対応をしようと努めますし、自社の商品・サービスにも誇りを持っているため自信を持って提案できます。その結果、顧客から見れば「この会社の社員は生き生きと働いていて感じが良い」「信頼できる対応をしてくれる」と評価されるでしょう。
一方で社員が不満だらけでいやいや働いていると、どうしても表情や態度にそれが出てしまい、顧客は敏感に察知します。例えば店舗スタッフが疲弊している店では接客態度が悪くなり顧客満足度が下がる、といったことが起こり得ます。
従業員満足度と顧客満足度の間には高い相関関係があるとされ、これを「サービス・プロフィット・チェーン(サービス利益連鎖)」という経営理論で説明することもあります。社員満足が上がればサービス品質が向上し顧客満足が上がり、その結果売上や利益が上がるという連鎖です。
実際にGallupの調査結果でも、エンゲージメントの高い従業員は顧客ロイヤルティ(忠誠度)と顧客維持率を向上させる傾向が示されています。これは顧客対応のちょっとした差が積み重なって大きな差になることを裏付けています。
特にサービス業・小売業では従業員の機嫌ひとつがお客様の満足度に直結する場面も多々ありますから、従業員エンゲージメントを上げることが顧客満足度向上策にもなるわけです。
さらに顧客満足度が上がれば企業の評判が良くなり、また社員の誇りも高まるという好循環が生まれます。自分たちの仕事が顧客から感謝されたり社会に貢献している実感が持てれば、社員のエンゲージメントはますます強固になります。
このようにES向上→CS向上→業績向上→更なるES向上というポジティブサイクルを生み出すためにも、まずは従業員の満足度・エンゲージメント向上に取り組むことが重要です。
従業員エンゲージメントを高めるための具体的な施策

職場環境・オフィス改善
従業員エンゲージメント向上の施策としてまず着手しやすいのは、職場環境やオフィスの改善です。社員が快適かつ安全に働ける物理的・精神的な環境を整えることは、満足度向上の基本でありエンゲージメント醸成の土台となります。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- オフィス設備の充実
- ICTインフラの整備
- レイアウトの工夫
- 在宅勤務・リモートワーク環境の整備
このように職場環境の物理的・制度的改善は、比較的短期間で効果が感じられやすい施策です。小さなことでも、例えばオフィスに観葉植物を置いてリラックス効果を狙うといった工夫から始めても良いでしょう。
社員から「働きやすくなった」「職場が快適だ」という声が聞かれるようになれば、それはエンゲージメント向上の第一歩です。
給与・賞与だけでない報酬制度の多角化
従業員のモチベーションを高めるには、報酬(Reward)制度の工夫も欠かせません。ここで言う報酬とは必ずしも金銭的なものだけを指すのではなく、広義の報酬=社員への様々な見返りと捉えてください。
給与や賞与はもちろん基本ですが、それ以外にも社員の貢献に報いる仕組みを用意することで、エンゲージメントを一層高めることができます。
- 非金銭的報酬(表彰・承認)
- 成長機会の提供
- 業績連動のインセンティブ
- 選択型福利厚生・休暇付与
以上のように、給与・賞与にプラスαする形で多様な報酬を設計することで、さまざまなタイプの従業員のモチベーションに火を付けることができます。
重要なのは、公平性を担保しつつも一律画一的ではなく多元的な報酬アプローチをとることです。経済的な報酬だけでなく心理的な報酬も組み合わせ、社員が「この会社は自分を大事にしてくれている」と実感できれば、愛社精神とエンゲージメントはおのずと高まっていくでしょう。
福利厚生の見直しと新制度の導入方法
従業員エンゲージメントを高める施策として、既存の福利厚生制度の見直しや新しい制度の導入も効果的です。福利厚生は従業員満足度に直結する要素であり、時代や社員ニーズに合った施策へアップデートしていくことが求められます。ここでは福利厚生見直しの進め方と、近年注目される新しい福利厚生の例について解説します。
見直しの進め方としてまず重要なのは、現状の把握と社員ニーズの調査です。自社で提供している福利厚生(各種手当、社内制度、社外提携サービスなど)が実際にどの程度活用され満足されているかをデータで確認しましょう。
利用率が低いメニューや不満の声が多い制度があれば見直しの余地があります。また、従業員アンケートやヒアリングを通じて「こんな制度があったら嬉しい」「ここを改善してほしい」というニーズを集めます。
若手社員とベテラン社員で求めるものが違うことも多いので、世代・属性ごとの声を幅広く集めることが大切です。
最近特に注目を集める新しい福利厚生としては、金融リテラシー支援や資産形成サポートがあります。
例えば、福利厚生型マネーリテラシー支援サービスの「マネーリペア」を導入し、社員が専門家からお金の相談やライフプラン設計のアドバイスを受けられるようにするケースです。
マネーリペアは企業向けのサービスで、税金・資産運用・保険などプロが包括支援し従業員の経済的不安を解消する福利厚生です。社員がお金の悩みを減らせれば仕事にも集中できるため、新しい時代の福利厚生として金融教育サポートを採用する企業が増えています。
他にも、リモートワーク定着を受け在宅勤務手当の新設や、副業解禁に合わせた副業支援制度(副業先でのスキル習得を評価するなど)なども登場しています。
導入手順としては、経営層の理解を得て計画を策定し、総務・人事で制度設計を行い、試行期間を経て本格導入、といった流れになるでしょう。費用対効果も考慮しつつ、自社ならではの魅力的な福利厚生メニューを整えていきましょう。

金融専門家が提案する福利厚生施策
社員のエンゲージメントを高める福利厚生の中でも、金融の専門家が提案する資産形成支援策は近年注目度が上がっています。お金の安心は社員の精神的安定につながり、仕事への集中や会社への信頼感を高める効果があるためです。
ここでは金融分野の専門知識を活かした福利厚生施策として、具体的な3つの方法を紹介します。
企業型確定拠出年金(DC)やiDeCoの導入メリット
企業型確定拠出年金(Defined Contribution plan:DC)は、企業が従業員のために導入できる年金制度です。従来の企業年金(確定給付型)と異なり、掛金を拠出して運用し、その成果を将来従業員が受け取る仕組みです。
社員それぞれが自分の年金資産運用を行う形ですが、掛金拠出時に税優遇があることや、運用益も非課税で再投資できることから、老後資産形成に非常に有利な制度です。
企業にとっても、退職金制度に代えてDCを導入すれば将来の年金債務を確定させられるメリットがあります(掛金は確定し、運用結果によって給付額が変動するため企業の追加負担が生じにくい)。
DC導入の従業員側メリットとしては、前述の税制優遇に加え、会社からの掛金拠出がある場合は実質的な給与増と同じ効果があります。自助努力で老後に備える意識が高まり、将来への安心感が得られるでしょう。
また、DCでは自分で運用商品(投資信託など)を選ぶ必要があるため、金融リテラシー向上のきっかけにもなります。会社が運用教育をしっかり行えば、社員の投資知識が高まり、私生活の経済面でも豊かさが増すかもしれません。
併せてiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用も促進すると良いでしょう。iDeCoは個人が任意で加入できる年金制度で、掛金全額が所得控除になるなど強力な税優遇があります。
企業型DCがあっても加入できる場合がありますし(企業型DCと併用可能な条件あり)、企業としては社員にiDeCo加入を推奨し手続きをサポートすることも立派な福利厚生となります。
例えばiDeCo説明会を社内で開いたり、加入申し込みの書類の書き方を指導したりといった支援です。社員からすれば「自社は老後資金作りを応援してくれている」と受け止められ、会社への信頼が高まるでしょう。
金融専門家の視点から言えば、DCやiDeCoは小さなコストで大きな効果を生む福利厚生です。会社の負担は制度導入の事務手続きや場合によっては事業主掛金程度ですが、社員にとっては数千万規模の老後資金形成につながる可能性もあります。
こうした制度を導入・奨励することは、社員の将来不安を和らげエンゲージメントを高める策として有効です。
従業員持株会・財形貯蓄の効果的運用
次に、従業員持株会や財形貯蓄といった伝統的な福利厚生制度も、エンゲージメント向上に活かすことができます。これらは昔からある制度ですが、その効果を再評価し、現代的な活用を図ることがポイントです。
従業員持株会は、社員が自社の株式をコツコツ買い増やしていく制度です。毎月の給料から一定額を天引きして自社株を購入し、会社側が奨励金(例えば購入額の5~10%を上乗せ)を出すケースが一般的です。
社員にとっては自社の業績が上がれば持ち株の評価額も上がり、会社の成長を自分の利益として実感できるメリットがあります。会社側にとっても、社員が株主になることで経営者意識や帰属意識の向上が期待できます。
いわば社員と会社の利害が一致する形になり、エンゲージメントを強化する効果があります。
持株会を効果的に運用するには、まず社員への周知と参加促進が大事です。「奨励金が出るのでお得ですよ」「長期投資で資産形成できますよ」といったメリットを伝え、若手社員にも参加を呼びかけましょう。
また、株価が下がった場合のリスクもある程度説明し、無理のない範囲での積立を推奨することも必要です。会社業績が振るわない時に社員の資産が目減りする可能性はありますが、逆に言えば社員も本気で会社を良くしようと奮起するきっかけにもなり得ます。
適切な奨励策と教育をセットで行い、社員にとってプラスになる持株会を目指しましょう。
財形貯蓄は、給与天引きで貯蓄を行う制度で、「一般財形」「財形年金」「財形住宅」の3種類があります。これらは一定要件のもとで利子に税金がかからない(非課税)などの優遇があり、住宅購入資金や老後資金を計画的に貯めるのに適しています。
バブル期以降利用者は減っていましたが、昨今の資産形成ブームで再注目されています。会社としては、財形貯蓄の奨励金を出したり利子補給を行ったりすることで社員の参加を促進できます。
例えば財形貯蓄を年間○万円以上積み立てた社員に対し、○%の奨励金を支給する、といった仕組みです。社員側は給料天引きで強制的に貯蓄されるため確実にお金が貯まり、将来の安心感が高まります。
財形貯蓄を効果的に運用するには、特に若年層社員にそのメリットを教育することが重要です。「財形って何?お得なの?」という新人社員も多いため、社内報や説明会で分かりやすく制度紹介をしましょう。
金融専門家の知見を借りて、「複利効果で◯年後にこれだけ貯まります」とシミュレーションを見せると興味を持ってもらいやすくなります。財形は堅実な制度ですが、上手に活用すれば社員の将来設計を支える強力な福利厚生になります。
専門家を交えた資産形成サポートプログラム
最後に紹介するのは、金融の専門家を交えた資産形成サポートプログラムです。これは社員一人ひとりの資産形成やお金の悩みに対して、専門知識を持つアドバイザーが継続的に支援するという福利厚生施策です。
従来から生命保険会社などが提供するマネーセミナーはありましたが、近年ではより踏み込んだコンサルティング型のサービスが登場しています。
例えば先述の「マネーリペア」は、企業向けの包括的なマネーリテラシー支援サービスです。税理士・ファイナンシャルプランナーなど金融の専門家がチームとなって企業の従業員をサポートします。
具体的には、ライフプラン相談(結婚や住宅購入、教育費、老後資金など)、資産運用アドバイス(NISAや投資信託の活用法)、保険見直し提案、税金対策アドバイスなど、お金にまつわるあらゆる相談に乗ってくれるのです。
社員からすると「会社が自分の個人的なお金の相談まで面倒を見てくれる」形になり、大きな安心感と満足感を得られます。お金の不安が減れば私生活が安定し、結果的に仕事にも集中できるようになります。
この種のプログラム導入メリットは、従業員の金融ストレスを軽減できることです。日本人は金融教育を受ける機会が少なく、老後2000万円問題など将来不安を抱える人も多いと言われます。
そこに企業が専門家の力を借りてサポートを提供すれば、社員の不安が和らぎエンゲージメント向上につながります。また「専門家が会社に来てくれて無料相談できる」となれば福利厚生としてのインパクトも大きく、社員エクスペリエンスの向上施策としても優秀です。
さらに、資産形成支援プログラムは企業のイメージアップにも寄与します。金融リテラシー向上は国を挙げて推進されているテーマであり、社員の生活力向上に取り組む企業姿勢は社会的にも評価されます。
社員に対しても「会社は自分たちの将来まで考えてくれている」と感じられ、ロイヤルティが深まるでしょう。実際にマネーリペアのようなサービスを導入した企業では「従業員のモチベーションが上がり、定着率も改善した」「仕事以外の悩みも相談できる安心感から会社への信頼が高まった」といった声が聞かれています。
金融専門家の知見を上手に活用し、社員が生涯にわたって安心して働ける環境づくりを進めることが、現代の先進的な人事戦略と言えるでしょう。
※マネーリペアのご紹介
マネーリペアは企業の福利厚生担当者様向けに提供されるマネーリテラシー支援サービスです。専門家による個別相談やセミナーを通じて従業員の資産形成を包括的にサポートし、従業員の安心と企業価値向上に貢献します。詳しくはマネーリペアのサービス紹介ページをご覧ください。

まとめ
従業員エンゲージメントとは何か、その重要性や従業員満足度との違い、高める方法について解説してきました。エンゲージメントは社員の企業に対する愛着心や貢献意欲を示す指標であり、満足度(ES)という土台の上に築かれるものです。
少子高齢化による人材確保難や価値観の多様化、国際競争の中で、社員一人ひとりのやる気と定着が企業価値を左右する時代となりました。従業員満足度とエンゲージメントの両方をバランスよく高めることが、企業の持続的成長には不可欠です。
社員のエンゲージメントが高まれば、業績向上・人材確保・顧客満足度向上という好循環が生まれます。規模の大小を問わず、どの企業でも取り組める余地があります。本記事の内容を参考に、自社の課題に合った施策からぜひ着手してみてください。
御社の従業員エンゲージメント向上に、金融福利厚生サービスの活用も検討されてみませんか?社員の資産形成やマネーリテラシー支援を専門家に任せることで、人事ご担当者様の負担を減らしつつ大きな効果が期待できます。
例えば本記事で紹介した「マネーリペア」は、従業員の金融リテラシー向上と経済的安心を実現し、企業全体の生産性向上に貢献するサービスです。
社員の将来への安心感はエンゲージメントを高め、結果的に企業業績や価値向上につながります。興味をお持ちの方はぜひマネーリペアのページをご覧いただき、資料請求やお問い合わせをしてみてください。専門家チームが貴社の福利厚生を力強くサポートいたします。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。

%2520(1).jpg&w=1080&q=75)