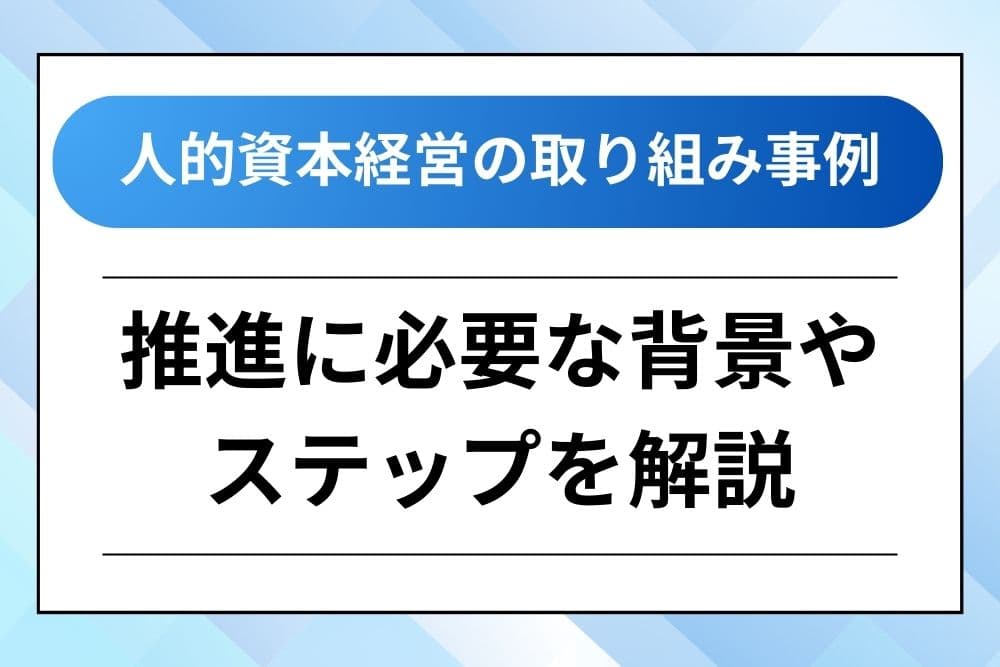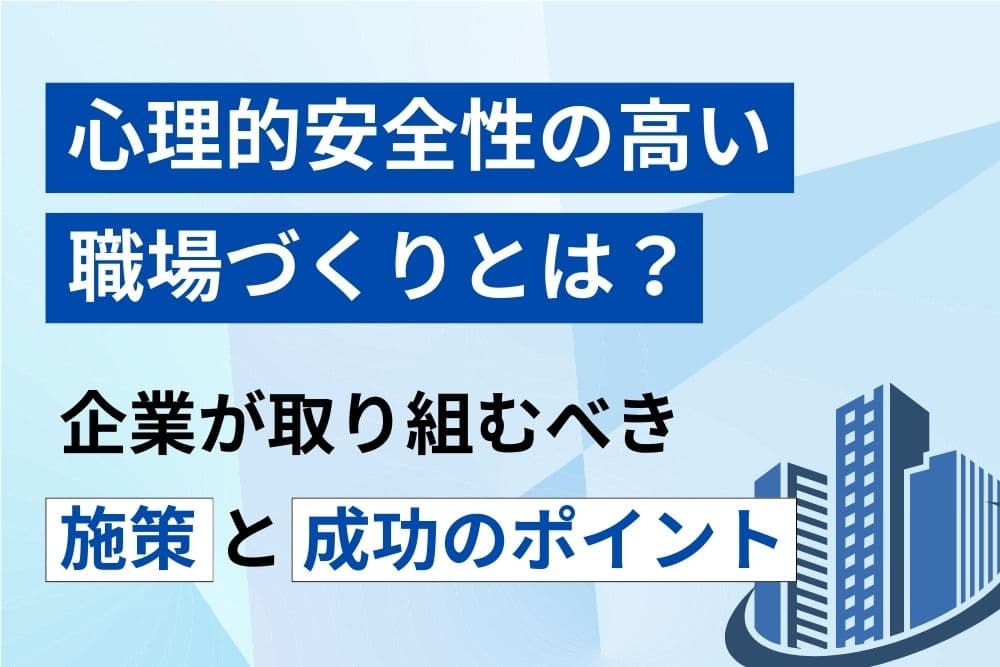お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
退職金制度は勤続年数が鍵!退職金カーブ設計のポイント
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
退職金制度と勤続年数の基本
退職金の平均額・相場
勤続年数による退職金の計算方法とポイント
退職金の主な種類4つ
勤続年数を考慮した退職金制度を導入するメリット
退職金制度は、従業員の働きがいや定着率を左右する重要な制度です。なかでも「勤続年数」は給付額を大きく左右する要素として設計に深く関わります。
本記事では、人事・金融の専門家が、勤続年数と退職金制度の関係性、制度設計のポイント、そして企業が押さえておきたい最新の動向までを詳しく解説します。
福利厚生の見直しや人材戦略の強化をお考えの企業様は、ぜひご一読ください。
目次
退職金制度と勤続年数の基本

退職金制度は従業員の長年の貢献に報いるとともに、退職後の生活を支える重要な仕組みです。勤続年数はその算定において最も基本的な要素となっています。
退職金制度の役割と目的
退職金制度は、長年企業に貢献してきた従業員への「感謝の証」であると同時に、退職後の生活保障という重要な役割を担っています。企業にとっては人材の定着促進や長期的な人材育成の基盤となり、従業員にとっては将来の経済的安定につながる重要な制度です。
退職金には主に3つの目的があります。
- 「功労報償」として、企業への長年の貢献に対する感謝の意を示すこと。
- 「生活保障」として、退職後の生活を経済的に支援すること。
- 3つ目は「人材の定着」として、長期勤続を促進し、企業の安定的な成長を支える
ことです。
これらの目的を達成するために、多くの企業では勤続年数を退職金算定の重要な基準としています。長く働いた従業員ほど高い退職金を受け取れる仕組みは、従業員のロイヤルティを高め、企業の人材基盤を強化することにつながるのです。
関連記事:退職金の制度を徹底解説!企業が導入すべき理由とは?
マネーリペアなら退職金制度の最適な設計をサポート
退職金制度の設計でお悩みではありませんか?マネーリペアの専門コンサルタントが、御社の状況に合わせた最適な退職金制度を提案します。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
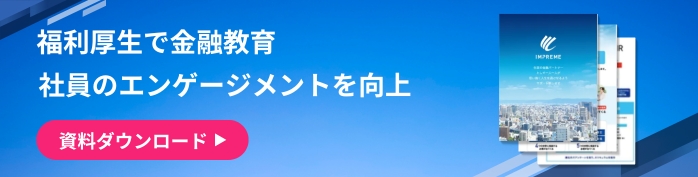
勤続年数が重視される背景
なぜ多くの企業が退職金制度において勤続年数を重視するのでしょうか。その背景には、日本の雇用慣行と企業文化が大きく関わっています。
伝統的な日本企業では「終身雇用」「年功序列」の考え方が根付いており、長く企業に貢献する従業員を高く評価する傾向があります。
勤続年数の長さは企業への忠誠心や貢献度の指標とみなされ、それに応じた報酬を用意することで、従業員の長期的な定着を図ってきました。
また、勤続年数の長い従業員は業務知識や経験が豊富であり、企業にとって貴重な人的資産です。そうした人材の離職を防ぎ、知識や技術の社内蓄積を促進するためにも、勤続年数に応じた退職金制度は効果的な手段となっています。
さらに、勤続年数という客観的な指標を用いることで、退職金の算定が明確かつ公平に行われるというメリットもあります。
勤続1年につき基本給の○カ月分といった形で計算することで、従業員にとっても将来受け取れる退職金の見通しが立てやすくなるのです。
退職金の平均額・相場

退職金の金額は勤続年数や学歴、退職理由などによって大きく異なります。ここでは最新のデータに基づいた平均額をご紹介します。
退職金の平均額 勤続年数/学歴別
勤続年数と学歴は、退職金額を左右する大きな要因です。一般的に、勤続年数が長いほど、また学歴が高いほど退職金額は高くなる傾向にあります。
大卒者の場合、勤続20年での平均退職金額は約1,800万円、30年では約2,300万円、40年では約2,700万円程度となっています。一方、高卒者では勤続20年で約1,500万円、30年で約1,900万円、40年で約2,200万円という調査結果があります。
(出典:経団連「2021年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果」)
この差は初任給や昇給ペースの違いが反映されたものですが、同じ勤続年数でも学歴によって数百万円の開きがあることがわかります。ただし、これはあくまで平均値であり、業種や企業規模、職種によっても大きく異なるため、参考値として捉えることが大切です。
勤続年数ごとの退職金の伸び率を見ると、多くの企業では20年目から30年目にかけての増加率が最も高く、30年を超えると伸び率が緩やかになる傾向があります。
これは長期勤続のインセンティブとして、特に中堅社員の定着を促進する設計になっていることを示しています。
退職金の平均額 退職理由/学歴別
退職理由によっても退職金額は変わってきます。一般的に「定年退職」が最も優遇され、「会社都合退職」「自己都合退職」の順に減額されるケースが多いでしょう。
大卒・勤続30年の場合、定年退職では平均約2,300万円、会社都合退職では約2,000万円、自己都合退職では約1,700万円という調査結果があります。高卒の場合は、それぞれ約1,900万円、約1,600万円、約1,400万円となっています。
会社都合退職の場合は、希望退職や早期退職制度を利用した場合に上乗せ金が支給されるケースもあり、実際の金額は企業の制度によって大きく異なります。
自己都合退職の場合でも、退職の理由や時期によって減額率が変わることがあるため、退職を考える際には事前に確認しておくことが重要です。
退職一時金/退職年金制度の平均額
退職金制度は大きく分けて「一時金方式」と「年金方式」に分類されます。一時金方式では退職時に一括で支給されるのに対し、年金方式では分割して定期的に支給されます。
一時金方式の平均額は、大企業(従業員1,000人以上)の場合、勤続30年・大卒で約2,500万円、中小企業(従業員300人未満)では約1,800万円という差があります。企業規模による格差は依然として大きいと言えるでしょう。
年金方式の場合、月額支給額に換算すると大企業で月額約15万円、中小企業で月額約10万円という調査結果があります。支給期間は10年から20年が一般的で、生涯にわたって支給される例は少なくなっています。
近年では一時金と年金を組み合わせるハイブリッド型も増えており、例えば退職金総額の60%を一時金で、残り40%を年金で受け取るといった選択肢を用意している企業も多くなっています。
このような柔軟な制度設計は、従業員のライフプランに合わせた選択を可能にする点で評価されています。
勤続年数による退職金の計算方法とポイント

退職金の計算方法は企業によって異なりますが、勤続年数を基準とした計算方式が多く採用されています。ここでは主な計算方法とそのポイントを解説します。
主な計算式の種類
退職金の計算式には主に以下の3つのタイプがあります。
1. 基本給連動型
最も一般的な方式で、「基本給×支給率×勤続年数」で計算します。支給率は勤続年数や職位によって変動することが多く、例えば勤続10年未満は0.8、10年以上20年未満は1.0、20年以上は1.2といった形で設定されるケースがあります。
計算例:基本給30万円×支給率1.2×勤続30年=1,080万円
2. ポイント制
勤続年数や職位、成果などに応じてポイントを付与し、退職時の累積ポイント×ポイント単価で計算する方式です。
- 勤続1年につき10ポイント
- 管理職昇進で50ポイント
など、多様な要素を反映させやすいという特徴があります。
【計算例:累積ポイント1,000ポイント×ポイント単価1万円=1,000万円】
3. 定額制
勤続年数のみに連動する最もシンプルな方式で、「勤続1年につき○○万円」といった形で計算します。中小企業や業績変動の大きい業界で採用されることが多いです。
【計算例:勤続1年につき30万円×勤続25年=750万円】
これらの方式は単独で採用されることもあれば、複数の方式を組み合わせたハイブリッド型で運用されることもあります。例えば、基本部分は定額制で計算し、職位や成果に応じた加算部分をポイント制で計算するといった具合です。
勤続年数のカウント方法と例外規定
勤続年数のカウント方法は、単純に「入社から退職までの期間」と思われがちですが、実際には様々なケースに応じた例外規定が設けられていることが多いです。
基本的なカウント方法
多くの企業では「入社日から退職日までの期間」を勤続年数としてカウントします。この際、月単位でカウントするケース(例:10年6ヶ月=10.5年)と、年単位で切り捨てるケース(例:10年6ヶ月=10年)があります。
育児・介護休業の扱い
法律上、育児休業や介護休業の期間は勤続年数に含めることが原則とされています。ただし、賃金が支払われない期間を一部除外するなど、企業独自のルールを設ける場合もあります。
休職期間の扱い
病気休職や自己啓発休職などの期間の扱いは企業によって異なります。全期間を勤続年数にカウントする企業もあれば、一定期間のみカウントする企業、まったくカウントしない企業もあります。
出向・転籍の扱い
グループ企業への出向期間は通常、勤続年数にカウントされます。転籍の場合は、転籍先での勤務期間を元の会社の勤続年数に通算する「勤続年数通算制度」を設けている企業もあります。
これらの例外規定は就業規則や退職金規程に明記されていることが一般的ですが、従業員にとってわかりにくい場合も少なくありません。人事担当者は、これらの規定を従業員に対して丁寧に説明することが求められます。
就業規則・社内規定でのルール設定
退職金制度を運用する上で、就業規則や退職金規程での明確なルール設定は非常に重要です。特に勤続年数に関するルールは、従業員の将来設計に大きく影響するため、慎重な設計が求められます。
規定に含めるべき主な項目
- 退職金の受給資格(最低勤続年数など)
- 勤続年数のカウント方法(入社日、試用期間の扱いなど)
- 休職・休業期間の扱い
- 退職理由による支給率の違い
- 支給時期と支給方法
これらの項目を明確に規定することで、従業員の納得感を高めるとともに、将来的なトラブルを防止することができます。
規定変更時の注意点
退職金規程を変更する場合は、労働契約法や就業規則の不利益変更に関するルールを遵守する必要があります。特に既存従業員の既得権を侵害するような変更(勤続年数の計算方法の不利益変更など)は、合理的な理由と適切な手続きが求められます。
変更を検討する際は、経過措置を設けるなど、既存従業員への配慮も重要です。例えば「規程変更前の勤続期間については旧制度で計算し、変更後の期間は新制度で計算する」といった措置を講じることで、従業員の理解を得やすくなります。
また、規程変更の際は、従業員への丁寧な説明と周知も欠かせません。変更の理由や新制度の内容、経過措置などについて、説明会の開催や資料の配布を通じて理解を促進することが重要です。
退職金の主な種類4つ

退職金制度には様々な種類があり、企業はそれぞれの特徴を理解した上で、自社に最適な制度を選択する必要があります。ここでは主な4つの種類について解説します。
1.退職一時金
退職一時金は、最も伝統的な退職金制度で、従業員が退職する際に一括して支給される方式です。企業が自社で資金を積み立て、管理・運用する「社内積立方式」が一般的です。
メリット
- 制度設計の自由度が高く、自社の状況に応じた柔軟な設計が可能
- 従業員にとって退職時にまとまった資金を受け取れる安心感がある
- 制度の理解がしやすく、従業員への説明が比較的容易
デメリット
- 企業の業績悪化時に支払い原資の確保が困難になるリスクがある
- 退職給付債務が企業の財務状況に大きな影響を与える可能性がある
- 退職時の一時的な高額所得により、税負担が大きくなることがある
勤続年数との関連では、一般的に「勤続年数が長いほど支給額が高くなる」設計が多く、特に中小企業では「勤続1年につき基本給の○カ月分」といったシンプルな計算式が採用されることが多いです。
2.退職金共済
退職金共済は、企業が外部の共済団体に掛金を拠出し、従業員の退職時に共済団体から退職金が支払われる制度です。主に「中小企業退職金共済(中退共)」「特定退職金共済」「建設業退職金共済」などがあります。
メリット
- 掛金が全額損金算入できるなど税制上の優遇がある
- 外部積立のため企業の倒産リスクから独立している
- 特に中小企業にとって事務負担が少なく、導入コストが低い
デメリット
- 制度設計の自由度が限られている
- 運用利回りが低めに設定されていることが多い
- 従業員の選択肢が限られている(一時金のみなど)
勤続年数との関連では、掛金は「勤続年数に関わらず一定額」とするケースが多いですが、支給額は「勤続年数に応じた利息相当分」が加算されるため、長期勤続者ほど有利な設計となっています。
3.確定給付年金(DB)
確定給付年金(DB:Defined Benefit)は、あらかじめ給付額が確定している年金制度です。企業が拠出した資金を年金資産として外部の金融機関で運用し、退職後に年金または一時金として支給されます。
メリット
- 従業員にとって将来受け取る年金額が予測できる安心感がある
- 運用リスクを企業が負うため、従業員の資産形成に配慮した制度といえる
- 一定の範囲内で柔軟な制度設計が可能
デメリット
- 運用リスクを企業が負うため、財務上の負担となる可能性がある
- 制度の維持・管理コストが比較的高い
- 年金資産の積立不足が発生した場合、追加拠出が必要になる
勤続年数との関連では、給付額の計算に「ポイント制」を採用するケースが増えており、「勤続1年につき○ポイント」「役職に応じた加算ポイント」などを組み合わせる設計が多くなっています。
これにより、単純な勤続年数だけでなく、役割や貢献度も反映した給付設計が可能になっています。
4.確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(DC:Defined Contribution)は、拠出額が確定している年金制度です。企業が毎月一定額を拠出し、従業員自身が運用商品を選択して資産形成を行います。日本版401kとも呼ばれ、近年導入企業が増加しています。
メリット
- 企業にとって将来の年金債務が発生せず、財務上の負担が軽減される
- 運用実績次第で従業員の受取額が増える可能性がある
- 転職時の資産の持ち運びが容易(ポータビリティがある)
デメリット
- 運用リスクを従業員が負うため、資産形成に対する知識・関心が必要
- 勤続年数と給付額の直接的な連動性が薄れる
- 従業員への投資教育など、新たな人事上の課題が発生する
勤続年数との関連では、多くの企業が「勤続年数に関わらず一律の拠出額」を採用していますが、一部では「勤続○年以上で拠出額を増額する」など、長期勤続のインセンティブを組み込む設計も見られます。
また、勤続年数と年齢を組み合わせた「ポイント制」を採用し、拠出額に差をつける企業もあります。
勤続年数を考慮した退職金制度を導入するメリット
勤続年数を考慮した退職金制度には、企業にとっても従業員にとっても多くのメリットがあります。ここでは主なメリットについて詳しく解説します。
1.退職金カーブの工夫による定着率と離職率へのインパクト
勤続年数に応じて退職金が増加する制度は、従業員の長期勤続を促進し、定着率の向上に直接的な効果をもたらします。特に「退職金カーブ」を工夫することで、戦略的な人材定着を図ることができます。
例えば、入社5年目までは緩やかな上昇、5年目から15年目にかけて急カーブで上昇、15年目以降は再び緩やかに上昇するといった設計にすることで、中堅社員の引き留め効果を高めることができます。
実際に、このような設計を導入した企業では、入社5〜15年目の社員の離職率が平均30%低下したという調査結果もあります。
また、業界や職種によって「退職リスクが高い時期」が異なるため、その時期に合わせた退職金カーブの設計も効果的です。例えばIT業界では入社3〜5年目に転職が多い傾向があるため、この時期に退職金が大きく上昇する設計にすることで、人材流出を防ぐ効果が期待できます。
長期的な視点では、勤続10年以上の社員比率が高い企業ほど、業績が安定している傾向も見られます。これは経験豊富な人材の蓄積が、企業の競争力や生産性の向上につながっていることを示唆しています。
関連記事:企業向け金融教育とは?導入メリットや成功事例、実践方法を徹底解説
2.企業ブランディングと採用競争力の強化
充実した退職金制度は、企業の福利厚生の重要な柱として、採用市場における競争力強化やブランディングに大きく貢献します。
就職活動中の学生や転職希望者にとって、退職金制度の有無や内容は企業選びの重要な判断材料の一つです。特に昨今は将来の経済不安から、若年層でも「老後資金」への関心が高まっており、充実した退職金制度は若手人材の獲得にも効果的です。
実際、新卒採用において「退職金制度あり」の企業は、「退職金制度なし」の企業と比較して、内定承諾率が平均15%高いというデータもあります。
また、「勤続年数に応じて手厚い退職金を用意している企業」は、「従業員を大切にする企業」「長期的視点を持つ安定した企業」というイメージにつながり、企業ブランディングにもプラスの効果をもたらします。
退職金制度を採用広報や企業PRに積極的に活用している企業も増えています。例えば「30年勤続で平均○○円の退職金」「業界トップクラスの退職金水準」といった具体的な数字を示すことで、応募者の関心を引きつけることができます。
ただし、退職金額は他の待遇と合わせて総合的に判断されるものなので、給与水準や働き方との整合性も重要です。
3.従業員のモチベーション・エンゲージメント向上
勤続年数に応じた退職金制度は、従業員の長期的なモチベーションやエンゲージメント向上にも効果を発揮します。
長期的な視点での報酬が明確になることで、従業員は「この会社で長く働く価値」を実感しやすくなります。特に日常の業務では評価されにくい「継続的な貢献」や「組織への忠誠心」に対する評価として、勤続年数に応じた退職金は大きな意味を持ちます。
また、退職金は「貯蓄の強制力」としての側面も持ち合わせており、従業員の将来不安を軽減する効果があります。「退職後の生活資金が会社によって準備されている」という安心感は、現在の仕事への集中力を高め、生産性向上にもつながります。
退職金の「見える化」も重要です。定期的に「現時点での退職金試算額」を従業員に通知している企業では、長期勤続へのモチベーションが高まるという報告があります。
例えば「あと5年勤務すれば退職金が○○円増加する」といった具体的な数字を示すことで、勤続意欲を喚起することができるでしょう。
勤続年数による退職金制度のデメリットと課題
勤続年数を重視した退職金制度には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。企業はこれらを理解した上で、最適な制度設計を検討する必要があります。
1.勤続年数が短い従業員に対する不公平感
勤続年数を重視した退職金制度では、短期間で退職する従業員に対して支給額が少なくなる、あるいはまったく支給されないケースもあり、不公平感を生じさせる可能性があります。
特に近年は「ジョブ型雇用」や「専門性重視」の傾向が強まっており、短期間でも高い成果を上げる従業員が増えています。そうした人材にとって、勤続年数のみで評価される退職金制度は魅力に欠け、優秀な人材の採用や定着を妨げる要因になりかねません。
また、ライフスタイルの多様化により、育児や介護、パートナーの転勤など、やむを得ない理由で退職するケースも増えています。そうした従業員に対して、勤続年数だけを理由に退職金を減額することは、企業の社会的責任の観点からも再考が必要かもしれません。
この課題に対応するため、「最低勤続年数の短縮」(例:従来の3年から1年へ)や「短期勤続者への一定額保証」などの工夫を導入する企業も増えています。また、勤続年数だけでなく「貢献度」や「成果」も加味した計算方式への移行も一つの解決策となるでしょう。
2.早期離職や転職が増加する時代への対応
現代の労働市場では、「終身雇用」の概念が薄れ、キャリアアップのための転職が一般的になっています。厚生労働省の調査によれば、近年では若年層を中心に平均勤続年数が短縮傾向にあり、特に20代では平均勤続年数が3年程度というデータもあります。
このような環境下では、勤続年数を過度に重視した退職金制度は時代にそぐわない可能性があります。例えば「勤続10年未満は退職金なし」という制度では、多くの従業員が退職金を受け取れないまま転職してしまうことになります。
また、企業側にとっても、長期勤続を前提とした退職金制度は将来的な財務負担のリスクとなり得ます。特に業績の変動が激しい業界では、数十年先の退職金支払いに備えた資金確保が難しい場合もあるでしょう。
これらの課題に対応するため、「ポータビリティ(持ち運び可能性)」を重視した退職金制度への移行が進んでいます。確定拠出年金(DC)はその代表例で、転職時にも資産を持ち運びできるため、早期離職のデメリットが少ない制度といえます。
また、「勤続年数のカーブを緩やかにする」「早期から一定額を保証する」といった工夫も有効でしょう。
企業は自社の人材戦略や従業員の年齢構成、業界特性などを総合的に考慮し、現代の労働市場に適した退職金制度を設計することが求められています。
勤続年数を重視しつつ柔軟な設計を行う方法
勤続年数を評価しながらも、現代の多様な働き方に対応した柔軟な退職金制度を設計するには、いくつかの方法があります。ここでは3つの主要なアプローチを紹介します。
1.一時金方式と分割支給方式の比較
退職金の支給方法には、一時金方式と分割支給方式(年金方式)があり、それぞれに特徴があります。
一時金方式のメリット
- まとまった資金を受け取れるため、住宅ローンの返済や子どもの教育資金など、大きな支出に対応しやすい
- インフレリスクを回避できる
- 受給手続きが一度で済む
分割支給方式のメリット
- 定期的な収入が確保できるため、老後の生活設計が立てやすい
- 一時金と比較して税制上有利になる場合がある
- 浪費を防止できる
多くの企業では、これらを組み合わせた「選択制」を導入しています。例えば「退職金総額の30%~70%を一時金で、残りを年金で受け取る」といった範囲内で従業員が選択できるようにする方法です。これにより、従業員の多様なライフプランに対応することができます。
また、勤続年数との関連では「勤続年数が長い従業員ほど年金部分の割合を高くする」といった設計も可能です。これは長期勤続者の老後の安定をより手厚く支援する考え方に基づいています。
2.成果主義や職務給との組み合わせ
伝統的な退職金制度では勤続年数を重視していましたが、近年では「成果主義」や「職務給」の要素を取り入れた設計が増えています。
勤続年数+成果要素の組み合わせ
退職金の基本部分は勤続年数で計算し、それに成果要素を加算する方式です。例えば「勤続年数による基本ポイント+評価による加算ポイント」といった形で計算します。これにより、長期勤続の価値を認めつつ、高い成果を上げた従業員を評価することができます。
具体的には「直近5年間の人事評価の平均が4以上(5段階評価)の場合、退職金を10%増額する」といった形で設計されることが多いです。
職務や役割に応じた設計
同じ勤続年数でも、担当した職務や役割に応じて退職金に差をつける方式です。例えば「管理職経験者は一般社員より高い支給率を適用する」「専門性の高い職種には特別加算を行う」といった設計が可能です。
これは「ジョブ型雇用」の考え方と親和性が高く、「同じ期間でも、より大きな責任を担った人にはそれに見合った退職金を支給する」という公平性の観点からも支持されています。
このような組み合わせ型の退職金制度は、従業員にとって「長く働くこと」と「高い成果を上げること」の両方にインセンティブを与える効果があります。また、企業にとっても人材の定着と高いパフォーマンスの両立を図れるメリットがあります。
3.確定拠出年金(DC)や前払い退職金制度との併用
伝統的な退職一時金や確定給付年金だけでなく、確定拠出年金(DC)や前払い退職金制度を併用することで、柔軟性の高い退職金制度を構築することができます。
ハイブリッド型の設計例
- 基本部分(60%):勤続年数に応じた退職一時金または確定給付年金
- 変動部分(40%):確定拠出年金(DC)
このような「ハイブリッド型」の設計では、基本部分で長期勤続のインセンティブを維持しつつ、変動部分で柔軟性や持ち運び可能性を確保することができます。勤続年数の短い従業員でも、DCの部分については転職時に持ち運びが可能なため、不公平感が軽減されます。
前払い退職金制度の活用
一部の企業では「前払い退職金制度」を導入しています。これは退職金の一部を毎月の給与に上乗せして支給する方式で、「即時還元型退職金」とも呼ばれます。
例えば「将来の退職金の20%を前払いとして毎月支給し、残り80%を退職時に支給する」といった設計が可能です。この方式は若手社員の満足度向上や採用競争力強化に効果があるとされています。
ただし、前払い部分は給与所得として課税されるため、税制上のメリットは減少します。また、退職時の受取額が減少するため、老後資金への影響も考慮する必要があります。
これらの制度を上手く組み合わせることで、勤続年数を重視しつつも、現代の多様な働き方やライフスタイルに対応した退職金制度を構築することができます。企業は自社の状況や従業員のニーズに合わせて、最適な組み合わせを検討することが重要です。
退職金制度の勤続年数に関するよくある質問
退職金制度における勤続年数に関して、従業員からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
Q.勤続年数が長いほど退職金は常に高くなるのでしょうか?
多くの企業では基本的に勤続年数が長いほど退職金は高くなる設計になっていますが、必ずしも比例関係にあるわけではありません。
一般的な退職金カーブは「右肩上がり」ですが、そのカーブの傾きは勤続期間によって異なるケースが多いです。多くの企業では以下のようなカーブを採用しています。
- 入社~5年目:緩やかな上昇
- 6~15年目:急な上昇
- 16~25年目:やや緩やかな上昇
- 26年目以降:緩やかな上昇
このようなカーブになっている理由は、中堅層(6~15年目)の定着を特に促進したいという企業の人材戦略が反映されているためです。
また、成果主義を取り入れた退職金制度では、同じ勤続年数でも人事評価や役職によって退職金額に差がつくケースがあります。例えば「勤続20年の一般社員よりも勤続15年の管理職の方が退職金が高い」といった逆転現象も珍しくありません。
自社の退職金制度がどのようなカーブになっているかを従業員に説明することで、長期的なキャリアプランを立てる上での参考にしてもらうことができるでしょう。
Q.中途入社の場合、勤続年数はどのように計算されますか?
中途入社者の勤続年数の計算方法は企業によって異なりますが、一般的には以下の3つのパターンがあります。
- 1. 入社日からのカウント
- 2. 前職キャリアの一部加算
- 3. 年齢ベースでの計算
どの方法を採用するかは企業の人材戦略や既存社員とのバランスを考慮して決定する必要があります。特に中途採用を積極的に行う企業では、前職キャリアを一定程度評価する方法が採用されるケースが増えています。
いずれの方法を採用する場合も、入社時に明確に説明することで、後々のトラブルを防止することができるでしょう。
Q.企業が退職金制度を廃止・変更する際、勤続年数の扱いはどう影響しますか?
退職金制度の廃止や大幅な変更を行う際、既存従業員の勤続年数の扱いは重要な問題となります。法的観点も含めた一般的な対応は以下の通りです。
制度廃止の場合
完全に廃止する場合は、廃止時点までの勤続年数に応じた退職金相当額を何らかの形で精算・保全する必要があります。主な方法としては:
- 一時金精算:廃止時点での退職金相当額を一時金として支給
- 確定拠出年金への移行:退職金相当額を確定拠出年金に移換
- 前払い退職金への切り替え:退職金相当額を月々の給与に上乗せして支給
これらの方法により、廃止前の勤続年数に対応する退職金相当額は保全されます。
制度変更の場合
制度を大きく変更する場合(例:退職一時金から確定拠出年金への移行)も、変更時点までの勤続年数に対応する既得権は保全されるのが一般的です。
具体的には:
- ポイント制への移行:それまでの勤続年数に応じたポイントを付与
- 二重制度の運用:制度変更日を境に旧制度と新制度を併用
- 移行措置の設定:激変緩和のため、一定期間は旧制度と新制度を併用
これらの対応は、労働契約法の「不利益変更」に関する規定も踏まえた適切な対応といえます。退職金は「既得権」の側面が強いため、勤続年数の扱いには特に慎重な対応が求められます。
制度変更を行う際は、対象となる従業員への丁寧な説明と同意取得プロセスを設けることで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
Q.若手の早期離職対策として勤続年数重視の退職金制度は有効でしょうか?
若手社員の早期離職対策として、勤続年数を重視した退職金制度の有効性については、見解が分かれています。
有効と考えられる側面
長期的な視点で見れば、勤続年数に応じて大きく増加する退職金制度は、若手社員に「長く働くことの経済的メリット」を示す効果があります。特に退職金カーブを工夫し、例えば「入社5年目を超えると急激に退職金が増加する」設計にすることで、最も離職リスクの高い3~5年目を乗り越えるインセンティブとなる可能性があります。
また、退職金の「見える化」も重要です。若手社員に対して定期的に「現時点での退職金試算額」と「あと○年勤務した場合の試算額」を提示することで、長期勤続のメリットを実感してもらうことができます。
効果が限定的と考えられる側面
一方で、現代の若手社員は「今」の処遇や成長機会、ワークライフバランスをより重視する傾向があり、数十年先の退職金よりも現在の給与や働き方に関心が高いという調査結果もあります。そのため、退職金制度だけでは早期離職対策として十分とは言えない場合が多いでしょう。
また、勤続年数重視の退職金制度は「長く働けば働くほど有利」というメッセージを発するため、短期間でも高い成果を上げたい若手社員にとってはモチベーション低下につながる可能性もあります。
まとめ:退職金制度と勤続年数を活かすポイント
退職金制度は、従業員の将来不安を軽減し、長期的な定着を促進する重要な役割を担っています。勤続年数を基本としつつも、現代の多様な働き方や価値観に対応した柔軟な制度設計を心がけることで、企業と従業員の双方にメリットのある制度となるでしょう。
人事担当者の皆様は、自社の状況や従業員のニーズを踏まえ、最適な退職金制度の構築に取り組んでいただければ幸いです。
【マネーリペアで退職金制度の最適化を】
退職金制度の設計や見直しでお悩みなら、マネーリペアの専門家にご相談ください。御社の状況に合わせた最適な制度設計をトータルにサポートいたします。
また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
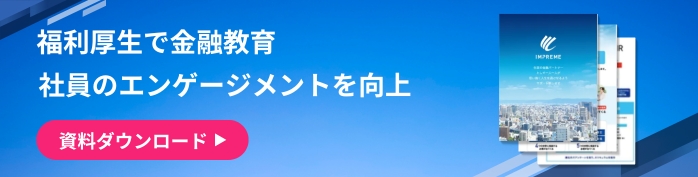

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。