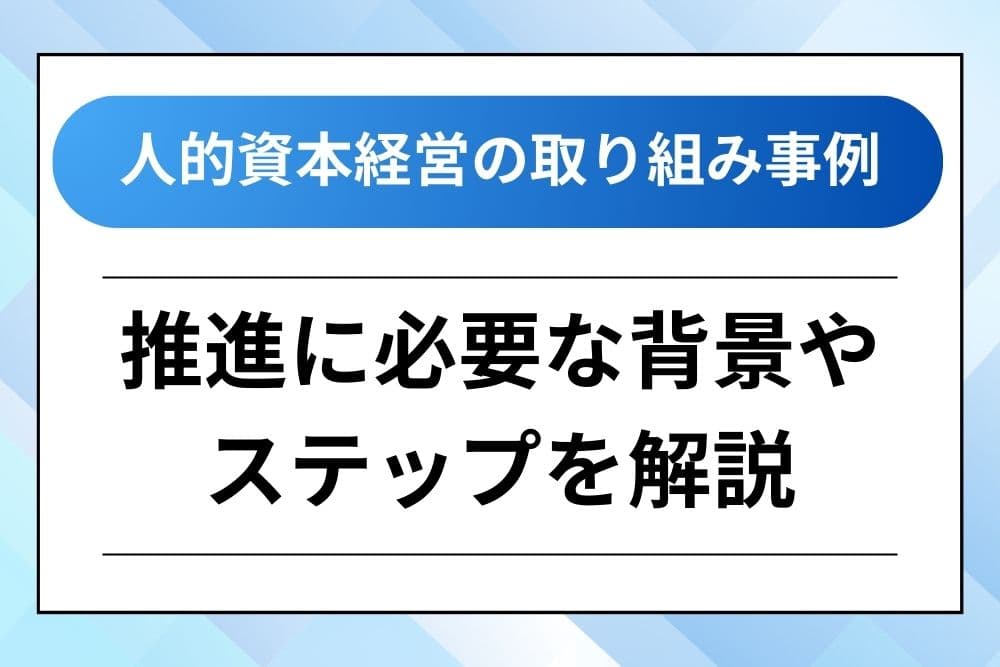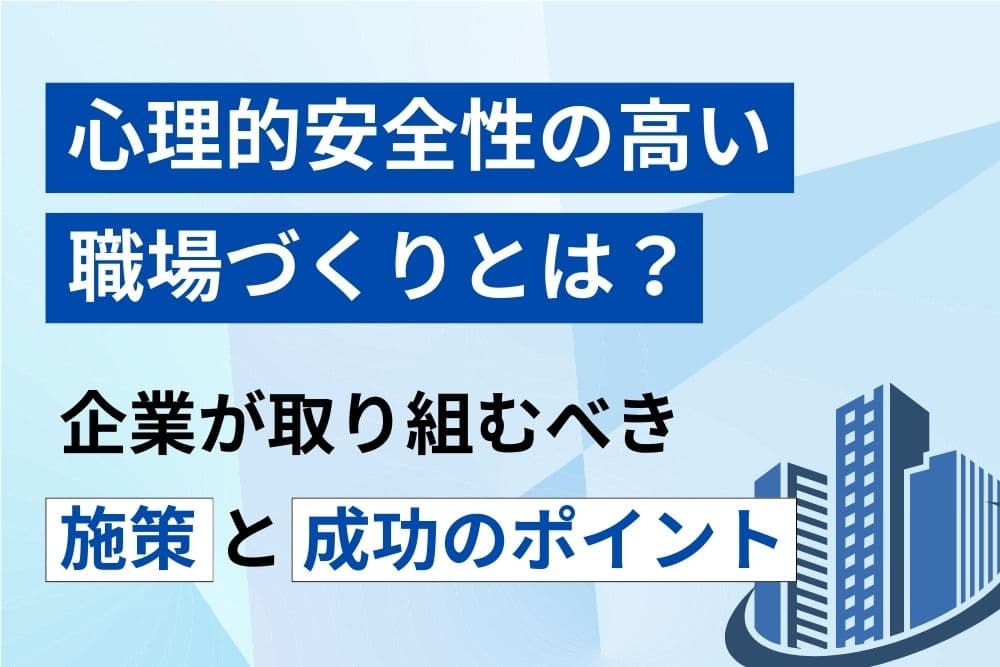お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
昇給のタイミングを見極める:企業と従業員のための実践方法を解説
 詳細を見る
詳細を見る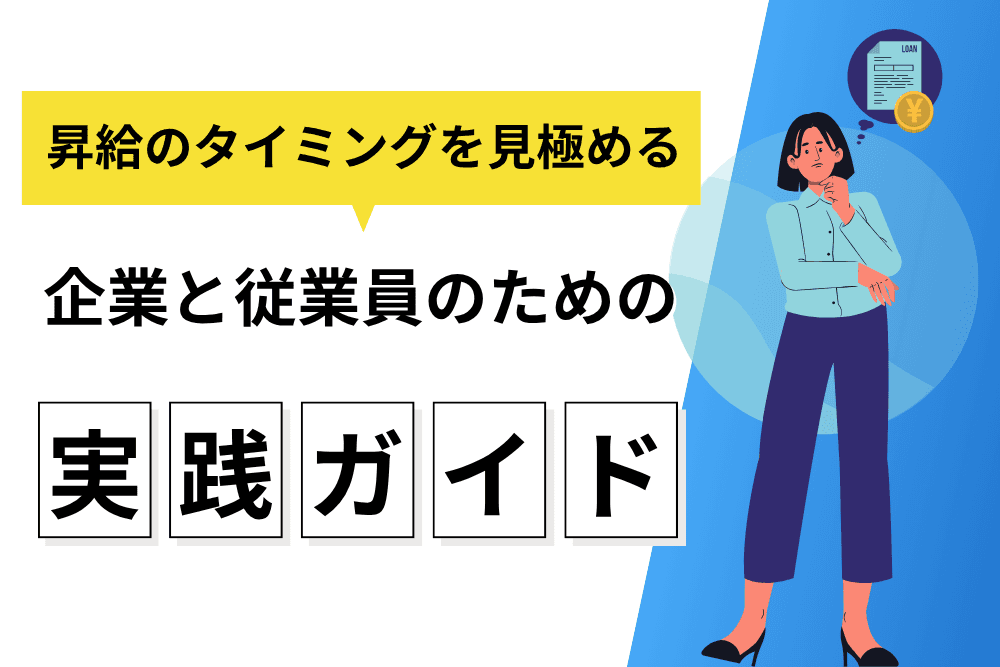
昇給の基本:制度とタイミング
昇給制度の種類と特徴
昇給がどうやって決まるのか
福利厚生サービスを活用した昇給支援
成功事例の紹介
企業で働き続ける上で、誰もが気になる「昇給」。今後のキャリアを現職で築くか、あるいは新たな環境に挑戦するかを考える上で、収入アップの可能性は重要な判断基準の一つとなります。
この記事では、昇給の時期や昇給率、昇給の種類といった基本的な仕組みから、福利厚生サービスを活用した昇給支援まで、昇給に関するあらゆる情報を詳しく掘り下げていきます。
昇給の仕組みを正しく理解し、企業の昇給支援の実践やキャリアプランをより具体的に描くための一助となれば幸いです。
目次
昇給の基本:制度とタイミング

まずは昇給の基本について解説をします。
- 昇給とは
- 一般的な昇給の時期と頻度
そもそも昇給とは何なのかについてから解説するので参考にしてください。
昇給とは
昇給とは、従業員の基本給や諸手当が増額されることを指します。
これは単なる金額の変更ではなく、従業員の成長や貢献度、企業の業績などを総合的に評価した結果として実施される重要な人事施策です。
昇給には大きく分けて以下の要素が含まれます。
- 基本給の増額:月々の固定給与の底上げ
- 諸手当の追加・増額:資格手当、職務手当等の新設や増額
- 賞与査定の向上:ボーナス算定における評価ランクの向上
昇給は従業員のモチベーション向上や人材定着に直結するため、多くの企業が戦略的に取り組んでいる重要な施策といえるでしょう。
一般的な昇給の時期と頻度
最も一般的な昇給時期は4月です。
これは日本企業の多くが4月を年度始めとしており、人事異動や新入社員の配属と合わせて給与体系を見直すタイミングとして最適だからです。
主な昇給時期とその特徴- 4月(年度始め):定期昇給、昇進・昇格に伴う昇給
- 10月(中間期):半期評価に基づく昇給、転勤に伴う調整
- 1月(年始):年間評価の反映、業績連動型昇給
- 随時:資格取得、特別な功績に対する臨時昇給
頻度については、年1回実施する企業が最も多いです。
昇給制度の種類と特徴

主な昇給制度の種類と特徴について解説をします。
- 定期昇給と臨時昇給の違い
- 成果主義と年功序列の比較
昇給の種類について知っておくのも重要なので、ぜひ覚えておきましょう。
定期昇給と臨時昇給の違い
定期昇給は、毎年決まった時期に行われる昇給制度で、日本企業の大多数が採用しています。これには従業員が将来の収入を予測しやすいというメリットがあります。
公平性では、同じ条件の従業員には同等の昇給が適用されるため、不公平感が生まれにくいです。安定性においては、企業の短期的な業績変動に左右されにくいという特徴があります。
一方、臨時昇給は特定の条件や成果に応じて不定期に実施される昇給です。柔軟性があり、市場変化や個人の貢献に迅速に対応できるメリットがあります。
成果主義と年功序列の比較
年功序列型昇給は、勤続年数や年齢を主要な評価基準とする伝統的な日本型の昇給制度です。
メリットとして、長期的な人材育成が可能であり、従業員の生活設計が立てやすく、社内の協調性が保たれやすいという点があります。
一方、デメリットとして、優秀な若手の早期昇進が困難で、人件費の硬直化や国際競争力の低下リスクが挙げられます。
成果主義型昇給は、個人の業績や成果を重視する昇給制度です。
メリットとして、高い成果に対する適切な報酬、従業員のモチベーション向上、優秀人材の獲得・定着が挙げられます。
一方、デメリットとして、短期的成果への偏重リスク、チームワークの阻害可能性、評価の客観性確保の困難さがあります。
昇給がどうやって決まるのか

昇給がどうやって決まるのかについて解説をします。
- 社内評価・実績・人事制度の仕組み
- 業界水準・相場と昇給額の目安
わかりやすく説明をするので参考にしてください。
社内評価・実績・人事制度の仕組み
人事評価制度による査定では、目標達成度として設定された目標に対する達成率が評価されます。
行動評価では企業価値観に沿った行動の実践度が、能力評価では職務遂行に必要なスキルの習得度が、貢献度評価ではチームや組織への貢献度がそれぞれ考慮されるのが一般的です。
職務等級制度では、多くの企業が職務や能力に応じた等級制度を設けており、昇格に伴って自動的に昇給する仕組みを採用しています。
360度評価では、上司だけでなく、部下や同僚、他部署からの評価も含めた多面的な評価手法も普及しています。
査定プロセスの透明性については、近年は評価基準の明文化や、評価理由の説明を重視する企業が増加しているのが特徴です。
これにより従業員の納得感と成長意欲の向上を図っています。
業界水準・相場と昇給額の目安
昇給額は業界や企業規模によって大きく異なります。
以下は一般的な昇給率の目安です。
業界別昇給率については、厚生労働省の2024年データによると、金融業・保険業で4.6%、製造業で4.4%となっており、業界によって昇給率に差があることが確認されています。公務員については近年2-3%程度の昇給率となっています。
引用:人事院
企業規模別昇給額については、厚生労働省の令和6年調査によると、5,000人以上の企業で15,121円、1,000~4,999人で12,317円、300~999人で10,618円、100~299人で10,228円となっており、企業規模が大きいほど昇給額も高くなる傾向があります。
引用:厚生労働省
これらの数値は景気動向や企業業績によって変動するため、自社の状況を定期的に市場相場と比較することが重要です。
福利厚生サービスを活用した昇給支援

福利厚生サービスを活用した昇給支援について2つの事例を紹介します。
- 福利厚生と昇給の関連性
- 金融リテラシー向上が昇給に与える影響
それぞれのポイントについて理解していきましょう。
福利厚生と昇給の関連性
従来、福利厚生と昇給は別々に考えられることが多かったのですが、近年は両者を連動させることで従業員の成長と企業の競争力向上を同時に実現する取り組みが注目されています。
福利厚生を通じた昇給支援の仕組みの代表例がスキルアップ支援制度です。
これには資格取得支援金の提供、外部研修費用の補助、語学学習プログラムの提供が含まれ、これらにより獲得したスキルが昇給査定に反映される仕組みとなっています。
キャリア開発プログラムでは、メンター制度の導入、キャリア相談窓口の設置、社内公募制度の充実により、長期的なキャリアパスと昇給計画の可視化が図られているのです。
健康経営と生産性向上では、健康管理プログラムによる生産性向上、ワークライフバランス支援による継続的な成長環境の整備が行われ、これらが間接的に昇給機会の拡大につながります。
金融リテラシー向上が昇給に与える影響
近年、従業員の金融リテラシー向上が昇給にも良いの影響を与えることが明らかになってきています。
金融リテラシーが昇給に与える具体的な影響として、目標設定能力の向上です。
将来の収入目標を具体的に設定できるようになり、昇給に必要なスキルや実績を逆算して計画でき、短期・中期・長期の収入計画を立てられるようになります。
自己投資の最適化では、収益率の高いスキル投資を選択でき、資格取得の費用対効果を正確に判断でき、転職市場での自身の価値を客観視できるようになるでしょう。
昇給交渉力の向上では、市場価値に基づいた適切な昇給要求ができ、数値的根拠を持った昇給提案が可能になり、企業側との建設的な対話が実現します。
企業側のメリットとして、従業員の自発的な成長意欲の向上、合理的な昇給制度の構築が可能、人材の定着率向上が挙げられます。
【金融リテラシーを向上できる福利厚生の紹介】
金融型福利厚生プログラム《マネーリペア》では、従業員のお金の基礎知識である金融リテラシーを向上させます。
- 固定費の削減
- 経済動向
- ふるさと納税
- 社会保険料の仕組み など
セミナーや個別相談など様々な方法で、従業員の方にもわかりやすくお金の知識を付けられる福利厚生です。
無料相談も行っていますので、資料は以下のリンクより無料で配布しています。

成功事例の紹介
昇給についての成功事例について、2社の取り組みについて紹介をします。
- 昇給の仕組みと評価制度を可視化した企業の事例
- キャリア相談制度と昇給面談を福利厚生で仕組み化した事例
ぜひご自身の企業への導入の参考にしてみてはいかがでしょうか?
昇給の仕組みと評価制度を可視化した企業の事例

A社(IT企業・従業員500名)の取り組みを紹介します。A社は従来の曖昧な評価制度を刷新し、昇給プロセスの完全可視化を実現しました。
導入した仕組みとして、デジタル評価プラットフォームを構築。全従業員がリアルタイムで自身の評価状況を確認可能となり、昇給に必要な条件と現在の達成状況を数値化し、過去の昇給実績と将来予測をグラフで表示できるようになりました。
透明性の高い昇給基準では、職位別の昇給条件を明文化し、評価項目ごとの重み付けを公開し、昇給決定プロセスを段階的に説明するようにしました。
定期的なフィードバック制度では、月次で上司との1on1面談を実施し、四半期ごとに昇給可能性を数値で提示し、年次で詳細な昇給計画を策定するようにしました。
成果として、従業員満足度が前年比30%向上し、離職率が15%から8%に減少し、昇給を理由とした転職が90%減少し、全社の生産性が25%向上したのです。
キャリア相談制度と昇給面談を福利厚生で仕組み化した事例
B社(製造業・従業員1,200名)の取り組みを紹介します。B社は従業員のキャリア開発と昇給を一体的に支援する総合的な福利厚生制度を構築しました。
導入した制度として、専門キャリアコンサルタント制度を設けました。外部の専門家による月2回のキャリア相談、個人のキャリアゴールと昇給計画の策定支援、社内外のキャリア機会に関する情報提供を行っています。
昇給プランニングサービスでは、ファイナンシャルプランナーによる収入設計支援、昇給額と生活設計のマッチング分析、税務上有利な昇給タイミングのアドバイスを提供しています。
スキル投資サポートプログラムでは、昇給に直結するスキル習得の費用支援(年間上限50万円)、社外研修やMBA取得費用の一部負担、取得スキルと昇給実績のデータベース化を行っています。
メンタリング制度では、上位職位の社員による定期的なメンタリング、昇進・昇給の実体験に基づくアドバイス、社内ネットワーク構築の支援を実施しています。
成果として、従業員のスキルアップ実施率が60%向上し、平均昇給率が業界平均を2ポイント上回り、管理職候補者が3倍に増加し、女性管理職比率が5%から18%に向上しました。
福利厚生サービス導入のステップ

福利厚生サービス導入のステップについて紹介をします。
- 導入前の準備
- 導入後のフォローアップ
福利厚生サービスを導入する際の参考にしてください。
導入前の準備
福利厚生を活用した昇給支援制度を導入する際は、綿密な準備が重要です。
現状分析では、既存の昇給制度の問題点抽出、従業員アンケートによるニーズ調査、競合他社の制度ベンチマーク分析、社内リソースの現状把握を行います。
目標設定では、制度導入によって達成したい具体的な目標設定、KPI(重要業績評価指標)の決定、投資対効果の試算、導入スケジュールの策定を行うのが良いでしょう。
ステークホルダーの巻き込みでは、経営陣の理解と承認獲得、人事部門とのプロジェクトチーム結成、労働組合との事前協議、管理職向けの説明会実施などです。
制度設計では、対象者の範囲決定、サービス内容の詳細設計、予算配分の決定、運用ルールの策定を行います。
システム・インフラ整備では、必要なITシステムの選定・導入、外部パートナーの選定、社内窓口の設置、関連文書の整備を行います。
導入後のフォローアップ
制度導入後の継続的な改善が長期的な成功を左右します。
利用状況のモニタリングでは、制度利用率の定期的な測定、利用者の満足度調査、制度の認知度調査、利用しない理由の分析を行いましょう。
効果測定では、昇給実績の変化分析、従業員満足度の推移確認、離職率・定着率の変化追跡、生産性指標の変化測定を実施してください。
継続的改善では、利用者からのフィードバック収集、制度内容の定期的な見直し、新しいサービスの追加検討、他社事例の継続的な研究を行います。
コミュニケーション強化では、制度の活用事例共有、成功体験の社内発信、管理職向けの運用研修、新入社員向けの制度説明を実施するのも良いでしょう。
長期的な戦略見直しでは、事業戦略との整合性確認、人材戦略との連動性強化、市場環境変化への対応、次世代制度の企画立案を行います。
よくある質問(FAQ)

昇給についてよくある質問をQ&A方式でまとめました。
- Q1. 成果が出ているのに昇給がない場合、どう対処すればいいですか?
- Q2. 金融リテラシーの研修は昇給判断に影響しますか?
それぞれのポイントについてしっかり理解しましょう。
Q1. 成果が出ているのに昇給がない場合、どう対処すればいいですか?
成果を出しているにも関わらず昇給がない場合は、以下のステップで対処するのが良いでしょう。
現状の正確な把握では、自身の成果を客観的に数値化・文書化し、同職位・同年代の昇給実績を調査し、会社の昇給制度や評価基準を再確認します。
上司との建設的な対話では、1on1面談を申し込み、昇給について率直に相談し、具体的な成果事例を示しながら昇給の妥当性を説明し、昇給に向けて何が必要かを明確に質問するようにしてください。
改善アクションの実行では、上司からのフィードバックに基づく改善計画を策定し、昇給に直結するスキルや資格の取得を進め、社内外のネットワーク構築により影響力を拡大します。
外部機会の検討では、転職市場での自身の市場価値を調査し、他社での昇給機会を具体的に確認し、必要に応じて転職も選択肢として検討するのが良いでしょう。
重要なポイントは、感情的にならず事実に基づいて建設的に対話することです。
Q2. 金融リテラシーの研修は昇給判断に影響しますか?
金融リテラシー研修は、直接的・間接的に昇給判断に良い影響を与える可能性があります。
直接的な影響は、目標設定能力の向上により、将来の収入目標を明確に設定し、そのための行動計画を立てられるようになることです。
投資判断力の向上により、自己投資の優先順位を適切に判断できるようになります。
間接的な影響として、仕事への取り組み姿勢の変化により、収益性を意識した業務改善提案ができるようになることです。
リーダーシップの向上により、チームの予算管理や投資判断において適切なアドバイスができるようになります。長期的なキャリア戦略により、短期的な給与アップだけでなく、長期的な資産形成を考慮したキャリア選択ができるようになるでしょう。
企業側からの評価ポイントとして、経営的視点を持った従業員として評価され、管理職候補としての適性が認められ、社内の金融・投資関連プロジェクトでの活躍機会が増えます。
ただし、研修受講だけでなく、学んだ知識を実際の業務や自己成長に活用することが重要です。
まとめ

今回は「昇給」について解説をしました。企業に勤めている以上、昇給は大きなテーマです。
ぜひ今回の記事を参考にしていただき、昇給についての細かい知識を身に付けていただければ幸いです。
【金融リテラシーを向上できる福利厚生の紹介】
金融型福利厚生プログラム《マネーリペア》では、従業員のお金の基礎知識である金融リテラシーを向上させます。
- 固定費の削減
- 経済動向
- ふるさと納税
- 社会保険料の仕組み など
セミナーや個別相談など様々な方法で、従業員の方にもわかりやすくお金の知識を付けられる福利厚生です。
無料相談も行っていますので、資料は以下のリンクより無料で配布しています。


- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。