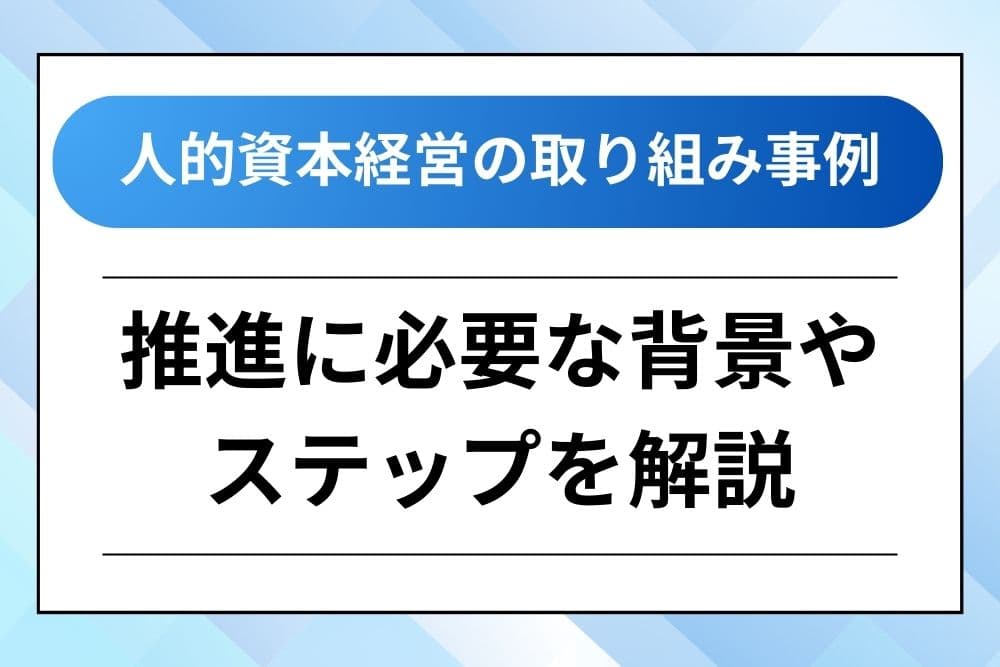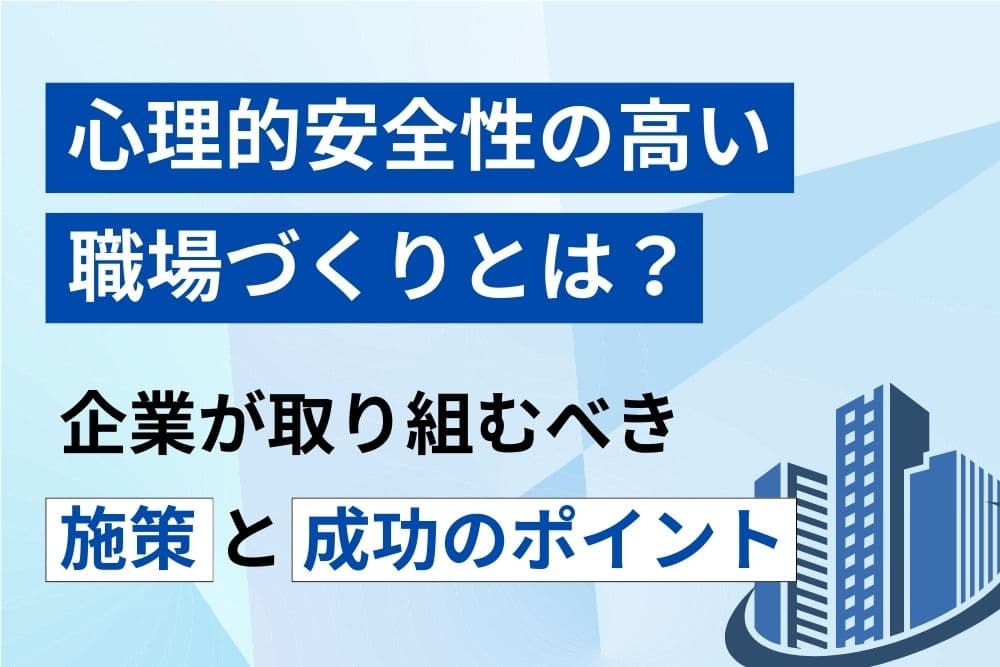お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
中小企業の賃上げは本当に無理なのか?課題と解決策を探る
 詳細を見る
詳細を見る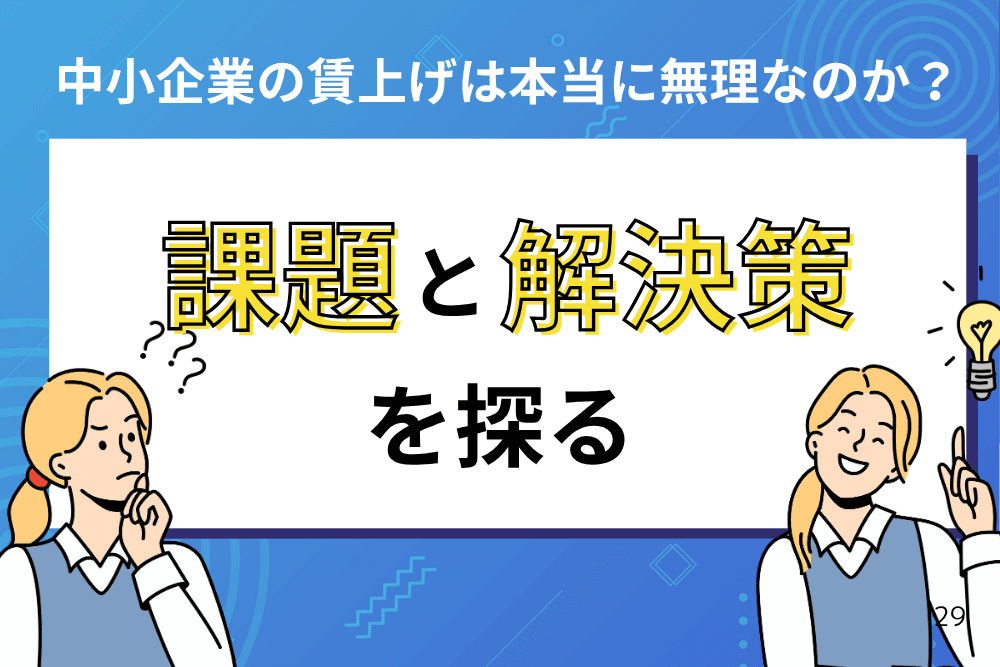
中小企業の賃上げが難しいとされる背景
賃上げに成功した中小企業の事例
賃上げを支援する制度の活用方法
福利厚生サービスを活用した賃上げ支援
よくある質問(FAQ)
この記事では「中小企業の賃上げは本当に無理なのか?」という疑問に対し、その背景にある課題を掘り下げつつ、解決策を探ります。
原材料費や運送費の高騰、価格転嫁の難しさ、そして生産性の低さと人手不足といった構造的な問題は、中小企業の賃上げを阻む大きな要因です。
しかし、これらの課題を乗り越え、賃上げを実現している中小企業も存在します。成功事例や活用できる支援制度、さらには福利厚生サービスの活用方法まで、見ていきましょう。
目次
中小企業の賃上げが難しいとされる背景

中小企業が賃上げに踏み切れない背景には、複数の複雑な要因が絡み合っています。
- 原材料費や運送費の高騰
- 価格転嫁の難しさ
- 生産性の低さと人手不足
中小企業の賃上げが難しい背景を見ていきましょう
原材料費や運送費の高騰
近年、国際情勢の不安定化やサプライチェーンの混乱により、原材料費や運送費が高騰しています。
特に中小企業は、大手企業と比較して仕入れ交渉力が弱く、こうしたコスト増を価格に転嫁しきれないケースが多いです。
この結果、企業の利益が圧迫され、従業員の賃上げに回せる原資が不足するという深刻な状況に陥っています。コスト増を吸収しきれないことが、賃上げを困難にする大きな要因の一つです。
価格転嫁の難しさ
中小企業が直面するもう一つの大きな課題は、価格転嫁の難しさです。
原材料費や運送費が上昇しても、取引先との力関係や激しい市場競争の中で、製品やサービスの価格にその増加分を上乗せすることが極めて難しいのが現状です。
特に下請け企業の場合、元請けからの値下げ圧力が強く、コストに見合った価格設定ができません。
このため、収益改善が進まず、賃上げの余力が出にくい構造的な問題が生じています。
生産性の低さと人手不足
中小企業の賃上げを阻む要因として、生産性の低さと人手不足も挙げられます。
多くの企業では、設備投資やIT化の遅れから一人あたりの生産性が伸び悩んでいます。生産性が向上しない限り、賃上げに見合うだけの売上増加やコスト削減は困難です。
また、少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企業における人手不足を深刻化させています。
優秀な人材を確保し定着させるために賃上げの必要性を感じつつも、その原資の確保に苦慮しているのが実情です。
賃上げに成功した中小企業の事例

賃上げが難しいとされる状況下でも、工夫と努力によって賃上げを実現し、企業成長を遂げている中小企業は数多く存在します。
- 生産性向上による賃上げ実現
- 業務改善助成金の活用
- 福利厚生の充実による人材定着
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
生産性向上による賃上げ実現
代表的な成功要因の一つは、生産性向上による賃上げ実現です。
例えば、製造業のある中小企業では、AIを活用した生産管理システムを導入し、製造ラインの最適化を図りました。これにより、製品の不良率が大幅に低下し、生産リードタイムも短縮。
結果として、生産性が向上し、売上が増加したことで、全従業員の基本給の引き上げを実現しました。業務効率化による残業時間の削減も、従業員の満足度向上に貢献しています。
業務改善助成金の活用
また、業務改善助成金の活用も有効な手段です。
あるサービス業の中小企業は、従業員のスキルアップを目的とした研修プログラムを導入する際に、業務改善助成金を活用しました。研修によって従業員の専門性が高まり、提供するサービスの質が向上した結果、顧客単価の上昇と新規顧客の獲得につながりました。
これにより生まれた収益を原資に、定期的な昇給制度を導入し、従業員のモチベーション維持に成功しています。
福利厚生の充実による人材定着
さらに、福利厚生の充実による人材定着も賃上げ効果を高める重要な要素です。IT企業のある中小企業では、賃上げだけでなく、柔軟な働き方を導入しました。
具体的には、リモートワークの選択肢を増やし、フレックスタイム制を導入。
また、社員食堂の充実やジム利用補助など、従業員の健康と生活の質を高める福利厚生を拡充しました。これにより、従業員のエンゲージメントが高まり、離職率が大幅に低下。
採用コストの削減にもつながり、結果的に賃上げと合わせて優秀な人材の定着を実現しました。
これらの事例から、賃上げは単に給与を上げるだけでなく、生産性向上や適切な制度活用、そして働きやすい環境づくりとセットで考えることが重要だと分かります。
賃上げを支援する制度の活用方法

中小企業の賃上げを後押しするためには、国や自治体が提供するさまざまな支援制度を効果的に活用することが不可欠です。
- 業務改善助成金の申請手順
- キャリアアップ助成金の活用
- 税制優遇措置の利用
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
業務改善助成金の申請手順
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資や人材育成などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げた中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
- 計画の策定: まず、賃金引上げ計画と業務改善計画を策定します。計画には、引き上げたい賃金額、対象となる従業員、導入する設備や研修の内容などを具体的に盛り込みます。
- 申請: 計画策定後、管轄の都道府県労働局に申請書を提出します。申請期間が設けられているため、事前に確認が必要です。
- 審査・交付決定: 申請内容が審査され、要件を満たしていれば交付決定がなされます。
- 実施: 交付決定後、計画に基づき賃金引上げと業務改善を実施します。
- 実績報告・助成金受給: 計画通りに実施が完了したら、実績報告書を提出します。内容が認められれば、助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金の活用
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善、人材育成などに取り組む事業主に対して助成する制度です。
- 正社員化コース: 有期雇用労働者や派遣労働者を正社員として雇用した場合に助成されます。
- 賃金規定等改定コース: 賃金規定等を改定し、賃上げを行った場合に助成されます。
引用:厚生労働省
これらのコースを活用することで、非正規雇用労働者のモチベーション向上と定着を図りながら、賃上げを実現できます。
税制優遇措置の利用
賃上げを促進するための税制優遇措置も活用できます。例えば、賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)は、一定の要件を満たす企業が賃上げを実施した場合、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。
- 適用要件: 適用される事業年度において、雇用者全体の給与等支給額が前年度と比較して一定割合以上増加していることなどが条件となります。
- 控除額: 賃上げ額に応じて、法人税額から一定割合が控除されます。
引用:経済産業省
これらの制度は、企業の賃上げ負担を軽減し、持続的な賃上げを後押しする重要なツールです。
各制度には細かな要件や申請期間があるため、事前に最新の情報を確認し、専門家への相談も検討することをお勧めします。
福利厚生サービスを活用した賃上げ支援

直接的な賃上げが難しい場合でも、福利厚生サービスの充実は実質的な従業員の満足度向上と人材定着に大きく寄与し、結果的に賃上げ効果と同様のメリットを生み出すことができます。
- 福利厚生と賃上げの関係性
- 金融リテラシー支援の効果
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
福利厚生と賃上げの関係性
福利厚生は、給与以外の形で従業員の生活や働き方をサポートするものです。
住宅手当、通勤手当、健康診断補助、育児・介護支援、社員食堂、レクリエーション費用補助など、その内容は多岐にわたります。
これらのサービスを充実させることで、従業員は生活費の負担が軽減されたり、心身の健康が保たれたりするなど、金銭的なメリットだけでなく、精神的な安心感を得ることができます。
例えば、家賃補助があれば実質的な可処分所得が増えたのと同じ効果が得られるでしょう。
これにより従業員のエンゲージメントが高まり、企業への帰属意識が醸成され、結果として離職率の低下や生産性の向上につながり、将来的な賃上げの原資確保にも貢献します。
金融リテラシー支援の効果
特に注目したい福利厚生サービスの一つが、金融リテラシー支援です。従業員の金融リテラシーを高めることは、賃上げの恩恵を最大限に引き出す上で非常に効果的です。
具体的には、ライフプランニングセミナーの開催、NISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用方法、投資信託や株式投資の基礎知識など、従業員が自身の資産を効果的に増やすための情報提供、さらには専門家による個別相談会の実施などが挙げられます。
このような支援を通じて、従業員は将来への経済的な不安を軽減し、安心して仕事に取り組むことができます。
企業側から見ても、従業員の経済的な安定は、仕事への集中力を高め、結果的に生産性向上にもつながるのがメリットです。
【金融リテラシーを向上できる福利厚生の紹介】
金融型福利厚生プログラム《マネーリペア》では、従業員のお金の基礎知識である金融リテラシーを向上させます。
- 固定費の削減
- 経済動向
- ふるさと納税
- 社会保険料の仕組み など
セミナーや個別相談など様々な方法で、従業員の方にもわかりやすくお金の知識を付けられる福利厚生です。
無料相談も行っていますので、資料は以下のリンクより無料で配布しています。

よくある質問(FAQ)

中小企業の賃上げについてよくある質問をQ&Aでまとめました。
- Q1. 賃上げの原資はどのように確保すればよいですか?
- Q2. 福利厚生サービスは賃上げにどのように役立ちますか?
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
Q1. 賃上げの原資はどのように確保すればよいですか?
賃上げの原資確保には複数のアプローチが考えられます。
まず、生産性の向上が重要です。
業務プロセスの見直し、ITツール導入による効率化、従業員のスキルアップなどで一人あたりの付加価値を高めましょう。次に、コスト削減も有効ですが、品質や従業員のモチベーションを損なわないよう慎重に進める必要があります。仕入れ先の見直しや固定費の削減などを検討してください。
また、価格転嫁も重要ですが、取引先との交渉力や市場の状況を考慮し、丁寧に説明責任を果たすことが大切です。
加えて、国や自治体の補助金・助成金(例:業務改善助成金)を積極的に活用することで、賃上げにかかる初期費用や一部コストを補填できます。
Q2. 福利厚生サービスは賃上げにどのように役立ちますか?
福利厚生サービスは、直接的な賃上げとは異なる形で従業員の満足度と定着率を高め、結果的に企業全体の利益に貢献することで、間接的に賃上げに役立ちます。
住宅手当や食事補助などは、従業員の実質的な可処分所得を増加させ、生活費の負担を軽減します。これにより、給与額が同じでも従業員はより豊かさを感じられるでしょう。
また、健康支援や自己啓発支援は、従業員のエンゲージメントとモチベーションを向上させ、企業への帰属意識を高めます。結果として、人材の定着率が向上し、採用コストの削減につながり、これが巡り巡って賃上げの原資確保に寄与します。
賃上げの今後と展望

賃上げの今後と展望について以下2点の観点から解説します。
- 持続可能な賃上げの実現
- 中小企業の成長と賃上げの関係
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
賃上げの今後と展望
持続可能な賃上げには、短期的な視点だけでなく中長期的な戦略が必要です。
単に給与を上げるだけでなく、生産性向上、イノベーションによる高付加価値化、そして適切な価格転嫁の交渉力強化が不可欠です。
従業員のスキルアップやキャリア形成支援を通じて、一人ひとりの市場価値を高めることも重要でしょう。
従業員の成長が企業の成長を促し、それが再び賃上げに還元されるという好循環を生み出すことが理想です。政府や自治体の支援制度を最大限に活用しつつ、各社独自の賃上げ戦略を策定し、実行していくことが求められます。
中小企業の成長と賃上げの関係
中小企業にとって賃上げは、優秀な人材の確保と定着、そして従業員のモチベーション向上に直結しやすいです。
人手不足が深刻化する中で、賃上げは他社との差別化を図る上で強力な武器となります。
従業員が安心して働き、自身の成長を実感できる環境が整えば、企業へのエンゲージメントが高まり、結果として生産性向上にもつながります。
これは企業の競争力強化に直結し、持続的な成長を可能にするでしょう。賃上げは、単なるコストではなく、従業員への投資であり、企業の未来を築くための重要な投資と捉えるべきです。
まとめ

中小企業の賃上げは、決して「無理」ではありません。
原材料費高騰や人手不足といった課題に対し、生産性向上、補助金・助成金の活用、福利厚生の充実といった多角的なアプローチで実現可能です。
賃上げは、従業員の生活向上だけでなく、企業の成長と競争力強化にもつながる重要な経営戦略です。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。