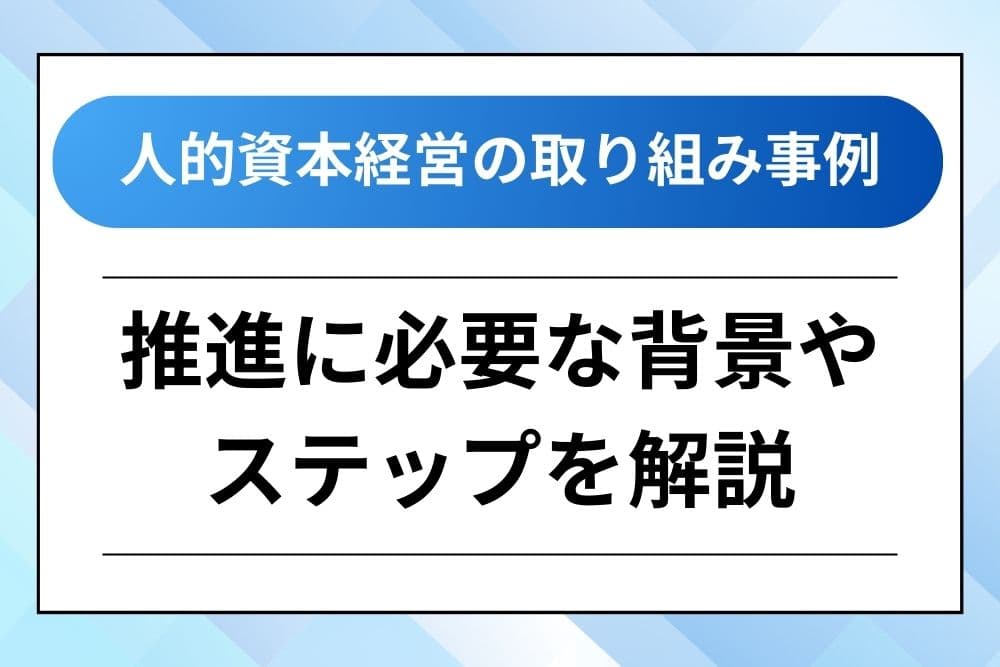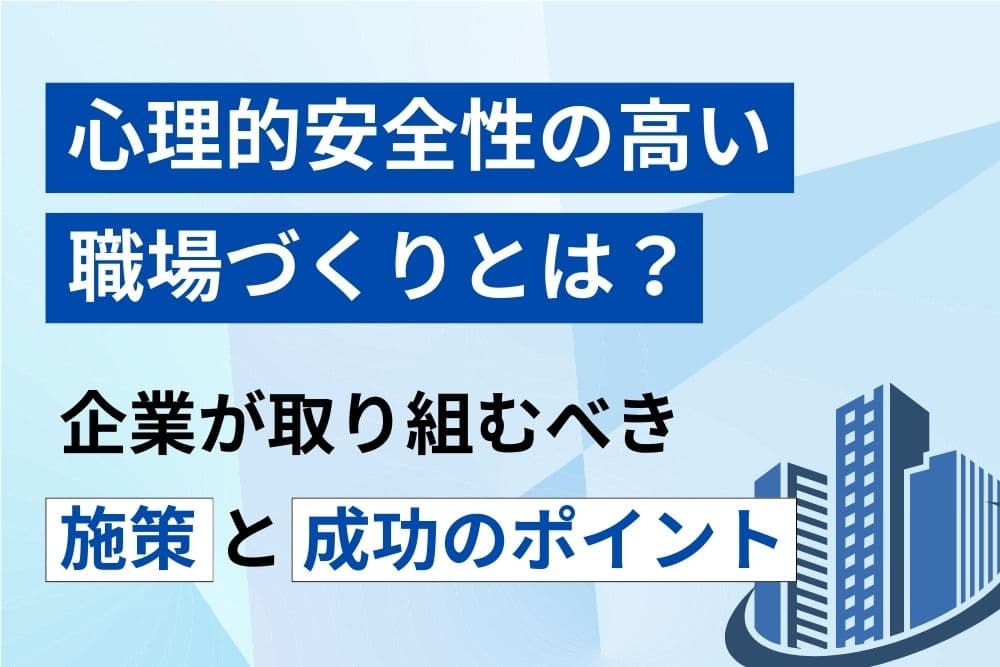お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
福利厚生で資産形成!企業が導入すべき福利厚生
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
福利厚生として資産形成する投資とは?
福利厚生としての投資の種類
企業が投資教育を福利厚生として提供する意義
福利厚生としての投資と税制優遇
海外企業の投資型福利厚生の事例
「福利厚生で資産形成?」と思われる方は多いのではないでしょうか?最近、資産運用ブームが起きておりNISAやiDeCoなどを利用している人も多くなりました。しかし、個人での資産運用はなかなか難しいと考えている方も少なくありません。
実は、会社の福利厚生の一環として資産形成ができます。
この記事では、企業が導入すべき投資型福利厚生の仕組みと成功事例についてご紹介します。
わかりやすく解説をしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
福利厚生として資産形成する投資とは?

福利厚生として資産形成する投資とは一体どんなものでしょうか。
2つのポイントから解説をします。
企業が投資関連の福利厚生を導入する目的
企業が投資関連の福利厚生を導入する主な目的は、従業員の経済的安定を支援しながら、組織全体の価値向上を図ることです。具体的には、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。
資産形成支援は、企業が従業員の将来を真剣に考えているというメッセージとなり、信頼関係の構築につながりやすいです。また、長期的な資産形成支援は、従業員の定着率向上にも効果があります。
企業のブランド価値向上の観点では、充実した投資関連の福利厚生は、人材採用市場での競争優位性を高めるでしょう。特に若手人材の採用において、将来の経済的安定を支援する制度の有無は、企業選択の重要な判断基準となっています。
さらに、従業員の資産形成を支援する企業として認知されることで、社会的責任を果たす企業というポジティブなイメージの醸成にもつながり、企業価値の向上に寄与してくれます。
従業員にとってのメリットとは?
投資関連の福利厚生は、従業員に多くのメリットをもたらします。
最も大きなメリットは、給与天引きによる自動的な積立で確実な資産形成の機会が得られることです。
また、会社からの奨励金や補助金により、個人で投資を始めるよりも有利な条件で資産を形成できます。
特に確定拠出年金やNISAでは、非課税での運用が可能で、長期的な複利効果も期待できるでしょう。コスト面でも、手数料の企業負担や優遇措置があり、投資コストを抑えられます。
また、給与からの自動引き落としにより、支出を意識することなく定期的な積立を継続できる点も魅力です。
さらに、企業が提供する投資教育プログラムを通じて、金融リテラシーを向上させることができます。
投資の基礎知識から実践的なノウハウまで、体系的に学ぶ機会が得られ、専門家のアドバイスを受けられるのもメリットです。
長期的には、退職後の資金計画を早期から準備できることで、将来の経済的安定性を確保できます。インフレリスクにも対応しながら、計画的な資産形成を実現することで、将来への経済的な不安を軽減できるのです。
福利厚生としての投資の種類

福利厚生としての投資の種類を紹介します。主に4つあります。
- 従業員持株会
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- NISA・iDeCo
- ファイナンシャルプランナーを活用した投資アドバイス
以上について詳しく解説いたします。
従業員持株会とは?企業と従業員の双方にとってのメリット
従業員持株会は、従業員が自社の株式を購入する制度です。
毎月の給与から一定額を天引きし、その資金で自社株式を定期的に購入する仕組みで、多くの場合、企業からの奨励金が上乗せされます。
従業員にとっては、給与天引きによる計画的な資産形成が可能で、株価上昇による値上がり益と配当金による収益が期待できます。
また、奨励金により実質的な購入価格が市場価格より安くなるのもメリットです。さらに、拠出金は所得控除の対象となり、税制面でもメリットがあります。
企業側では、従業員の株主化により経営参画意識が高まり、業績向上へのモチベーション向上が期待できるでしょう。
また、安定株主の確保にもつながります。税制面では、奨励金支出が損金算入できる他、証券会社への委託手数料も経費として計上が可能です。
拠出金と奨励金の組み合わせにより、従業員は市場価格より有利な条件で自社株式を取得でき、長期保有による資産形成が可能となります。
ただし、株価変動リスクがあるため、投資先の分散を考える必要はあります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の仕組みと導入メリット
企業型DCの基本的な仕組みは、企業が毎月、従業員の個人専用口座に掛け金を拠出し、従業員自身がその資金の運用方法を選択する制度です。
運用商品は主に投資信託や預金などから選択でき、運用結果が将来の年金受給額に直接反映されます。
企業側のメリットとしては、掛け金の全額損金算入が可能で、税務上の優遇措置が受けられることです。
また、確定拠出年金のように、将来従業員が受け取れる年金額が決まっていないため、企業年金の財政リスクを軽減できます。さらに、福利厚生の充実により人材確保や従業員の定着率向上にも効果があります。
従業員にとっては、掛け金が非課税で運用でき、運用益にも課税されないため、効率的な資産形成が可能です。
60歳以降の受給時まで課税が繰り延べられ、退職所得控除も適用されます。
また、転職時に持ち運べる利便性があり、自身のライフプランに合わせた運用ができる点も魅力です。
ただし、運用の自己責任や投資教育の必要性、従業員の投資経験や知識の差への対応など、導入時には十分な準備と継続的なサポート体制の構築が重要となります。
NISA・iDeCoを活用した投資支援の仕組み
NISAは非課税投資制度で、2024年から新制度となり、年間120万円までの積立投資枠と年間240万円までの成長投資枠で、長期投資を促進する仕組みになりました。
・NISA制度の概要
成長投資枠
つみたて投資枠
1年間に投資できる金額
240万円
120万円
投資できる総額
(一生涯の総額)
1,800万円
(そのうち成長投資枠は1,200万円まで)
投資できる期間
無期限
無期限
投資できる商品
上場株式や投資信託など
金融庁が定めた基準を満たす一定の投資信託
投資方法
積立も単発(スポット)も可能
積立のみ
対象年齢
18歳以上
特徴は、投資による収益(配当金・譲渡益)が非課税となり、無期限の非課税期間が設けられていることです。
企業の投資支援としては、NISA口座開設のサポートや投資教育の提供、積立投資の給与天引きプランなどが一般的です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛け金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となる制度です。企業型DCに加入していない従業員向けに、iDeCo加入を支援する企業も増えています。
毎月の掛け金を給与天引きで納付できるよう制度を整備し、投資教育や商品選択のアドバイスを提供する企業もあります。
これらの制度を組み合わせることで、従業員は税制優遇を最大限活用しながら、長期的な資産形成を効率的に行うことが可能です。
企業側も、従業員の資産形成をサポートすることで、福利厚生の充実を図れます。ただし、各制度の特徴や制限を理解し、従業員の状況に応じた適切な支援を検討することが重要です。
社内ファイナンシャルプランナーを活用した従業員向け投資アドバイス
社内FPの主な役割は、従業員一人ひとりの生活設計や資産形成に関する相談に応じ、具体的なアドバイスを提供することです。
企業の福利厚生制度や投資商品の説明から、ライフプランに基づいた資産形成プランの策定まで、総合的なサポートを行います。
特に重要な機能として、確定拠出年金やNISA、従業員持株会などの制度を最適に組み合わせた運用プランの提案です。
従業員の年齢、収入、家族構成、将来の目標などを考慮しながら、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供できます。
このサービスのメリットは、
- 従業員が気軽に相談できる環境の整備
- 継続的なフォローアップが可能
以上の点です。
また、外部FPと異なり、企業の制度を熟知している社内FPならではの、より実践的なアドバイスが可能となります。
企業側から見ると、定期的なセミナーの開催や個別相談会の実施により、従業員の金融リテラシー向上にも貢献します。これにより、従業員の資産形成に対する意識が高まり、福利厚生制度の活用度の向上が期待できるでしょう。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。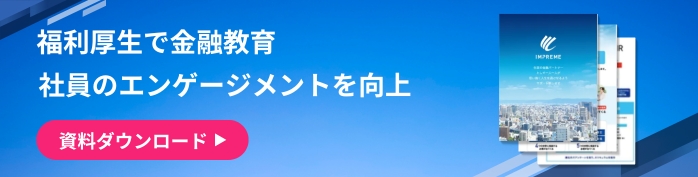
企業が投資教育を福利厚生として提供する意義

企業が投資教育を福利厚生として提供する主な意義は2つあります。
- エンゲージメント向上
- 退職金・年金の適切な管理を支援
以上について詳しく解説いたします。
従業員の金融リテラシー向上が企業経営に与える影響 エンゲージメント向上
企業が投資教育を福利厚生として提供することは、従業員の金融リテラシー向上を通じて、組織全体に大きな価値をもたらします。
従業員が資産形成の知識を身につけることで、自身の将来設計に前向きになり、長期的なキャリア形成への意識の高まりが期待できるでしょう。
これは仕事へのモチベーション向上につながり、結果として企業へのエンゲージメントが強化されます。
また、財務的な知識を持つ従業員が増えることで、企業の経営状況や財務指標への理解も深まり、経営目標達成に向けた個々の貢献意識の高まりも期待でき、業績アップにつながる可能性があるでしょう。
このように、投資教育の提供は、単なる福利厚生にとどまらず、企業価値向上の重要な施策となります。
退職金・年金の適切な管理を支援する取り組み
退職前の早い段階から、退職後の資金計画をサポートする退職準備セミナーの開催が重要です。
このセミナーでは、退職金の受け取り方法や税制、年金制度の説明に加え、退職後の生活設計や資産運用の基礎知識を提供します。
具体的な支援策として、退職金の運用方法に関する個別相談の実施が一般的です。
- 一時金として受け取るか
- 年金として受け取るかの選択
- 退職金の効果的な投資方法について
などを社内FPや年金専門家による専門的なアドバイスを提供します。
また、企業型DCから個人型DCへの移行支援も重要です。退職後も継続的な資産形成ができるよう、手続きの説明や運用方法の見直しについてサポートします。
さらに、退職後も利用できる相談窓口を設置する企業も増えています。
生涯にわたる資産管理をサポートすることで、従業員の退職後の生活の安定性を確保し、現役世代の将来不安の軽減にもつながるでしょう。
福利厚生としての投資と税制優遇

福利厚生としての投資と税制優遇についての主なポイントは2つです。
企業が活用できる税制優遇制度の種類
企業型確定拠出年金では、企業が拠出する掛け金が全額損金算入でき、給与としての支給と比べて社会保険料負担を抑制が期待できるでしょう。
また、従業員持株会への奨励金も損金算入が認められ、効率的な報酬制度として機能します。
財形制度を活用した場合、事務手数料が非課税となり、従業員の資産形成支援と同時に企業の負担を軽減することが可能です。
これらの制度を組み合わせることで、従業員への還元と社会保険料の最適化を両立させることが可能になります。
従業員側にとっての税制メリット
企業型確定拠出年金(DC)では、企業が拠出する掛け金が給与所得として扱われないため、所得税や住民税、社会保険料の課税対象から除外されます。
また、運用段階での収益に対しても非課税となり、受給時まで課税が繰り延べられるのもメリットです。
60歳以降の受給時には、退職所得控除や公的年金等控除が適用され、税負担を抑えることができます。従業員持株会では、毎月の積立金が財形貯蓄控除の対象となり、給与所得から控除されます。
また、企業からの奨励金も一定額まで非課税です。
株式売却時の譲渡益については、特定口座を利用することで確定申告が不要となり、税務手続きも簡単です。
財形貯蓄制度では、住宅財形や年金財形の利子が非課税となり、長期的な資産形成に税制上のメリットがあります。
これらの制度を組み合わせることで、給与や賞与とは異なる形で、税制優遇を受けながら効率的な資産形成が可能です。
海外企業の投資型福利厚生の事例

海外企業の投資型福利厚生の事例について3つほど紹介をします。
アメリカの401(k)と比較した企業型DCの特徴
制度の基本構造では、両者とも従業員の老後資産形成を目的とした確定拠出型の企業年金制度ですが、運用方法や拠出限度額に違いがあります。
401(k)では従業員自身による拠出(給与天引き)が中心で、企業がマッチング拠出を行うのが一般的です。
一方、日本の企業型DCは主に企業拠出が中心となっています。
拠出限度額については、401(k)の方が大幅に高く設定されており、より柔軟な資産形成が可能です。
また、401(k)では50歳以上の従業員に対してキャッチアップ拠出(追加拠出)が認められていますが、日本の企業型DCにはそのような制度はありません。
運用商品の選択肢も、401(k)の方が幅広く、自社株式投資も一般的です。一方、日本の企業型DCは運用商品が限定的で、自社株式投資は原則として認められていません。
ただし、中途引き出しに関しては、日本の企業型DCの方が制限が厳しく、老後資金としての性格が強くなっています。
401(k)では、一定の条件下でローンや中途引き出しが可能だからです。
このように、両制度は基本的な枠組みは似ていますが、実際の運用や柔軟性において違いがあります。
参照元:アメリカ401(k)の仕組みは? | Union Tax Solutions
参照元:拠出金(掛金)について|確定拠出年金(企業型DC)|ろうきんの勤労者の資産形成に係る役割発揮宣言
欧米企業における投資支援策の具体例
多くの欧米企業では、従業員の資産形成を支援する包括的なプログラムを提供しています。
例えば、従業員の生涯設計に応じた投資アドバイスサービスを無料で提供し、専門家との定期的な面談機会を設けているなどです。
また、投資教育においては、オンラインプラットフォームを活用した自習型の学習システムを導入し、従業員が自身のペースで金融知識を習得できる環境を整備しています。
出典:米国で広がる民間金融教育サービスの概要とわが国への示唆
これらのプログラムでは、
- 基礎的な投資知識
- リスク管理
- 税制対策
まで、段階的に学べる仕組みを提供してくれているのが一般的です。
さらに、従業員の投資をサポートするため、給与の一部を自動的に投資に回す401Kや、投資目標に応じたポートフォリオの自動リバランス機能なども提供しています。
参照元:【DCコラム Vol.41】米国DCで「自分で運用派」は少数に、2025年拠出限度額も公表
このように、効率的な投資支援が特徴です。
これらの支援策は、従業員の金融リテラシー向上と資産形成の両面で効果を上げています。
日本企業が学ぶべき海外の福利厚生投資のポイント
日本企業が海外の福利厚生投資から学ぶべきポイントについて説明します。
第1に、投資教育のアプローチです。海外企業では、従業員の投資知識レベルや年齢に応じて、きめ細かく設計された教育プログラムを提供しています。
デジタルツールを活用した双方向型の学習システムや、実践的なワークショップなど、従業員が主体的に学べる環境づくりを重視しているのが特徴です。
第2に、選択肢の多さです。従業員のライフステージや投資目的に応じて、複数の投資プランから選択できる柔軟な制度設計が特徴になります。
また、投資商品の選択においても、ESG投資など、従業員の価値観に合わせた選択肢を提供しています。
第3に、包括的な資産形成支援の姿勢です。単なる投資商品の提供にとどまらず、ライフプランニング全般のコンサルティングや、退職後の資産管理まで視野に入れた長期的なサポート体制を構築しています。
これにより、従業員は将来への不安を軽減し、より積極的な資産形成に取り組むことができます。これらのポイントを参考に、日本企業も従業員の資産形成支援をより充実させることが重要です。
福利厚生まとめ
今回は投資型福利厚生の仕組みと成功事例について解説をしました。
投資ブームが起きる中、投資型福利厚生の導入は従業員のエンゲージメントを高め、採用にも良い影響を与えます。
従業員自身にも企業からの資金提供や税制面での優遇など様々なメリットがありますので、ぜひ自社の福利厚生の一環として、投資型福利厚生の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
福利厚生で資産形成ならマネーリペア
「自社でこれらを一から用意するのは大変そうだ」と感じた経営者・人事担当の方もいるかもしれません。
マネーリペアは、当社が提供する金融教育に特化した福利厚生サービスで、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。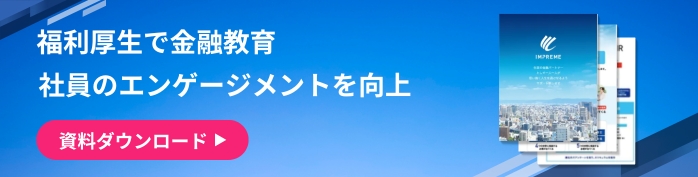

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。

.jpg&w=1080&q=75)