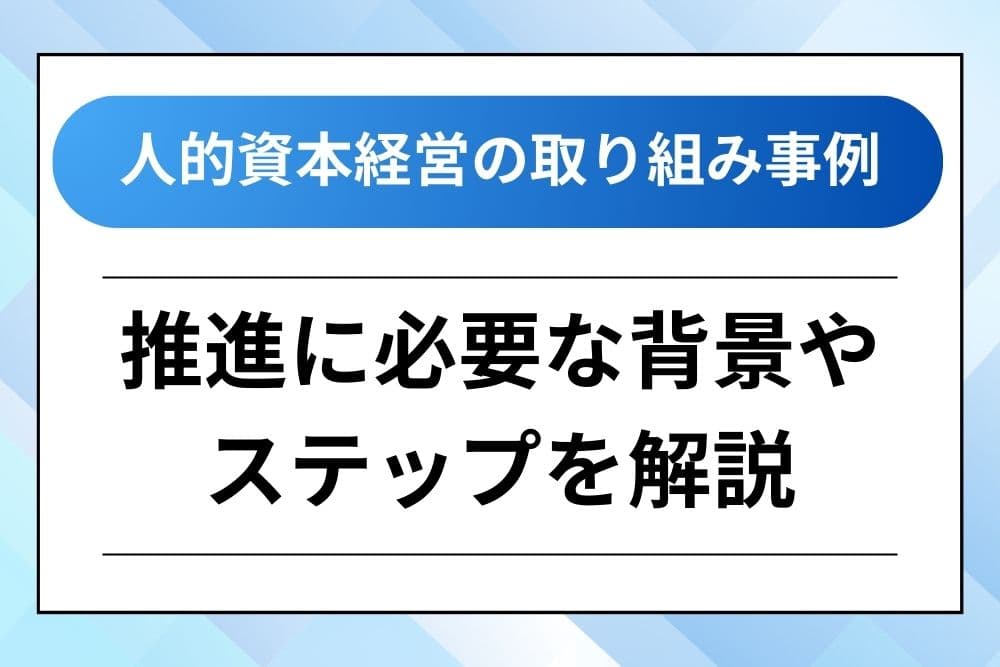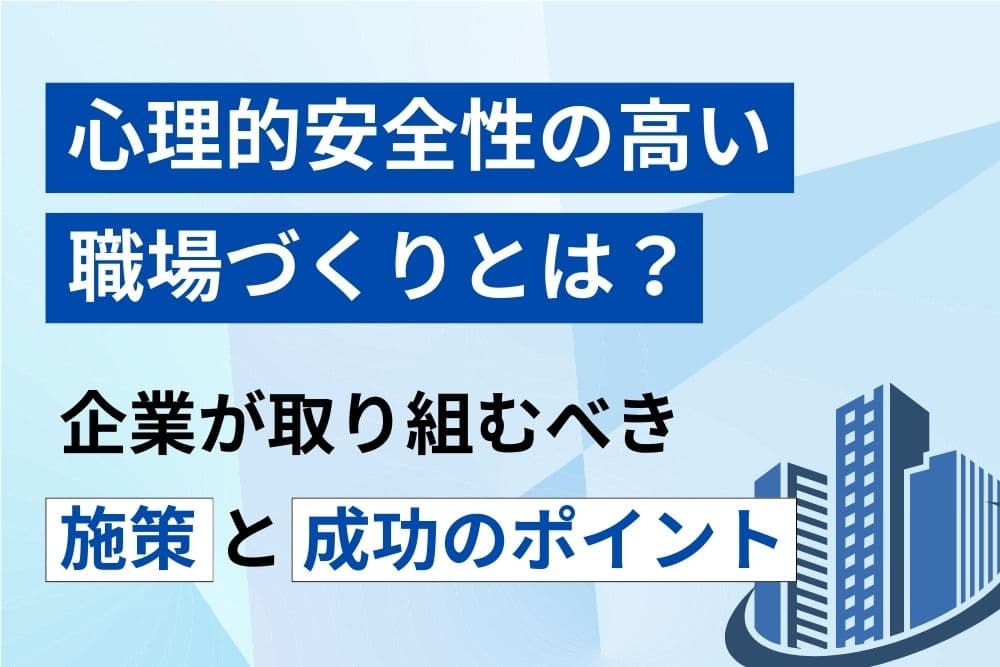お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
職場積立NISAとは?企業導入のメリットと注意点を解説
 詳細を見る
詳細を見る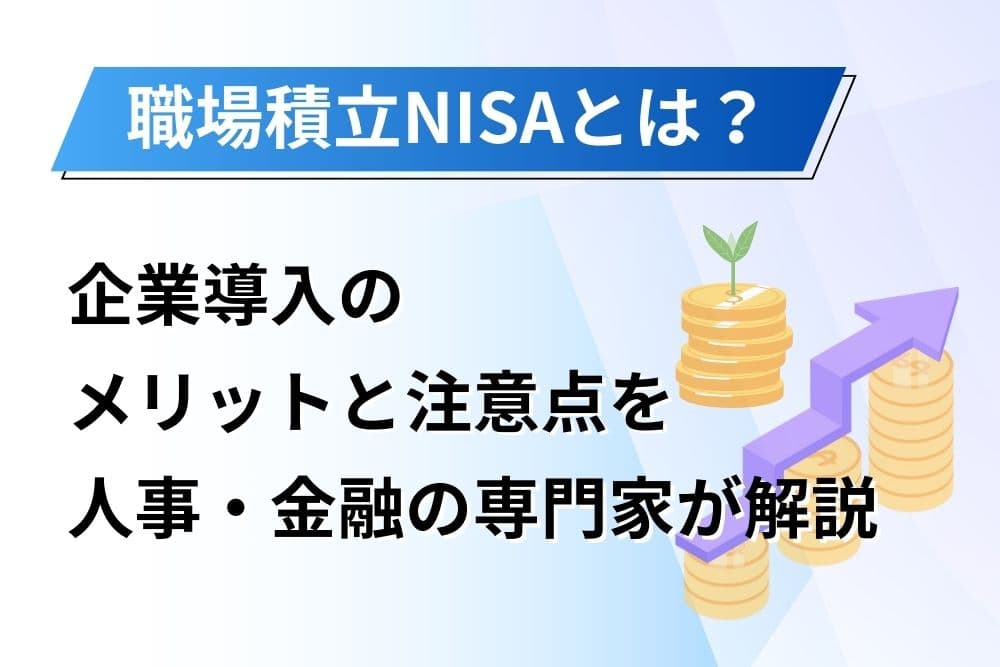
職場積立NISAとは何か
職場積立NISAを導入するメリット
職場積立NISAを導入する流れ
運用商品選びと金融リテラシー向上のポイント
職場積立NISAにおける注意点とよくある課題
今、資産運用がブームになっています。株式や投資信託で資産運用を始めたいと言う方も多いのではないでしょうか。しかしどのように始めて良いかわからない方も多いと思いますし、何から始めて良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、投資のきっかけにもなる職場積立NISAについて解説をします。
企業導入のメリットや注意点についてもわかりやすく解説をしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
職場積立NISAとは何か

まずは職場積立NISAについて3つの観点から解説をします。
- 仕組みと基本的な特徴
- 従来の積立NISAとの違い
- 企業を通じて導入するメリット
職場積立NISAについて理解していきましょう。
仕組みと基本的な特徴
職場積立NISAは、会社を通じて社員が新NISAの「つみたて投資枠」を利用できる制度です。
企業が提携金融機関を選定し、従業員は給与天引きで積立投資を行います。最大のメリットは、通常のNISAと同様に運用益が非課税になる点です。
特徴としては、給与からの自動引き落としにより、忙しい社会人でも継続的な積立が簡単にできること、また企業が従業員向けに投資教育を提供するケースが多いことが挙げられます。
年間120万円までの非課税投資枠が利用でき、非課税期間は無期限です。商品は企業と金融機関があらかじめ選定した投資信託に限定されますが、長期・分散・積立という資産形成の基本を実践しやすい環境が整っています。
福利厚生の一環として導入する企業が増えており、従業員の資産形成を支援する新たな仕組みとして注目されています。
従来の積立NISAとの違い
職場積立NISAと従来の積立NISAの最大の違いは、投資の申し込み方法と資金の拠出経路です。
従来の積立NISAは個人が直接金融機関と契約し、自分の銀行口座から資金を引き落とす形式でしたが、職場積立NISAは給与からの天引きで投資を行います。
選択できる金融機関と商品についても違いがあります。従来の積立NISAでは投資家が自由に金融機関や対象商品を選べましたが、職場積立NISAでは企業が提携する金融機関と、その中から厳選された商品に限定されます。
また、投資教育の面でも差があります。職場積立NISAでは企業が従業員向けのセミナーや教育プログラムを提供するケースが多く、投資初心者でも始めやすい環境が整っています。
一方、非課税枠や運用期間などの基本的な制度内容は同じで、どちらも年間120万円までの投資枠と無期限の非課税期間が適用されます。つまり税制上のメリットに違いはなく、主に投資の手続きと教育面での違いが特徴となっています。
企業を通じて導入するメリット
企業を通じて職場積立NISAを導入する最大のメリットは、給与天引きによる自動積立の仕組みです。これにより「毎月投資するのを忘れる」「面倒で先延ばしにする」といった問題が解消され、継続的な資産形成が実現しやすくなります。
企業が従業員に対して投資教育を提供することも大きなメリットです。多くの企業では導入に合わせて資産形成セミナーや個別相談会を開催し、投資初心者の不安を軽減する取り組みを行っています。同僚と一緒に始められることで、孤独感なく投資を続けられる心理的メリットもあります。
また、企業と金融機関の交渉により、通常より低コストの商品が提供されるケースもあります。特に大企業では、スケールメリットを活かして運用コストの引き下げに成功している例もあるようです。
さらに、福利厚生の一環として企業が導入を推進するため、従業員は「会社公認」の安心感を持って投資に取り組めます。長期的な資産形成の重要性を会社が認めているというメッセージは、投資を始める後押しとなるでしょう。
近年の傾向として、こうした従業員の資産形成支援は企業の魅力として評価される要素にもなっています。
職場積立NISAを導入するメリット
職場積立NISAを導入する主なメリットは3つです。
- 従業員の資産形成サポートと福利厚生効果
- 人材採用・定着率向上への期待
- 企業ブランド力・社会的信用度アップ
それぞれのメリットについて、わかりやすく解説をしますので、ぜひ参考にしてください。
従業員の資産形成サポートと福利厚生効果
職場積立NISAは、企業が従業員の資産形成を支援する有効な手段です。給与天引きで定期的な投資が可能となり、「貯めてから投資」ではなく「先に投資」する習慣が身につきます。
また、職場で金融リテラシー研修などを実施することで、従業員の投資知識向上にも寄与してくれるでしょう。福利厚生としては、会社が投資環境を整えることで従業員の将来不安を軽減し、満足度向上につながります。
特に若手社員にとって「会社が将来を考えてくれている」という安心感は大きく、人材確保・定着の観点でも効果的です。
マネーリペアは、企業の福利厚生制度の構築や従業員向け金融教育を支援するサービスです。退職金制度の導入・見直しを検討する際には、ぜひマネーリペアをご活用ください。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。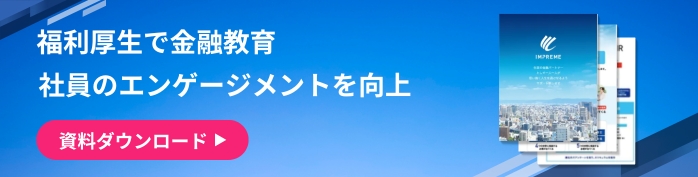
人材採用・定着率向上への期待
職場積立NISAの導入は、人材採用と定着率向上において大きな効果が期待できます。近年、就職活動生の間で将来の資産形成に対する関心が高まっており、積立投資制度を福利厚生として提供する企業は、採用市場での競争優位性を獲得できます。
特に金融リテラシーに関心の高いZ世代には強いアピールポイントとなるでしょう。
また、従業員が長期的な資産形成の道筋を会社でサポートしてもらえることで「この会社で働き続ける価値」を感じやすくなります。定期的な投資が続くことで会社への帰属意識も自然と高まり、キャリアの継続性を重視するようになるため、離職率の低下につながるでしょう。
企業ブランド力・社会的信用度アップ
職場積立NISAの導入は、企業ブランド力と社会的信用度の向上に大きく貢献します。従業員の資産形成を積極的に支援する姿勢は、「従業員を大切にする企業」というイメージを社会に強く印象づけます。
また、金融教育を含めた福利厚生の充実は、就職ランキングや働きがい企業としての認知度向上につながり、業界内での企業ブランドの差別化要因となりやすいです。
求職者だけでなく、取引先や投資家からも「将来を見据えた経営をしている企業」と評価され、事業パートナーとしての信頼性も高まります。
職場積立NISAを導入する流れ
職場積立NISAを導入する流れは以下の通りです。
- 企業側の準備:社内規定整備と運営管理機関の選定
- 運用開始までの流れ
- 導入後のフォローアップ:従業員への情報提供
それぞれのプロセスについて、詳しく解説をしますので、参考にしてください。
企業側の準備:社内規定整備と運営管理機関の選定
職場積立NISAの導入に向けて、企業はまず社内規定の整備から着手する必要があります。積立金額の上限や拠出方法、投資対象商品の範囲などを明確にした規定を策定し、労使間の合意形成を図る必要があります。また、給与天引きの仕組みを給与システムに組み込むための調整も重要です。
並行して運営管理機関の選定を行います。複数の金融機関から提案を受け、手数料体系、提供される投資信託の種類、従業員向け教育支援の充実度などを比較検討します。特に従業員向けの投資教育やサポート体制が充実している機関を選ぶことが、制度の活用率向上につながるでしょう。
選定後は運営管理機関との契約締結、給与システムとの連携テスト、従業員への説明会実施など、スムーズな導入に向けた準備を計画的に進めることが重要です。社内規定と運営体制の両面を整えることで、持続可能な制度運営の基盤を構築できます。
運用開始までの流れ
職場積立NISAの運用開始に向けては、まず導入プロジェクトチームを結成し、人事部・経理部・総務部の担当者を集めて役割分担を明確化します。
次に従業員への告知を行い、制度概要・メリット・申込方法を記載した資料を配布するとともに、説明会を複数回開催して疑問に答える機会を設けます。
続いて従業員からの申込受付を開始し、NISA口座開設と積立設定の手続きをサポートします。
この段階では金融機関の担当者と連携し、従業員一人ひとりの投資ニーズに合わせた商品選択の相談に応じることが重要です。必要書類の提出確認や口座開設状況の管理も丁寧に行います。
全ての準備が整ったら、給与システムとの連携テストを実施し、初回積立のタイミングを決定します。運用開始後も定期的なフォローアップセミナーを実施し、従業員の投資状況や満足度を確認しながら、必要に応じて制度の改善を図ることで、持続的な資産形成支援の仕組みを確立します。
導入後のフォローアップ:従業員への情報提供
職場積立NISA導入後は、継続的な情報提供が従業員の投資意欲維持と制度活用促進に不可欠です。
例えば、四半期ごとに運用状況レポートを配布し、投資信託の実績や市場動向の解説を提供します。専門用語を避けた易しい表現で、長期投資の意義を繰り返し伝えることが重要です。
また、定期的な金融セミナーを開催し、資産形成の基礎知識や市場の見方、ライフプランに合わせた投資戦略などをテーマに取り上げます。ビデオ録画やオンデマンド配信を活用し、全従業員がアクセスできる環境を整えるのも重要なポイントです。
マネーリペアは、企業の福利厚生制度の構築や従業員向け金融教育を支援するサービスです。退職金制度の導入・見直しを検討する際には、ぜひマネーリペアをご活用ください。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。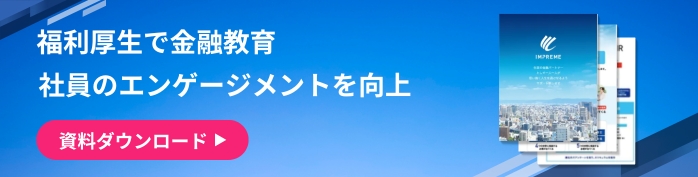
運用商品選びと金融リテラシー向上のポイント
運用商品選びと金融リテラシー向上の主なポイントは3つです。
- 投資信託の選択基準と比較方法
- 従業員の金融教育が必要となる理由
- 会社・従業員が気をつけたいリスクマネジメント
それぞれのポイントについてわかりやすく解説をします。
投資信託の選択基準と比較方法
職場積立NISAにおける投資信託選びでは、まず長期投資に適した商品特性を理解することが重要です。インデックス型(株価指数に連動)とアクティブ型(運用者の判断で銘柄選択)の違い、コスト(信託報酬)の長期的影響、分散投資の考え方など、基本的な選択軸を従業員に解説します。
比較方法としては、過去の運用実績だけでなく、シャープレシオ(リスク対比のリターン)やコスト面での優位性を示す指標を活用し、単純な収益率比較を超えた多角的な評価方法を伝えます。
また、同じカテゴリーの商品を比較表形式で提示し、各商品の特徴や違いを視覚的に理解できるよう工夫します。金融リテラシー向上のポイントとして、「なぜその商品が良いのか」という判断基準を自分で持てるよう促すことが大切です。
従業員の金融教育が必要となる理由
職場積立NISAを効果的に機能させるには、従業員への金融教育が不可欠です。多くの日本人は学校教育で体系的な金融教育を受けておらず、投資の基本概念や長期資産形成の重要性を十分理解していません。
この知識不足が投資への不安や誤解を生み、せっかくの制度が十分に活用されない原因となります。
また、適切な金融教育がないまま投資を始めると、短期的な相場変動に一喜一憂し、市場下落時のパニック売りや、逆に過度なリスクを取ってしまうなどをしてしまいがちです。
会社・従業員が気をつけたいリスクマネジメント
職場積立NISAを導入する際、会社側は複数のリスクを想定した対策が必要です。まず「強制加入と誤解されるリスク」を避けるため、あくまで自由参加の福利厚生であることを繰り返し明示し、不参加による不利益がないことを保証します。
また、おすすめの投資商品が「運用成績の保証」と誤解されないよう、元本保証がないことや市場変動リスクの説明を徹底する必要があるでしょう。従業員側では、「過度な期待による失望リスク」に注意が必要です。
短期的な市場下落局面では冷静さを保ち、長期投資の視点を持つことが重要です。
また、職場積立に頼りすぎて追加的な資産形成を怠る「依存リスク」も避けるべきで、NISA枠の上限や退職後の資金計画も含めた総合的な資産形成戦略を持つことが大切になります。
関連記事:退職金の制度を徹底解説!企業が導入すべき理由とは?
職場積立NISAにおける注意点とよくある課題

職場積立NISAにおける注意点とよくある課題については、以下の通りです。
- 制度上の制限事項と対応策
- 退職・異動時の取り扱いはどうなるのか
- 企業側コストの把握と運用管理体制づくり
それぞれのポイントについて、わかりやすく解説をするので、ぜひ参考にしてください。
制度上の制限事項と対応策
職場積立NISAを運用する上で、いくつかの制度上の制限事項に注意が必要です。NISAの年間投資枠(現行120万円)は職場積立分と個人的な積立分の合計で管理されるため、既に個人でNISA口座を活用している従業員は上限管理に注意が必要です。
また、NISA口座は1人につき、1つの金融機関でしか保有ができないため、こちらも注意点になるでしょう。さらに、投資対象商品が運営管理機関の提供するものに限定される点も留意すべきです。
従業員の多様なニーズに応えられるよう、
- インデックス型・アクティブ型
- 国内・海外
- 株式・債券
など、バランスの取れた商品ラインナップを持つ金融機関を選定することで、この制限に対応することができます。制度の制約を事前に把握し、適切な対応策を講じることで、職場積立NISAの効果を最大化できます。
退職・異動時の取り扱いはどうなるのか
職場積立NISAにおける退職時の取り扱いは、投資資産と口座管理の2つの側面から考える必要があります。退職時には給与天引きによる積立は自動的に終了しますが、すでに積み立てられた資産は当然ですが、従業員のものです。退職者には主に3つの選択肢があります。
第1に、NISA口座をそのまま金融機関で継続し、個人で追加投資を行う方法です。この場合、給与天引きから口座振替などの支払方法に変更する手続きが必要となります。
第2に、NISA口座を別の金融機関に移管する方法があります。これには所定の移管手続きが必要で、一定期間取引できなくなる点に注意が必要です。
第3に、投資を中止して資産を売却する方法もありますが、長期投資の効果を失う点を考慮すべきです。
一方、社内異動の場合は基本的に制度の継続に影響はありませんが、地域をまたぐ転勤では管轄の金融機関支店が変わる可能性があります。この場合も資産は継続保有されますが、担当者変更などの手続きが必要になることがあります。
企業は退職・異動時の取り扱いマニュアルを整備し、従業員が円滑に資産管理を継続できるサポート体制を構築しておくことが重要です。
企業側コストの把握と運用管理体制づくり
職場積立NISAの導入には、企業側でいくつかのコストと管理体制構築が必要です。まず初期コストとして、制度設計のための外部コンサルタント費用や、給与システム改修費が発生します。
また、従業員向け説明会や資料作成のコストも計上すべきです。運用段階では、専任担当者の人件費や継続的な教育セミナー費用が必要となります。
効果的な運用管理体制としては、人事部門を主管とし、経理部門・総務部門・システム部門が参画する横断的な運営チームの構築が望ましいです。特に給与天引き処理の正確性確保と金融機関との連携窓口を明確化し、加入者名簿や積立額の管理、従業員からの問い合わせ対応体制を整備します。
コスト削減と効率的な運営のポイントは、既存の福利厚生システムとの統合や、金融機関が提供する管理ツールの積極活用です。
まとめ
今回の記事では、職場積立NISAについて詳しく解説をしました。従業員の資産形成を助けるためにぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。導入するためのポイントはいくつかありますが、それほど難しくありません。
ぜひ、この記事をきっかけに多くの企業が職場積立NISAに興味を持っていただければ幸いです。
マネーリペアは、企業の福利厚生制度の構築や従業員向け金融教育を支援するサービスです。退職金制度の導入・見直しを検討する際には、ぜひマネーリペアをご活用ください。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
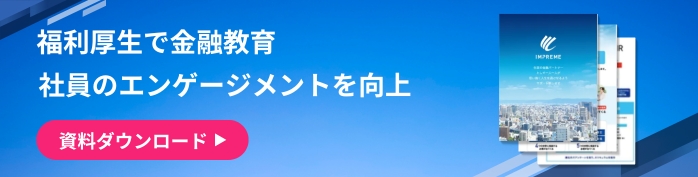

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。