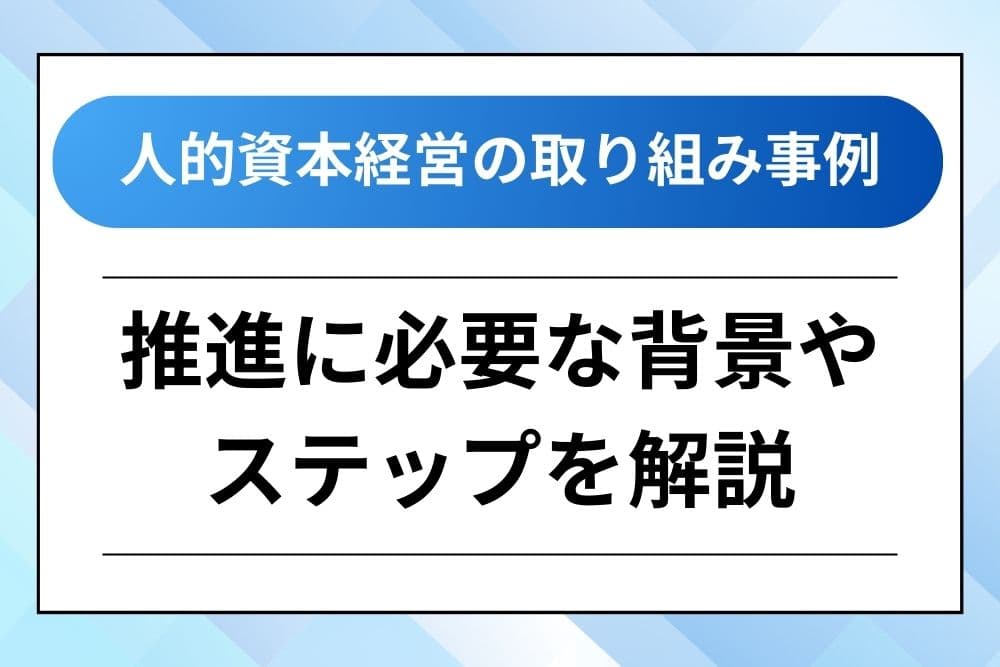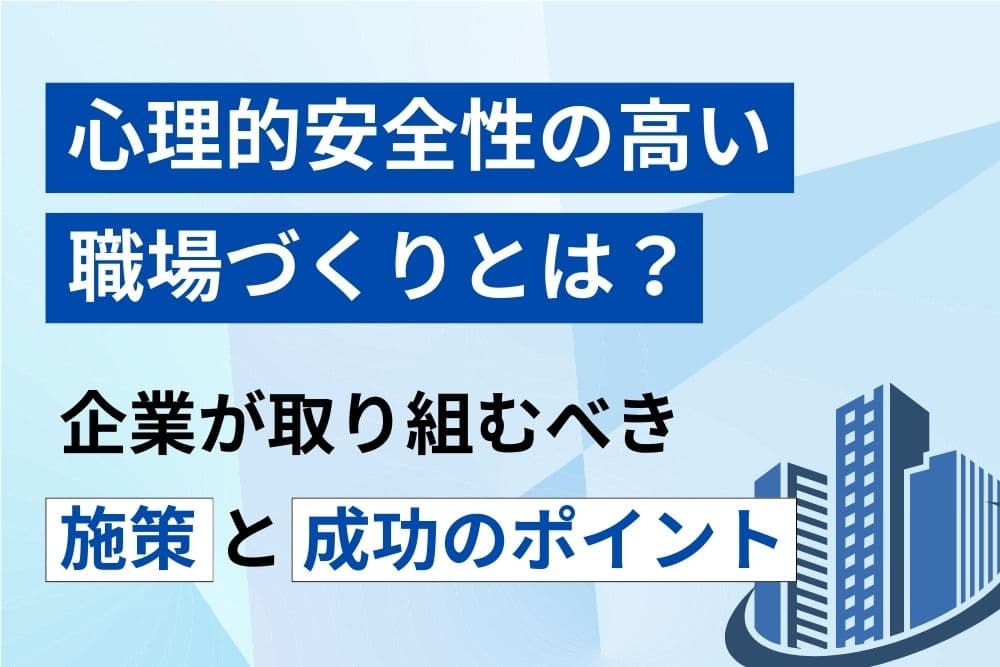お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
退職金制度の外部積立を徹底解説!確定給付型と確定拠出型の違いや選び方
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
退職金制度の積立とは何か
退職金制度を導入するメリットと積立の重要性
退職金の積立方式の種類と特徴
企業が退職金制度を選ぶポイント
退職金積立に関するよくある質問
退職金制度は従業員の将来を支える重要な仕組みであり、制度の有無が企業の魅力や経営の安定性に直結します。そのため退職金積立制度を新しく導入し、福利厚生として採用競争力の強化、既存社員のモチベーション維持をお考えの企業もあるでしょう。
本記事では、退職金制度の積立方法や種類ごとの違い、導入時のポイントをわかりやすく解説します。
目次
退職金制度の積立とは何か

退職金制度の積立とは、企業が従業員の退職金を将来支払うために、事前に資金を計画的に積み立てて準備しておくことです。積立方法には、社内で資金を確保する内部積立と、社外の仕組みを活用する外部積立の2種類があります。
内部積立(社内積立)と外部積立
企業が退職金のための資金を積み立てる方法には、内部積立(社内で積立)と外部積立(社外の制度を活用)の二通りがあります。
内部積立は退職金原資を社内にプールしておく方法で、例えば毎期の利益の一部を引当金として積み立て、従業員の退職時に支給します。自社で自由にルール設計でき、積立金を他用途に流用することも可能ですが、業績悪化で十分積み立てられない場合には支払いが滞るリスクがあります。
一方、外部積立は生命保険会社や退職金共済など社外の団体に掛金を拠出して退職金原資を積み立てる方法です。拠出した資金は基本的に戻せないものの、計画的に資金を確保でき、会社が倒産しても従業員への退職金が一定程度保全されます。
また、多くの社外積立制度では掛金を損金算入できるため、税負担を抑えながら準備できるメリットもあります。
退職金制度を積立する背景と目的
日本企業における退職金制度は、長年の終身雇用慣行の中で発展してきました。退職時にまとまった金額を支給することは従業員への報奨であると同時に、給与の後払い的な性格を持つ制度です。
企業にとって、従業員の退職金を支払うための財源を事前に積み立てて確保することは、将来の財務負担を平準化し安定した支払いを可能にするという目的があります。
また、退職金制度を通じて従業員の老後を支えることは、「会社が従業員を大切にしている」という安心感を与え、従業員の勤労意欲や会社への信頼を高める効果もあります。
関連記事:退職金の制度を徹底解説!企業が導入すべき理由とは?
企業が退職金制度を用意すべき理由
法的義務はありませんが、退職金制度を用意することは企業にとって大きなメリットがあります。優秀な人材の確保と定着に効果があり、福利厚生が充実している企業は求職者や従業員から選ばれやすくなります。
また、従業員の老後を支える姿勢が企業の社会的信用を高め、結果的に企業価値の向上につながります。総合的に見て、退職金制度の導入は人材戦略と企業の安定経営に寄与すると言えるでしょう。
積立の有無で生まれる企業間の差
退職金積立を行っている企業と行っていない企業では、財務の安定性や従業員の安心感に大きな差が生じます。
積立をしていない場合、退職金支給時に多額の資金が必要となり、資金繰りを圧迫するリスクがあります。業績悪化時や倒産時には退職金を支払えなくなる恐れもあり、従業員との信頼関係にも悪影響を及ぼします。
一方、計画的に積立を行っていれば、退職者が集中してもスムーズに支給でき、突発的な財務負担を回避できます。特に社外積立なら会社が万一倒産しても退職金が社外で確保されるため、従業員も安心です。結果として優秀な人材の定着や対外的な信用力向上にもつながります。
退職金積立が注目される社会的・経済的要因
近年、退職金積立の重要性が改めて注目されています。その背景にはいくつかの社会的・経済的要因があります。
まず、少子高齢化と平均寿命の延伸により老後資金への不安が高まっており、公的年金を補完する企業の退職金制度への期待が増しています。
また、雇用の流動化で勤続年数が短期化する傾向に合わせ、ポイント制退職金や確定拠出年金(DC)など途中退職者にも対応しやすい制度が注目されています。
経済的な要因では、退職給付債務の会計処理が厳格化されたことや長引く低金利により、企業は従来以上に計画的な資金積立と効率的な運用を求められるようになりました。政府の制度改革による後押しもあり、企業の退職金準備の重要性は一層高まっています。当社が提供する「マネーリペア」では、退職金制度の見直しや積立計画に関する相談が可能です。自社の制度設計に不安がある場合は、専門家によるアドバイスをぜひご活用ください。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
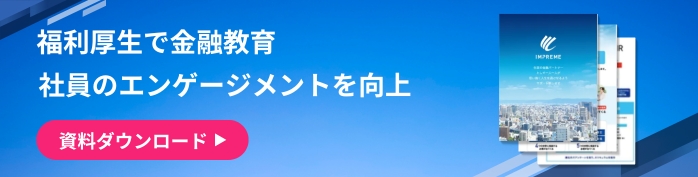
退職金制度を導入するメリットと積立の重要性

退職金制度を導入し、計画的に積立を行うことには、多くのメリットがあります。以下では主なメリットと積立の重要性について解説します。
人材確保・定着率向上への効果
退職金制度があることは、採用と定着の両面で効果を発揮します。求職者は同程度の条件であれば退職金制度のある会社を選ぶ傾向があり、制度を整えている企業は採用面で有利です。
また、在職社員にとって退職金制度は長期勤務の大きな動機づけとなります。
勤続年数に応じて退職金額が増える仕組みであれば、将来のまとまった報奨を期待して社員は会社に留まりやすくなります。その結果、離職率の低下や人材の長期活用による企業力向上につながります。
企業ブランディングと社会的信頼度の向上
退職金制度を着実に運用している企業は、社内外から「従業員を大切にする誠実な会社」と評価され、ブランドイメージや社会的信頼度の向上につながります。従業員に対する手厚い待遇はCSRの観点からも企業価値を高め、取引先や投資家からの信頼感にも寄与します。
さらに、従業員自身の会社への安心感・帰属意識も高まり、良好な労使関係の構築や従業員満足度の向上にもつながります。
関連記事:企業向け金融教育とは?導入メリットや成功事例、実践方法を徹底解説
積立によるキャッシュフロー安定化とリスク分散
退職金を計画的に積み立てることで、毎期の支出を平準化でき、退職者が重なった場合でも一度に多額の支払いを避けられます。突発的な現金流出が防げるため資金繰りが安定し、財務の見通しも立てやすくなります。
さらに、社外積立の活用やDC導入、専門機関での運用により、退職金に伴うリスクを分散することも可能です。
当社が提供する「マネーリペア」では、退職金制度の見直しや積立計画に関する相談が可能です。企業の退職金制度や社員の資産形成支援に関するソリューションを提供しています。制度導入や運用に悩んだら、マネーリペアにご相談ください。
また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
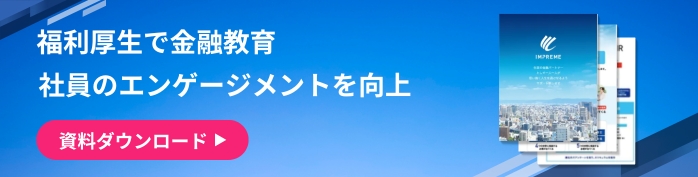
退職金の積立方式の種類と特徴

退職金制度には、資金の積立方法(社内か社外か)や給付方式(確定給付型か確定拠出型か)によってさまざまな種類があります。ここでは、それぞれの代表的な制度と特徴を解説します。
企業内積立(社内預金・社内信託など)
企業内積立の例として社内預金や社内信託があります。社内預金制度は従業員が会社にお金を預ける制度で、会社は預かった資金を運用し、従業員には市中より有利な利息を付けて後に返却します。
従業員にとって手軽な社内貯蓄となり、会社側は内部資金として活用できます。社内預金自体は退職金とは別ですが、退職時にまとめて受け取ることで退職金の補完的役割を果たす場合もあります。
一方、社内信託(退職給付信託)は、会社が退職金原資となる資産を信託銀行に預けて運用する仕組みです。自社内に積立金を確保しつつ、資産を外部管理することで安全性を高める狙いがあります。
外部積立(生命保険や基金への拠出)
外部積立の方法には、生命保険の活用や退職金共済への加入、企業年金基金への拠出などがあります。例えば、養老保険など積立型の保険に加入し、満期時や解約時の返戻金を退職金原資に充てる方法は、中小企業でよく用いられます。
また、中小企業退職金共済(中退共)や特定退職金共済(特退共)といった公的・半公的な退職金共済制度に加入して社外に積み立てる手段も一般的です。
大企業では、自社で確定給付企業年金(基金)を設立し、拠出金を外部運用して退職金を年金形式で支給するケースもあります。いずれにしても、社外に資金を蓄えることで確実に退職金原資を準備することが目的です。
確定給付型の退職金制度のメリット・デメリット
確定給付型は、退職時に受け取る給付額があらかじめ確定している制度です。従業員にとって将来の受取額が明確で安心感がありますが、企業にとっては必要資金を不足なく準備する責任があり、運用状況によっては追加拠出が発生するリスクも伴います。
退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員が退職する際に一度きりでまとまった退職金を支給する方式です。多くの企業が採用する基本的な形態で、社内規程で勤続年数や最終給与に基づく算定式を定めて運用します。
シンプルで導入しやすく、従業員にとっても退職時にまとまった資金を得られるメリットがあります。ただし、生涯にわたる定期的な給付がないため、受け取った退職金を長期的に管理・運用する必要があります。
また、退職者発生時の企業側の資金負担が大きくなるため、事前の積立が不可欠です。
確定給付企業年金制度(DB)
確定給付企業年金(DB)は、企業が外部の年金基金に拠出金を積み立て、従業員の退職後に年金または一時金として給付する制度です。年金形式で長期にわたり定期的に給付できる点が特徴で、従業員にとって老後の安定収入となります。
一方、運用が思わしくないと企業が不足分を補填する必要が生じるなど、企業側の財務負担リスクは大きくなります。制度運営には専門的な管理や法的手続きが必要であり、中小企業が単独で導入するのは難しい場合もあります。
確定拠出型の退職金制度のメリット・デメリット

確定拠出型は、企業が拠出する掛金額があらかじめ確定しており、その運用結果で将来の給付額が変動する退職金制度です。企業にとって将来の負担額が予測しやすい反面、運用リスクは従業員自身が負います。
企業型確定拠出年金制度(DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が毎月一定額の掛金を拠出し、従業員ごとの個人年金口座に積み立てる制度です。従業員は用意された投資商品(投資信託や定期預金など)から運用先を選び、運用成績に応じて最終的な受取額が決まります。
転職時に資産を他の年金制度へ持ち運べる点や、掛金・運用益に税制優遇がある点も特徴です。企業にとっては退職給付債務が発生しないため導入が進んでいます。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業向けの国の退職金共済制度です。企業が毎月、従業員ごとに定めた額の掛金を中退共に納付し、独立行政法人が資金を運用します。
従業員の退職時には、それまでの掛金納付期間に応じた退職金が共済から直接支払われます。掛金は全額損金算入でき、国からの掛金助成(新規加入時の一部補助)など中小企業に有利なメリットがあります。
短期間の勤続で退職した場合は給付金が出ない、掛金の減額はできないなどの制約はありますが、中小企業で広く利用されています。
関連記事:中小企業の退職金制度を解説!中退共などは活用すべきなのか?
特定退職金共済制度
特定退職金共済制度(特退共)は、商工会議所や業界団体が運営する退職金共済制度で、企業規模に関係なく加入できます。仕組みは中退共に似ており、企業が毎月掛金を拠出し、退職時に共済から給付金が支払われます。
ただし、中退共のような国の助成はなく、給付水準や条件が運営団体によって異なる点が特徴です。中退共に加入できない企業や、別の選択肢を求める企業によって利用されています。
企業が退職金制度を選ぶポイント
企業が退職金制度を検討する際には、自社の規模や財務状況、従業員構成などに応じて最適な制度を選ぶことが大切です。以下に制度選択時の主なポイントを解説します。
自社の規模・加入条件
企業規模や業種によって利用できる制度が異なります。中小企業なら中退共など公的共済が利用可能で、一定規模以上であれば企業年金の設立も検討できます。
財務状況とリスク許容度
将来の負担額とリスク許容度を考慮します。負担を安定させたいなら確定拠出型、手厚い給付を重視するなら確定給付型が適しています。
人材戦略(定着か流動か)
長期勤続を促したいなら勤続年数で給付額が増える確定給付型が有効です。若手が多く転職も頻繁な業態なら、ポータビリティの高い確定拠出型を取り入れることで公平性を保てます。
制度運営の体制
社内で制度を管理運営する人員やノウハウがあるか検討します。リソースが限られる場合、外部機関に運用を任せられる中退共や企業型DCの方が負担が少なくなります。社労士や金融機関など外部専門家の助言を得るのも有効です。
他制度との併用
必ずしも一つの制度に絞る必要はありません。例えば退職一時金に企業型DCを追加するなど、確定給付型と確定拠出型を組み合わせたハイブリッド型も可能です。
退職金積立に関するよくある質問
退職金積立について、経営者や人事担当者の方からよく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1. 退職金積立は法的義務ではないと聞きますが、なぜ導入を検討すべきなのでしょうか?
法的義務はありませんが、多くの企業が退職金制度を導入しています。それは優秀な人材を獲得・定着させ、従業員の老後を支えることで会社への信頼を高められるためです。退職金制度が整っていることは求職者にとって魅力となり、在職社員にも将来への安心感を与えます。
Q2. 中小企業でも退職金積立を行うメリットはありますか?
はい、あります。中小企業でも退職金制度を用意することで、大企業に負けない魅力ある福利厚生を提供できます。優秀な人材の流出防止や採用時のアピールにつながり、従業員の安心感も高まります。
また、中小企業退職金共済(中退共)などを活用すれば、少額からでも計画的に積立が可能で、掛金に税制優遇も受けられます。急な退職金支出による財務リスクを軽減できる点もメリットです。
関連記事:中小企業の退職金制度を解説!中退共などは活用すべきなのか?
Q3. 退職金制度をいざ辞めなければいけない時はどうなるのか?
退職金制度を廃止する場合は、労働条件の不利益変更となるため慎重な対応が必要です。
まず廃止の理由を明確に説明し、従業員代表と協議の上、可能な限り退職金相当の補償(過去勤務分の一時金支給や他制度への移行など)を行います。
Q4. 積立方式の変更や廃止を検討する場合、従業員の反発はどう対応すればよいでしょうか?
制度変更や廃止に際して従業員の反発を抑えるには、コミュニケーションと配慮が重要です。変更の必要性をデータやシミュレーションで示し、従業員の将来にマイナスにならないよう代替措置(移行時の一時金加算や新制度での補填策など)を提示します。
また、事前に従業員の意見を聞き、可能な範囲で反映することで納得感を高めることも効果的です。従業員にとって納得できる形にすることで、反発を和らげスムーズな移行が図れるでしょう。
Q5. 積立と確定拠出年金を併用するメリットは何ですか?
退職金の内部積立(確定給付型)と確定拠出年金(DC)を併用すると、それぞれの長所を生かすことができます。確定給付部分で最低限の退職金を保証しつつ、DC部分で運用次第ではさらなる上乗せを期待できます。
従業員は安定した給付と自己運用の機会を両方得られ、企業は将来負担を抑えつつ従業員のモチベーション維持が可能です。
まとめ:退職金制度の積立がもたらす価値
退職金制度の積立は、企業と従業員双方に大きな価値をもたらす仕組みです。適切な制度設計と計画的な積立によって、企業は財務の安定と人材の定着を得られ、従業員は老後の安心を確保できます。
法的義務ではありませんが、長期的に見れば退職金制度への投資は企業の持続的発展に寄与すると言えるでしょう。
マネーリペアは、企業の福利厚生制度の構築や従業員向け金融教育を支援するサービスです。退職金制度の導入・見直しを検討する際には、ぜひマネーリペアをご活用ください。また資料請求も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
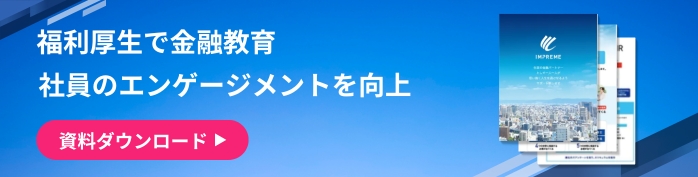

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。