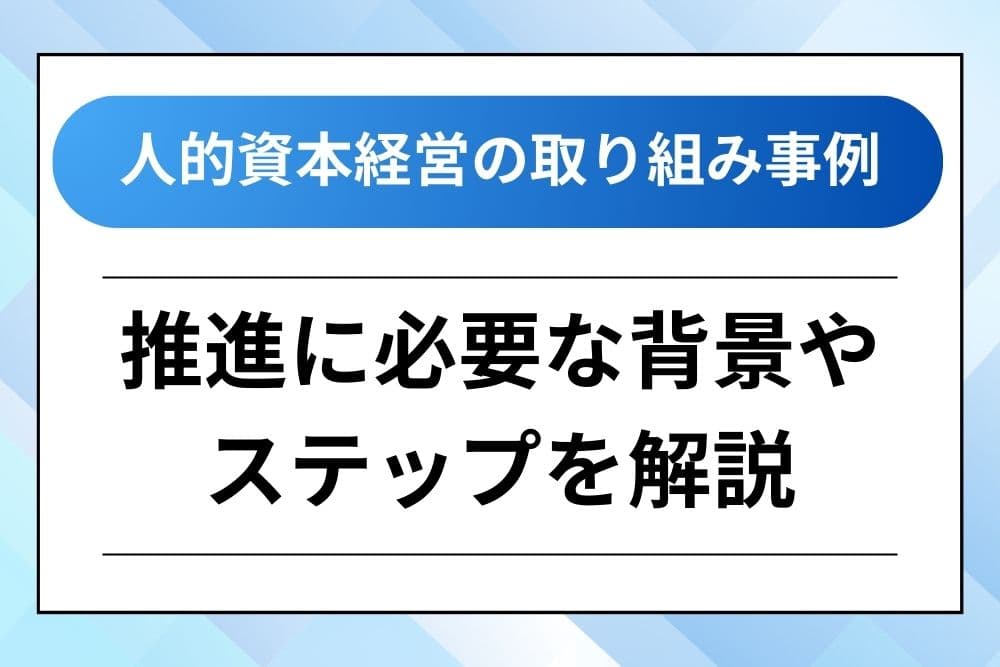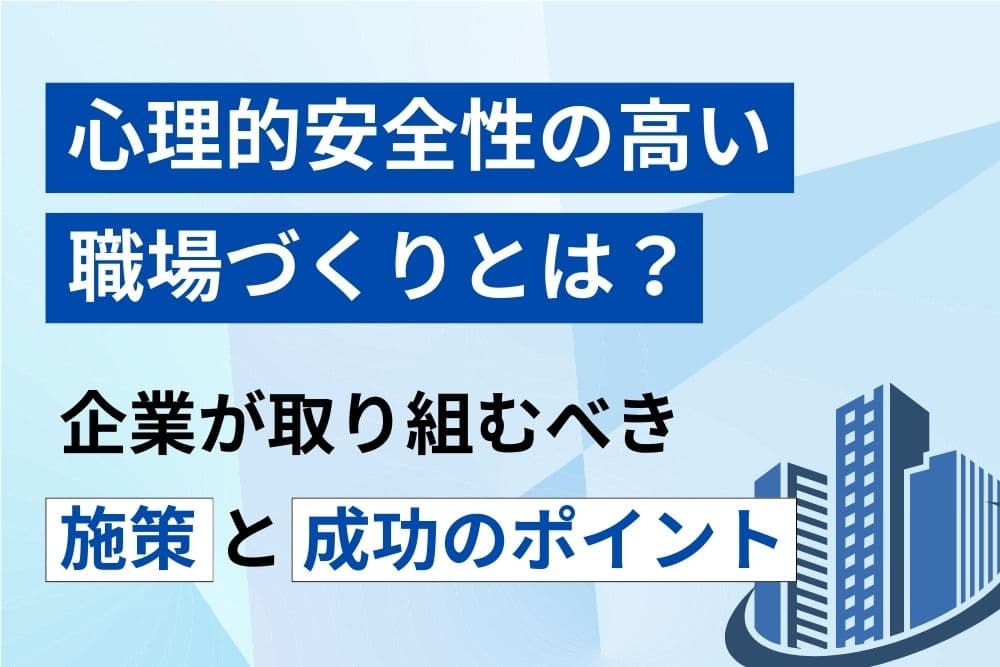お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
従業員ロイヤリティを高めるには?制度・事例・福利厚生活用まで詳しく解説
 詳細を見る
詳細を見る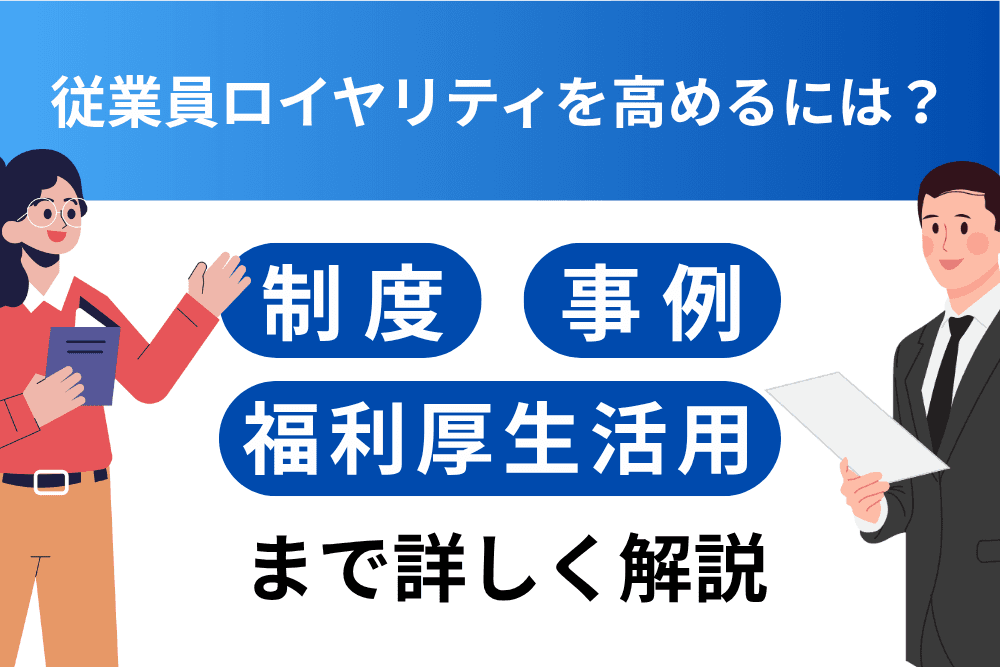
従業員ロイヤリティとは?
従業員ロイヤリティを高めるメリット
従業員ロイヤリティ向上のための施策
福利厚生サービスを活用したロイヤリティ向上
従業員ロイヤリティ向上のためのステップ
企業経営において、従業員の定着と活躍は不可欠です。そこで重要になるのが「従業員ロイヤリティ」という概念です。従業員ロイヤリティが高まることで、企業は様々なメリットを享受できます。
この記事では、従業員ロイヤリティの定義や重要性から、具体的な向上施策、さらには福利厚生サービスを活用したロイヤリティ向上まで、詳しく解説していきます。
目次
従業員ロイヤリティとは?

「従業員ロイヤリティ」とはそもそもなに?というところから解説します。
- 定義と重要性
- ロイヤリティとエンゲージメントの違い
上記2つのポイントから解説しますので参考にしてください。
定義と重要性
従業員ロイヤリティとは、従業員が企業に対して抱く「忠誠心」や「愛着」のことです。単に給与や待遇が良いからという理由で働くのではなく、企業のビジョンや文化に共感し、その一員であることに誇りを感じている状態を指します。
従業員ロイヤリティが高い企業では、従業員が自社の製品やサービスに自信を持ち、顧客に対しても積極的に貢献しようと思いやすいです。
これは、顧客満足度の向上やブランドイメージの強化にも繋がり、結果として企業の競争力向上に大きく貢献します。
また、従業員が企業に長く留まる傾向があるため、人材育成にかかるコストの削減や、知識・スキルの蓄積による組織全体のレベルアップも期待できるでしょう。
ロイヤリティとエンゲージメントの違い
従業員ロイヤリティと混同されやすい言葉に「従業員エンゲージメント」がありますが、この2つの言葉は似ていますが、明確な違いがあります。
従業員エンゲージメントは、従業員が自身の仕事や組織に対して抱く「熱意」や「貢献意欲」を指すのが一般的です。
例えば、「この仕事は面白い」「もっと会社に貢献したい」といったポジティブな心理状態がエンゲージメントが高い状態といえます。一方、従業員ロイヤリティは、企業への「愛着」や「帰属意識」に重きを置くのが特徴です。
エンゲージメントが高くても、より良い条件の企業があれば転職を検討する可能性はありますが、ロイヤリティが高い従業員は、多少の不満があっても企業に留まることを選択する傾向があります。
つまり、エンゲージメントは「今、仕事にどれだけ没頭しているか」、ロイヤリティは「この会社にどれだけ長くいたいか」という違いで捉えることができます。企業としては、両方を高めることで、より強固な組織を築くことが可能です。
従業員ロイヤリティを高めるメリット

従業員ロイヤリティが高まることは、企業にとって計り知れないメリットをもたらします。ここでは、特に重要な2つのメリットに焦点を当てて解説します。
- 離職率の低下
- 生産性とモチベーションの向上
わかりやすく解説しますので参考にしてください。
離職率の低下
従業員ロイヤリティが高ければ高いほど、従業員が自社に長く留まる傾向が強まります。企業への愛着や忠誠心があるため、短期的な不満や他社からの誘いがあっても、安易に転職を考えることが少なくなるからです。
離職率の低下は、企業にとって非常に大きなメリットです。まず、採用コストの削減に繋がります。新たな人材を募集し、採用するまでには、求人広告費、面接担当者の人件費、そして入社後の研修費用など、多大なコストが発生します。
離職率が低いことで、これらのコストを大幅に抑えることができます。次に、生産性の維持・向上に貢献しやすいです。
新しい従業員が業務に慣れるまでには一定の期間を要し、その間は既存従業員の負担が増えることもありますが、熟練した従業員が長く在籍することで、業務の効率が上がり、チーム全体の生産性が向上します。
また、社内に知識やノウハウが蓄積されやすくなり、組織全体の競争力強化にも繋がるでしょう。
生産性とモチベーションの向上
従業員ロイヤリティの高い従業員は、単に会社に留まるだけでなく、仕事に対して高いモチベーションを持って取り組みます。
企業への愛着があるため、「会社のために貢献したい」という意識が強く、自ら積極的に課題解決に取り組んだり、新しいアイデアを提案したりするようになりやすいです。
モチベーションの向上は、個々の従業員の生産性を高めるだけでなく、チーム全体の活気にも繋がりやすいです。互いに協力し合い、助け合う文化が醸成されることで、より良い成果を生み出しやすくなるでしょう。
さらに、ロイヤリティの高い従業員は、企業の目標達成に対して主体的に関わろうとします。彼らは単なる「労働力」ではなく、企業の「パートナー」として事業の成長に貢献しようとします。
これは、企業の売上向上やイノベーションの創出にも直結し、持続的な成長を可能にする重要な要素です。
従業員ロイヤリティ向上のための施策

従業員ロイヤリティを高めるためには、具体的な施策を継続的に実施することが重要です。
- 表彰制度の導入
- 1on1ミーティングの実施
- 福利厚生の充実
ここでは、特に効果が期待できる3つの施策を紹介します。
表彰制度の導入
従業員の貢献や努力を正当に評価し、表彰する制度は、ロイヤリティ向上に非常に有効です。金銭的な報酬だけでなく、会社からの公式な承認は、従業員のモチベーションを大きく高めます。
例えば、月間MVP、年間最優秀社員、プロジェクト成功貢献賞など、様々な形で表彰制度を設けることが可能です。
表彰の際には、単に賞状を渡すだけでなく、なぜその従業員が表彰されたのか、どのような功績があったのかを具体的に共有することで、他の従業員にも良い刺激を与え、模範となる行動を促すことができます。
また、表彰式を社内イベントとして開催することで、一体感の醸成にも繋がりやすいです。
1on1ミーティングの実施
1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に個別で行う面談です。
このミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリアパス、スキルアップ、プライベートな悩みなど、幅広いテーマについて話し合います。
1on1ミーティングの最大の目的は、部下の成長を支援し、エンゲージメントとロイヤリティを高めることです。部下は自分の意見や悩みを安心して話せる場があることで、会社への信頼感を深めます。
また、上司は部下の個性や強みを理解し、適切なフィードバックやサポートを提供することで、部下の能力を最大限に引き出すことが可能です。
これにより、部下は「会社が自分を大切にしてくれている」と感じ、企業への愛着を深めるでしょう。
福利厚生の充実
福利厚生の充実は、従業員が安心して働き続けられる環境を提供し、結果としてロイヤリティを高める上で非常に重要です。
給与や賞与といった直接的な報酬だけでなく、従業員の生活をサポートする様々な制度を導入することで、企業への満足度を高めることができます。
例えば、住宅手当、通勤手当、健康診断の補助、育児・介護支援、財形貯蓄制度、カフェテリアプラン(従業員が選択できる福利厚生メニュー)などが挙げられます。
これらの福利厚生は、従業員の日々の生活に直接的な恩恵をもたらし、「会社が従業員とその家族のことを考えてくれている」という安心感を与えるでしょう。
福利厚生が充実している企業は、採用活動においても有利に働き、優秀な人材の獲得にも繋がります。
福利厚生サービスを活用したロイヤリティ向上

従業員ロイヤリティ向上において、福利厚生は非常に重要な役割を担います。
- 福利厚生とロイヤリティの関係性
- 金融リテラシー支援の効果
特に、近年では「福利厚生サービス」を導入することで、より効果的にロイヤリティを高めることが可能です。
福利厚生とロイヤリティの関係性
福利厚生は、従業員の生活の質を向上させ、安心して仕事に集中できる環境を整えるための重要な要素です。
充実した福利厚生は、従業員が企業から「大切にされている」と感じるきっかけとなり、企業への信頼感や満足度を高めます。
この満足度が高まることで、従業員は企業に対してより強い愛着や忠誠心を抱くようになり、結果としてロイヤリティ向上に繋がりやすいです。
例えば、健康経営を意識したフィットネスクラブの利用補助や、自己啓発のための語学学習支援、リフレッシュのための宿泊補助など、多岐にわたる福利厚生は、従業員のエンゲージメントを高め、企業文化への共感を促します。
これにより、従業員は単に業務をこなすだけでなく、企業の成長に貢献したいという意欲を持つようになります。
金融リテラシー支援の効果
福利厚生サービスの中でも、特に近年注目されているのが「金融リテラシー支援」です。
従業員の資産形成やライフプランニングに関する知識向上をサポートすることで、将来への漠然とした不安を軽減し、安定した生活基盤を築く手助けをします。
例えば、ファイナンシャルプランナーによる個別相談会の実施、資産運用セミナーの開催、確定拠出年金(DC)やNISA(少額投資非課税制度)に関する情報提供などが挙げられます。
これらの支援を通じて、従業員は自身の将来設計を具体的にイメージできるようになり、経済的な不安が軽減されやすいです。経済的な安心感は、従業員が仕事に集中できる環境を作り出し、ストレスの軽減にも繋がります。
結果として、従業員は企業に対して感謝の気持ちや信頼感を抱き、ロイヤリティの向上に貢献します。
金融リテラシー支援は、従業員の長期的なキャリアプランと連動し、企業への帰属意識を一層強固なものにするでしょう。
【金融リテラシーを向上できる福利厚生の紹介】
金融型福利厚生プログラム《マネーリペア》では、従業員のお金の基礎知識である金融リテラシーを向上させます。
- 固定費の削減
- 経済動向
- ふるさと納税
- 社会保険料の仕組み など
セミナーや個別相談など様々な方法で、従業員の方にもわかりやすくお金の知識を付けられる福利厚生です。
無料相談も行っていますので、資料は以下のリンクより無料で配布しています。

従業員ロイヤリティ向上のためのステップ

従業員ロイヤリティを効果的に向上させるためには、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。
- 現状の把握と課題の特定
- 施策の計画と実行
- 効果測定と改善
ここでは、そのための3つのステップを紹介します。
現状の把握と課題の特定
まず、自社の従業員ロイヤリティが現状どうなっているのかを把握することから始めます。
従業員アンケートやサーベイ、個別面談などを通じて、従業員の満足度、企業への愛着度、離職意向などを調査します。
具体的には、以下のような項目を調査すると良いでしょう。
- 企業文化やビジョンへの共感度
- 仕事内容への満足度
- 上司や同僚との人間関係
- 評価制度や報酬への納得度
- 福利厚生の充実度
- キャリアパスの明確さ
これらの結果を分析し、ロイヤリティ向上のために改善すべき具体的な課題を特定します。
例えば、「評価制度への不満が多い」「コミュニケーションが不足している」といった課題が見つかるかもしれません。課題を明確にすることで、次の施策計画に繋げることができます。
施策の計画と実行
特定した課題に基づき、具体的な施策を計画・実行します。計画の際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 目標設定: 「半年後に離職率をX%削減する」「従業員エンゲージメントスコアをY点アップさせる」など、具体的な目標を設定します。
- 施策の優先順位: 複数の課題がある場合、効果が高く、実現可能性が高いものから優先的に取り組みます。
- 担当者の明確化: 各施策の責任者や担当者を決め、役割分担を明確にします。
- タイムラインの設定: 各施策の開始時期、完了時期を定めます。
計画した施策は、部署を巻き込みながら実行していきます。
例えば、表彰制度の導入、1on1ミーティングの定期実施、新たな福利厚生の導入など、段階的に進めていくことが重要です。
効果測定と改善
施策を実行したら、その効果を定期的に測定し、必要に応じて改善を行います。
効果測定には、現状把握で用いたアンケートやサーベイを再度実施するほか、離職率やエンゲージメントスコアなどのKPI(重要業績評価指標)の変化を追跡してください。
測定結果に基づいて、施策が目標達成に貢献しているかを評価します。
もし期待通りの効果が得られていない場合は、原因を分析し、施策の内容や実施方法を見直しが必要です。
例えば、1on1ミーティングの質が低い場合は、上司への研修を強化する、福利厚生の利用率が低い場合は、広報を強化するといった改善策が考えられます。
この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」のPDCAサイクルを回し続けることで、従業員ロイヤリティを継続的に向上させることが可能です。
よくある質問(FAQ)

従業員ロイヤリティでよくある質問をQ&A方式でまとめました。
- Q1. 従業員ロイヤリティを測定する方法は?
- Q2. 福利厚生サービスはどのように選べばよい?
それぞれのポイントについて詳しく解説をします。
Q1. 従業員ロイヤリティを測定する方法は?
従業員ロイヤリティを測定するには、主に以下の方法があります。
- 従業員満足度調査(ES調査): 従業員の仕事内容、職場環境、人間関係、報酬、福利厚生などに対する満足度を定量的に評価します。
- 従業員エンゲージメントサーベイ: 従業員の仕事への熱意や貢献意欲、組織への愛着度を測るための質問票を用います。
- eNPS(Employee Net Promoter Score): 「この会社を友人や知人にどの程度勧めたいですか?」という質問を通じて、従業員の企業に対する推奨度を測る指標です。
- 1on1ミーティングや個別面談: 定期的な面談を通じて、従業員から直接意見やフィードバックを聞き、定性的な情報を収集します。
- 離職率の推移分析: 離職率の変化は、従業員ロイヤリティの変化を示す重要な指標の一つです。
これらの方法を組み合わせることで、多角的に従業員ロイヤリティの現状を把握することができます。Q2. 福利厚生サービスはどのように選べばよい?
福利厚生サービスを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 従業員のニーズ: 従業員の年齢層、家族構成、ライフスタイルなどを考慮し、どのような福利厚生が求められているかを把握します。アンケート調査などを実施するのも有効です。
- サービスの多様性: 従業員の多様なニーズに応えられるよう、選択肢が豊富なサービスを選ぶことが重要です。カフェテリアプランを提供しているサービスも検討に値します。
- 導入・運用のしやすさ: 導入にかかる手間やコスト、導入後の運用負担が少ないサービスを選ぶと良いでしょう。
- コストパフォーマンス: 提供されるサービスの質と費用が見合っているかを確認します。従業員一人あたりのコストも考慮しましょう。
- サポート体制: 導入後もベンダーからのサポートが充実しているかを確認しておくと安心です。
複数の福利厚生サービスを比較検討し、自社の従業員にとって最適なサービスを選ぶことが、ロイヤリティ向上に繋がります。
【金融リテラシーを向上できる福利厚生の紹介】
金融型福利厚生プログラム《マネーリペア》では、従業員のお金の基礎知識である金融リテラシーを向上させます。
- 固定費の削減
- 経済動向
- ふるさと納税
- 社会保険料の仕組み など
セミナーや個別相談など様々な方法で、従業員の方にもわかりやすくお金の知識を付けられる福利厚生です。
無料相談も行っていますので、資料は以下のリンクより無料で配布しています。

従業員ロイヤリティ向上の今後と展望

従業員ロイヤリティの向上は、一過性の取り組みではなく、企業の持続的な成長のために不可欠な戦略として、今後ますます重要性が高まっていくでしょう。
- 企業と従業員の協力による実現
- 持続可能なロイヤリティ向上施策の構築
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
企業と従業員の協力による実現
従業員ロイヤリティは、企業側が一方的に提供するものではなく、企業と従業員が協力し合うことで初めて真に実現するものです。
企業は、従業員が能力を発揮し、安心して働ける環境を整える責任があります。これには、公正な評価制度、適切な報酬、ワークライフバランスの推進、キャリア開発支援などが一般的です。
一方で、従業員もまた、企業のビジョンや目標に共感し、自身の役割を理解して積極的に貢献する意識を持つことが求められます。
企業が提供する機会を最大限に活用し、自らも成長しようとする姿勢が重要です。
このように、企業と従業員が互いに理解し、信頼関係を築きながら協力していくことで、より強固なロイヤリティが醸成され、企業全体の生産性とエンゲージメントが向上します。
持続可能なロイヤリティ向上施策の構築
VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代において、企業を取り巻く環境は常に変化しています。
従業員の価値観やニーズも多様化しており、画一的な施策だけではロイヤリティを維持することは困難です。
今後は、データに基づいた従業員のニーズ分析を定期的に行い、それに合わせて施策を柔軟にアップデートしていくことが求められます。
テクノロジーを活用した従業員体験(EX)の向上、個々の従業員のキャリアパスに合わせたパーソナライズされた支援、そして多様性を尊重するインクルーシブな職場環境の構築などが、持続可能なロイヤリティ向上施策の鍵となるでしょう。
従業員ロイヤリティの向上は、企業が競争力を維持し、未来を切り拓いていくための重要な経営戦略として、今後も進化し続けることが期待されます。
まとめ

従業員ロイヤリティは、企業に対する従業員の愛着や忠誠心を指し、その向上が離職率の低下や生産性・モチベーションの向上に繋がる重要な要素です。
ロイヤリティを高めるためには、表彰制度の導入、1on1ミーティングの実施、そして福利厚生の充実といった施策が効果的です。
特に福利厚生サービス、中でも金融リテラシー支援は、従業員の経済的な安心感を高め、ロイヤリティ向上に大きく貢献します。
従業員ロイヤリティの向上は、現状把握から始まり、計画・実行、そして効果測定と改善のサイクルを繰り返すことで実現します。企業と従業員が協力し、ニーズに応じた持続可能な施策を構築していくことが、今後の企業の成長には不可欠です。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。